“凛とした女優”尾野真千子さんはカッコイイ
若林盛亮 2024年11月5日
朝ドラを見ない私が最近、リバイバル朝ドラ「カーネーション」にはまっている。現在の朝ドラ「おむすび」の前にやるのを偶然、目にしたとき主演が尾野真千子さんだったからだ。
尾野真千子さん演じる主人公は、先駆的ファッションデザイナー、コシノジュンコの母親、和装全盛の時代に「洋装を日本の女性に広める」という志を胸に逆境を順境に変え洋裁の道を開拓していくとても意志が強くて魅力的な主人公だ。“凛とした女優”尾野真千子さんにピッタリの役。
この女優は「寅と翼」のあの独特のナレーションでも有名になった方だ。
私が尾野真千子さんを知ったのは衛星放送で見た「始終点駅」という映画だが、主人公の弁護士の人生を決めるような女性を演じたのがとてもカッコよかった。
尾野真千子さんが演じた「彼女」には、東北大学(たしか)時代に学生活動家仲間で同棲中の恋人がいた。それが佐藤浩一演じる主人公、鷲田完治だ。
「彼女」の恋人、鷲田君は学生運動を辞め司法試験を受けようとしている。「彼女」はそんな彼を責めるのではなく、「司法の現場も闘いよ」と忠告だけを与える。彼は司法試験の合格発表に自分の名前を見た日、アパートに戻ると「彼女」の歯ブラシがなくなっていて机の上に「彼女」からの贈り物らしい万年筆ケースが置かれているのを発見する。ケースを開けると「闘え 鷲田完治」と書かれた紙切れが万年筆と共にあった。
彼は「司法の現場も闘いよ」と励ましてくれた夜の「彼女」の言葉-「闘え 鷲田完治 逃げるな」! を想い出す。
時は経ち結婚して男の子も設けた彼は旭川の裁判所に勤務、他方で雪深い町の小さな酒場マダムらしい「彼女」との関係も続けている、がある夜「彼女」は「短命と占いに出た」、「誰かに負担をかけて生きたくないからそれもいいかな」と語る。そんな逢瀬の翌朝、町の駅で見送る彼の目の前で「彼女」はホームに入ってくる電車に飛び込み自死を遂げる。謎めいた微笑みだけを彼に残して・・・。
以降の彼は裁判官を辞し、妻とも離婚、東京での家庭生活も捨て北の果ての町、釧路で小さな法律事務所を営み、ただ国選弁護人の仕事のみを受ける清貧の「人助け」弁護士-「闘え 鷲田完治 逃げるな」を生きる。「彼女」からの万年筆を武器に。
司法の道に転進する彼を横目に「闘え 鷲田完治 逃げるな」とベッドでタバコを燻くゆらせながらつぶやく「彼女」には鬼気迫る迫力があった。
尾野真千子さんの印象は品のあるツンとした鼻がとても凛としていて、それだけで「凛とした女優」を感じさせる方だ。
「カーネーション」ではどんな「凛としたコシノジュンコの母」を見せてくれるのか楽しみだ。
西田敏行さんの冥福を祈る
赤木志郎 2024年11月5日
俳優の西田敏行さんがなくなった。親しみやすい俳優として多くの人がファンになっている。私もその一人で、ラジオの名作劇場を聴いたり、テレビでドラマ(釣りバカ日誌、大河ドラマ)や映画を見たことがある。歌「もしもピアノが弾けたなら」なども私の気持ちと同じだった。
私がとくに親近感をもっていたのは、生年月日がまったく同じだからだ。だから、西田さんが活躍していると私も頑張らなければという気持ちになるのだった。
しかし、その西田さんが亡くなったので、ちょっとショックだった。77歳の喜寿の祝いをおこなう前だったろうに。西田さんは名優として舞台、ドラマ、映画で大活躍をしてきたので大きな足跡を残したといえるだろう。
私といえば、厚遇をしてくれる朝鮮にたいし何もしていないが、それでも老人として敬意を払ってくれる。商店や市場で道を譲ってくれるのである。そんな時に、私も人から道を譲られる歳になったのだろうと実感し、また、悪いような気がするのである。
人間は人が喜ぶことをやっていくと生きる意味を感じるという。それに照らして思えば、人が嫌がることをあえてやるというのが多かった。老いれば老いるほど、「老いの一徹」も意義があるかもしれないが、頑迷・頑固になっては老害にしかならない。少しでも改めたいと思うのである。
西田敏行さんが亡くなったのち、改めていろんな考えに耽った。私を励ましてくれた西田さんのご冥福を祈りたい。
地域愛-最後に愛は勝つ
魚本公博 2024年11月5日
大リーグでは大谷翔平選手が所属するドジャースが優勝を果たしました。
本拠地ロサンゼルスは興奮のるつぼ。歓喜の声が夜遅くまで鳴り響きました。
それを見て思うのは、地域愛です。地域は、多くの人々と関係を持つ暮らしの場であり、人間の最も身近な共同体です。その一員としてのドジャースの優勝は、まるでロサンゼルスが優勝したかのような気分をもたらしたのでしょう。
そして、大谷選手の活躍。ホームランと打点の2冠。ホームラン54本に盗塁59の「54-59」という前人未到の大記録達成。地区優勝やナショナルリーグ優勝までの活躍、ワールドシリーズでは亜脱臼を押しての出場がチームを元気づけました。ロサンゼルスの大谷ファンの一女性は「大谷はチームに特別な力をもたらし、街に希望を与えてくれた」と述べています。
日本でも大谷の郷里の花巻や山本選手の郷里である岡山県備前市などで同様に光景が見られました。
人は地域を愛し、その成員の活躍を自分のことのように喜び、元気づけられる。それが理屈ではなく、素直に伝わってくる、そんな風景でした。
今、日本の地方・地域は「地方消滅」の危機に瀕しています。そればかりか、対中軍事対決の最前線に立たされ、国土のミサイル基地化も進んでいます。
愛する郷土を何とかしたい、ましてや対中前線基地化などさせてはならない。そういう地域愛・郷土愛が政治を変えていく。「最後に愛は勝つ」、そんな気にさせられたドジャース優勝でした。
私の心の風景
若林佐喜子 2024年11月5日
衛星テレビで、NHK朝ドラの後の番組「こころの旅(こころの風景)」を楽しみに見ています。10月23日の放映は火野正平さんのピンチヒッターなのか、俳優の田中要次さん。その日のお便りは、70歳の加藤さん(男性)からの小学生時代の初めての写生場所、和歌山県の○○神社を訪ねて下さいという内容でした。加藤さんは、保育園に通わず絵本を見たことがなく絵の時間が苦痛だったのですが、初めての写生で絵を描く楽しみを発見、さらに担任の先生に「うまいね」と褒められその絵は特別賞に選ばれたそうです。本人の描いた上手な○○神社の絵が同封されていました。
番組をみながら、私は小学生時代の出来事を思い出していました。私の故郷は埼玉の稲沢という山田舎でした。私は、絵を描くのは苦手で特に立体感を出すのが駄目でした。ところが、確か小学校4年生の時、私の描いた稲の干してある田圃と紅葉した山々の風景画が教室に張り出されたのです。実は、その風景画は10歳違いの兄に紅葉の色つかいを手伝ってもらったもので、立体感にあふれなんか上手くなったような気分になっていた私でした。今から考えると22人のクラスなので、ほぼ全員がはりだされていたのかも知れませんね(笑)。小学校6年生までしか住んでいないのですが、私のこころ風景というと、山奥の田舎と紅葉風景にまつわる出来事、そして金魚のふんのようにまとわりついていた兄との思い出です。
そんな私の心の風景、これからも大切にしていきたいと思った10月でした。
大谷、その凄さの秘密
小西隆裕 2024年10月20日
大谷が凄い。
大リーグで本塁打王、打点王、打率と盗塁は2位。信じられない。
今年大リーグに行き、活躍した今永が言っていた。「彼は、日本人ではない。アメリカ人でもない。大谷人だ」。
なぜこんなに凄いのか。
それについてアメリカの女の人が言っていた。
「彼は正しいマインドセットを持っている。チームプレイヤーで、何をするにしてもチームのためにやっている。それこそが彼を成功に導いた理由だと思います」(10月2日付朝日新聞朝刊)。
個人主義の国だと思っていた米国の女性からこういう言葉が出てくるとは思わなかった。感動した。確かにその通りだと思う。
「詩を歌う」Bob Dylan?ノーベル文学賞受賞の理由わけ
若林盛亮 2024年10月20日
衛星放送BS1「アナザーストーリーズ」でボブ・ディランのノーベル文学賞受賞に関する秘話をやった。
まずは本題に入る前にこの番組で知った事実を一つ。
「フォークの神様」だったディランがビートルズの衝撃的デビューに影響を受けてロックをやり始めたことは知っていた。でもジョンがディランのファンだったこと、ビートルズの1964年2月の初訪米公演時にジョン・レノンがディランに会いに来たということは初めて知った事実だ。ディランとジョンは夜通し曲作りについて話し合ったという。
二人の出会いは化学融合を起こし、その一年後、1965年1月にはディランは全曲ロックのアルバム“Bring It All Back My Home”を世に問うた。
他方、ビートルズ、特にジョンはこれまでの十代男女の恋の軽いやりとりといった他愛のない歌詞から一転、人間の内面を歌うような歌詞と曲作りに変った。ディランの初ロック・アルバム発売と同時期発売の”Rubber Soul”は歌詞も曲もこれまでと違った変化を20歳の私も感じたものだ。当時はディランの詩に影響を受けたのだとは思いもよらなかった。ビートルズはティーン・エイジャーの英雄から「アーティスト」になった。
ディランは初のロック・アルバム発売半年後の7月、ニューポート・フォーク・フェスティバルでブルース・バンドを従えてエレキトリック・ギターで登場、かの有名な“Like A-Rolling Stone”を大音響で演やった。「神聖な」なフォーク祭典でのディランの演るロックを「フォークの神様」の「裏切り」と見たファンはいっせいに大ブーイングを浴びせた。この時の出来事は音楽史に残る「ブーイング事件」として語りぐさになっている。
私はといえば、シングル盤としては異常の楽曲、10分以上も次から次へと歌詞の進行する不思議なロック“Like A-Rolling Stone”にノックアウトされてボブ・ディラン大好き人間になった。
さて本題のディランのノーベル文学賞受賞秘話のこと。
ディランの受賞は2016年だが、実はすでに1997年から10年以上もの間、ストックホルムにあるノーベル文学賞選考委員会にディランを推薦し続けていた人物がいた。でも「クレージー」などと一蹴され続けた。ついに2008年、彼は推薦を断念した。だが断念から8年を経て突然、選考委員会はボブ・ディランをノーベル文学賞受賞者に指名した。
その受賞理由とされたのが「古代ギリシャの吟遊詩人ホメロス(英雄叙事詩“イーリアス”は有名)によって詩は歌として語られ、歌となってホメロスの詩は人々に口承されて多くの人々のものとなった。ディランの歌曲作品もホメロス同様の文学的価値がある」というものだった。
それは「ボブ・ディランをノーベル文学賞に」と言い続けてきた人物が、受賞指名の19年前から十余年に渡って推薦文に書き続けてきた「推薦理由」そのままだったというのが面白い。その人物にとっては「寝耳に水」のディラン受賞決定の報せを聞いて「涙が思わず出た」そうだ。
この人物の名前はゴードン・ポール。二十歳の大学生時代からロックを演るボブ・ディランに傾倒、彼の詩に魅了されアメリカ現代詩の研究者にまでなった人物だ。
彼の言うように「ホメロスの古代ギリシャ時代、詩は歌であり、詩人は歌人だった」、吟遊詩人ホメロスは竪琴を片手に「詩を歌った」、その歌を聴いた人々が歌を覚えて口承されてホメロスの詩が広く伝えられ今日に残る古典文学になった。
現代のディランはホメロスのように「詩を歌う」。
ディランは「レコード、CDに僕の歌はない、ライブ公演の中に僕の歌がある。僕はパーフォマーなんだ」と語ったことがある。
ディランは同じ歌でもライブの舞台毎に演奏も歌い方も「これが同じ歌か?」と思うほど変えてしまうことで有名だ。それは聴衆や会場の空気によって「詩の伝え方」、つまり「詩の歌い方」が変わる、変えねばならないということなのだろう。相手の顔を見て「詩を歌う」?これがボブ・ディランなのだと私は納得した。
最後に一言。
ディランはノーベル文学賞授賞式を「多忙」を理由に欠席、代理をディランの盟友、パティ・スミスが務め、ディランの初期プロテストソング「激しい雨が降る」を授賞式で歌った。この歌は核戦争の恐怖が世界を襲ったキューバ危機時、破滅に向かう世界に警鐘を鳴らした初期ディランの代表作だ。
ノーベル文学賞授賞式欠席、そしてパティ・スミスの歌に託した「激しい雨が降る」でボブ・ディランは何を言いたかったのか? それは本人のみぞ知る、私は想像するしかない。
大谷、その凄さの秘密
小西隆裕 2024年10月5日
大谷が凄い。
大リーグで本塁打王、打点王、打率と盗塁は2位。信じられない。
今年大リーグに行き、活躍した今永が言っていた。「彼は、日本人ではない。アメリカ人でもない。大谷人だ」。
なぜこんなに凄いのか。
それについてアメリカの女の人が言っていた。
「彼は正しいマインドセットを持っている。チームプレイヤーで、何をするにしてもチームのためにやっている。それこそが彼を成功に導いた理由だと思います」(10月2日付朝日新聞朝刊)。
個人主義の国だと思っていた米国の女性からこういう言葉が出てくるとは思わなかった。感動した。確かにその通りだと思う。
“我は女の味方ならず”の与謝野晶子を観て
若林盛亮 2024年10月5日
衛星放送BS1の歴史ドキュメント「英雄の選択」で与謝野晶子をテーマに取り上げた“我は女の味方ならず”を観た。
私の親しい知人に「作家志望の詩人」がいたが、彼女は「明治の近代黎明期に彗星のように現れた平塚らいてうや樋口一葉が憧れの作家、でも与謝野晶子はあまり好きじゃない」と言っていた。与謝野晶子は “君死にたもうことなかれ”が教科書にも出てくる有名な歌人だったから「あまり好きじゃない」という彼女の言葉はちょっと気になったが、理由は聞きそびれた。
今回、観たTVドキュメント“我は女の味方ならず”でなんとなくその理由がわかった。
与謝野晶子は歌人であると共に社会批評もやったが、中でも有名なのが平塚らいてうとの母性保護論争だ。
平塚らいてうは女流文芸誌「青鞜(せいとう)」の有名な創刊の辞で「元始、女性は太陽であった。真性の人であった」と高らかに宣言した女性解放運動の先駆者として有名だが、与謝野晶子も「青鞜」創刊号のために「山の動く日来(きた)る」という詩を書いて寄稿した。この詩に感動したらいてうは晶子の詩を巻頭に飾った。
そんな互いに尊敬し合う間柄の二人は、やがて「母性保護論争」という激しい論戦を繰り広げることになる。
晶子は男女平等の実践として「女子が自活し得るだけの職業的技能を持つということは、女子の人格の独立と自由とを自ら保証する第一の基礎である」と女性自身の覚醒と努力を説いた。要するに男性に経済的に依存する女性にはなるな、自活しうるだけの職業的技能を持ちなさいと、そんな「女性の自立」の側面を強調した。
晶子は「女はあらゆる男子の、知識と筋力と血と汗を集めた労働の結果である財力を奪って我が物の如くに振る舞って居る」と当時の女性を批判、ついには「私はまず働かう、私は一切の女に裏切る」とまで宣言。
ついには「我は女の味方ならず」と題した一文を「青踏」に発表した。
このような晶子の主張に8歳年下のらいてうが噛みついた。
「実に人間としての婦人の権利の主張のみならず、女性としての婦人の権利も主張されねばならない」と。
要は男女平等とは言っても男性と女性の違いは厳然としてあること、「女性としての婦人の権利も主張すべき」こと、特に「母性保護」を婦人の権利として強く主張した。
らいてうは「子供というものは、たとへ自分が生んだ自分の子供でも、自分の私有物ではなく、其の社会の、其の国家のものです」とし、だから国家は婦人の母性を保護する責任があるという論理を立てた。
後に晶子は「(らいてうと)私とは決して目的に於いては異なって居ないのです」とこの論争からは降りるが、らいてうはその後も若き市川房枝らと「婦人と母と子供の権利の擁護」を掲げ「新婦人協会」設立に至る。さらに老いては私たち戦後世代と共にベトナム反戦、反安保の闘いにも身を投じ社会運動家としての生涯を貫く。
晶子は歌人としても社会批評家としても一流で金を稼げる人、当時では希少な自立した職業婦人だった。稼ぎのない歌人の夫、与謝野鉄幹のフランス遊学費用も6人の子(後には11人の子の母に)を育てながら、いまの金額にして4千万円を稼ぎ出して都合を付けたほどの才女だ。
しかしながら当時の女性が晶子のような「男に依存しない」自立した職業婦人になれるのはごく希(まれ)で、ましてや男にはない母性保護という婦人特有の問題もかかえている。らいてうはこうした現実の女性問題を解決しようと社会運動に身を投じた。
こうした晶子とらいてうの女性の自立、解放という目的は同じでも歩みは異なる姿を私は知った。
「作家志望の詩人」が「憧れの作家は平塚らいてう」、「でも与謝野晶子は余り好きじゃない」と言った理由が私はようやくわかる気がした。
“我は女の味方ならず”の晶子を知って、平塚らいてうを深く知り、「作家志望」のかつての知り合いのことをもっと理解できた。
南浦市近況
魚本公博 2024年10月5日
今、朝鮮は地方発展に力を入れています。
これまでコロナ禍で地方には行けなかったのですが、8月に行った2泊3日の龍岡温泉旅行で、朝鮮の「地方発展」を垣間見ることができました。
平壌から南浦まで高速道路(幹線道路)が通じており、その決済がスマホで行われていることも驚きでしたが、南浦の市街地は、まるで小型平壌のような街に一変していました。
瀟洒なビルが立ち並び、道も大きくなり、港湾地区から臥牛島地区までトロリーバス(電車)が通り、平壌で運行されている最新型の電車が走っていました。市街地の末端は、陸上競技場や体育館が立ち並ぶ体育文化地区になっており、市街地全体が、モダンで明るく、文化都市のようになっていました。
感心したのは鉄道。以前の黒ずんだ木製の枕木はコンクリート製に代えられ砂利も綺麗に整備されていました。
鉄道は、龍岡温泉のある温泉郡にも走っており、温泉郡まで鉄道沿線を通りましたが、その沿線の農村風景も中々のものでした。この辺りは昔から製塩や養魚が盛んな地域でしたが、それが延々と続きます。気が付いたのは、ヒマ畑が広がっていたこと。ヒマは虫下しのヒマシ油で有名ですが、他の油脂にはないリシノール酸が主成分であり、潤滑油や化粧品にも使われる貴重な工業油脂です。
そしてブドウ。一昔前の棚仕立てではなく、西欧風の垣根仕立て、一本仕立てのブドウ畑が広がっており、ブドウ酒用のブドウのようです。朝鮮でブドウ酒といえば、カンゲ・ブドウ酒が有名でしたが、今はサリウォンなど各地のブドウ酒がブランド化されており、そのうち、南浦ブドウ酒も名を上げるのではないかと楽しみです。
国が責任をもつ「地方発展」、地域の特性を生かした「地方発展」。「地方発展」「地方振興」の極意を教えられたような気がする南浦の発展ぶりでした。
仲秋の名月
赤木志郎 2024年9月20日
仲秋というのは秋の真ん中、もっとも秋らしい秋だそうだ。そのときの月が満月でもっとも美しいといわれている。実際、今年の仲秋の名月はひときわ美しかった。でも、この日、昼間は夏のように暑かった。まだ残暑が続いている。
この日、朝鮮では墓参りの日。家族で山にある墓を訪ねるか、遺骨保管所に行って、花とお酒を供え故人を偲ぶ。春の清明節(4月8日頃)と同様だが、今年の9月17日(旧暦の8月15日)は秋が深まることや満月ということもあってひとしお心が沁みる日だ。
私の故郷は都会だったので、とくにこれといった行事はなかった。K子さんがいたときはこうした日に家で団子など供え物を作って行事をよくやっていた。私は里芋を育て料理するなど、とてもできないので何もしないで月を眺めるだけだった。
しかし、今年はSさんがお萩を作ってくれた。お萩は私の大好物だ。漫画の昔話でおじいさんがおばあさんに隠れてお萩を食べる話があったのを思い出す。老人は甘いものに目がないのだろう。10年以上の前のことか、饅頭(とくに大福餅)の好きな子供のAさんにお萩が食べたいなとなにげなく漏らしたら、翌日、大皿に山盛りのお萩を作ってきてくれた。大食のAさんならでのことだった。びっくりしてなんとか食べ尽くしたのを覚えている。
満月の月を眺め、お萩などをたべるのも、日本人らしい季節の迎え方だ。さて、日本に帰国した女性、子供たち(今は立派な大人)はどんな風にこの日を迎えているのだろうか。気になる日でもあった。
中秋の名月
魚本公博 2024年9月20日
9月17日は、中秋の名月。朝鮮では秋夕(チュソク)の日になります。朝鮮では、この日は4月7日ころの清明節と共に、墓参りの日です。
中秋の名月は、「芋名月」とも言われ、日本各地で、里芋を備えたり食べる習慣があります。私も里芋が好きなので、植えており、この日に掘り出して食べるのを習慣にしています。
今年は、春先にイノシシに掘り返され、植え直したので育ちが悪いのですが、何とか小さいものを収穫して食べました。
中秋の名月は旧暦の8月15日で「お盆」に当たります。朝鮮は墓参りですが、日本のお盆は先祖の霊が家に帰ってくる日です。
私の故郷では、子供の頃、集落の男の子が総出で、松明を掲げて、墓場の近くまで行き、「ショウロウ(精霊)様ー」と呼びかけた後、先祖の霊を集落まで連れて帰ります。そしてお盆の3日間は、各家で行灯様の提灯を並べて火を灯し、食べ物を備え、皆で会食します。
精霊では、お盆が終わり、先祖の霊を送り帰す、精霊(ショーロウ)流しが有名です。私の故郷ではそういう行事はありませんでしたが、母親の故郷では、初盆を迎えた家が藁で作った小船に食べ物を乗せて川原に並べ、花火を打ち上げ、火を付けて大野川に流していました。
先祖の霊を迎え、送り帰す。この感覚は日本独特のものではないでしょうか。
中秋の名月は、旧暦の「お盆の日」ですから、その日の満月を見ると、亡くなった父母や祖母のことを思い出します。昨日はあいにく曇りでしたが、雲の間に顔を見せる満月を見ながら、父母や祖母、戦死した叔父などに語り掛け挨拶しました。
「都に残ってあなたをずっとずっと見ています」の一念が生んだ源氏物語
若林盛亮 2024年9月5日
大河ドラマ「光る君へ」第33回は「式部誕生」、源氏物語がこの世に初デビューを飾る時期を描いていて興味深い。
まひろは道長のたっての願いで中宮・彰子あきこ(道長の娘)の女房として物語を書くことに専念する任務を受け容れる。
それは一条天皇の寵愛深かった前の中宮、今は亡き定子から帝の寵愛が現中宮・彰子に向けられるようにという道長の策であった。
当時、亡き中宮・定子の兄、藤原惟親が定子の女房だった清少納言の書いた「枕草子」で一条天皇の関心を定子に引き留めるなどして道長から朝廷政治の実権を奪おうとする惟親の様々な策謀があり、これを砕くための策、つまり彰子の女房となったまひろの書く物語で一条天皇の心を中宮・彰子に向け、野心家、惟親との政争に勝つための道長の遠望熟慮の策。
まひろは中宮・彰子の女房として藤とうの式部しきぶの名を与えられ、中宮の館、藤壺で彼女の書く物語が「俺の最後の賭だ」と道長からうち明けられる。それを重く受けとめる藤式部となったまひろ、彼女は「必ず書き上げて帝に」と固く誓う。
すでにまひろの書き始めた物語は一条天皇の関心を引き、続きができたら、まひろに会いたいというところにまで来ている。
そしてまひろは物語の第一巻を書き上げる。これを読んだ一条天皇は、直々にまひろに会う。
まず帝から出てきた言葉、それはまひろの物語にある一節をとらえ「朕の政事まつりごとに堂々と意見を述べたてたおなごは今は亡き母以外になかった」だった。また主人公「光る君」のモデルについて思い当たる節があるのか「あの書きぶりには腹が立った」など発せられる帝の言葉にあわや不興を買ったかとまひろたちは緊張させられる。ところが帝は一転して「されどそのたの物語はなぜか朕の心にしみ入っていった」と深い感動を述べる、そしてこの物語を自分一人で読むにはもったいない、皆が読めるようにせよとの有り難い言葉を藤式部に伝える。
道長の「最後の賭」に成功の曙光が差し始めた瞬間だった。
それはまひろの物語に賭ける一念が見事、花開く瞬間でもあった。
かつて「駆け落ち」を持ちかけた道長に恋成就を捨てる決心を伝え、「あなたには使命があります」、「私は都に残ってあなたをずっとずっと見ています、死ぬまで見つめ続けます」と誓ったその一念が藤式部ことまひろをして「源氏物語」という素晴らしい物語を書かせしめたのだ。
これは脚本家・大石静さんの創作だろうが、私はそこに「源氏物語」の真実があると信じたい。
そしてそのことを強く匂わせるとてもいい場面が出てくる。
道長から「褒美である」とまひろに一振りの扇が贈られる。その扇を開いてみたまひろはあっと驚く。扇には童子と童女が描かれ、空には小鳥が飛んでいる。それは少女時代のまひろが「鳥が逃げてしまった」と少年道長に訴えたとき「だいたい鳥を鳥かごで飼うのが間違いじゃ、鳥は空を飛ぶものだ」と道長が答えたあの懐かしい場面、二人のなり染めの頃そのものを描いた絵だった。
道長君、実に奥ゆかしいシャレ男、こんなことができるってとってもエエなあと感動した。
9月はじめ
赤木志郎 2024年9月5日
9月に入ってちょっと涼しくなった。朝がそうである。昼間はまだ30度以上だ。それにしても今年の夏は暑く雨が多かった。日本では平壌以上である。40度もなる地域ではどんなふうに過ごしているのか、ちょっと想像がつかない。私の家は冷房をつけ放しだがそれでもなかなか30度以下にならない。今日(2日)、温度計を見ると28度になっていた。
病院に行くとき見えるプール(ウォターレジャーランド)は人で溢れかえっていた。市内に行ったときに目立つのは、鴨緑江の洪水で避難してきた子供たちのバスだ。1万人以上避難している。市内のあちこちを見学している。バス1台にお医者さんと看護婦さんが付き添っている。能登半島地震で何もしない政府と大違いだ。
数日遅れの労働新聞で朝鮮大学の卒業班の学生たちが平壌に到着した記事があった。飛行場での写真は皆、嬉しそうだった。自分の祖国に抱かれ、学ぶことができるのだ。この数年間、訪朝できなかった一方、平壌は大きく変貌したので、その喜びはひとしおだろう。市内のどこかで偶然、出会うことになるかもしれない。
朝鮮では地方の全面的発展の政策が基本スローガンとなっており、毎年20個の郡に各種工場(基本は衣食住に関連したもの)を建設し、10年間に全国200ある郡すべてが均衡的に発展した現代的な郡にする闘いが取り組まれている。最近、地方で開かれた会議で病院や教育施設をも建設していく方針が採択された。こうして都市と地方の格差をなくしていき、国全体として強固で全面的に発展した国に建設させていく雄大な計画だ。
その推進力は「愛国」であり、「愛国で団結しよう」というスローガンをかかげられており、TVでは連日、各分野の多くの愛国者が紹介されている。一言で国中が沸き立っている。
その中で私も煽られ、じっとしておれなくなる。9月は心身とも充実していく季節だ。うだるような夏に別れを告げ、新しく出発していこう。
またまた「ウナギの話し」
魚本公博 2024年9月5日
先月もウナギの話しをしましたが。「面白かった」という声もあったので、再度「ウナギの話し」を。
日本は、今年の夏は酷暑で大変でしたが、朝鮮も例年になく暑い日が続きました。暑いと言っても最高35度程度でしたが、それでも暑かったです。
この暑さを乗り切るために朝鮮では「三伏」の日にケージャン(犬肉スープ)を食べますが、日本では土用の日のウナギです。
このウナギ、今、通っているランラン(楽浪)区域の市場で売っています。これまでも生きたものを売っていましたが20万ウォン(20$)以上もして手が出ませんでした。ところが今年は、すでに捌いたものを売っており、捌いたものはキロ3万ウォン(3$)、一匹は300gほどで安いので2、3匹買っておいて、土日の自炊の日に家で料理します。
作り方は「付け焼き」。コンロの火で何回か付け焼きした後、身をほぐして「櫃まぶし」風にしたものを飯の上に乗せ、そこに「付け焼き」で出来た濃厚な汁を掛けて食べます。
今年の夏は、もう7、8匹は食べています。栄養満点、精力増強ですが、それでどうということは在りません(笑い)
料理ついでに言えば、最近の定番は、鱒の鉄火丼です。普通は鮭ですが、鮭は大きすぎて一人では食べきれないので、鱒を使った鱒丼です。捌いて半分は丼にし、半分はマリネにしてパンに塗って食べています。
何か食べ物の話ばかりで恐縮ですが、もう老骨、健康管理には注意しています。
これから食欲の秋、皆さんも酷暑で落ちた体力を回復し、お元気でお過ごしください。
興味津津、朝ドラ「虎に翼」
若林佐喜子 2024年9月5日
朝晩は、大分、過ごしやすくなった今日この頃です。
衛星テレビを前に、NHKの朝の連続ドラマ「虎に翼」を楽しみに見ています。
もう内容はご存知だと思いますが、日本初の女性弁護士、判事、家庭裁判所の所長となった三淵嘉子さんをモデルに女性法律家、猪爪寅子(伊藤沙莉役)の活躍と家族の物語。
特に、9月2日からの第23週「始めは処女の如く、後は脱兎の如し?」は、実際に、三淵嘉子さんが次席裁判官として担当した「原爆裁判」にまつわる内容なので、どのような展開がくりひろげられるのか興味津津です。
「原爆裁判」とは、1955年に、広島と長崎の被爆者5人が、国に損害賠償を求めて東京、大阪地方裁判所に訴訟をおこし、1963年12月に、「原爆投下は、無差別爆撃で国際法違反」」とする判決が言い渡された裁判。日米両政府が原爆の責任から目をそむける中、下された画期的な判決で、その後の被害者救済にもつながったと言われています。
国の代理人は、「日本は、米国に対する損害賠償を平和条約で放棄している」の一点張り。相当な政治的プレッシャーがあったことは想像できます。
来年は戦後80年、日本で「新しい戦争」の脅威、不安を言葉にする人々が増えていると言われます。朝ドラを見ながら、改めて考えさせられました。「原爆投下は、無差別爆撃で国際法違反」。原爆投下、即ち、原爆の使用。これまで、無辜の国民に対して原爆を使用したのは唯一、米国のみ。日米同盟新時代の中にあって、核抑止力の強化が取り上げられていますが、この歴史的事実に対して、唯一の被爆国である日本、日本人としてしっかり向き合うことが問われているのではないでしょうか。
4年ぶりの旅行
赤木志郎 2024年8月20日
平壌市内から地方に出かけるのはコロナ閉鎖もあり4年ぶりだった。でも遠い所には疲れるので3時間以内でいける平安南道にある龍崗温泉に出かけることになった。
私はそこにはかつて2回、療養所に入院療養したことがあるので、その効用はよく知っていた。とにかく若返るのである。ラドンを含む塩化温泉で関節炎や皮膚病に効果があるという。たった2泊で4-5回入っただけで皆、顔色がよくなった。よく眠れたという。若い人には特別な変化は感じなくても、高齢者には効果が感じられる。会議や情勢討論、原稿執筆の日々から解放されたのも気分を転換させる。
いたく満足した気持ちでいざ平壌に帰ってみると、まだ蒸し暑い夏のさかり。いっぺんに身体が元にもどったようだった。そのうえ、メールが溜まっており、新聞などを読むのに半日以上かかった。さまざまなニュースに接して頭脳が動きはじめた。世の中の動きを知ってこそ、いろいろなことを考えるようになる。毎日ニュースを知って生きることが重要だなと今更のように感じた。これも温泉旅行の効用かもしれない。
刺激を受けた8月
若林佐喜子 2024年8月20日
残暑お見舞い申し上げます。
台風の便りが伝えられる今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
この夏は、コロナ禍の終息にともない4年ぶりに、皆で、ナムポ(南浦)市の隣にあるリョンガン(龍岡)温泉に2泊3日で行ってきました。
8日の朝、日本人村を出発。ピョンヤン、ナムポ間の高速道路の入り口にて、車両通行料金の支払いがスマホ決算にちょっと驚きで、スマホなしの私たちの生活の立ち遅れを再認識しました。
すでに稲穂がつきはじめた田園風景を目にしながら、11時半頃に、水素イオンとラドンが含まれ、高血圧、関節炎、神経痛、腰痛、婦人病、慢性胃炎、皮膚病などに効果があるリョンガン温泉に到着。温泉浴室付のツインルームの宿泊所に入る。浴室のドアに注意書きがあり、15分以上は禁止、飲酒後は禁止、高齢者は必ず介助者付とある。浴槽が高く捕まる場所がない!? 後期高齢者の男性陣4人、高齢者の女性2人なのに・・。「ここでは、老老介護だね」と、言いながら思わず大笑い。滞在期間、しっかり温泉につかったせいか、帰路の朝には、「10年若返った」「身体が軽くなった」との声。確かに、初日の疲労感あふれたお顔が皆、すっきり、さわやかに。私は、お肌がすべすべ、心身ともにリフレッシュして大満足。
10日、宿所前で記念写真を撮り、帰路へ。昼食は、ピョンヤンホテルのレストランで久しぶりにお寿司を満喫。
待っている時に、レストラン内のテレビでキム・ジョンウン総秘書が8.9日に平安北道、水害被害地域を再び訪問したニュースが流れました。特に、保育、教育問題は天が崩れても絶対に譲歩できない第一の国事であるとして、災害復旧期間中、水害民家族らの子供、学生たち全員、老人と病弱者、栄誉軍人と乳幼児の母親ら計1万5千余名をピョンヤンの4.25旅館、閲兵訓練基地にて、国家の負担と責任で保護、サービスを提供するという発表がありました。
思わず、「凄いことだね」と、つぶやいてしまった。周りのお客さんたちが嬉しそうに見入っていたのが印象的でした。
近年の世界的な異常気候による今回の洪水被害に対して、洪水防止能力を科学的に打算して、より安全な場所に「農村文化都市」として最短期間(2、3ケ月)で復旧建設をするという。すでに人民軍兵士と青年たちが平安北道の復旧建設現場に13万人、その他、計30万人が志願して旧ピッチで復旧作業がおし進められている。
つい、能登半島地震での災害復旧状況や南海トラフ地震への不安の中で生活する日本の人々の姿が重なり、国、政府が国民の命と暮らし、国の未来である子供たちに全的に責任を負う朝鮮の姿に改めて強い刺激を受けた8月の私でした。
「笛は聞くものです、見るものではありません」よくぞ言った彰子ちゃん!
若林盛亮 2024年8月5日
いつもの大河ドラマ「光る君へ」、先週の第28回「一帝二后」、一人の帝に二人の后という前代未聞の出来事編のエピソード一つ。
一度は出家させた中宮(帝の后)、定子との愛に溺れ、政治を疎かにする一条天皇を定子と切り離すために道長は姉、詮子の「あなたも血を流す時が来たということよ」との叱咤を受けてついに娘、彰子を帝に后として差し出す決断を下す。
道長も決断を迷った娘、彰子はまだいたいけな少女、しかも常に無表情、無感動、というより常に悲しげで愁いを帯びうつむき加減で何を聞かれても自分の意見も述べず、何を考えているかわからない不思議な少女。おそらく幼いながら藤原家の娘として政略結婚の定めにあることを自分の宿命として受け容れ、自分の感情を押し殺して生きているのだろう。
ドラマではそんな彰子の意外な場面が出てくる。
一条帝が「朕の笛を聴かせよう」と彰子の元を訪れる。帝の笛をうつむいたまま聴く彰子に一条帝は「なぜ朕を見ない」と尋ねる。しばらく間を置いて彰子が答える。
「笛は聴くものです、見るものではありません」!
この彰子の意外な答えに周囲の女房連中は驚愕の表情を隠さない。
一条帝は「参ったなあ」の一言・・・
私はこの一場面でいっぺんに彰子ちゃんのファンになった。
この一言に込めた彼女の強い意志、言いたかったことを私流に解釈すれば「私はあなたに惚れたはれたでここに来たんじゃない、あなたが愛に溺れて政治をよくやらないから私が来ることになったんじゃないですか」!
そんな心中を「笛は聴くものです、見るものではありません」! の一言で言い切った彰子ちゃん、このセリフは素晴らしい。
そして彰子役を演じる少女っぽい見中愛さんの演技も光っている。
いつも無表情、無感動、悲しげで愁いを帯びる表情を維持するのも大変だと思うが、彰子が画面に登場するとその場の空気がどよ?んと淀よどむ。でもその無表情のまま、こんな強い意志をさらっと彰子が語るや空気は一変、画面はキリリと引き締まる。
まだ十代の女優さんだと思うが今回のセリフの語りぶりには唸らされた。
ドラマでは結局、この一件の後に一条帝は彰子を后とすることを承諾する。
「笛は聴くものです、見るものではありません」?よくぞ言った彰子ちゃん!
これからは彰子ちゃんにも注目しよう。そして見中愛という「女優の卵」にも。
再び衛星放送受信障害
赤木志郎 2024年8月5日
7月中旬、またBS衛星放送の信号がゼロになった。ゼロになるということは、チューナーかLNBか、それともありえない衛星自身の問題かしかないと考えていた。3つとも正常だという。強風が吹いたのでアンテナに問題があるという話があったが強風で鉄製のアンテナが歪むとは考えにくい。技術者に連絡したが、忙しくてすぐに来れないという。結局、2週間以上、日本のTVを見ることができなかった。
やっと技術者の方に来てもらうと、すぐに受信信号ゼロの原因が解明された。なんとアンテナを支えていた2個の支柱の一つがはずれ、アンテナの方向が大きく狂っていたのだった。下手すればアンテナ全体が落下しそうな状態だった。アンテナを注意深く見ればすぐに発見できる問題だった。しかし、私は鉄製のアンテナが簡単に壊れるはずがないという先入観をもっていた。
技術者の話によると、長年、手入れせず接合部が錆びついたからだという。直径5mアンテナは移転して10年以上経つ。移転した時に、油を塗っただけだった。雪や風雨にさらされ、雪を除くときに棒で網状のアンテナを下から棒で突いたり、箒で掃いたりし、でこぼこになっていた。もはや老体のアンテナだった。
人間でも歳いけば整備しなければならない。鉄製のアンテナならいっそうそうだ。
日曜日だったが、すぐに管理所の人に来てもらい、1時間以上かけてはずれた支柱をなんとか元に戻してもらった。つぎにLNBとアンテナの方向の微調整だ。それはスムーズにいった。単にスムーズにいっただけでなく、これまで見ることができなかったBS1や松竹東急の番組まで見ることができるようになった。
実はBS3が臨時的に能登半島向けのNHK総合放送が放映されていたのが、7月1日にうち切りになり、朝ドラや大河ドラマ、NHKニュースを見ることができなくなっていた。それがBS1を受信できるようなったので、それらを見ることができる。そればかりか、別の録画できるチューナーが3局しか受信できなかったのがすべて受信できるようになり、録画機能を有効的に使えるようになった。禍転じて福となすとはこのことだ。
めでたしめでたし。
道長の姉・詮子を演じる吉田羊さんは女優中の女優!
若林盛亮 2024年7月20日
またまた大河ドラマ「光の君へ」のよど号LIFE。
私は近頃、主人公のまひろ(紫式部)より存在感抜群の道長の姉,、詮子一筋になっている。
非情さと可愛い気、一見相矛盾するものを合わせ持ち、どちらもホンモノ。
決定的な時点で道長や帝を動かし朝廷政治を危機から救う詮子、自分が見込む弟・道長を愛し信じて、大事な局面で弟の政事まつりごとを力強く助ける、才気と深い愛情を持ったいいお姉さん。とても魅力的だ。
詮子の息子である一条帝は出家したはずの愛妻、中宮・定子に溺れて道長の建言も無視し政治を疎かにしている。ために都を大洪水が襲って多大の犠牲者を出した。陰陽師、安部清明は道長に強く進言する-帝を政治に顔を向けさせるには、帝と中宮・定子を切り離す他はない、そのためには道長の娘・彰子あきこを入内じゅだいさせること、帝の妻に迎える以外にないと-しかし道長はそれはできぬと拒む。
これを知った詮子は道長を自分の元に呼ぶ。
「おまえが今日まで政争に巻き込まれず、ここまでやってこれたのはただ運がよかっただけ。そろそろ身を切れということよ」と忠告。
これに「いつでも身を切る覚悟はできています」と答える道長、しかしまだいたいけな子供、彰子の入内だけはできないと拒む。
「それそれ・・・娘をかばうよき父親の顔をしてお前は苦手な宮中の力争いから逃げている」と厳しく批判する詮子、「私はねえ」と彼女は自身のことを語る。自分は父に裏切られ、夫の先帝の寵愛を受けられず、息子(いまの帝)を中宮に奪われた、でも自分はそれでもいいのですと言いながら道長に強く言い渡す。
「それはねえ、道長もついに血を流す時が来たということよ」、「彰子をお出しなさい」!
一瞬、驚きの表情の道長、「姉上がそのように私を見ておられたとは私は知りませんでした」と絶句。
素直な反応を見せた道長に詮子さんは厳しい表情を和らげ姉の顔になる。そして顔を寄せて弟にささやきかける。そのセリフがまたとてもいい。
「大事な弟ゆえ、よく見ておっただけよ」
厳しい表情が瞬時に弟思いの姉の顔に変わる、そしてさり気ない「大事な弟ゆえ・・・」の姉の語調への切り替えが秀逸。私は詮子役を演じる吉田羊さんの演技に惚れ惚れした。
「この方は女優だ」! そう思った。
私の恩人に「俳優の卵」がいたが、その人が初めて準主役の大舞台に立った時、舞台の彼女はまったく別人だった。舞台上のその人は国家反逆・軍脱走の恋人との森の逃避行という苛酷な運命を生きる波乱の純愛渦中のドイツ娘そのもの、これには私も唸った。
演劇女優の醍醐味は、自分とは全く異なる人間を演じることで、自分の人生では一生かかっても体験できない色んな人生を味わえること、人間を学べることだというようなことをその人は言っていた。
吉田羊さんは詮子という政略渦巻く朝廷政治の中を生き抜くいわば悪女的才女、そして愛し信じる弟、道長の「よき政事」をひたすら助けるよき姉の二面性を見事に演じ分ける素晴らしい女優さんだ。
吉田羊さんも詮子という平安時代の苛酷、波乱の貴族女性の人生を生きた人間を演じることをご自身、楽しんでおられるのだろう。それは演技というより吉田羊さん流の「詮子」創造だと思う。
「光る君へ」の中でこの方は存在感抜群、演技はピカ一だ。このドラマで初めてお目にかかった吉田羊さん、この方は女優中の女優、これからはこの人に注目したい。
ウナギの思い出
魚本公博 2024年7月20日
朝鮮では、これから7月15日、25日、8月14日がチョボク(初伏)、チュンボク(中伏)、マルボク(末伏)になります。伏せるほどの暑さということですが、その暑さを乗り切るため、この日は「ケージャン」(犬肉スープ)を食べます。
日本で「土用の丑の日」に、ウナギの蒲焼きを食べるのと同じです。
ウナギ料理は煙でいぶすと旨みが増します。それで西欧でもフューメ(いぶす)の文字がついた料理名が多いそうですが、その中でも炭火で焼く蒲焼きは理想的ないぶし方で世界最高のウナギ料理だとか。
ウナギは、小さい頃、自分で釣ってきたものを父親と一緒に料理した思い出があります。
私の地方では、50㌢ほどの竹ヒゴの先にウナギ針をタコ糸を捩って縛り付けたものにミミズを餌にして川の流れが入り込むような穴に数本差し込んで当たりを待つという釣り方でした。強く引き込むやつを引っ張りだした時の嬉しさは今でも思い出します。
家の前に幅2mほどの小川があって、釣り上げたウナギを持って帰ると父親が「おー釣ったか」と喜色満面。「こうするんじゃ」と教えてもらったのが「付け焼き」。甘い醤油のタレに、焼いては浸けてを数回繰り返す。こうやるとタレの旨みが増す。身は崩れますが、それを飯に載せて、濃密なタレを掛けて食べる美味さは格別でした。
今の蒲焼きは、串を刺して身が崩れないようにし、焼くのも2回しかやらないようです。それで父親が教えてくれた「付け焼き」は田舎風の邪道かと思っていたのですが、旅番組で四国の四万十川で父親が教えてくれた「付け焼き」のやり方で食べているのを見て、私としては「これぞ正道」と思った次第です。
身を崩して使うのは名古屋の「ひつまぶし」が有名。「ひまつぶし」みたいで妙な名だと思っていたのですが、尾張藩時代からの高級郷土料理で「櫃まぶし」でした。
これから盛夏、高温現象が予想されますが、蒲焼きでも食べて、暑さ乗り切ってください。
昔から夏の暑さを凌ぐというのでウナギやドジョウを食べる習慣がありましたが、平賀源内が宣伝して土曜の丑の日に食べることが定着したのだとか。
市場でも売っています。養殖ものですが、悪くありません。ちょっと値が張りますが、先日、買って、翌日、フライパン式のものを食堂に持って行ってみんなにも、お裾分け。ま、好評でした。
木炭で焼くなど出来ないし、コンロで焼くのもめんどくさいのでフライパンで焦がし気味に焼いて作ります。
「ええお姉ちゃんやったなあ」-77歳にして姉を想う
若林盛亮 2024年7月5日
前回書いた大河ドラマ「光る君へ」の道長と姉・詮子(あきこ)のやりとりを見て、なぜか私の姉のことを想った。道長と詮子のように姉と弟との間には独特の微妙な空気感がある。
私には長兄がいるが10歳以上歳が離れていて高卒後に都会の商社に行ったのであまり「一緒」の記憶がない。だから二人の姉にはさまれて私は育った。末っ子ということもあって特に5歳上の次姉には可愛がられた。
幼児の頃は「おままごと」に「お父さん役」で付き合わされた。姉の女友達らに「はいお父さん、ご飯ができました」と砂の入ったお茶碗をもらって「おいしい」と食べるマネをした。姉の友だち、「きれいなお姉さん」が喜ぶのが嬉しくて「ご飯、おかわり」! のお父さんを演じた。どうってないことだが、なぜかこのことを思い出す。
小中学生の頃は映画館によく連れて行ってくれた。初期は東映時代劇、中村錦之助、東千代之介の映画、次第に西部劇やローマ帝国時代のアメリカ映画を一緒に観るようになった。そのうち「理由なき反抗」や「エデンの東」のジェームス・ディーンの大ファンになった姉は私を置いて独りで映画を観にいった。「スクリーンの恋人と会う」のに私が邪魔だったのだろう。
私の音楽趣味も姉の影響が大きい。姉はよくポップ音楽を聴いていた。パット・ブーンやハリー・ベラフォンテetc.そのうちエルビス・プレスリーにイカレるようになってプロマイド写真を机に置いたりしていた。自然に私の耳にポップ・ミュージックが馴染んで、長じて高校生の私がビートルズからロックへ、「長髪の盛もり亮あきちゃん」になった責任の「一端」は姉にある。
ビートルズ縁の「特別な同志」OKと初デートの時、田舎の高校生にデート用の服などなくて姉が淡い青と空色の格子こうし縞じま、縮緬ちりめん地のボタンダウン半袖シャツを貸してくれた。初対面の相手は長い髪のいかにも都会育ちの夏のしゃれたホワイトのワンピース姿、姉のおかげで何とか釣り合いがとれた。きっと姉は「盛亮、がんばりや」! と心ひそかにわくわくしていたのかもしれない。
余談だが私の渡朝後、OKは母を慰めによく来てくれたそうだが姉とも親しくしたようだ。東京から故郷に帰った姉が妊娠した時、ママでは先輩格の6歳下のOKから出産育児の本や雑誌をもらったと手紙に書いてきた。
高三以降、私が長髪になって「昼間の社会」からずれていくようになったが、姉は「髪を切りなさい」とか干渉がましいことは言わなかった。心配はしたかも知れないが、「弟には弟の考えがある」、信じて見守るという感じだったのだろう。
東大安田講堂で逮捕された私が23日間の留置期限が終わる頃、刑事の「釈放されたら着替えとかいるだろう、親か親戚に知らせてやる」という誘導に「釈放」の幻想が芽生えてつい名前と住所をしゃべった。東京にいた姉が綾瀬警察署に面会に来たが、飢餓状態の私は姉の差し入れのおまんじゅうを一箱ぺろりと平らげた。そんな私を見て姉はぽろぽろ涙をこぼしていた。あの姿をいまも思い出す。小菅の拘置所にも夫婦で面会と差し入れに来てくれた。
最後に会ったのはよど号ハイジャック闘争を前にした時期、町田にいた姉と喫茶店で会った。「しばらくは会えなくなる」とだけ伝えた。姉は何も言わなかったが「身体には気を付けなさい」と言った。
朝鮮に渡った私と手紙の往来ができるようになって「あなたの黒のとっくりセーターを着てあなたを思い出しています」とか「夜空の星を見上げてあなたも同じ星を見てると思うとなぜか・・・」といったまるで恋人の手紙のようなことを書いてきた。
私たちが結婚を公表して家族が日本人村に来れるようになると姉が「村」に来てくれた。姉は私が結婚できたことをとても喜んでくれた。日本での私の行状を見て結婚して家庭に収まるような弟じゃないだろうとひそかに心配していたのかもしれない。
山あいの豊かな緑に囲まれた日本人村を見て「こんな自然の豊かな別荘地みたいな所に住むのは日本じゃ最高のぜいたくやで」と言いながら「感謝の心を忘れたらあかんで」と私を諭さとしてくれた。
帰国した私の長男、次男を琵琶湖観光や父母の墓参り、食事に連れて行ったり、なにかと面倒を見てくれた。
そんな姉の長男は初恋の女性との結婚を「ハイジャック犯の叔父」のためにふいにしたと母から聞いた。でも姉はそんなことはおくびにも出さなかった。
夫を数年前に亡くし姉は独り住まいだったが、認知症の症状が出始めて姉の長男が引き取ったと聞いた。以来、姉との音信はぷっつり途絶えた。おそらく姉とは生涯、もう言葉も交わせないだろう。
だから姉のことをぼけないうちに書いておこうと思ったのかも知れない。
「ええお姉ちゃんやったなあ」と思う。言葉をかけるとしたら「おおきに」しか浮かばない。
プーチン訪朝歓迎音楽コンサート
赤木志郎 2024年7月5日
プーチン・ロシア大統領の訪朝は、深夜到着からその日の夜出発という実質一日間の短い期間だった。主な道路や大きな建物にはプーチンの肖像画を掲げ、歓迎式典は金日成広場でおこない、会談や条約調印と記者会見、勲章授与式を行った後、歓迎音楽公演がピョンヤン体育館で行われた。その後、晩餐会ですぐに出発だった。密度の濃い日程だった.
日程の基本である会談、条約調印などが終わったあと、メインは朝鮮芸術人による音楽公演だった。
朝鮮の音楽は「朝鮮労働党万歳」、「愛国歌」、民謡「モランボン」、「我々の国旗」といずれも迫力のある力強い歌と踊りだった。ロシアの歌としてはソ独戦争のときの「正義の戦い」「ただ勝利一つのみ」、社会主義建設のときの歌「モスクワの窓辺」など。そして祖国愛を歌い上げた「祖国は何から始まるのか」「祖国について」など。自然にたいする愛着を歌った「白樺」「ボルガからエニセイ河まで」「カチューシャ」。すべての歌には深く熱烈な祖国愛で一貫されていた。とくに「立ち上がれ」という歌は倒れた英雄たちを歌いあげるもので、ロシア人観客の中には涙を流している人もおり、プーチン大統領も立ち上がって敬意を表していた。
どの国民、どの民族にとっても祖国愛がもっとも人々の魂を揺るがせるものだ。それを朝鮮の歌手が格調高く表現するのだから、ロシアの人々に心の琴線を激しく響かせるものになっていた。おそらくこの音楽公演がプーチン大統領一行にもっとも強烈な印象をあたえたのではないかと思う。
マスコミでは朝ロの軍事的同盟関係の強化が脅威だと報道していたが、自主独立のための軍事的協力は東北アジアの平和と安定を保障するものとして日本にとっても良いことだ。それを脅威とすることの方がおかしいのではないか。そのことを「祖国愛」にもとづく一体感、高揚感であふれる音楽公演会が示しているのだと思う。朝ロ両国の協力関係の基礎には朝ロ人民の互いの「祖国愛」にもとづく強い絆にあるということだ。
孫の名前、間違えました
魚本公博 2024年7月5日
この前、次男の誕生日にみんなと一緒に祝賀のメールを送ったのですが、孫の名を間違えてしまいました。女の子で、○イとなっている名を○衣と書いたところ、次男からの返礼の中で、○生だと訂正されました。
今、孫は全部で6人ですが、皆、名前が難しく覚えるのが大変です。
最近の子供の名は、戸籍登録で漢字の採用の巾が広がり、キラキラネームも採用されるようになり、宙をソラと読んだり、元来の漢字ではありえない読み方も多くなっています。
それにしても昔は、女の子であれば○○子というのが一般的でしたが、今では、子の付く名前はすっかり見かけなくなりました。代わりに美を使った名が多く、親御さんの「美しく育って欲しい」という思いが伝わってきます。
男の子も、最後に郎、夫、男などを付ける名が多かったのですが、今は、大谷翔平や内村航平の影響からか、○平も多く、その他、○斗、○人なども良く見かけます。
私は次男には、○太と付けたのですが、太は東日本に多い、ダイダラボッチという巨人伝説の影響から来た日本的な名前だというので付けた名前です。
平、人、斗なども日本的で日本回帰の気がして悪くありません。
所変われば品変わるになぞらえれば、時代変われば名も変わるということでしょうか。
孫の名の間違いに、時代の変遷を感じさせられたこの頃です。
野球監督の仕事
小西隆裕 2024年6月20日
野球の監督の仕事にはいろいろある。
その中の一つが試合の流れをつくることだ。
先日のソフトバンクVSヤクルト戦は、その典型を見せてもらった。
試合は7回裏、ソフトバンクの攻撃。2対0でヤクルトが勝っていた。
2番今宮、3番栗原、連続ヒット、4番の山川もそれに続いて、今宮、生還。打者は、最強打者、5番近藤。
この時、小久保監督は、一塁走者山川に代えて、ピンチランナー仲田を出した。勝負に出たと言うことだ。
近藤は、これに応えて、ヒットを畳み掛け、栗原生還して、試合は、2対2同点。塁上には、2塁に仲田、1塁に近藤。ともに俊足。
打者は、6番柳町。彼は、この日、ヒットを2本打って好調。
だが、監督が柳町に命じたのはバントだった。
柳町は、それに応えて、バント成功。
そこでバッターは、7番中村晃、このベテランが打ったのが左中間へのヒット。これで二者生還。
試合は、4対2,ソフトバンクの快勝だった。
このあっと言う間の逆転劇には、流れがあった。
監督の作戦とその意図を理解して応える選手たちのプレイ。その頭と心の流れが試合の鮮やかな流れをつくり出した。
野球の監督にはいろいろと仕事がある。しかし、この選手たちの心をとらえてつくり出す試合の流れからは、人の心を愉快にする絶品が往々にして生み出されるものだ。
恋を知らない道長の姉・詮子さん、でもとってもチャーミング
若林盛亮 2024年6月20日
いま私が入れ込んでいる大河ドラマ「光る君へ」、先週の第23回「雪の舞う頃」の道長の姉・詮子(あきこ)さんはとてもカワイイ! と思った。
詮子は現在の帝・一条天皇の母親だが帝の愛妻、中宮・定子を道長と共に政治的理由から出家に追いやった張本人でもある。帝の後妻として一族の元子と娶めあわせるため道長と図って帝の笛と元子の琴という協演の場を設ける。しかし帝は心ここにあらず物思いにふけるように途中で演奏をやめた。
こんな「お見合い」のまずい展開に道長と詮子は思案に暮れるが、そこから次のような姉と弟のやりとりが生まれる。これが実に面白いのでそのまま再現する。
詮子:帝の中宮(定子)への想いは熱病のようね
あんなに激しく求め合う二人の気持ちが私にはわからないの
お前にはわかる?
道長:・・・・・・
詮子:わかるはずもないわね。
・・・(ややあって)・・・
道長:「私には妻が二人いますが、心には別の女がおります。自分ではどうしようもありません、でももう終わった話です」
(“やっぱりね~”の表情の)詮子:下々の女でしょ、お前が捨てたのね
道長:「いや、その女に捨てられました」
詮子:エーッ、道長を捨てるって、どんな女なの!?
道長:「よい女にござりました」
詮子:どんな風によいの? ねえ、ちょっと教えて・・・
(すたすたとその場から逃げ去る道長)
詮子:何よ、自分から言い出しておいて~! ねえ、もっと聞かせなさいよ
道長の姉、詮子は男女の愛、恋というものを知らない。
上流貴族の名家、藤原家の娘として「女は政略結婚の道具」、それが当たり前の「女の道」という家庭で育ち、父・兼家の筋書き通りに時の帝の正妻、現在の帝の母として家訓通り、「朝廷政治を藤原家が握る」を実現した道長の姉、詮子。
だから栄華職にある道長をふったような女(まひろ)のことを「よい女にござりました」と男の心に残すような男女の愛の機微が理解できない、でも興味津々。
もう孫もできたいい歳をして「どんな風によいの? ちょっと教えて」と弟にせがむ才女・詮子さん、こんなお姉さんはとてもチャーミング! 詮子さんがもっと好きになった。
まあそれだけの話だが、この姉と弟の交わす会話は実に微笑ましくて心ほかほか、なぜか私の姉を思い出させた。
詮子さんみたいに才女でも栄華を極めたわけでもない、ごく平凡な83年の人生をつつましく生きてきた姉。けれどいつも私のような弟を信じ愛してくれた、「いいお姉ちゃんやったなあ」と思う。ドラマの姉弟のやりとりを見て、ぼけない内にいつか姉のことを書いておこうかなと思った。
東大生のガザ大量虐殺反対の運動
赤木志郎 2024年6月20日
6月中旬、TVで東大の50名余りの学生が大学構内にガザ大量虐殺反対のテント張りの様子を報道していた。あまりこうした報道はないので思わず見入ってしまった。大学当局は撤収の指示を出しているが、強制しないで静観している。
テント群の近くで集会がおこなわれ、500名ほど参加していた。リーダー格の学生がインタビューに応じていたが、ごく平凡な普通の人だった。活動も呼びかけが主でいたって平和的な運動だ。そのまま企業に就職してもおかしくない学生だった。
57年前の1967年10月、佐藤首相訪ベト阻止羽田闘争を契機に学生運動の高揚が始まったが、その頃のことを思い出した。11月の佐藤首相訪米阻止羽田闘争の前夜には駒場の教養学部に泊まり込み、翌朝、大学祭に来た父兄たちの前でデモストレーションをおこない、羽田に向かった。
東大闘争は、68年大学封鎖をしている全共闘とそれに反対する秩序派との闘いが熾烈になり、テレビで報道を見ていた私は全共闘系が負けるのでないかと危機感を抱き、69年1月安田講堂に立てこもり逮捕され、10ヶ月後、保釈になった。機動隊の前に学生は手も足も出ない状態に陥っていた。革命に身を投じることを決心し、赤軍派に参加するため東京に向かったのは12月24日。そしてハイジャック・・・。
走馬燈のようにめぐる過去の日々を思い出しながら、現在の学生運動の様子を眺めていた。
私の学生運動への参加は、階級闘争を説くマルクスレーニン主義への理解もあったが、動機としては日本が再び戦争を行ってはならない、軍国主義をやってはいけないという思いだった。ベトナム侵略戦争の荷担はまさに戦争への道だった。いわば、日本という国の運命と自分を結びつけていたといえる。今の東大生はどうなのか、詳しく話を聞いたわけでないけれど、ガザ無差別虐殺を黙ってみてはならない、人間としての良心が許さないというような人間の根源的な生き方に触れているような気がした。だから左翼的な匂いが一片もなく、素朴な人間性だけを感じるのだと思う。
赤軍派として活動していたとき、東京の高校生から「銀行に就職した普通の同窓生が革命闘争に参加するようにどうすれば良いのか」と聞かれたことがあった。私は「我々が蜂起したときにそれを見て態度を決めればよい」と答えた。高校生は唖然としていた。そのとき普通の人々が闘いに立ち上がることを考えてなかった。
ジャン=リュック・メランション(「服従しないフランスLFI」)はガザ虐殺に反対するデモ行進に際し、「あまりに大きい不正と不平等、侮蔑に抗する、「意識(良心)の蜂起」の時が来ている」と述べた。
かつて、私たちは「前段階武装蜂起」で人民の覚醒を促し革命を展望したが、今は、民衆自身の「良心の蜂起」により社会を変えようとしている。同じ「蜂起」という言葉を使っているが、民衆を信じ民衆に依拠した闘いの点で根本的に異なっている。
そんなことを考えながら、今、新しい時代を迎えているのでは思った。
久し振りの魚料理レストラン
小西隆裕 2024年6月5日
久し振りに魚料理のレストランに行った。
できたばかりの時だったから、もうかれこれ5年になるか。
中に入ると、昔と同じように、大きないくつかのプール状の水槽に大小100匹を優に超えるチョウザメの群が泳ぎ回っていた。
これを客の前で、網ですくい取ったものを調理してくれるのだ。
取ってくれた調理師の人に感謝して、予約していた食卓に向かった。
これは良い。目の前にテドン江、4、500メートル向こう、対岸にはピョンヤン市街が広がる。
焼酎で乾杯し雑談しているところにまず出されてきたのは、頭付きの刺身。
その頭に焼酎を少々注ぐと、頭がびくんと跳ねた。活け作りとはこのことだ。食べ物に手を合わせる昔からの風習も分かる気がする。
山盛りに持ってこられた、多分朝鮮製の青々としたわさびを醤油に溶かし、刺身を回して食べたが、その新鮮さは最高だった。
その後出されてきた煮物、和え物などもなかなかの味だった。悪くない。昔と比べて料理の腕は確かに上がっている。などと、ビールのジョッキなども空けながら、わいわいがやがややっている中に、ピョンヤン冷麺など主食の後、コーヒーやケーキなどデザートが持ってこられた。それが、また、良かった。
2時間ほどの楽しい時間を過ごして、帰りながらレストランの他の部屋も覗いてみた。案の定、どの部屋にも客が、家族連れ、アベック、大勢寄り集まって、思い思い皆楽しそうに食事していた。
やはり、この店は腕が上がっている。評判がいいのだろう。
しかし、腕を上げているのはこの店だけではない。この間、朝鮮全体の水準が上がっている。テレビなどを観ていても、料理番組がよく出てくるし、各種料理の品評会などもよくやられているようだ。
人々の生活の水準が上がっていくのは、見る方にとっても気持ちのよいものだ。
清少納言に枕草子執筆を示唆したのは紫式部だったのか!?
若林盛亮 2024年6月5日
大河ドラマ「光る君へ」は毎週、興味が尽きない。
第21回は「旅立ち」、まひろ(紫式部)の父、中国語を解する藤原為時が国司・越前の守として宋人の「越前開港要求」を拒む任務を藤原道長から受け、まひろも都を離れる篇だ。父の任期期間中までとはいえ都を離れることはまひろには道長との別離を意味する。「私はかの地で生まれ変わってきます」と道長に万感をこめた口吻のシーンはとても絵になるものだった、けれどそれは言葉で語れるものじゃない。
それとは別途に今回のドラマにはとても興味深い“発見”があった。
それは源氏物語と並ぶ平安文学、というより日本古典文学の粋、枕草子の誕生秘話だ。
紫式部と清少納言が同時代を生きた人物だということを知ったことは前に書いたが、枕草子の誕生に紫式部の関与があったというのは驚きだった。もちろん脚本家・大石静さんの想像による創造だと思うが、でも「なるほどネエ~」と妙に納得させるものがある。だから歴史ドラマは面白い。
ききょう(清少納言)とまひろは共に教養ある才女として親友、ききょうはよくまひろを尋ねて宮廷内の出来事、悩み事などを話す、そんな関係に二人はある。
ききょうの仕える帝・一条天皇の愛妻、中宮・定子は兄・惟これ親ちかが道長の命に背き地方への出仕(都からの追放)を拒むことで咎とがを受け、その妹である定子は最愛の帝から「宮廷から出よ」の命を受けたことに絶望、出家を決意する。実は彼女のお腹には御子が宿っていたが子の安全のため、天皇にも事実を隠していたとかそんな悩みに健康も害する中宮の失意をいかに慰めたらよいのか、ききょうはまひろに持ちかける。
まひろは以前、ききょうから聞いた「高価な紙」が帝と中宮に献上された話に思いが浮かぶ。
その「高価な紙」に帝は司馬遷の「史記」を書き写しているとききょうから聞いていたまひろ、そして中宮から「私は何を書けばよいかしら」と聞かれた時、ききょうが「枕ことばでもお書きになれば」とお答えしたが「なぜだと思う?」の問いにまひろは、「史記が史記物しきもの(敷物しきもの=枕)だからですか?」と即答、これにききょうは「キャハ、よくおわかりのこと」とくすくす笑う。そのノリで中宮からその「高価な紙」を分け与えられたが、それで何を書いたらよいかとまひろに尋ねる。まひろは「その紙に中宮様のために何かお書きになったら」と提案、そして「帝が司馬遷の史記しきだから中宮様には春夏秋冬の四季しきとか」と示唆を与える。「まひろさま! 言葉遊びがお上手なのね」と驚くききょうの清少納言。このやりとりの妙に笑い合う二人、互いに得心の表情でうなづき合う。
こうして清少納言の傑作随想「枕草子」が生まれるようになった。
二人の才女の「言葉遊び」から古典的名作が生まれたというのは、まさにそれ自体、ドラマだ。大石静さんの創作とはいえ、じゅうぶん「ありえる」。才女二人の会話の絶妙な言葉のやりとりも「あの二人なら」と思わせるもので、とってもいいお話ではある。
私は大石静版の「枕草子誕生秘話」をこれから信じることにする。
イノシシ捕獲しました
魚本公博 2024年6月5日
3年ほど前から、よど農園の周辺に、イノシシが出没するようになり、作物が荒らされて困っていると、このコーナーで書いてきましたが、数日前に、一匹捕獲しました。
罠に掛かっていたそうで、管理人の人たちが、縛った足に棒を通し数人で担いで持って行くのを見かけました。
重さは150㌔ほどで、イノシシとしては中型だそうです。よど農園周辺で出没するイノシシの足跡は10㌢ほどもある大物なので別物かも知れません。他にも、足跡3㌢ほどの小型の足跡も見かけます。
イノシシは夜行性で行動範囲が広く一日に数㌔も移動するそうで、村の山野に生息しているのではなく、隣の山から降りてくるのではないかと思っていましたが、罠に掛かっていた場所も隣の山との境なので、そこから降りてくるようです。
それで、これに懲りて、我が村に来るのは控えるのではないかと期待しています。
ま、それだけの話しですが、「イノシシ出没」とお騒がせした手前(な、ことないか)、ここに「イノシシ捕獲しました」ことをお知らせする次第です。
先日、サツマイモを植え、今年は食堂からも近い所に、犬がいるので近寄らないのではと思って。
日本でも最近、クマやイノシシなどの獣が市街地にまで出没するニュースが増えました。
捕獲の専門家も増えてBSでも見かけます。
原因は気候不順で、山に食料が減っていうからだとか、地域の過疎化で、住民区域に出没するようになったという説です。
政府の「地域を見捨てる」政策で、進む過疎化。そこで増えた獣の人間居住地への進出。
そういう意味では人災か。それへの警告か? 自然の警告かもしれませんね。
イノシシ捕獲の話しを聞きながら、そうしたことを考えてしまいました。
学生運動の新しい波
小西隆裕 2024年5月20日
今、学生運動の新しい波が生まれてきている。
イスラエルのハマスを絶滅させるという無差別空爆により、パレスチナの4万を超す子どもたち、非戦闘員大衆が虐殺されていることに対する抗議の闘いだ。
米コロンビア大学を発火点とする闘いがイスラエルだけでなく、その後ろからそれを推進、促進する米欧帝国主義、覇権主義勢力に反対して、全米へ、欧州へと広がりながら、日本の大学にまで広がってきている。
これを見て、思い起こされるのは、50数年前、ベトナム戦争に反対し、日本政府のこの戦争に反対して立ち上がったわれわれの闘いだ。
あの時と極めて似ていながら、大きく異なっているのは、闘争対象である米国や日本の帝国主義、覇権主義勢力の弱体化だ。
あの時とは比べものにならないほど弱体化している。彼らは、この中東での戦争と同時に、ウクライナ、東アジアでも、三正面で窮地に陥っている。
半世紀ぶりに相対するこの闘いで、どう闘うかが、われわれ自身にも切実に求められていると思う。
平安時代の女性は「男の心を動かす魂の力」で政治まつりごとをやった
若林盛亮 2024年5月20日
大河ドラマ「光る君へ」は実に興味深い。
平安時代の政治は朝廷政治、政治は貴族・公家の男がやるもの、貴族社会の女性は政略結婚の道具以外の何ものでもなく政治からは排除されていた。でも第18回「岐路」を見て、平安時代の女性がどのように政治に関わったかがよくわかった。
今回の「岐路」は、独裁的権勢を振るった道長の長兄、関白・藤原道隆が病死、後継関白を巡る政争を描いていた。道隆は息子の惟これ親ちかを後継関白にするため生前から一条天皇にも圧力をかけていたが朝廷公家の間で惟親に人望がないのを知る一条天皇は道隆の弟、道長の次兄・道兼を関白に任命、しかし就任と同時にその道兼も急死、後継関白を巡る政争が起こる。道隆、道兼の弟、道長か? 道隆の息子、惟親か? 道長は醜い政争までして関白になる気はさらさらなく、他方、惟親は自分の勢力を集めていく。一条天皇は仕方なく後継関白を惟親とすることを心の内で決める。
これを知った一条天皇の母親で道長の姉、詮子あきこは関白になろうとしない道長を呼んで「お前が関白になるべき」ことを強く説く。詮子は幼い頃からの弟、道長の人となりを見て、彼こそ関白となりうる逸材と見ていた。
そして詮子は息子である一条天皇に深夜にもかかわらず強引にも天皇との直談判に及ぶ。惟親はお家の繁栄しか考えず関白ともなれば天皇は利用されるだけの飾り物になるだけ、自分は幼い頃から弟道長をよく知っている、人の心を知り人に優しく自分の栄達を考えない人間、だからこそきっと天皇の支えになる政治をやる道長をぜひ関白に! と懇願する。しかし一条天皇にとって惟親は愛妻、定子の兄でもあり迷いつつも「もう惟親に決めています」と断る、けれど母の思いもよくわかる。
結局、一条天皇は道長を右大臣に任命、関白は空席とした。事実上、道長に朝廷政治を託すことになる。
政治を託された道長はある夜、月を見上げながら、まひろ(紫式部)に駆け落ちを持ちかけたしのび逢いの夜を想う。「あなたには世の中を変える使命があるのよ」と敢えて恋を捨て「誰よりも愛おしい道長様がこの国を変えていくお姿を私は死ぬまで見つめ続けます」と熱く語ったまひろの言葉を思い浮かべる。
そんな道長はある夜、かつてのしのび逢いの場所にまひろを呼び出す。道長の様子を見て「(道長は)昔の己おのれに会いに来たのだ」と直感するまひろ。「でももう語る言葉は何もない」と道長と少し目を合わせるだけ、言葉を交わすこともなくその場を去るまひろ。でもそれだけで道長に心は通じたはずだ。
いまの政治を憂い世を変えることを願う二人の女性、道長の姉・詮子、そして道長の恋人・まひろ、直接、政治に関わることはできずとも志に生きる彼女たちは、自分の息子や弟、恋人という「男の心」を動かす「強い魂の力」を持っていた。
自分の考えを持つしっかり者の姉、詮子、そして男に優る能力を秘め持つ道長の恋人、まひろ、二人の女性を見て平安時代の女性がどのように政治に関わったのかを知った。
ドラマの詮子とまひろは本当にカッコイイ! この二人がいてこその道長だったのか! ますます「光る君」が見たくなる。道長君、頑張れよ。
「蜂」騒動
赤木志郎 2024年5月20日
3週間前よりBS衛星TVの信号が時々ゼロになる問題が起こっていた。昼間、信号が来るのだが、だんだん信号がまったくこないときが多くなった。衛星TVの信号は、衛星からの電波の発射、それを受け止めるパラボアアンテナの先についているLNB、そしてチューナー(受信機)が正常であってこそ、受信できるようになる。衛星に事故があったというのはまず考えられない。チューナーも正常でLNBに送る15Vの直流電流も出ている。とすると、LNBに問題があると考えた。しかし、来てくれた技術者はLNBが故障するのはありえないという。
2週間後、専門家から別の大型アンテナのLNBに鳥が入って電波を遮断するということがあったので、こちらでも虫が入ったのではないか、LNBにビニールテープを貼って虫が入るのを防ぐのが良いという連絡が入った。
それでLNBにテープを貼ったが、直前まで見えていた衛星TVの信号がゼロになった。それでLNBを分解していったら、なんとそこに比較的大きい蜂がいた。つまり作業中に蜂が入ったのだ。蜂を追い出し、透明のテープを貼って組み立てたら、衛星TV信号が正常になった。
これまで蜂がLNBに出入りし、信号がゼロになったり正常になったりしていたのだ。信号ゼロの原因が明確になり対策も講じられたので、今後、安心してBS衛星TVを見ることができる。蜂は再びやってきたが、テープを張っているのでもはや入って来れない。きっと春の陽光を浴びて熱を帯びたLNBの中が清潔で気持ち良かったのだろう。しかし、ここは君の住処でないのだよ。
お祭り
魚本公博 2024年5月20日
BSで「日本の祭り」という番組があり、時々見ています。
有名な祭りだけでなく、地域の小さな祭りも紹介され興味深いです。
今は、どの地域も過疎化し、祭りを維持するのも大変なようです。そういう中でも、稚児は男児となっていたのを女児にするとか、近くの集落も参加させるとか知恵を絞っています。
地方の色々な祭りを見るたびに、私も、子供の頃の村の祭りを思い出します。別府市街地に隣接した石垣という農村地帯の例祭で、お神輿が出て、行列や獅子舞が続くという単純なものでしたが、私が小学6年の年には子供御輿も出て、担ぎ手になりました。
そして、神社に奉納する神楽、これがめっぽう面白い。天照大神が天岩戸に隠れる話しから、素戔嗚尊のオロチ退治までを面をかぶった踊りで演じる岩戸神楽ですが、その中で青鬼が舞台から飛び降りて子供を脅したり、大黒様・恵比寿様が飴や菓子をばらまく場面もあってドキドキ、ワクワクしながら見たものです。
「日本の祭り」では、最近、郷里大分県の中津祇園祭りをやっていました。この祭りは、山車の屋台で子供が踊りを演じるという古い形が残されており、それが終わると市内を猛スピードで引き回し、山車同士をぶつけ合うという勇壮なものです。
感心したのは、この祇園祭りが昔から、若い世代が引き継ぐという精神で行われてきたという点です。祭りは、長老たちの祝い唄で始まりますが、その最後の歌詞は「若い衆に頼む」です。そして現場指揮も若者がやり、山車の速度を決めるコンコンチキの鉦を打つのも高校までの若者がやり、代を引き継いでいきます。
地方の過疎化が進む中、何としても祭りを維持していこうとする各地の努力を見るにつけ、どの地方地域も「若い衆に頼む」の精神で頑張ってほしいと思います。
令和維新
小西隆裕 2024年4月20日
泉房穂さんが「令和維新」を提唱した。
「議会開設」、「廃藩置県」を行った「明治維新」に対して、
「首相公選制」、「廃県置圏」の「令和維新」だと言うことだ。
近代150年の歴史を経て、新しい革命の提起。
政治の閉塞状況が続く中、夢のある問題提起だと思う。
そこでもう一声、「脱亜入欧」の道を選んだ「明治維新」に対して、
「覇権的多極秩序」から「反覇権的多極秩序」への「令和維新」というのはどうだろうか。
下級武士が主力を担った「明治維新」。
広範な国民皆が夢の花を咲かせる「令和維新」が近づいているのではないだろうか。
「光る君へ」で知った清少納言と蜻蛉かげろう日記
若林盛亮 2024年4月20日
私は若い頃、あまり文学とは縁がなかった。友人に文学好きや作家志望はいたが、私はなぜか文学を読みたいと思わなかった。自分がいかに生きるかに精一杯でそんな心の余裕がなかったのかも知れない。
たしか50代頃から文学の醍醐味、面白さがわかるようになったかな、と思う。一定の人生体験が必要だったのかも知れない。
4月7日放映のNHK大河ドラマ「光る君へ」第15回には平安文学の粋とも言える「源氏物語」、「枕草子」、「蜻蛉日記」の豪華な女流作家達が顔を揃える。なんでもない日常の普通の人としてこんな豪華メンバーが揃うなどというのも大河ドラマの魅力だろう。これらが同じ時期の作品だということも初めて知った。
まず「枕草子」の清少納言。
ドラマではまひろ(紫式部)の友人、“ききょう”として登場。夫も子供も捨て宮中での女房という仕事に生き甲斐を見いだす、ばりばりのキャリア・ウーマンだったことも初めて知った。
仕えることになった一条天皇の妻、中宮・定子から名前をいただく、「清の少納言」と。この名前もこれまで私の頭の発音では「清少/納言」的に「清少」と「納言」を区別していた。定子が名付けた「清の少納言」だから正しい発音は「清/少納言」なのだ。ちょっとしたことだけれど私にとっては数十年ぶりに誤りを正せた新しい発見だ。
次ぎに「蜻蛉日記」のこと。
まひろが石山寺詣でに行った折りに出会うのが「蜻蛉日記」の作者、道長の父、兼家の妻で道長の腹違いの弟、道綱の母だ。
まひろは、自分が幼い頃「蜻蛉日記」をよく読んだが「切ない心」とかがよくわからなかった、「でもいまはよくわかります」と作者に述べる。すると「心と身体は別ですからねえ」と「蜻蛉日記」作者の年輩女性が語る。この言葉にまひろは道長の告白をあえて断ったあの夜の逢瀬を想い出す。
「蜻蛉日記」の作者、藤原兼家の妻は兼家が他の女性に心を移し家に来なくなって以降、思うに任せぬ愛、子への愛など心の問題を日記に書くことで解決したと語る。
おそらく石山寺の「蜻蛉日記」作者との出会い、その体験はまひろ、紫式部が「源氏物語」を執筆する上で大きな影響を与えたことと思う。これも脚本家、大石静さんの創作かもしれないが・・・
清少納言が「枕草子」という随筆を残し、紫式部が「源氏物語」という物語、恋愛小説を残したのは二人の作家のキャリアというか生活経緯の違いから来るものだろうということがわかった。
“春はあけぼの やうやう明けゆく・・・”という随想のリズム感は、ばりばりのキャリア・ウーマン、清少納言の中宮を支える仕事に打ち込んでいたという生活感のなせる業だろう。
他方、まひろ、紫式部は道長との辛い恋、恋と志に揺れたりとかかなりドラマチックな生活経緯を経た人、だからある種の人間ドラマ、「源氏物語」が書けたのだろう。宮中での女官仕事に打ち込むあの“ききょう”、清少納言にはたぶんドラマ、物語は無理だったと思う。
このようにまひろの「光る君へ」はいろんな想像をたくましくしてくれる。
やはり大石静さんのシナリオの「創作」の素晴らしさのせいだろう。
春の祭典
赤木志郎 2024年4月20日
4月半ば、つつじ、れんぎょう、あんずなどの花がいっせいに咲いた。いつもなられんぎょうが先に咲くのだが、やはり今年は花が咲くのが遅いようだ。そこに急に暖かくなって同時に咲いたのだろう。マンスデーへの坂道にある桜の花も満開だった。花と緑に囲まれたこの日本人村にはキジが多く、ゆっくり散歩している。そしてウグイスが「ホーホッケキョ」と啼いている。まるで桃源郷にいるような気がするほどだ。
4月の楽しみと言えば、「春の祭典」という公演だ。今年はコロナ封鎖から解放され中国、ロシア、モンゴル、ベトナム、イタリアなど多くの芸術代表団が訪れた。中国の場合は朝中友好75周年を祝っての代表団が訪れ、合同の公演がおこなわれ、上海曲芸団の公演もあった。ロシアは舞踏団、協奏団など多彩だった。日本と中国の海外同胞の芸術団はネットを使っての参加だった。
歌と踊りで圧倒していたのはロシア芸術団だった。シベリアの荒野を開拓する踊りは、自然の恵みと労働に対する愛着がこもっていた。軍人の戦闘的な踊りは皆が器械体操選手のようなきびきびした動きを見せていた。
今回、気になったのはロシアの歌手が朝鮮の歌を歌うとき、低音になってしまうことだ。民族によって音程が異なるからかしら、いつも聞くロシア民謡の腹の底からの力強い響きがない。同じ歌でも朝鮮の歌手とロシアの歌手では音の高さが異なっている。ロシア民謡を日本人が歌うともの哀しい響きに近くなる。ということは、ロシア人は音の高さが低いということなのだろうか。
反対に、中国人の場合、音の高さが非常に高い。朝鮮人の場合は中国人ほど高くないが日本人よりははるか高い。接待員の喋る声が高すぎて何を話しているのか、まったく分からない時がある。と、いろいろ考えてみた。
結論は、その国の歌はその国の人が歌うのが一番だ。日本人がいくらイタリア民謡を練習してもイタリア人のように上手に歌うのは難しいと言われている。むしろ、民族的特性を生かした方が、世界の人々にも愛されるのでないだろうか。
各国の芸術団が一同に集う「春の祭典」は、世界の各民族の良さを発揮し、人々を楽しませる絶好の機会だ。今年も私を充分堪能させてくれた。
今年もイノシシ出没-よど農園近況報告
魚本公博・よど農園管理責任者 2024年4月20日
一昨年以来、よど農園近辺にイノシシが出没して、農作業に支障が出て困っています。
今年も、周辺の原野に直径1m深さ50㌢にもなるような大きな穴があちこちに。狙いは、葛の根のようです。葛は、棍棒のような大きな根が地中深く張っており、それを掘り起こして食べるようです。
イノシシの足は、ひづめのようになっており、これと牙を使って掘り起こすようですが、ひずめの大きさは長さ10㌢ほどもあり、昨年の足跡に比べても巨大化しています。
今のところ畑への被害はあまり出ていませんが、イノシシはサツマイモが好物で昨年も全滅でしたので、これからが思いやられます。
農園で真っ先に採れるのはフキノトウ。フキは世界中で日本人しか食べない、日本だけの野菜だとか。30年ほど前に、旅行先で見つけて畑の近辺に植えたものですが、あちこちで根を張り、数カ所で群落になっています。
日本の野菜化したフキに比べると、スジが多く堅いのですが、野性味があって美味いです。
これからはアスパラガスの季節。これもあちこちに植え付け皆に好評な野菜です。
他の野菜も種蒔きしましたが、まだ寒くて芽生えがよくなく、蒔き直しが必要なようです。
巨大イノシシの出没とは物騒ですが、イノシシは夜行性だし、臆病で人間には近づかないとのことなので、一応、畑仕事は安心して続けています。
以上、よど農園近況報告でした。今後の状況は次の機会に報告します。
大相撲にわき起こった若い熱気
小西隆裕 2024年4月5日
少し旧聞に属するようになったが、大相撲春場所、いつもと違う活気というか熱気のようなものがテレビの画面を通じても伝わってきた。
それは、尊富士、大の里、二人の新鋭の登場によっているのは明らかだった。
入幕して間もなく、髷もろくに結えない二人が強い。最後は二人の優勝争いにまでなった。
単に若くて強いだけではない。根性というか精神が良い。特に尊富士などは、前日敗れた際、足首を痛め、担架で退場するほどだったのに、自力優勝を目指し、びっこを引きながら登場し、勝って優勝を決めたのだから凄い。
その上によかったのは、二人とも、久方ぶりに登場した日本人の若者だったことではないか。
これが日本人でなかったなら、ここまで盛り上がったことか。
もちろんどの国の力士であろうが若くて強い力士がでてくれば、熱気は生まれる。だがやはり、同じ日本人だというとどこか違ってくる。
これは、人間として仕方がないことなのだろう。
「一椀の酒で未練と決別」-“道長とまひろ”の恋、その2
若林盛亮 2024年4月5日
前回、「“道長とまひろ”恋の頂点に源氏物語の原点を見た」というようなことを書いたが、NHK大河ドラマ「光る君へ」、3月24日放映のそれは藤原道長との恋を捨てたまひろ(紫式部)の揺れる心を描いたものだった。
ある夜、まひろは道長の呼び出しの文を受け密会場所に向かう、そこで道長から結婚に踏み切る決意を告げられる。一瞬、顔がこわばるまひろ、でも藤原家のための政略結婚にようやく断を下した道長を励まし「結婚おめでとう」の意を表す。
その夜、帰宅したまひろの心中を察する弟が酒を満たしたお椀を差し出す、「姉上も召し上がったら?」・・・お椀を受けたまひろ、彼女はあおるように一気に酒を飲み干す。心の動揺を一挙に沈めるかのように・・・
私はそんな「弱さ」も見せるまひろ、紫式部が「かわいい!」と思った。
まひろとの恋成就のために「一緒に都を出よう」と決心を告げる道長の申し出を敢えて断り、「あなたには世の中を変える使命があります」、「私は都に残ってあなたをずっとずっと見ています、死ぬまで見つめ続けます」と気丈に自分の決心を恋人に告げたまひろだったが、いざその愛いとしい人が他の女性との結婚を決めたという現実を前にすればやはり心は揺れる。しかもその結婚相手の女性が彼女の知る権勢ある源家の娘、倫子という自分と心の通じる友であること、それを祝福しなければならない自分がよほど辛かったのだろう。
まひろ、紫式部は、心の動揺として噴出した道長への断ち切りがたい想いを「酒をあおって飲み干す」、当時の女性としてはしたない行為で断ち切ったのだ。
私はそんな彼女にとても共感を覚える。
「ちっぽけな愛などクソくらえ」!
よど号ハイジャック渡朝闘争を前に決意文を求められた私は「たとえ死んでも人民の大きな愛の中で生きる」というような自分の決心を書いたが、なぜかその最後に上記の言葉を書き添えた。それは赤軍派参加のためには終止符を打つしかなかった「京都最後の恋」への未練があったからだろう。
ちょっと品がないし、いま見れば書かなければよかったと思うような言葉だ。でもあの時の大事を前にした私にはああいう形ででも未練を断ち切ることが必要だったのだと思う。まひろ、紫式部がお椀いっぱいの酒をはしなくもあおるように飲み干したように・・・。
ピョンヤン到着以降、私の未練はすでに「時効の恋」となって記憶の引き出しの中に深く仕舞いこまれた。決意文に添えた「心の揺れ」戒めのあの少々品のない言葉のおかげかも知れない。
今後のドラマの展開では、まひろの道長への未練がましい場面はもうないだろう。まひろはひたすら前へ前へと進む、そして幾多の人生遍歴を経て紫式部として「源氏物語」執筆へと向かう、これは私の主観的願望であり主観的確信でもある。
私は、まひろをますます好きになった。
ロシアドラマと日本サスペンスドラマの共通性
赤木志郎 2024年4月5日
こちらではロシアドラマを見る機会が多い。最近、「女性内務員たち」が放映され見た。ソ独戦争末期、ある地方で男性の多くは前線に行ってほとんどいず、女性内務員(警察官)だけで事件に対応していた。秩序が乱れていた中で強盗殺人事件が多発し、そこに中央の反スパイ局から派遣された男性内務員が単に除隊した元内務員として女性内務員を助けていく。派遣されたのはその地方からドイツスパイが発信した電波をとらえたので、そのスパイを摘発するためだった。一連の殺人事件は、実は男性内務員が寄宿していた家の娘が起こしたものであった。その娘はドイツで訓練を受け、身分を偽って市責任秘書の娘として浸透し破壊活動をおこなっていた人物であった。そのことが暴露されるのは最後の場面であり、それまで誰が犯人なのかまったく分からない状況だった。犯人が意外にも近くにいたのだった。終わりは、その男性内務員と女性内務員責任者が結ばれるというハッピーエンドだ。
この展開の仕方は、日本のサスペンスものでも似ていると思った。数多く放映されるサスペンスもの、刑事ものには、真犯人が近くにいた意外な人物だったというのが多い。
これまでサスペンスものに関心がなかったが、人気があるのはその意外な展開があるということなのだろう。そして、ロシアドラマにもその共通性があったのも「意外」な発見だった。
終活
小西隆裕 2024年3月20日
最近は、「就活」ならぬ「終活」が盛んになっている。
今朝もNHKの海外放送を聞いていたら、「終活」についてのご案内をやっていた。
これも、身寄りのない老人が増えているためだという。
核家族化、未婚者や離婚者の増加、家庭崩壊、等々、理由は、近年、増えているのではないか。
その反映としての「終活」案内だと思う。
いやいや大変な世の中になったものだと思って聞いていたが、わが身を振り返った時どうなるのか。
私たちにとっての「終活」、それはやはり、拉致容疑逮捕状の撤回を勝ち取っての帰国以外にない。
そこで改めて思ったのは、全員、後期高齢を超えた私たち男4人の年齢だ。拉致容疑逮捕状撤回の帰国闘争も「終活」として推し進めることが問われてきているのではないか。
“道長とまひろ”恋の頂点に「源氏物語」の原点を見た
若林盛亮 2024年3月20日
日本のいや世界の古典的名作と言われる紫式部の「源氏物語」だが、私はずっと偏見を持っていて読みたいと思わなかった。どうせ平安貴族の女遊び道楽、「恋愛ごっこ」だろうと全く読む気が起こらなかった。でもいまは読んでみたいと思う。
NHK大河ドラマ「光る君へ」、3月10日放映「月夜の陰謀」篇は藤原道長とまひろ(紫式部)の恋の頂点、そこに紫式部が極めた愛の真実を見た思いがしたからだ。
父、兼家から摂政関白として朝廷政治を藤原一族が支配することを期待されている末子、三男の道長は政略結婚まですでに決められている。まひろへの想いを断ち切れない彼はついに決断を下す。まひろと添い遂げるため藤原家を捨て都を離れ、海の見える遠い国でまひろと生涯を共にする、と。
時あたかも帝・花山天皇を出家に追い込み、帝に嫁がせた兼家の娘、道長の姉、詮子の子を帝に立て藤原家が朝廷政治を支配する、そんな「月夜の陰謀」成就を前にした時。まさに道長が自らの運命を決める決断を迫られた時だった。
道長はまひろに想いを伝える和歌を送る、まひろは漢詩で応える。ちなみに和歌は自分の心を伝え、漢詩は志を表すものとのことがドラマでは語られる。数通のやりとりの後、二人は夜のしのび逢いで互いの気持ちに決着をつける。
藤原家を捨てまひろと都を離れ愛する人と添い遂げる決心を道長から告げられ、まひろは「うれしゅうございます」、「あなたが好きで好きでたまりません」と自分の道長への想いを熱く伝える。しかし回答は断固たる「一緒に行くことはできません」!
道長への恋と彼女の志は同じ方向を向かない。
「あなたはこの世を変えるために高貴なお家に生まれた方です」、「あなたには使命があります」、「私は都に残ってあなたをずっとずっと見ています、死ぬまで見つめ続けます」!
彼女は母親と親友の無念の死が世の理不尽から来るものであること、そしてこの世を変えることができるのは人々への熱い心を持つ道長しかいないと確信している。
道長との恋を敢えて断ち、愛する人に使命を遂げさせる道を選んだまひろ。
「都であなたを死ぬまで見つめ続けます」-これがまひろ、こと紫式部の道長との恋の頂点で極めた究極の愛の形!
そんな紫式部の恋と愛に私はしびれるような感動を覚える。
辛い別れを越え、大きな愛に生きる! 愛は恋の成就のみにあらず!
こんな道長とまひろの恋の頂点で紫式部が極めた愛の形-これが「源氏物語」の原点! 私はそう確信した。
これは全くの私の主観だが、当たらずとも遠からずだと思っている。「源氏物語」を読めばそれがわかるだろう。
豚汁
赤木志郎 2024年3月20日
昨年の療養生活で作ってもらった豚汁が美味しく忘れられなかった。いかにも関東風の庶民の料理だ。茸と野菜、そして豚肉を入れて味噌で味をつけて煮込む。いたって簡単な料理だ。私にははじめてでこれが関東料理の典型かと思った。おでんも簡単だが美味しい。関西ではおでんを関東だきとよぶ。いろんな具を一緒に煮込むのが関東料理の特徴のようだ。
今年に入って新聞の投書欄で豚汁を作って食べるのが楽しみだという話が掲載されていた。それを読んで私も作ろうと決心し、料理の仕方を教えてもらい、試してみた。美味しかった。いろんな具の味が出ているのだった。
こうした料理で問題は材料だ。1人前しか必要ないのに、少量の肉、野菜などを購入するのが難しい。なんでもキロ単位で売っているのだ。冷蔵庫で保管しても1週間ぐらいしかもたない。それで痛んだ肉、野菜を処分することが多い。もったいない。それで今ではにんじん1個、ピーマン1個と相手が嫌がっても個数で買うことにしている。ほうれん草だけはそうできない。
テレビドラマで男性が子供にせがまれてハンバーグを料理する場面を見て、これなら私にもできるのではないかと思っていたので、次にハンバーグに挑戦しようと考えた。ちょうどそのときに商店にハンバーグをただ揚げればよい状態で売っていたので買ってたしかめると美味しく食べることができた。10年以上も前から食べたいと思っていたものだったので嬉しかった。これからハンバーグや豚汁を心配しなくてもいつでも食べられる。
食生活は人間の生活で重要な分野だ。楽しい食生活、そして健康を維持し、頑張っていこうと思っている。
北陸新幹線の敦賀延伸に思う
魚本公博 2024年3月20日
3月16日に北陸新幹線が敦賀まで延伸され地元は活気付いています。
敦賀は歴史好きで古代日朝関係史に興味がある私としても関心がある地域です。
「日本書紀」には、「任那の王子都怒我阿羅斯等(ツヌガアラシト)が漂着して角鹿(つぬが)と名づけた」とあります。それが奈良時代に敦賀と改められました。
この説話は、アラシトが偶然手に入れた赤石を部屋に飾っていたところ、乙女になったので妻にした。乙女は珍味の料理を出すなど尽くしたが、次第に傲慢になったアラシトは乙女を蔑ろにするようになった。怒った乙女は「吾は汝の妻になる女ではない。祖(おや)の国に行かん」と去る。それを追いかけたアラシトだが、乙女は住吉大社の祭神として祀られていた。落胆したアラシトが諸国を巡り落ち着いた所が敦賀だというものです。
敦賀は天然の良港で、奈良、平安の昔から東北、北陸の物産を京阪地域に運ぶ主要ルート。敦賀から琵琶湖に出て船で京都まで運べば最短にして大量に運べます。そればかりでなく敦賀は朝鮮、中国東北部との交易の要所として繁栄を極めました。
この地域の若狭という国名も、朝鮮語の「ワッタ ガッタ」(来たり行ったり)する所(ソ)、ワカソに由来しているという説もあります。
今、日本の地方政策は、「全ては救えない」として、弱小地域を見捨てる米国式の新自由主義な思考に基づいています。その上、米中新冷戦に追随し、中国、朝鮮、ロシアと敵対し交易禁止・削減を強要する政策などで多くの地域が打撃を蒙っています。そうした政策を止め、周辺諸国と仲良くしながら、「どんな地域も見捨てない」という思考で、それぞれの特性を活かし、どんな地域も発展する道はないのか。地域衰退に悩む敦賀の人々が北陸新幹線延伸に期待する声を聞きながら、そうしたことを考えずにはおれませんでした。
「裸のラリーズ」水谷孝の詩集が刊行された
若林盛亮 2024年3月5日
3月1日の読売新聞夕刊の文化欄に私の目がとまった。
“裸のラリーズ 孤高の世界観 詩集に”
この表題の記事に驚きと共に「やっぱしね」という感慨が湧く。
「裸のラリーズ」水谷孝が逝って4年余、彼の詩集が刊行されるというのは驚きだった。バンドの音楽ではなく水谷の詩がそれ自体で詩集となって刊行されるというのには意外感がある。
水谷孝が「詩人」であることは事実だが、彼はそれをロックで表現する道を選んだ。
オリジナルメンバーの中村武志(現在は写真家・中村?きょう)はこう語っている。
「水谷さんは詩人で、すでに歌詞を書いていたし、それをロックでやりたかった。」
私が同志社の学館で水谷、中村と出会ったのは「それをロックでやりたかった」という時点だから話は「日本の音楽界を革命する」バンドのイメージが主だった。
水谷の詩を私は目にしたことがない。でも水谷に「詩人」を感じさせるものがあったのは事実だ。
3人でよく京都の街をつるんだり、ジャズ喫茶「しあんくれ~る」でたまったりしたが、議論や日常会話というものをやった記憶はあまりない。阿吽あうんの呼吸、必要最低限の言葉で成り立つ不思議な「黙示録グループ」だった。極論すれば水谷は「イカシてる」「イカさないな」、この二つで会話が成り立った。言葉の無駄遣いをしない、私たちはそんな3人組だった。
水谷はバンドが有名になってからもインタビューを受けたり、自分の書いたものを何かに発表するということがいっさいない人だった。彼が何を語ったか、彼の「言葉」は公式の文献にはいっさいない(例外的に彼のフランス在住時の音楽評論家・湯浅学とのファックス・インタビューのやりとりがある)。
いま思えば、水谷は言葉というのを大切に扱う人だったのかもしれない。
「詩をロックでやりたい」、バンドで詩を形にする、それが彼の詩人人生だったのだろう。
今回、刊行される詩集は、哲学者の市田良彦という方によって水谷の音楽の聴き取りや創作ノートなどから校訂が行われたという。そんな手間暇かけてでも詩集の形にしようという人がいる、そして水谷の詩は日英仏の3カ国語で紹介される。それは水谷孝の詩がそれほどワールドクラスの魅力のあるものだということだ。
水谷孝、その人自身、彼の人生そのものが「詩」だったのかもしれない。
2019年暮れに水谷孝は彼の「バンドで形にした詩」だけを遺のこして、誰に知られることもなく逝った。
私は詩人じゃないけれど、とても詩的な人、水谷孝と「詩的な青春」の一時期を共にできたことを幸せなことだと思っている。
世羅高校駅伝部の活躍を見て
魚本公博 2024年3月5日
NHK・BSの「スポヂカラ」という番組で世羅高校駅伝部のことを取り上げていました。
世羅高校は広島県の山間部に位置する世羅町にある高校。高校駅伝の常勝チームで、昨年に続き今年も優勝したのだとか。高校の庭には優勝を記念する御影石の記念碑が5つ以上も建っていました。
世羅町も日本の多くの地方と同じく衰退した町で、中心街もシャッター街化しています。
この町を盛り上げたい、その思いで学校の裏手の山道を駆け上がる5キロのコースを毎日、2、3回往復するという過酷な練習に耐え、競技でも必死に走る選手たちの姿。
町民にとっても世羅高校駅伝部は誇りです。駅伝大会への旅費も町民が募金で集めます。寂れた町での募金は苦労が多いようですが、それを「あの子たちの努力に比べれば、私たちの苦労なんて小さなものだ」との言葉が胸を打ちます。
そして優勝して帰ってきた選手たちの歓迎。その日は、町を離れた人々も駆けつけるのだとか。その歓迎ぶりをシャッター街と対比させた歓迎風景の映像。町の人たちが選手たちに「よく頑張った、ありがとう」と口々に叫ぶシーンに胸がジーンとなりました。
世羅に関しては、次のような話しを聞いたことがあります。朝鮮総連系の広島の企業家が銀行から融資を受けようとしたが、保証人のなり手がない。それを知った銀行の担当者が「世羅の子孫なら信用できる」と保証人なしで融資してくれたという。
世羅は、鬼ヶ城に住む世羅という鬼を大和朝廷が退治したという「世羅伝説」の地ですがこの伝説は、朝鮮からの渡来民が朝鮮式山城に住み、先進文化をもたらしたことを反映しており、広島の人々にとって世羅は地域の発展に尽くした恩人だということなのです。
それにしても、シャッター街と歓迎の対比風景は、弱小地域は「見捨てる」という、この国の地方政策の冷たさと郷里を愛する郷土愛の強さを浮き彫りにしており、冷たい政治を何とかしなければならないとの思いを一層募らせるものでした。
能登の震災に思う
小西隆裕 2024年2月20日
元旦の朝、能登の震災を知った。
私はニュースを聞いていなかったので、皆に教えてもらった。
あれから一ヶ月半、ラジオから聞こえてくる被災者の声は淡々としている。
復旧の遅れに対して、「まあこんなものでしょう」という声が多い。
それへの怒りや悲しみの感情は抑制されているように聞こえる。北陸、過疎の地の人々の気持ちが伝わってくる。
私自身、岸田首相をはじめ、政府の対応の遅さには、怒りとともに、何か諦めのようなものが含まれている。
自民党政権の震災への対応というものは、みなこんなものか。
しかし、今回はいつもにも増して、動きが鈍いように感じる。
地方衰退の現実が迫ってくる思いだ。
人口減、高齢化、取り残された限界集落、そうした中、失われずに済む命までが失われていっている。
政治の温かさが求められている。
こういう過疎地に対してほど、政治は温かくなくてはならない。
そこに政治の真価が問われる。
今回の能登の震災に直面して、一番痛切に思われることだ。
リヴァプール監督・クロップ辞任、名将の花道はゼッタイ優勝!
若林盛亮 2024年2月20日
今回のLIFEは「好き者の戯言」と思って聞いてほしい。
新年早々、私はマグネチュード10級の大激震に襲われた。
私が英プロサッカー、リヴァプール「命」の熱烈サポーターであることは何度も書いたとおり。そのリヴァプールの名監督、クロップが突然の辞任を発表、チームが首位独走中での発表だから、私には青天の霹靂、世界中のサポーターにも衝撃が走っていることだろう。
9年前、低迷していた名門チームを欧州チャンピオンズ・リーグ優勝、そして悲願の英プミアリーグ優勝も果たし、「名門復活」という偉業を成し遂げた名将、それがクロップだ。
今季はリーグ制覇も見え、チームは絶好調だ。なのになぜ??
「エネルギーが切れた」?それが辞任の唯一の理由。
一瞬、そんな殺生な! と思った。でも冷静に考えればサッカー監督業、ましてや英古豪の名門チームの監督が消費するエネルギー量は並大抵じゃない。シーズン多忙な時は英プレミア以外に国内カップ戦、そして一流チームなら欧州チャンピオンズリーグ戦など三日に一度の試合となる超激務の過密日程が続く。試合毎の戦術研究やチームの選手管理など頭は常にフル回転状態が連日連夜続く。おまけに英プレミアはクリスマス、正月休みもない激戦が続くリーグだ。シーズンオフだって家族と過ごす時間などプライベートにとれる時間はごく限られるだろう。
「常勝が当然」の名門チームの監督のプレッシャーは私など想像もつかないものだろう。
だから「エネルギーが切れた」のたった一言、クロップのこの言葉は重い! 愛する名将の言葉のまま私は重く受けとめる。いままで本当にありがとう、と言うしかない。
シーズン半ばでの早すぎる「辞任」発表は驚きだ。これにもクロップなりの理由がある。
「クラブには次期の準備時間が必要だろう」
名門の名将の後釜だけに次期監督選抜はクラブにとってとても大変な事業、これをわかるからクラブのために辞任発表時期を早めた。クラブ愛の強い監督らしい行動、辞任発表もチームのために!
辞める時もクロップはカッコイイ!!
12/20のLIFEにも書いたが、強いチームがボール保持に重きを置く退屈なポゼッション・サッカー主流のこの世界にあってクロップは「カオス(混沌)」戦術、相手攻撃時のボール奪取で敵防御陣の混乱(混沌)を主導的につくり、即速攻でゴールを奪うチームスタイルを考案、「スピード・サッカー」というワクワクさせる新しい世界サッカー「標準」をつくった。また「世界最強3トップ」を誇るリヴァプール攻撃陣旋風などプロサッカー界にも多大の功績を残した名将だ。
日本がらみで言えばドイツ、ドルトムンド時代に香川慎二をトップクラスの選手に育て、リヴァプール時代には南野巧実をうまく使い、いまは遠藤航を中盤守備の要、守から攻へのスイッチ切り替えに優れた選手、準レギュラーにまで育成しつつある恩人でもある。
名将辞任はサポーターとして痛恨の想いだが、今季リーグ優勝は最後のクロップ・リヴァプールの花道になる、だからリーグ優勝はゼッタイ不可欠の必要十分条件だ。今季、私は全身全霊を賭けて応援する、そして声を限りに歌う?リヴァプール讃歌“You’ll never walk alone”!
建国記念日?
赤木志郎 2024年2月20日
ラジオを聞いていると建国記念日があるので連休3日間という話があった。ちょうど朝鮮でも建軍節(2月8日)と旧正月(2月10日)があり日曜日が連なり連休となった。私は日本でも連休かと思いながら、はて建国記念日とはなんのことなのか、思いつかなかった
数日経って、それが紀元節のことをさして言っているのだと気づいた。それなら2月11日だ。日本にいたときは、紀元節を建国記念日としたことに違和感をもっていたのでそのことを忘れなかった。朝鮮に50年間も生活しているせいか、紀元節の日を建国記念日にしていることをすっかり忘れてしまっていた。
考えてみれば、日本の祭日には巧妙に天皇制にかんする行事を組み入れている。明治天皇の誕生日を戦前は明治節としてあったのを今は文化の日としているし、昭和天皇の誕生日をみどりの日という祝日にしている。極めつけは、大嘗祭の日を勤労感謝の日としていることだ。
そんな涙ぐましい努力にもかかわらず。建国記念日=紀元節などを日本を創った日としてどれだけの人が思っているのだろうか。単なる休みの日としか感じていないのではないだろうか。
国民大衆の大部分が共感する、心から祝える日を迎えるのはいつのことか。
初めて知りました
魚本公博 2024年2月20日
朝鮮の2月は旧暦が身近に感じられる月です。今年は10日が旧正月になり、それから15日後の24日が満月で「デボルム」になり、これらの日は祝日になります。
日本は旧暦から新暦に替えたときに日時だけ当てはめたので、元来、満月の日である8月15日の「お盆」も満月にはなりません。成人の日も1月最初の満月の日を祝うものでした。
月の満ち欠けで日々の移ろいを知る旧暦は中々、趣があります。
そうしたことも関連して、最近、月の動きに興味をもつようになりました。
きっかけは、柱時計が故障して枕元に卓上時計を置いたことです。その時計は中国製で陰暦の日時も表示されるので、今日は三日月の日だ、満月の日だと分かるので、その日の夜は月を見るようになりました。
そうして分かったことは、月の出入りは、日々変わるということです。辞書で調べると一日で52分ほど早まります。出入りの場所も随分変ります。
当たり前と言えば当たり前なのでしょうが、七十歳を過ぎて初めて知りました。
「八十の手習い」という言葉がありますが、まるで七十の手習いです。
それにしても不思議ですね。70数年間、月は見ているのに、いつ、どのように出て沈むのかなど、知らなかったし、知ろうともしなかったのですから。
次の満月の日「デボルム」、月がどの方角から、いつ出るのか、楽しみに待っています。
照ノ富士、優勝の弁
小西隆裕 2024年2月5日
大相撲、初場所が照ノ富士の優勝をもって終わった。
最後は、ともに13勝2敗、横綱照ノ富士と関脇琴ノ若の優勝決定戦、それを堂々の横綱相撲で制しての優勝だった。
そして、恒例の優勝カップ授与式、式が終わってからの土俵下でのインタビュー。
優勝の感想を問うアナウンサーの質問に、照ノ富士は、「3番取れるか、4番取れるかとやってきましたが、ここまで来ました。嬉しいです」と答えた。
実際、場所前の状態は、とても優勝をねらえるようなものではなかったらしい。稽古場で2,3番取ると、すぐ息があがってしまう、そんな状態だったと言う。
膝の怪我による休場が続き、昨年休まなかった場所は優勝した一場所だけ。
そこでアナウンサーが聞いた質問、「久し振りの優勝、感想はどうですか」に答えた照ノ富士の弁が気が利いていた。
「いつも久し振りなので慣れました」。
このとっさの名回答に場内が沸いたのは言うまでもない。
このような場でも、自分を客観的にとらえてジョークを飛ばせるところに、大関から再起不能といわれた膝の大怪我で序二段にまで転落し、そこから再びはい上がって、横綱にまで上り詰めた後にも、怪我での休場を重ねながら、9回に及ぶ優勝も重ねてきた照ノ富士の「大横綱」たる所以があると思った。
啄木の「にがいココア」と東アジア反日武装戦線メンバーの言葉「最期は本名で迎えたい」
若林盛亮 2024年2月5日
明治の歌人、石川啄木の詩歌に「にがいココア」というのがある。この題名が合ってるか自信はないが、私が東大安田講堂死守戦で逮捕、起訴され獄中にあった時、この啄木の詩歌が胸を打ったことを覚えている。
言葉は正確かどうかわからないが、たしかその結語はこうだった。
我は知る テロリストの そのにがい にがい心を
ココアの苦味にテロリストの苦衷の心を重ね合わせ共感する啄木の心を映す詩歌だった。ココアの味にテロリストの心を託す、そんな一面があの叙情的な「一握の砂」の啄木にあったことを知って獄中にある身として彼をより身近に感じた。
当時、啄木は天皇暗殺未遂事件とされた大逆事件、その中心人物とされ死刑に処せられた幸徳秋水や管野スガらの無政府主義に心を寄せた。啄木が当時書いた論評「時代閉塞の現状」がこの事件の影響を受け「朝日文芸欄」への掲載が見送られたことに「時代の閉塞」を実感したからだろう。
この事件の影響を物語る啄木作品としては「日本無政府主義者陰謀事件経過及び附帯現象」「‘V NAROD SERIES A LETTER FROM PRISON」、「はてしなき議論の後」9編の詩があるとされている。「にがいココア」はこの中の作品中の詩歌だったと思う。
先日の新聞で東アジア反日武装戦線の桐島さんが約49年に渡る逃亡生活の末に発見された。その理由が「最期は本名で迎えたい」として自ら「桐嶋聡」と名乗り出たからだ。桐島さんは末期癌で余命なしと診断され事実、名乗り出た四日後に亡くなられた。
「最期は本名で迎えたい」、その真意はご本人にしかわからないことだ。でも私は想像してみた、いや「その心」を知りたいと思った。
「本名、桐島聡で最期を迎える」ということは「東アジア反日武装戦線」の企業爆破犯として最期を遂げるということでもある。これがこの世に「桐島聡」という人間が存在したことを示すもの、この人のある種のアイデンティティだったのかもしれない。企業爆破という手段の誤りはご本人もいまやわかっていたことだろう、でも「東アジア反日」という理念で闘った日本人だったこと、それは彼が人間として自負できることだったのではないだろうか。
「アメリカには頭を下げたが、アジアには頭を下げなかった」戦後日本、北ベトナム爆撃のためにB29が沖縄基地から飛び立っていた1970年代初期、「東アジア反日」を掲げた人たちはそんな日本に抗した人たちだった。死刑囚となった人たちもいる。
‘80年代になっても若い人たちの中で「東アジア反日武装戦線」の訴えに耳を傾け連帯する運動が大きな広がりを持っていたことを覚えている。学生運動が死滅した時期にあって注目すべき現象だった。「戦後日本はおかしい」の訴えが’80年代の若い人の心にも響いたのだ。
それは21世紀の日本人、いや「パックスアメリカーナの終わり」の見えるいまはもっと多くの日本人が考えるようになるであろうと私は確信している。
自分を隠した逃亡生活で一生を終えた桐島さんの人生は辛いものだったと思うが、「最期は本名で迎える」ことによって戦後日本に異議を唱えた「桐島聡の人生」を世の人の記憶にわずかでも残した、それが「桐島聡の心」だったのではないか、そう私には思える。
「我は知る テロリストの そのにがい にがい心を」
この啄木の詩歌がふと胸に浮かんだのもそんなことを思ったからだろう。
能登の近況に思う
魚本公博 2024年2月5日
こちらは暖冬です。そうは言っても最低気温は零下10度近くにはなります。そうした冬の寒さの中、どうしても思うのは能登のことです。
しかし、国会では「政治とカネ」の論戦ばかり。何か、「能登が置き去りにされている」という思いに駆られます。
元々、政府の地方政策は、地方の中核都市にカネ・モノ・ヒトを集中し弱小自治体は「切り捨て」「見捨てる」というものでした。能登への対応を見ると、復興もほどほどにして、「見捨てる」になるのではないかと危惧せざるをえません。
今、政府や県は、「二次避難」に躍起ですが、それが地域を「見捨てる」ことに繋がるものであってはならないと思います。
この「二次避難」に対し、多くの人が「離れたくない」と言っています。その理由は「仕事」や「家族の介護や子育て」、即ち、生活の基盤がある郷土から「離れたくない」というものです。そこでは「楽しい思い出がつまっとる」「血は繋がっていなくてもファミリーや」の声や「残る人たちに申し訳ない」という声も上がっています。
能登の人たちの強い郷土愛、それは、陸の孤島と言われる自然環境の中で歴史的に育まれたものなのでしょうが、それは大なり小なり、全国の地域に共通するものだと思います。
こうした中、能登現地では「政府の言いなりではダメだ」「自分たちで郷土の復興を考えないと」という声が強まっています。
大災害に直面した被災者に、そうしたことを言わせる政府とは一体何なのでしょうか。責任をもって復興を実現にする、それこそが政府の役割ではないでしょうか。
国難とも言える未曾有の災害に対し、政治とは何かが問われています。弱者を切り捨て、弱い地域を切り捨てる「冷たい政治」ではなく、「誰も見捨てない」「どんな地域も見捨てない」温かい政治への希求が高まり、日本の政治を変えていく、それを願わずにおれません。
政治家
小西隆裕 2024年1月20日
マックスウェバーは、政治家に求められる資質として、情熱、判断力、そして責任感を挙げたという。
なるほど、言われてみればその通りだ。
自分が属する共同体の活動を指揮し組織する役割を担う政治家には、自分の共同体を誰よりも熱く思う情熱がなければならず、その思いを実現する判断力、責任感がなければならない。
ここで何よりもまず問われるのは、共同体への思い、その誰一人欠けることのない愛だろう。
それは、日常生活の一つ一つで問われており、特に共同体が危機に陥った時、もっとも鋭く問われるようになる。
能登半島地震が起きたこの正月、岸田首相の言動が誰よりも厳しく問われているのは当然なことだと思う。
日本という自分の共同体を何よりもまず思い、とりわけ能登半島の被災者たち一人一人の安否に胸を痛めているのか。
何をまず考え、どうしているのか。
岸田首相をはじめ、すべての政治家にはそのことが誰よりも厳しく問われていると思う。
美男子トラクター
若林盛亮 2024年1月20日
朝鮮に「美男子トラクター」という言葉がある。
新型トラクターのニックネームだが、従来の角張った野暮ったいスタイルから一転して楕円形のスマートなカッコよさ、だから「美男子」トラクター。近くの農場でもよく見かけるようになった。
最近、朝鮮で脚光を浴びているのが商業デザイン(朝鮮語では「産業デザイン」)だ。経済活動に欠かせない美術分野になっている。商業デザイナーをめざす学生も多い。
商品のロゴやパック、包装紙もデザイン重視で各メーカーが人気獲得を競っている。
最近は季節毎の服飾展示会がよく開かれ、新しいデザインの服飾発表が若者から中年までの人気を集めている。
工場、企業所の仕事服も一昔前の単なる「作業服」から企業毎の独自のデザインの制服になった。レストランによってはスチュワーデスのような制帽制服のところまであって楽しい。
最近は各種農機の展示会でも性能と共にデザインを競うようになった。
ニュータウン建設も各アパート、商業施設もデザインの独自性を競い、そして公園化、緑化設計にするよう気を配られ街全体がアートになった。最近、拍車のかかった農村住宅建設も独特のデザインを競うようになった。
身近なところでは床屋で理髪を終えると理髪師アジュモニが「美男子になったでしょ」と私に聞く。理髪師というのは、その人の顔や頭の形に合うよう髪を美しく刈り整える芸術家、一種の彫刻家なのだそうだ。
このように仕事や生活がアートになって日常が美しく楽しくなる。
なぜ災害克服立国ができないのか
赤木志郎 2024年1月20日
こちらではBS放送3が一日中NHK金沢放送局の番組を流しており、能登災害の様子がよく分かる。いまだ断水、停電、道路寸断、集落の孤立が続いている。石川県は日本海側では有数の経済・文化の発展した地域で古くから伝統文化が残っている。それが復旧の見通しが立たないほどの被害を受けた。
周知のように日本は自然災害が非常に多い国だ。地震、津波、台風、火山の噴火、そして山崩れなどなど。これに原発事故まで加わる。今回の能登半島地震災害は改めてそのことを示した。
国の役割は昔より治山治水だと言われてきた。にもかかわらず、これまで対策が放置され、「想定外」で責任逃れをしてきた。今回の能登震災にたいしても岸田首相の鈍感ぶりが批判されている。2日目の1000名自衛隊員派遣の少なさ、そして新年会のハシゴ、被害者をどう見ているのか、まったく見ていない。無関心なのだ。今、多くの人たちが倒壊した建物の下にいるのだ。
「上流国民」には下流国民とくに限界集落に住む人々の命なんかは関係ないのだ。かれらに日本を災害の心配のない国をつくることができない。
国民のことを考えず関心がなく守ることができない輩は、国の政治をおこなってはならない。言いかえれば自己の保身出世よりも、国民大衆のために考え懸命に努力し汗を流す人こそ政治を担っていくようにしなければならないとつくづく思うのである。
朝鮮の教育状況から…
森順子 2024年1月20日
朝鮮では、昨年末、5カ年計画の3年目になる年の総括会議があった。
教育部門においては、教育科学研究中心拠点である教育研究院が新しく建設され、秀才教育法も新たに制定された。そして、子どもたちに、より先進的な教育を与えられるシステムが準備され、教育部門の物質的、技術的土台を固めた昨年は、確実な進展があったという評価だ。また、教育の内容と形式、方法においても質的変化があったという。時代と世界の教育発展の趨勢に合うように、今はどの国も、多様で先進的な教育内容と方法を探し出し実践している。いかにして生徒、学生の創造的な思考力や想像力を育てる知識を与えられるかだ。朝鮮では、教員の交流会や発表会を重視し、そこで評価された教育内容や方法は全国に一般化されるようになっている。昨年の教育の質的成果は、きっと教員たちの奮闘の結果だ。教育の質は、教員の質だと言われるが、教育において教員の役割は決定的だと言える。
どういう教育をすれば、子どもたちが、モチベーションをもって主体的に勉強できるようになるのか、日本でも試行錯誤している学校は多い。とくに教員が決定的に不足している現状にあっても、いろいろな取り組みを試行している。ある小学校では、「受け身的な一斉授業」から脱し、「自由進度学習」が注目されている。それぞれ思い思いに自分で課題を決めて実行させるやり方だ。これを導入した教諭は、「受け身の人間より、自立した学習者にすることが大事」だと言う。また、教員の負担軽減のために算数のAIロボが授業をする小学校もある。しかし、ロボット先生は、正しい解き方を教えることしかできないから、生徒が間違った原因は、やはり先生と生徒が対話しなければ分からない、当然、ロボット先生の限界がある。このような取り組みの評価はいろいろだ。だが、そういう中でも、学校や教員たちのこういう様々な取り組みがあり交流があれば、今までにない新たな教育の形が生まれてくるに違いないと思った。
年賀メールと「情」
小西隆裕 2024年1月5日
新年、元旦の朝、Kさんから年賀メールが来た。
みんなで過ごしたクリスマスパーティーのこと、
激動する世界情勢のこと、
そして最後に、「このメールにはAIからとったものが含まれています。どれがそれだと思いますか。当ててみてください」とあった。
それでもう一度メールを読み直してみた。
そう言われてみると、何行かの文章が浮かび上がった。
なるほど、この文章には「情」がない。
Kさんの情の深さとともに、情という精神活動の高級さが改めて思われた。
今年のお正月は
若林盛亮 2024年1月5日
新年早々、能登半島付近の震度7の大地震と津波、羽田空港での飛行機事故があって、日本では「おめでとう」とは言えないお正月になったようだ。富山からの年賀メールはそんな雰囲気を感じさせるものだった。
こちらピョンヤンのお正月は気温も温かく穏やかな年明けになった。
元日は田中義三の命日でもあるので午後に焼香をして夕方、皆が集まり新年会をやった。
ピョンヤンでは新年カウントダウン音楽祭がメーデーー競技場で金正恩総書記を迎えて行われた。
二日にそれをTVで見たが、壮大華麗なものだった。15万人収容の競技場の半分を使って舞台と大スケートリンクが設けられ、音楽とスケート芸術のアンサンブルの音楽祭典が繰り広げられた。観客は手に手に光るものを持ってリズムに合わせてそれらが揺れるので音楽会場全体が光の渦が踊るようになる。若手ホープのチョン・ホンランさんも出演、テンションの上がった観客の歓声が「ワオーッ」と夜空に響くとてもいい雰囲気の音楽公演で、着飾った若い男女の多い会場は従来以上に華やかさを増したように見える。
昨年は経済建設が100%以上の成果だったとか、特に農業が単なる豊作に留まらず科学農法、治山治水の徹底によって食糧問題解決の目途が立ち農村住宅建設で農村の面貌が一新されるなど文字通り「変革と転換の年」になったことが新年音楽会の盛り上がりになったのだろう。
他方、わが国の新年は災害や事故のせいばかりではない不安の年明けになったが、「大転換」を国民自身が求める年でもあるように感じる。
昨年は「パックスアメリカーナの終わり」を世界が見た。わが国は「米国ついていけば何とかなる」という戦後日本の生存方式からの脱却が問われる年になる。誰かについていくのではなく自分で進路を考え選択し決定する、ある意味、日本のアイデンティティ確立の契機とすべき年でもある。
2月に喜寿、77歳になる私だが老骨に鞭打ってもっともっと頑張る年にしなければと思う。
ふっとんだ正月気分
赤木志郎 2024年1月5日
昨年の欧米諸国の凋落と非米諸国の著しい台頭により、今年はさらに動乱の年になると予想していた。しかし、正月は正月、お屠蘇をいただき餅を食べるのが恒例の行事。しかも、今年の正月は非常に暖かく、最高温度は零度以上だ。凍り付いた道路の氷がどんどん溶けていく。
良い正月だなあと思っていたら、1日の夕方、TVをつけると「すぐに逃げろ、津波が来る」という連呼だった。能登半島沖での地震で最大8メートルの津波がくるおそれがあるということである。注意予報は、石川県以外に富山、新潟、北海道、福井、京都、兵庫などの日本海沿岸に出された。どのチャンネルも津波注意のお知らせで、通常の放送は中止になっていた。能登半島では家が崩壊したり火事になったりしているという。
2日の夕方、今度は羽田空港での日航機炎上のニュースだ。300人以上の乗客がいる大きな飛行機がまるごと炎上している。幸い、乗客、乗務員は全員無事だったが、乗客の方々は口をそろえてパニックに陥ったと述べていた。原因は滑走路で海上保安庁の飛行機と衝突し火災が起きたためだと翌日、報道していた。
能登半島の地震でも100人近くの死者が出て、航空機の衝突でも海上保安庁の航空機で数人の死者が出ている。
3日目にはこの二つの事故について詳しく報道されはじめた。完全に正月気分がふっとんだ。酒も餅も口にする気がなくなった。むしろ、今年が不安に漲った年になるのではないかという気分になった。
ただでさえ国内政治は機能停止のまま、対中、対朝鮮の戦争準備だけがどんどんすすんでいる。まるで希望が見えない。そのうえ、世界ではウクライナ戦争、パレスチナVSイスラエルの戦争が行われており、世界の分断は克服されていない。一見、混沌とし不安な様相にあるが、その中にこそ新しい芽が生まれ、希望の光が差し込んでくるのでないだろうか。その闘いの一端に私も担っていきたい。
今年も宜しく。
今年もよろしくお願いします
魚本公博 2024年1月5日
こちらは、温かい年末年始でした。例年だと、零下10数度の日々が続く一番寒い時期なのですが、今年は零下にもならず小雨が降るような状況で、朝鮮に来て50年以上になりますが、こんなことは初めての異常さでした。
そして日本では元旦から能登での大地震と、まさに天変地異の年明けになりました。
今年は辰年。辰年の年には、政治的にも大事件が起きるのだとか。ロッキード事件も、リクルート事件も辰年でした。昨年来のパーティー券のキックバック問題も引き続き、自民党はガタガタ、令和のロッキード、リクルート事件になりそうです。
事件を主導しているのは東京地検特捜部。その裏に米国があるのは政治の世界では常識。
米国としては、日本を米中新冷戦の最前線に立たせる。そのための自民解体まで視野に入れた政界再編を企んでいるということではないでしょうか。
私自身は、年末年始、テレビを見て過ごしました。
BSでは紅白歌合戦は見れませんが、「魚が食べたい」で佐田岬が出てきて久しぶりの故郷・別府湾の風景に癒されました。
元旦の「日本歌手協会・新春12時間歌謡祭」では、老齢の歌手の方々が多く出演されていましたが、中でも90歳の菅原洋一さんのケサラの熱唱など励まされる思いでした。
辰には、暗さを払うという意味もあるとか。米国主導の政界再編、政治の再編を国民主導国民主体でやり、この暗さを明るさに変える。今年は、そういう年にしたいものです。私たちも、老齢の身ではありますが、少しでもこれに寄与したいと思っています。そういう意味で「今年もよろしくお願いします」です。
安全と幸せのために
若林佐喜子 2024年1月5日
穏やかな元旦と思いきりや、夕方に能登半島で震度7の地震発生との速報が伝わり、心配、不安は深まるばかり。3日、朝鮮中央テレビの国際ニュースでも多くの家屋が崩壊し、陥没した道路などの様子を報道していました。4日現在、73名の方の犠牲が確認されています。心よりご冥福をお祈り申し上げます。
昨年、選ばれた漢字は、一位が税で続いて暑、戦。今年も激動の年になるのでは、と思ってはいましたが、まさか元旦に、日本でこのような地震災害が起きるとは考えていませんでした。揮毫された清水寺の森貫主さんの言葉ではないですが「国民を幸せにする税であって欲しい」、という思いを、より一層強くしています。国民の税をどのように使うのかが、国、政治の大きな役割の筈。
政府は、脱炭素化のためのGX(グリーン・トランスフォメーション)政策で小型原発の開発、原発回帰に舵を切りました。しかし、地震大国である日本、国民生活の安全を考えるとき、今回の地震で、石川県内の志賀原子力発電所、1、2号機(いずれも運転停止中)で、外部からの電源を受ける一部の系統が使えなくなり、別の系統に切り替えて必要な電源を確保したとの発表がありました。もし、稼働中であったらと思うとぞっとします。地震対策のためにやれること、やることはまだまだあるのではないでしょうか。
今年こそ、日本の政治が、国民生活の安全と人々の幸せのための政治になることを心から切に願う新年、早々でした。
日本では、インフルエンザが流行っているそうですので、くれぐれもお身体ご自愛下さい。どうか、今年もよろしくお願いいたします。
東京地検特捜部
小西隆裕 2023年12月20日
年末、どうも政局があわただしい。
法務、財務、文科など副大臣の不祥事、辞任があったと思ったら、
自民党安倍派、二階派など各派閥のパーティー券、裏金問題、岸田首相自らの統一教会との接触問題、等々、立て続けだ。
そこに決まって顔を出すのが、御存知、泣く子も黙る東京地検特捜部だ。
「正義の味方」、悪の巣窟に踏みいり、悪人どもを挙げて回る姿は、こういう形容詞がつけられて、宜なるかなだ。
だが、一つ思うことがある。
それは、この「正義の味方」、いつも日常的に活動しているようには見えないことだ。
悪者が悪事を働く時、いつもまとめて働くわけではないだろう。日常的に働くことが多いのではないだろうか。
ところが、地検特捜部の活動はそうはなっていない。
随分前にあったことも、この間あったことも、皆まとめて出してくる。
何か目的があって、その目的のため、いろいろあったことをためておいてまとめて出してくる、そんな感じがするのも正直なところだ。
今回もそうだ。
何か目的があるのか。あるとすれば何か。
そこで思い当たるのは、岸田政権が先送りしようとしている「解散総選挙」だ。
確かに、この間の一連の不祥事で打撃を受けるのは、当然のことながら、岸田政権に他ならない。
実際、その支持率は、さらに急降下。15%。どん底もどん底だ。
これでは、つい先日先送りを表明した「解散総選挙」もやらざるを得なくなるのではないか。
こう考えてみると、東京地検特捜部、「正義の味方」説も、さらに深く考えて見る必要が出てくるのではないか。
悪徳、岸田政権が滅びるまで許さない「正義の権化」なのか、それとも「解散総選挙」を先送りさせない、何か他の目的を持った何者かの手先なのか。推理は、さらに深める必要があるようだ。
リヴァプールがトップに立った
若林盛亮 2023年12月20日
私の「ピョンヤン青春記」を彩るひとつがサッカー英プレミア・リーグの古豪、リヴァプールFC(フットボール・クラブ)のサポーターを楽しむこと。日本の同好の士からのメール詳報で毎週、試合結果に一喜一憂している。目標はリーグ制覇、優勝だ。先週やっとリーグ首位の座に就いた。
昨季は「世界最強3トップ」はじめ主力が30代を越え移籍や世代交代の過渡期などがあって5位という不本意な結果だっただけに今季はなんとしてもリーグ優勝することが私の悲願だ。
なんでリヴァプールFCを愛するのか?
一つは若かりし頃、私に「長髪ひとつで世界は変わる」契機をくれたビートルズの出生地、産業革命以来の労働者階級の街、港町リヴァプールの地のチームであることと無縁ではない。
また「永遠のキャプテン」と言われるスティーブン・ジェラードというサッカー人をこよなく愛し、彼が愛しサッカー人生を捧げたこのチームを彼と共に愛したいと思うからだ。
あと一つは現監督のユルゲン・クロップのサッカー戦術がとても素晴らしいと思うからだ。一時、サッカー界を席巻したスペイン式の「ポゼッション・サッカー」、圧倒的ボール保持率で終始、試合の主導権を握り、弱い相手を攻めたてるいわば「イジメ・サッカー」が私はとても嫌だった。高額で買った足技の巧みな選手達が自分たちでボール回しをしながら一瞬の相手防御のスキを見逃さず得点を決めるやり方だが、試合のほとんどを自分たちのボール回しを延々と見せつけられる側にとっては退屈この上ないサッカーだ。
他方、クロップのサッカーは「カオス・サッカー」とも呼ばれる独自のもの、カオス=混沌をつくりだしそれを好機に代えるサッカーだ。ボール保持よりボール奪取優先の速攻サッカー、つまり相手のボール保持時、攻撃時こそがチャンスだという逆転の発想、なぜなら相手の攻撃時には防御陣も前がかりになって相手の防御に穴が出やすい状態、だから攻撃に出た相手のボールを一瞬で奪い敵防御陣の整う前に速攻に移行、一気にゴールを奪うという斬新、かつ奇抜な発想から生まれた戦術だ。これをやるためにゲーゲン・プレスという2人、3人と相手ボール奪取に狩人のように組織的に人が動く圧力守備、ボール奪取後すぐに攻撃へのスイッチ切り替えへと、これをチーム全員が一体となってやるのは簡単じゃない。90分間を通じ走力持続と相手との格闘体力も選手に求められる。それをクロップはやり遂げ、いまはそれが英プレミア、いや欧州、世界の標準になりつつある「攻守の切り替えの速いサッカー」、サッカーに機動性、ダイナミックさをもたらした。
私から言わせれば、サッカー界からイジメを一掃する革命的サッカーだ。足技の卓越した高額の選手を雇えないチームでも工夫努力すればできる戦術でもある。
いまは相手にも研究され尽くした戦術だけに、これにポゼッション(ボール保持)も取り入れたものに戦術も進化しており、これがまたリヴァプールを強くしている。
今季は攻撃陣の世代交代も熟成度を増し「世界最強の攻撃陣」ができつつある。また今季途中加入の日本代表キャプテン、遠藤航わたる君も中盤の底を固める役割を担っている。まだレギュラーの座には遠いが、ようやくチーム戦術に馴染んだところ、なんとか頑張ってほしい。
クリスマスから新年にかけては他のリーグはお休みなのに英プレミアは休みなしの「国民サービス月間」、超過密日程が続く。ワタル君の出番も多くなるだろう。ここを乗り切ったチームが優勝に近づく。この時期にリヴァプールはトップを維持、他チームとの勝ち点差を広げ独走状態に移行する。これが私の年末年始のゲーム・プランだ。
広がる麦畑
魚本公博 2023年12月20日
こちらは厳冬期に入り、零下の日々が続いています。
そういう中で、目につくのが麦畑です。市内に出かける周辺の麦畑が昨年に比べても随分広がっています。多くはトウモロコシの後の二毛作ですが、稲刈りを終えたコメの田んぼでも麦畑があちこちに作られています。
寒冷地の朝鮮で米と麦の二毛作を行うには、生育期間の短い品種が必要ですが、その研究開発も進んでいるようです。今後、米麦の二毛作が全面化すれば穀物の収穫量は大幅に増えますから期待は大きいです。
日本でムギ畑と言えば、「麦踏み」が冬の風物詩です。朝鮮ではそういう風景は見られないので辞書を見たら、「麦踏みは日本独特」とありました。火山灰地の日本は土が軽くて霜に持ち上げられるために麦踏みが必要なのだとか。
私は麦には色々と思い入れがあります。私の家は、農家ではありませんでしたが若干の田畑があり、コメや麦も作っていたので、麦踏みもやっていました。
それから麦飯。家では60年代まで麦飯でした。とくに山芋のトロロには麦飯が最適、麦の臭いとよく合い美味かったです。
大分の郷土料理、「ヤセウマ」や「ダンゴ汁」も麦が原料。母親が鍋の内側に貼り付けたダンゴをツツーと伸ばして作る様子は、まるで手品でした。味噌も麦酵母を使った麦味噌を作っていました。最近では大分の「麦焼酎」も有名になっていますね。
朝鮮の米麦の二毛作。来年には周辺の田んぼにも全面的に取り入れられるのではないでしょうか。冬の田畑に広がる麦畑が「冬の風物詩」になる日を今から楽しみにしています。
関ヶ原
小西隆裕 2023年12月5日
大河ドラマ「どうする家康」を毎回見ている。
正直言って、余り面白くない。
その主な原因は、私が思い描いてきた家康像と大分違うからだ。
これほど家康はちゃちではない。
ところが、先日「関ヶ原の決戦」を見て、作家を少し見直した。
一進一退の緊迫した攻防にあって、戦況を一変させる兵の押し出しをやってのけたところだ。
敵、三成や戦況を見ながらどちらにつくか決断しかねている毛利、これらすべての人々の心理を見透かして、皆を驚かし、皆を動かす「押し出し」に打って出た家康の機略を分かりやすく表現していたと思った。
家康は、信長や秀吉、信玄などと比較して、武将としての評価は低い。
しかし、様々な合戦で、ここぞという時の機略は並々ならぬものだった。
なぜ、家康にそんなことができたのか。
それは、家康が「自分には何もない。皆が在っての自分だ」と自分の役割に徹していたところにあるのではないか。
この辺が作者の言いたかったことの一つなのかなと思えた「関ヶ原」だった。
目標ある限り青春
若林盛亮 2023年12月5日
11月の新聞に82歳にして現役の建築家、安藤忠夫さんの記事を目にした。
「70歳でも、80歳でも目標がある限り青春です」
これが安藤さんの持論。
安藤忠夫氏の「一人ひとりの心に残る建築を届けたい」という目標には揺るぎがなく、八十代のいまも青春を続けておられる。
最近は、「子供が特別な一冊に出会う場」として図書館「子供の本の森」を大阪中之島に建造、そして岩手県遠野市、神戸市にも「子供の本の森」を完成させ、さらに松山市、熊本市、バングラデシュでも計画が進んでいる。
その安藤氏は十二指腸乳頭部癌、膵臓癌を患い、膵臓癌は5年生存率10%の難治性のものだったが克服、「五つの内臓をとっても元気でいる」人としても有名だそうだ。
目標ある限り青春!
いま76歳の私にとって頼もしい言葉だ。
二十代の頃は「目標を求め暗中模索の青春」だったとすれば、七十代のいまはようやく「目標に向かう青春」だと言えるようになった気がする。
天皇陛下万歳からアメリカ万歳に変わっただけの敗戦直後の日本に生まれた私は、「アメリカに追いつけ追い越せ」の戦後日本に常に違和感があった世代だ。「米国についていけば何とかなる」という戦後日本の生存方式に違和感を覚え、自由と民主主義では日本社会よりアメリカ社会が優れているという風潮、曖昧模糊としたなんとなく平和で民主主義という日本、自分の国を誇れないような「戦後日本はおかしい」と反発するようになった。そんな私の二十代の青春は暗中模索の果てにベトナム反戦、反安保の学生運動に出会って戦後日本の革命をめざすようになり、「よど号ハイジャック闘争」で渡朝し今日に至っている。
いまは「覇権帝国の米国についていけばなんとかなる時代じゃない」どころか「覇権破綻の米国と無理心中するのか否か」というところまで来ている。
いま日本はどの道を進むべきか? 「戦後日本の革命」は現実問題として問われてくる!
76歳のいま、私の目標はますます明確になった。この目標実現の道は戦後日本の曖昧模糊化された日本のアイデンティティ確立の道でもある。
安藤忠夫さん式に言えば「目標ある限り青春」、だから私は七十代の青春を「戦後日本の革命」という目標実現の時として精いっぱい生きていきたいと思う。
リバイバル韓ドラ
赤木志郎 2023年12月5日
日本から送られてくる新聞およびネット情報を見ることと、原稿書きおよび研究の毎日だが、息抜きになっているのは韓ドラをみることだ、最近は、百斉時代を背景にした「スベクヒャン」と、高句麗創建を描いた「朱蒙」、商いでの道徳の重要性を描いた「商道」の三つを見ている。いずれも10年以上前の作品ですでに見たことがあるので、会議などで時間がない場合、省略している。結局、一日でひとつ見れば良い方だ。以前見たことがあるものでも新しい発見がある。
韓ドラ放送の合間に広告があるが、うっとうしいのでチャンネルを変えるとドラマとしてやっているのは日本の刑事ものだ。この手のものは警察にたいする幻想を与える国策ドラマだとし、これまでほとんど見なかった。しかし、韓ドラの合間にときどき見ていると、犯人探しよりもベースは人情ものだ。そういう意味では韓ドラも共通している。(日本警察が人情に溢れているとはとても思えないが)。
結局、人のために尽くす人情が人々の共感を呼び起こすのだろう。人情というは人を人間として尊重し慈しむ人々がもつ自然な感情だと思う。歳を経てその大切さを感じるこの頃だ。
じいさんの「闘病記」
小西隆裕 2023年11月20日
久し振りに風邪を引いた。
この数年、病気とは無縁だったので、勝手が違った。
早朝3時頃、目が覚めた時、いつもと何がが違った。何か身体の調子がよくない。
それで体温計を探しだし、検温してみると8度5分だった。
それでもう一度寝たのだが、その時、厚着して十分身体を温め、汗が出るようにして寝るべきだった。
皆が起き出す頃合いを見計らって、佐喜子さんに朝の会議への欠席を告げたのだが、どうも調子がよくない。熱は少し下がったが、気分が良くない。
それでようやく記憶をたどり、汗が出るように対策をとった。
昼、佐喜子さんが食堂でつくってくれたお粥を運んでくれた。
夕食も同じく。
しかし、翌朝になっても熱は7度5分から下がらない。以前とは違う。
森さんは、食堂につくってもらった生姜漬けを持ってきてくれた。
翌日も同じく。佐喜子さんには世話になり続けている。
ようやく、次の日の朝、体温も6度台に下がり、事務所に。
しかし、咳は治まらない。それでマスクをつけての事務所通いとなった。
「一晩寝れば」だった風邪も、「皆の助けを借りてなんとか」になった。
じいさんの「闘病記」でした。
アイヌ神話を守った乙女
若林盛亮 2023年11月20日
月刊誌「選択」連載の石井妙子さんの女性讃歌「をんな千一夜」を愛読していることは前にも書いた。11月号で「アイヌ神話を守った乙女」、知里幸恵のことを知った。19歳の命を民族の消えゆく物語を書き残すことに捧げた少女にとても感動した。
明治政府は北海道開拓の名の下にアイヌから土地を奪い、同化の名の下に文化を奪った。
アイヌは文字を持たず、神話や物語は独特のリズムで謳い残してきた。英雄叙事詩のユカラ(ユーカラ)は有名だが、幸恵はアイヌきってのユカラの名手といわれた祖母、伯母からアイヌ語を学び、ユカラを聞いて育った。
優秀だった幸恵は日本語も巧みで北海道の女子職業学校に進学、しかし学校では「アイヌの分際で学校に入ってくるとは」と言われ口も聞いてもらえなかったという。
そんな彼女を言語学者、金田一京助との出会いが変える。
金田一京助は名手である祖母と伯母のユカラに耳を傾け、それをローマ字で書き取っていた。それを見た幸恵は、東大を出た学者がなぜアイヌなどに興味を持つのか、ユカラにそんな価値があるのかと驚く。
金田一は少女の疑問にこう答える。
「あなたたちアイヌは人間と犬の間の子のように言われ、侮蔑を我慢して生きている。でもあなたたちのユカラは叙事詩という口伝えの大変、優れた文学なんだ」と、そして世界でも口承で叙事詩が伝えられはしたが、今となっては世界でユカラをおいて他に例がない。それほど貴重なものなのだと。
この言葉にアイヌであることを恥じてきた幸恵は大きく目を開かれ、金田一にこう答えた。
「アイヌに縁もゆかりもない先生がそこまで思ってくださるとは。私も全生涯をあげて先祖が残してくれたユカラの研究に捧げます」
以降、幸恵は大学ノートの左半分にアイヌ語の神話をローマ字で記し、右半分に自分で考える日本語翻訳を記し、これを金田一に送り続けた。これに感激した金田一は東京に来て自分を助けてほしいと懇願。ついに彼女は上京、金田一宅に下宿しながら4ヶ月かけてアイヌ神話の原稿を完成させる。そしてその完成の晩に心臓発作で19歳の生涯を閉じる。
実は彼女は心臓が弱く気候風土の変わる東京行きに両親は猛反対、また彼女には未来を約束したアイヌの恋人がいた。しかしそれらを敢えて押して上京、文字通り「ユカラ研究に捧げます」生涯を彼女は生きた。
翌大正12年、知里幸恵の「アイヌ神話集」が出版され、消えゆく運命にあったアイヌの民族遺産は後世に末長く残るものとなった。
19歳の乙女が民族の命脈存続を命がけで訴えた物語にとても感動した。
自分が命がけで守り誇れるものがあるというのが何かとても羨ましく思えるのはなぜだろう・・・
大スペクタル映画を思い出しながら
魚本公博 2023年11月20日
今、イスラエルによるガザ地区への攻撃を非難する声が世界中で沸き起こっています。
こうした中、幼い頃に見た「アラビアのロレンス」や「十戒」などの映画を思い出します。
「アラビアのロレンス」は、第一次世界大戦時、英国が枢軸国トルコ帝国との戦争を有利に進めるためトルコ領内のアラブ独立運動支援し、その軍事顧問として活躍したロレンスを描いた映画です。確か、中学生の頃の映画でしたが、血沸き、肉踊る活劇に興奮したものです。
私の小中学生の頃はハリウッドの大スペクタル映画の全盛時代で、ユダヤ教の原点であるモーゼの十戒成立過程を描いた「十戒」なども見ました。その壮大さにも引き込まれました。私は見ていませんがイスラエル建国を描いた「エクソダス」も話題になりました。
イスラエルのガザでの蛮行が行われているという今の時点から振り返ると、こうした映画は、イスラエルを称賛し、欧米の中東政策を擁護しその正統性を宣伝するためのものでした。
パレスチナ問題の原因は欧米の「二枚舌」「三枚舌」政策にあると言われていますが、私も見事、その術策に嵌ったというわけで赤面ものです。
しかし今、イスラエルのガザ地区での虐殺蛮行を眼前にして、世界では、それを支持し後押しする欧米の「二枚舌」「二重基準」政策への怒りが噴出しています。
この怒りは、米国を窮地に追いやり、米国覇権を崩壊させずにはおきません。「アラビアのロレンス」や「十戒」を思い出しながら、大スペクタル映画全盛の時代とは違う時代の流れをひしひしと感じるこの頃です。
老人の孤独
小西隆裕 2023年11月5日
日本のラジオニュースを聞いていると、連日、銃を持ち人質を数名閉じこめた立て籠もり事件が報道されていた。
聴くでもなく聴かないでもなく、聴いていたが、どうやら死人、怪我人も出ることなく決着が付いたようだ。
そこで驚いたのは、何より、犯人が86歳の老人だったことだ。
86と言えば、私より7歳上だ。
「何でまたそんな老人が」、そう思った瞬間、その訳が分かった。
どうやら、その根本理由は、老人の孤独にあるらしい。
老人が一人暮らしの孤独に耐えきれず、世間を騒がせる大事件をひき起こしたということだ。
そこで思ったのがわれわれのことだ。
日本から遠く離れたピョンヤンの郊外、ここ日本人村で生活している。
しかし、一人ではない。6人の仲間がいる。
もう5,6年前になるか。まだコロナで国境が封鎖される前のことだ。
代表団で来ていたM氏が言っていた。
「あなた方は幸せだ。いつも6人で討論できるじゃないですか。私なんかいつも一人ですよ」
自分の境遇に対する感謝の気持ち、そのことを思い返させてくれた事件だった。
54年前の11月5日、京都から上京の日
若林盛亮 2023年11月5日
54年前の11月5日正午前、前日深夜に京都を発った私は東京駅に着いた、赤軍派参加のためだ。
京都青春記、最後の恩人との別離に胸は痛んだが22歳の私は心機一新、新たな闘争舞台に立つ期待に胸を膨らませていた。
この11月5日はまた特別の意味を持つ日だ。
東京駅から連絡先に電話を入れると「すぐに新聞を買って読んでから来い」と言われた。新聞には「大菩薩峠で軍事訓練中の赤軍派大量逮捕!」の記事、この赤軍派にとっての一大事変がその後の私の運命を決めることになる。
この事変を契機に赤軍派は国内での軍事訓練の限界性を悟り、海外に軍事訓練拠点を設ける「国際根拠地建設」の闘争に入った。翌年初冬、その「国際根拠地建設の軍」に参加を求められた私はよど号ハイジャック闘争で朝鮮に渡ることとなる。それが今日に至る私の人生の出発点になった。
そういう意味で11月5日は私には特別な意味を持つ。
赤軍派の武装闘争路線は多くの問題点があり、失敗、敗北に終わった。でも私自身に関して言えば、よど号ハイジャック闘争参加でこの道に生きる覚悟が固まったのも事実だ。
赤軍派の闘いの失敗を通じて革命とは単なる個人的決意や覚悟だけでできるものではないことを知った。誰のために何のためにを常に心すべきこと、また失敗から学ぶことの大切さ、そして革命には責任が伴うことも学んだ。
あれから54年の歳月が流れた。いま「米国についていけば何とかなる」という戦後日本の生存方式を支えた「パックスアメリカーナ(アメリカによる平和)の時代」は終わり、このまま米国と無理心中するのか否かという時点にあって、日本人自身が日本の進むべき道を自分の頭で考え自分の力で開拓すべき時を迎えている。
ある意味、いまが戦後日本の革命のために尽くすべきその時であり、なにがしかの力にはなれる時であると感じている。
76歳になった自分に残された時間は限られている。でもやれること、やるべきことを考え、微力ではあれ最大限、力を尽くしたいと強く思う。
11月5日を前にしてそんなことを思う。
ラグビー・ワールドカップ
赤木志郎 2023年11月5日
ラグビーワールドカップフランス大会が南アの勝利で終了した。南アは準々決勝戦以来1点差で勝ち抜いてきたうえでの優勝だ。その勝利の味わいはひとしおだっただろう。こちらではBS放送で放映されていたがアンテナの不調で全試合を見ることができず、情報はもっぱら新聞に頼った。日本は惜しくもアルゼンチンに負け、決勝トーナメントに参加できなかった。力不足だという。前回の日本大会ではアイルランドを破るなどの大活躍をしたが、今回は身体の大きくスタミナのある選手が揃っている欧州、南米、奥州の強豪にどれひとつ勝つことができなかった。大きな壁にぶつかったといえる。前回はその壁を、1人を倒すのに使った2人タックル、倒れながらのボールの連絡、非常に低い姿勢でのスクラムの戦術を駆使して決勝トーナメントに進出することができた。今回はそうした戦術を生かすことができなかった。
かつてのワールドカップでは数十年間もトライゼロの敗戦続きでまったく相手にならなかった。それが前々回のワールドカップで南アに勝って自信をつけ前回の華々しい活躍につながった。
私は高校時代にラグビー部に属した。一学年上の先輩3人が家の近くで下校途中、市電の中で誘われたのがきっかけだった。入部してすぐ他校との試合があり、ルールもまだ知らない私はどうしていいかまったく分からなかった。しかし、タックルをおぼえどんな大きな相手でも足にさえタックルすれば倒せることにラグビーの魅力を感じた。
ラグビーの特色は、スクラムを組むフォワードとセンターが繋いだボールをラインを組んだバックスでパスしていく、一人一人が役割が異なり、皆が力を合わせてはじめて試合を展開することができる。個人のスタンドプレーなど嫌われ、どこまでもチームの一員として黙々とその役割を果たしていく。この集団主義にラグビーの最大の魅力があるのではないだろか。
ラグビーは一見、乱暴な競技に見え、はじめて観戦する人は驚くそうだ。しかし、ラグビー選手はその集団的精神によりいたって紳士的だ。かつてラグビーをやってたことがあるというだけで非常な親しみを感じるのもそこに要因があると思う。
私のラグビー生活は高校3年生の最後の試合で終わった。県ベスト4まで進出したので高校から大勢な生徒、先生が応援に来てくれた。それが絶頂期だった。
私はラグビーからチームの一員としての戦闘精神、どんな強い選手も倒せるという不屈の精神を学んだ気がする。大学時代の学生運動参加にもそのことが影響している。
全日本ラグビーが今後、力と戦術で世界を制覇する強力なチームになるよう願っている。
食欲の秋
魚本公博 2023年11月5日
食欲の秋、夏痩せするタイプの私には、体力回復、健康増進の季節です。
最近では、周囲に生えている朝鮮リンゴを焼酎に漬け込みました。日本では和リンゴと言われるリンゴの原種の一つで酸味が強いリンゴ・リキュールになります。
そして銀杏。銀杏は悪臭がして手がかぶれるので日本では土に埋めて表皮を腐らせてから実を採り出しますが、朝鮮は寒いのでよく腐りません。それで今年は直接実から搾り出すやり方でやってみたところ、かぶれることもなく、大量に採取でき、皆にも配って好評です。
秋といえばサツマイモ。よど農園にも植えているのですが、今年は猪のために全滅。仕方ないので市場で買っていますが安いので助かります。毎日、夕食後に2個ほどオーブンで焼き芋にして食べています。
好物の柿も安いので2キロあまりも買って、毎日、4、5個は食べています。
海産物では牡蠣。最近は昔に比べ身の大きなものが出回っています。日本でも牡蠣の産地は仙台や広島など後背に豊かな山林がある所ですが、朝鮮も近年、山林保護に力を入れ、植林が大々的に行われており、牡蠣の養殖場に流れ込む水も栄養豊富になっているのでしょう。
その美味い牡蠣で牡蠣フライ、最近の自炊時の定番で嵌っています。
やはり日本人は海産物ですね。私の故郷別府の前の別府湾は、今ではブランド品になっている関サバ、関アジや日出の城下カレイなど魚の美味しい所で、市街地から離れた私の地区(石垣)でも新鮮で美味い魚が出回っていました。
そんなことも思い出してしまう、食欲の秋のこの頃です。
最近の出来事
森順子 2023年11月5日
子どもたちが、夏の思い出写真を送ってくれた。
マザー牧場に行ったとか、プールにも行って、江戸川でハゼ釣りをしたとか、猛暑のなかでも元気に楽しく過ごせた様子でした。
ところが、送られてきた内容は、カタカナや英語文字なので肝心のことが意味不明。頭をよぎったのは、最近では、新聞や出版物もカタカナや英語表現が何と多いことかということ。この間も、「リテラシーって何のこと?」という会話になって、皆、?です。早速、調べて解決しましたが、アナログ世代の我々には、覚えるのが大変です。
それで、マザー牧場で、グランビングに泊まったとか、BBQしたとか。これも、早速、何をしたの?解りませんと返信。答えは、グランビングとは、グラマラス(豪華な)とキャンピングを組み合わせた言葉で、キャンプ道具を用意しなくてもキャンプを楽しめる体験のことらしい。中は、ホテルのようにベッド、エアコン、冷蔵庫も備えてあって快適のようです。そして、BBQは、バーベキュ―のこと。何―んだ。結局、テントに泊まって、焼き肉したってことじゃない。そう書けば、ややこしくないのにと思いながら、日本人同士でも日本語が通じないようになる日が来るのではないかと、思ってしまった出来事でした。
秋の風物詩と思い出
若林佐喜子 2023年11月5日
先日、アパートの階段にボール一杯の皮なしの白いぎんなんの実が登場。魚本さんがよど農場ならず、日本人村の銀杏の木、実をつけるのは2本のみで収穫したものです。皮が綺麗にむけていたので「どうやって?」と聞くと、素手でプシュッと皮を取り除き、ザルに入れて水洗いをし、乾燥させただけとのこと。「ええ!?」と、驚く私。実は、数年前、秋に里帰りした青年たちに青いぎんなんを添えた松茸ご飯を食べさせようと、顔をそむけながら、ゴム手袋をして皮をむいたにもかかわらず顔がかぶれてしまったのです。魚本さんの面の皮があついのか? ぎんなんの皮が熟しきっていれば大丈夫なのか? なんとも不思議なことがあるものです(笑)。
一方、現在、ピョンヤン市内では、黄色く鮮やかに色づいた銀杏並木が人々の目を楽しませてくれています。今年は特に遅い黄葉だと報道で伝えていました。温暖化の影響なのでしょう。
この時期になると思い出すのが、2007年の10・4北南首脳会談です。市内を移動するノ・ムヒョン大統領の車列とともに真っ青な秋空と黄色の銀杏並木がテレビ画面に映し出されていたからです。そして、その時、マンスデ議事堂(日本の国会)を参観した大統領が記帳した「幸福の殿堂」という言葉がなぜか私の心に強く残ったのでした。
最近、コロナに感染した、風邪をひいたという日本からの便りが届いています。皆様、くれぐれも健康管理に留意され多忙な日々を乗り切っていきましょう。
クライマックスシリーズ
小西隆裕 2023年10月20日
こんな試合は初めて観た。
プロ野球、パリーグ、クライマックスシリーズ・ファーストステージ、ロッテ対ソフトバンク第三戦。
こう言われても、野球を知らない人にはちんぷんかんぷんだろうが、要するに、4月から戦い続けたペナントレースでセパ両リーグ、各々2位と3位のチームが3回戦し、先に2勝したチームが1位だったチームと戦って、セパの覇者同士が日本一を決める日本シリーズへの出場権を得るための第一段階、その決勝戦だと言うことだ。
1回戦は、8対2でロッテ、2回戦は3対1でソフトバンクが勝ち、この戦いでファイナルステージに出るチームが決まる。
戦いは双方譲らず、9回0対0のまま、延長戦に入った。延長10回の表、先攻のソフトバンク、すでにツーアウト。そこで出てきたピンチヒッターの柳町が右中間を破る二塁打。続く周東がセンター前にはじき返し、二塁にいた代走、上林が三塁を回って、一挙本塁へ、頭から滑り込んで、間一髪セーフ。均衡を破ってからのソフトバンクは凄かった。2番、川瀬、3番、柳田ともに初球を狙い撃って、それぞれ左中間、右中間を破る三塁打と二塁打。それで点差は3対0。誰もが勝負あったと思った。満員にふくれあがったロッテの本拠地、マリンスタジアムは、静まりかえった。
だが、この日のハイライトはその次に待っていた。
10回の裏、ロッテ最初の打者、誰だったか忘れた。そして二番目の打者、角中。この二人に、ソフトバンクのリリーフ、津森が四球を与えてしまった。もっともやってはいけないことだ。ヒットは打たれても仕方がない。しかし、四球だけは与えてはならない。リリーフの鉄則だ。それも二人連続で。悪い予感が走った。その次の瞬間だった。次打者、藤岡のバットが火を噴いた。第一球、快音とともに打球は右中間、中段に飛び込んだ。
3対3の同点!その瞬間、球場は大歓声の渦に巻き込まれた。
だが、試合はまだ終わっていない。泣き崩れる津森に代わったリリーフ、大津にロッテの打線が襲いかかった。名前は覚えていない。塁に出た走者一人を置いて、5番安田のバットがとどめの火を噴いた。球は右中間を深々と破る二塁打。とったソフトバンク右翼手の懸命のバックホームをかいくぐって、一塁走者が本塁に頭から滑り込むのを見て、安田が飛び上がり、ダッグアウトから全選手が万歳をしながら飛び出、球場全体が歓喜のるつぼと化した。
こういう試合もあるのか。ソフトバンクが敗れた残念な気持ちと人間の心、精神の高ぶりと集中、それが生み出す事の流れの思いもかけない展開に呆然とした夜だった。
同窓会に出席!?
若林盛亮 2023年10月20日
10月14日、草津市のボストンプラザ・ホテルでは中学の同窓会があって、今年は私も「出席」-「写真参加」という形で。
実は友人がデジ鹿通信連載の「ロックと革命in京都」著者紹介欄の私の「近影」写真に私からの簡単なメッセージをプリントして同窓会に持ち込んでくれたのだ。かなりの枚数を持ち込んで主立った友人に渡したり見せたりしたそうだ。
ただそれだけのことだが、なにか私は同窓会に出席したような気になったから不思議だ。
「近影」写真に友らはとても懐かしがってくれたそうだ。どんな話が交わされたか想像するだけでも楽しい。
メッセージにはこう書いた。
“春には草津川の桜並木、想い出すように、故郷を想うときは同窓を思い出す。いつか堤防の満開の桜の下でみんなでおにぎり弁当食べてみたいなと思う。
みなもう後期高齢者、おたがい健康に気を付けて同窓会でまた会えるように願ってる。”
(わか)
今年は前回より20名ほど参加者が減少したそうで次回開催は80歳記念の3年後だとか。これ以上減ってほしくないと思う。
同窓との共通の故郷の思い出は、なんといってもあの天井川の桜並木だ。
私は本当に草津川の満開の桜の下でみなとおにぎり弁当を食べてみたいと思う。かなわぬ夢だろうが、そんな夢を見させてくれるのも故郷の同窓たちなのかもしれない。
日本の「運動会」
魚本公博 2023年10月20日
10月8日は体育の日、この日を前後して日本では運動会が行われます。
14日が私の妻の誕生日なので電話しましたが、話題は孫たちの運動会の話に。私の孫は、今6人。保育園、小学校などあちこちで運動会があって、彼女も大忙しだったようです。
孫たちの運動会の話しを聞きながら私も運動会のことを思い出しました。楽しかったですね。紅白に分かれての熱戦、とくに小学校での地区対抗リレーは盛り上がりました。ある年のリレーでは私の地区の最終走者は国体出場者。圧倒的な速さで、それまで3位だったのがグングン追い抜いて1番になったときのことを今でも思い出します。
運動会と言えば、ここ「日本人村」でも子供たちが居た頃は、管理所の人も入れて運動会やりました。リレー、瓶釣り競争、玉入れ競争、サッカーのPK戦、宝探しなどなどで盛り上がったものです。
運動会は、日本では紅白の対抗戦になり互いに紅白で色分けするのが常識ですが、これは日本だけだとか。朝鮮では、「白頭山組vs金剛山組」などに分け、色分けも青や黄色の帽子などになります。欧米にも日本のような運動会はないようです。欧州の初等学校は元来、教会の付属施設として出発したためか、そもそも運動場がありません。
どうも日本の運動会は日本独特のもののようです。
地域の人が集まり、子供たちを応援し、食事を共にして楽しむ。そうしたところに日本の運動会の良さがあるように思います。
孫たちの運動会の話を聞きながら、昔の運動会の楽しい思い出が様々に蘇ってきた「ジイジ」の一日でした。
らんまん
小西隆裕 2023年10月5日
「らんまん」が終わった。
これが朝ドラのことだと言う必要もないくらい、「らんまん」は評判になったようだ。
私も「はまった」。
なぜか。それは、主として主人公、万太郎のあり方に共感し、それを描いた作者、脚本家、監督、そして出演した役者たち皆に共感したからだと思う。
そうした中、印象的だったのは、主人公が言った「雑草という草はない。すべての草には名前がある」という言葉だった。
そう言いながら、主人公は、人間に対しても、自分の妻に対し、家族皆に対し、すべての人々に対し、渾身の愛を注いだ。
一言で言って、主人公は、草花を愛しただけでない。人間も、否この世の生きとし生けるもの皆に愛情を注いだのではないか。
言い換えれば、生命共同体そのものへの底抜けの愛だ。
このドラマを見た多くの人々が引きつけられたのも、多かれ少なかれ、そういったところではないだろうか。
ある評者は、この作品には、どうでもよい脇役が一人もいない。皆が生きている。と言っていたが、そういったところにも、このドラマの真髄が貫かれていたのではないかと思う。
満月の悪戯いたずら、あるいは魔力
若林盛亮 2023年10月5日
9月29日は日本では中秋の名月、朝鮮では「秋夕(チュソク)」といって祖先のお墓参りの日だった。今年のような完璧な大きな円形になる満月は7年後にしか見れないものだったそうだが、夜空を明るく照らす満月には不思議な魅力がある。
中秋の名月といえば青春期の淡い思い出がよみがえる。
私が高3、17歳の時、ビートルズに倣ならった長髪を体育教師に「女の子の授業はあっちだ」ととがめられたのに反抗、「なら、あっちに行ってやる!」を契機に始まった私の進学校、受験勉強からのドロップアウト人生。そんな私の無謀な決心を「いいんじゃない、若林君はぜんぜん悪くないよ」と言ってくれたビートルズ同好の士、16歳の女子高生OKとは「心強い同志」関係になった。
自我に目覚め始めた十代の二人はいつしか昼夜別なく路上トークが習慣になった。話は取り留めもなくはずみ、狭い草津の町を行ったり来たりを繰り返していた。
路上トーク中は周りの景色など眼中になくトークに夢中というのが常だった。
あれはたぶん9月の中秋の名月の頃と思うが、草津川という天井川の堤防道での路上トーク中にふと夜空に浮かぶ満月を見つけた。あまりに明るくてきれいだったからだろう。
「今夜は満月なんや」と二人で思わず見とれた。「ちょっとお月見しよか」とトークを中断して土手の草むらに座って二人で満月を眺めた。「ホントきれいね」とか二言三言交わした後は話の途切れたままなぜか沈黙の時間が流れた。
人気のない夜の土手、肩の触れあう距離、彼女の息づかいや体温まで感じられる微妙な空気感、私はとても息苦しい気分になった。それはいつもの路上トークの取り留めのない時間とは全く違う不思議な時間だった。重苦しくてとても長い時間に感じられた。
恋に不慣れな17歳の私はとても耐えられそうもなくてつい「帰ろか」と切り出し、彼女の家まで送ったが、二人ともなぜか口が重くなって月明かりの中をただ黙々と歩いてその日は終わった。
たったそれだけのことだが、満月の夜以来、いままで意識もしなかった「恋してる」を意識するようになった。
もし満月を見なかったら、いつものただの路上トークの夜として終わっていただろう。
「トーク同志」から「恋」への化学変化-中秋の名月、満月の悪戯、あるいは魔力なのかも知れない。
中秋の名月
赤木志郎 2023年10月5日
秋晴れで中秋の名月を堪能することができた。とくに今年はSさんが皆にいなり寿司とお萩を差し入れしてくれて久しぶりにお萩を食べることができた。お萩は甘いもの好きの年寄りには一番だ。
新聞を見ると、中秋の名月の日に「子供たちが『お月見どろぼー』を名乗って店先のお菓子を食べる慣習がある」とのこと。実は私の故郷である神戸でも8月15日前後の地蔵盆の日には、夕方、店先にある果物やお菓子が食べ放題だった。それでいろんな店に行って満腹するまで食べ歩いた。食べながら子供心に「なんで子供に食べ物をただで勧めるのか」という思いがかすったが、食べ物を勧めるやさしいそうな老人の笑みをいまでも忘れることができない。
新聞記事によると江戸時代からの風習だそうだ。その年の豊作や子供の健康に御利益があるという。都会に農業をやっているはずもなく、店の繁盛のことだろうか。しかし、そうした目先の利益ではなくもっと良いものをめざした何かがあると思う。なによりもその地域の和やかな雰囲気を醸し出す。子供には自分の地域にたいする愛着と感謝の気持ちが自然に身につくようになる。地蔵盆の日は全体が地蔵様の光で満ちているようだった。
今も神戸の下町にそうした風習が残っているのだろうか。中秋の名月の日に60数年前の思い出に浸った。
秋夕の日、お盆の思い出
魚本公博 2023年10月5日
今年の中秋の名月は9月29日でした。朝鮮では秋夕(チュソク)と呼び祝日(休日)となり墓参りをする日です。
朝鮮は元々土葬ですが、大都市のピョンヤンでは土地の確保が大変なので火葬が主で、火各地域ごとに納骨場があり、そこで墓参りした後、付近の広場や家で親族が集まって会食します。ちょうど、前々日に買い物に出かけた折、市場の食料品売り場がいつになく大混雑で何故?と思ったのですが、秋夕の会食のための買い物だと思い当たりました。
この日は旧暦8月15日のお盆。日本は明治になって旧暦の行事の日をそのまま新暦に当てはめたので新暦の8月15日がお盆になりますが、この日に先祖供養するのは同じですね。
お盆の日に先祖が帰ってくるというのは日本独特の観念だそうで、精霊流しの行事などが各地でおこなわれます。私の故郷(別府市・石垣)では、子供たちが1メートルほどの竹のポンポコ(竹筒)に軽油を入れて火を付けた松明を持って墓場の近くまで行き「ショウロウサマー(精霊様)」と何回か呼び掛けて帰るだけの簡単なものでしたが、母親の故郷の鶴崎(大分市)では、稲束で作った船を大野川の川辺に並べ、それにお供え物を載せ、花火を打ち上げ、最後は藁舟に火をつけて川に流す「精霊流し」をやっていました。
中秋の名月は「芋名月」と言われ、里芋を供え物にして豊作を願う行事が本来の姿だとか。私も、この日はヨド農園で栽培している里芋を食べるのが「私の年中行事」になっています。
当日はあいにくの曇り空でしたが、白い雲全体が移動するので、満月が濃淡を繰り返しながら動いているように見え、隠れた月の光で雲が光輝くなど実に幻想的な風景でした。
収穫の秋、食欲の秋
若林佐喜子 2023年10月5日
朝晩は、肌寒さを感じる今日この頃です。
ピョンヤン郊外の畑では、トウモロコシの収穫あとに秋麦がまかれ、田圃では稲刈りがほぼ終了しました。今年は、全国的に豊作のようです。とりわけ、台風6号の被害で農地が浸水したにもかかわらず、人民軍隊によって即、排水作業、農薬の散布が行われた江原道の豊作の便りは、一層、人々を喜ばせています。
そんな中、先日、管理人の人が焼き栗を準備してくれました。日本人村には山栗の木が多いのですが、準備してくれたその栗は、管理人室の横にだけあるちょっと大き目な栗です。
箱の中にはイガの開いたものや青いままのものが山盛り。小枝を下にして薪を組み、その上にイガをバサットと置き、小枝に火をつけ大きな炎となって約8分後、パンパーンとはじける音が連続し、栗が勢いよくはじけ飛びました。ふと、子供たちが幼い頃やった、劇「さるかに合戦」の場面が目に浮かんできました(笑)。早速、はねた栗を食べるとほくほくして美味しいこと。食べ頃になり、食べるのが好きなWさんと焼き栗大好きなAさん、しばらくしてMさんも加わり・・。みな、熱心に食べること食べること。そして、「う~ん、ちょっと甘みが足りないかな」「少し固いね」と言い始める。が、途中で、それでは、「栗が可哀想だね」ということになり、皆で大笑い。わいわいがやがや言いながらの食欲の秋の一時でした。
また、日本の皆様と日本人村の銀杏の木の下で、松茸ごはんやよど農場の収穫物、テドンガンビールでご一緒できたらなあーという思いが深まった一日でもありました。帰国支援センターの山中代表の話ですと、訪朝希望者が100名いるとか!? 日本は、まだ残暑が厳しく、夏の疲れが出るときでもありますので、皆様、くれぐれもお身体ご自愛下さい。
久し振りの水泳
小西隆裕 2023年9月20日
何年振りだろう。久し振りに泳いでみた。
コロナでできなかった水泳が解禁になり、皆で市内の大型商業施設にあるプールに行ってみた。
そこで、普段余り感じないことを感じた。
久し振りの水泳は、この間の自らの老いを、否応なく感じさせてくれた。
まず、手足の動きが何となくぎこちない。
次に、身体がなかなか前に進まない。
25メートルのプール、端から端まで、平泳ぎで何分かかったか。
われながら嫌になったが、それでも片道三回、三回目にはかなりスムーズに行くようになった。
余りしょっちゅうというわけには行かないが、若返り方として水泳は良いのかも知れない。
皆の感想もそうだったようだ。
「呑み」ニケーションの醍醐味
若林盛亮 2023年9月20日
朝鮮の国慶節、今年は建国75周年の9月9日、私たちは再び新規オープンの大型商業施設屋上ビヤガーデンで食事会を持った。
ジョッキのビールで乾杯の後、朝鮮の新製品、味噌焼酎の呑み会となった。
古来、朝鮮では家庭で味噌をつくる。練った味噌を一塊り毎に縄で縛り、つるして干し味噌独特の風味を引き出すのだが、ある時誤って干し味噌が酒瓶の中に落ちたが、そのことを知らず酒瓶の主人がその瓶の酒に独特の芳香があって美味ということでこの焼酎が生まれたのだそうだ。
干し味噌の香りがほのかにする甘くも35度の少し強めのお酒、皆はすぐほろ酔い加減でいい気持ち。
ほろ酔いでいい気持ちは私たちだけじゃなかった。20人ほどの隣の席では歌が始まり踊りが出てきて盛り上がっている。こういうときは必ず「お調子者」のリーダーがいて中年のアジュモニ(おばさん)が率先垂範、司会もかねて場を盛り上げていた。屋外だからいくら大声を上げても踊り騒いでも大丈夫、野外ビアガーデンというのは人々の心を開放するものだ。
そのうち小学生くらいの女の子と幼稚園くらいの女の子が踊り出した。子供とは思えないカッコイイ踊りだった。また首に赤紫のリボンを巻いた小学生風の女の子のドレスが明るい赤紫系でデザインもとてもしゃれていたので私は写真を撮り始めた。まわりのアジュモニらも「撮れ、撮れ」と私を急かした。
その勢いでおばちゃんらの歌と踊りもバシャバシャ撮った。そのうちおばちゃんらは私の手を取って踊りの輪に引き込んだ。踊り好きの赤木も加わって、何ともにぎやかな踊りの輪ができていっそう盛り上がった。
私の手を取って一緒に踊ったハルモニ(お婆ちゃん)は70歳くらいの人で、「私は名古屋に居たんよ」と私に言った、「へ~っ、そうですかあ、そりゃあ奇遇ですわ」。隣の席だから私たちが日本語で話しているのが聞こえたのだろう。それ以上の話はできなかったが、とても親愛に満ちた笑顔で踊りを一緒に踊ってくれた。
5歳の時に帰国したというこのハルモニの家族も日本ではいろいろあったんだろう。こうして祖国に帰ってきて息子娘や孫に囲まれて自分の祖国の誕生した日を歌い踊って楽しんでいる。何も話さなくても皺に刻まれたそのハルモニの人生がわかるような気がした。
隣の席に日本からの帰国者が混じっていたのが、もっと場を盛り上げてくれた。
これこそ「呑み」ニケーション-呑んで歌って踊ってコミュニケーション、その醍醐味やなと思った。とても華やいだ楽しい一日になった、ありがとう「ほろ酔い」アジュモニたち!
チョンソ
魚本公博 2023年9月20日
私たちの村には、チョンソが多いのですが、秋になり、収穫の季節になったからか、最近しばしば見かけるようになりました
チョンソとは朝鮮リスのこと。ユーラシア大陸の北方に住むキタリスの一種で、日本の北海道にいるエゾリスや内地の日本リスも同属です。
日本ではリスは可愛い動物のイメージですが、ここ日本人村では「憎悪」の対象です。というのは、このチョンソが五葉松の実を食い荒らすからです。五葉松の実は、御存知のように栄養価に優れ、朝鮮では滋養剤として使われ、朝鮮冷麺にも入れたりする高価な高級食材です。
村には五葉松がたくさん植わっていて、それを収穫できればよいのですが、チョンソが松ぼっくりが出来る夏頃からまだ実が成熟していないのに、その根元を齧って落とすので秋の収穫時には松の実などすっかりなくなってしまいます。
石を投げて追っ払おうとしても敏捷なので効果なし。
欧州でもリスは人に会うと素早く木の裏に姿を隠すことや、声も不吉だとして悪魔の使いなどという地方もあるそうですが、日本のリスの愛らしさはまったくありません。色も黒く、冬には頭に2本の房毛が生え異様、眼も野性的で愛嬌のかけらもありません。
動物好きの私ですが、どうもチョンソだけは好きになれません。
「国」と植物学
小西隆裕 2023年9月5日
朝ドラ、「らんまん」を観ていて少し気になることがある。
それは、「国」を悪者にしていることだ。
ドラマで何かと出てくるのは、主人公、万太郎と「帝国大学」植物学科の矛盾、衝突だ。
「植物学科」は、何かと「国益」を振り回し、万太郎の植物への愛を踏みにじってくる。
気になるのは、「国」が悪者にされていることだ。
元来、人々の共同体である「国」は、人々の心、人々の利益と矛盾するものではあり得ない。
万太郎の心を踏みにじり、植物学を弾圧する「帝国」は、「国」ではない。人々の「共同体」ではなく、人々の上に君臨する「支配者」だ。
その「支配者」を「国」だと言って、「国」を否定するのは、「国」を否定して、その上から人々を支配する者の利益と合っているのではないだろうか。
「国」に抗して、植物を愛し、植物学のために生きようとする主人公を観ながら思ったこと。
屋上ビアガーデンと同窓との逸話
若林盛亮 2023年9月5日
二週間ほど前、みんなでピョンヤン市内のビアガーデンに行った。
新規オープンの大型商業施設22階にある屋上ビアガーデン。市内全景が一望の下、まさに「絶景かな 絶景かな」。夕方だから涼風もあって気分はサイコー、生ビールを大ジョッキで乾杯! 久々にビアガーデンの醍醐味を味わった。
こんな気分、前にもあったよなあ・・・
京都駅前の屋上ビアガーデンのこと、バイト帰りに会った同窓と行った想い出だ。
学生時代、私は東本願寺前の小路を入った所にある矢野洋行という「貸し物屋」で古都の三大祭りなどイベント道具を貸し付け設営もするバイトをよくやった。ある日、バイトの帰り道でバッタリ小中同窓の女の子に会った。その子は東本願寺前の老舗仏具店に勤めていた。同窓とはいえ、あまり話したこともない間柄だったけれど、互いの職場が近いので退勤時にたまに会うと草津まで一緒に国電で帰る間柄になった。
夏の暑いある夕方、「生ビールでも飲んで帰ろか」となった。当時の長髪人間の私はみんなでがやがやワイワイ騒ぐような所に行くのは性に合わなくてビアガーデンもほとんど行ったことがなかった。でもせっかくだからご一緒した。
京都駅前のたしか百貨店の屋上ビアガーデンだった。枝豆などをつまみに友とジョッキで豪快に流し込む生ビールは、仕事でたっぷり汗を流した身体には五臓六腑にしみこむように旨かった。広々とした屋上で夕陽と涼風を浴びるのも快感だった。
「あんたは学生やから私がおごるわ」と言ってくれた。気さくでこだわりのない人だった。それから一、二回はビアガーデンにご一緒したように思う。
数年前、中学の同窓会があって、なんとなくそのことを想い出し、ぜひその同窓にお礼を言いたくて友人にその話をした。「俺が見つけてやる」となって、名前も忘れたので顔の特徴や彼女の職場の名前を伝えてその「恩人」を探してもらった。するとなんとその人が見つかった。
友人の話を聞いて「それは紛れもなく私のこと」と名乗り出た人があった。友人が見つけてくれたその「恩人」は「せっちゃん」、そうそう「せっちゃん」やったと私も名前を思いだした。
同窓会の集合写真で見た「せっちゃん」は茶色に染めたショートカットに真っ白のツーピース、昔のまんまのほっそりした姿そのままだった。まわりの老いた同窓の中でぜんぜん「お婆ちゃん」を感じさせない若々しさを保っていた。それがなにか嬉しかった。
ただそれだけの話だが、同窓会で昔の「恩人」を探し当てるというのはとてもドラマチックなことだ。
今年の秋にも同窓会が予定されていると聞く。次はどんなドラマがあるのだろう・・・
異常に長い梅雨
赤木志郎 2023年9月5日
朝鮮では日本の梅雨のことをジャンマという。やっとジャンマが終り、すがすがしい秋のはじめの晴天の日を迎えている。
今年のジャンマは6月から8月末まで2ヶ月あまりも続いた。これまで日本から梅雨前線が北上し、時には数日間の雨が降って終わることがあった。今年は断トツの長さだ。
おまけに、連日30度を超える暑さ、湿度も高いから不快指数がこのうえ高かった。
このとき役に立つのはエアコン。冷房をかければ、湿気も除くことができる。数年前、あまりの暑さで空調機を配備したのが効果を発揮した。
今は涼しい日々だが、日本ではきびしい残暑がつづいている。暑さとの闘いが残っている。今年の暑さは40度にもなるもので大変だったと察します。
これから台風のシーズンです。自然災害の多い日本ですが、皆さんの生活の安全と健康を願っています。
ビタミン論争
魚本公博 2023年9月5日
NHKのBS放送の番組「ビタミン論争」を興味深く見ました。
この論争は、明治の頃、国民病と言われた脚気を巡って陸軍と海軍の間で起きた論争です。
海軍の場合、とりわけ深刻で、ある軍艦は7割が脚気になり航行不能になるほどでした。
そこで海軍医学部門の責任的地位にあった高木兼寛という軍医が欧米の海軍には脚気患者が少ないことに着目し、軍艦「筑波」にハワイまでの8ヶ月の航海訓練をさせ、その間、食事を欧米と同じパン食にした実験を行います。その結果は脚気発生「ゼロ」。その後、海軍は白米食を麦飯に変え脚気発生を大幅に減らすことに成功します。
高木は、この成果を学術論文に発表し、陸軍にも麦飯への転換を薦めます。しかし陸軍はこれに反発。その論陣の先頭に立ったのが陸軍医学界のエリートであった森鴎外こと森林太郎でした。
彼はドイツへの留学経験もあり、その師はコッホ。コッホはフランスのパスツールと共に「病気は細菌によって起こる」という病気細菌説の大家であり、その弟子である森は、食事が原因という説は科学的でないとして論陣を張ります。
一方、高木の論文にヒントを得た防疫学者の鈴木梅太郎が精米の過程で捨てられるコメ糠に脚気と関連する物質があると見て、その成分の抽出に成功。これをコメの学名を採ってオリザニンと命名し学術論文に発表し、陸軍にもその採用を懇請しますが森はこれをも拒否。
森がここまで頑なだったのは、薩長閥、陸軍閥、東大医学閥が絡んでいたからです。彼自身は麦食が脚気に効果があるとは分かっていたようですが閥の関係上、死ぬまで、その主張を変えることはありませんでした。
鈴木が学術誌に論文を発表した2ヵ月後、同じ内容の論文をポーランドのフンクが発表し、その物質にビタミンという名をつけます。そして、そのきっかけを作ったとしてオランダ人のエイグマン、ポプオンズがノーベル賞を受賞。
オリザニン(ビタミン)の発見は、すべての病気は細菌によるという考え方を根本的に変える革命的なものであり、その後、各種のビタミン類の発見に繋がりました。それは日本人初のノーベル賞受賞者・湯川秀樹博士の受賞の33年前のことでした。
高木兼寛の功績は海外では高く評価され、南極の英国基地がある岬の一つにはTAKAGIの名が冠されています。
それにしても、余りにも派閥第一の論争。その教訓は結局、日本の利益、国民の利益第一の立場に立つこと大事であり、それは人類共通の利益にもなる、ということではないでしょうか。そしたことを改めて考えさせられた番組でした。
時計付き二階建て大型バス
小西隆裕 2023年8月20日
この間、佐喜子さんがわれわれの小型バスの中から外の光景を撮ろうとしていた。
私は、二度目にそれが外を走っている黄色い二階建て大型バスを撮ろうとしているのだと知った。
そして三度目、何であのバスを撮ろうとしているのだと誰に言うとでもなく皆に聞いてみた。
それで皆に呆れられた。
あれは、朝鮮で最近つくられた最新式のバスで、中でもその前面につけられた大きな時計が市民に受けていると言うことだった。
それまで私は、最近変わったバスが走っているなとは思ったが、大して気に止めていなかった。前面の時計も単なる飾りでしかなかった。
で、その時はじめて、私は、佐喜子さんの行動を理解したのであった。
おそまつ。
自我の確立-尾崎豊の場合、平塚らいてうの場合
若林盛亮 2023年8月20日
尾崎豊という言葉を聞いて、50代の方は青春時代を懐かしく想い出されることだろう。
1980年代後半期、衝撃的なデビューで当時の高校生はじめ若者に圧倒的に支持され、その若者たちは「尾崎豊世代」とも言われた。当時、私たちは季刊誌「日本を考える」を発行していたが若者との交流が拡大したのがこの世代だった。だから私にとっても尾崎豊は感慨深い。
尾崎は「15の夜」「17歳の地図」「卒業」など「ロックの名曲」を数多く世に出した。
「卒業」はこんな歌だ。
“行儀よくまじめなんて くそくらえと思った
夜の校舎 窓ガラス壊してまわった
逆らい続け あがき続けた 早く自由になりたかった”
当時は「管理教育」が徹底され、これに反発する中高校生らの「校内暴力」や「特攻服を着た暴走族」という形で若者の反乱があった。この「管理教育」は‘60年代末から’70年代初めに全国の高校、大学で起こった全共闘運動のような「学生の反乱」が起きることのないようにとした政府、文部省が学生の「自主的活動」を封じ込めるためのものだった。だからこの世代の若者と私たちとは奇妙に波長が合った。
「死んだように生きたくない」! が当時の若者の合い言葉になった。
自分を押し殺して死んだように生きることを拒否する若者らの「支配からの卒業(解放)」を代弁したのが尾崎豊であり、尾崎そのものがそんな若者の一人だった。
尾崎が主張したのは一言でいって「自分らしく生きる」-自我の確立、運命の自己決定権だ。
しかし尾崎は20歳を間近に曲が書けなくなった。そしてアルコールと薬物でぼろぼろの身体である日、一民家の庭で雨に打たれずぶ濡れの死体として発見された。尾崎の「自我の確立」の闘いは志半ばで行き場を失った。同時に尾崎豊世代も行き場を失った。
他方、女性の「自我の確立」の先駆者として明治近代の黎明期に彗星のごとく現れた平塚らいてうという女性がいる。女性の自立を訴えた機関誌「青踏」創刊号の彼女自身の筆になる有名な「創刊の辞」にはこうある。
“元始、女性は太陽であった。真性の人であった。
今、女性は月である。他に依って生き、他の光によって輝く、病人のような蒼白い顔の月である。”
尾崎世代よりも女性の自立自体が社会的に認められない近代黎明期、らいてうら「青踏社」の女性は石礫を投げられた。それでもらいてうは屈することなく闘った。
そんな平塚らいてうだったが、彼女は年下の画家と恋に落ち、子をもうけ母性に目覚める。これが彼女の転機になった。
新婦人協会の機関誌「女性同盟」創刊号に「社会改造に対する婦人の使命」と題してらいてうはこう書いている。
“今や私共は人間としての自覚から更に進んで女性としての自覚に入りました。あの個人主義的な(寧ろ狭隘の意味での個人主義的な)婦人論は最早過去のもの、時代おくれのものとなり、婦人思想論の中心問題は、男女対等、男女同権、機会均等などの問題から両性問題(恋愛及び結婚の問題)、母性問題、子供問題へと移行いたしました。そしてこれは同時に個人主義から集団主義へ、利己主義から利他主義への移行を意味するものであります。”
平塚らいてうは、女性自身の覚醒、個として自我の確立から一歩進んで、恋愛と結婚という両性問題、子を持つ親としての母性問題、子供問題へと意識化、思想を高めていった。すなわち一個人の自覚を高める問題から、婦人という社会的人間への自覚から母性の保護、子供の養育、教育を社会制度として国に要求、実現していく婦人運動へと歩を進めた。
これがらいてうの言う「個人主義から集団主義へ」だった。
こうして平塚らいてうは「元始、女性は太陽だった」からさらに歩を進めて婦人の権利擁護運動、戦後は日米安保廃棄、ベトナム反戦など平和運動の中で彼女の「個人主義から集団主義」を実践していった。
「死んだように生きたくない」を叫んだ尾崎豊は志半ばで行き場を失い、ある意味「挫折」の苦悩の中で人生を終えた。他方、平塚らいてうは「元始、女性は太陽であった」から更に歩を進めて婦人運動、平和運動へと生涯その志に生きた。
これはらいてう自身の語った「個人主義から集団主義へ」の思想の飛躍、個の自我への覚醒から社会的人間としての自覚に自分の意識を進めることができたか否かの違いにあるのではないか、そんなことを考えさせられた。
戦艦長門の最後に思う
魚本公博 2023年8月20日
8月15日は終戦記念日です。そうした中、朝日新聞に「長門軍艦旗 核への無言の抗議」と題する記事がありました。「何でも鑑定団」で司会を務めていた石坂浩二さんが、2005年に米国人が出品した長門の軍艦旗の評価額が1000万円だったのを、その場で出品した米国人に購入したいと申し出て、それを広島県呉市にある「大和ミュージアム」に寄贈したのだそうです。
長門は終戦時、唯一残った戦艦で、戦後米軍に接収され、1946年に原子爆弾の威力を試す実験に使われました。南太平洋のビキニ環礁の実験場に曳航され、集められた数十隻の艦船が核実験に使われました。その一回目の実験では多くが一瞬のうちに沈んだのに、長門は耐え、2回目の実験でもすぐには沈まず、その夜、忽然と姿を消しました。
石坂さんは、そのことについて「『核兵器では沈まない』という痛々しさを感じ」、「あの軍艦旗は核兵器に対する無言の抗議」だと思ったそうです。
私は、高校生の頃は、反米愛国の気分濃厚で、毎日新聞編纂の十数巻にもなる「太平洋戦争」などを読んで、その話しを知っていました。
私は当時、米国の核で真っ赤になりながら耐え続け、2回目の実験があった夜、誰に見取られることなく、忽然と沈んでいった情景を思い描きながら、ああ長門は、後代に「祖国日本を守ってくれ」と遺言を残して逝ったのだと思ったものです。
多分に軍国主義的な愛国でしたが、日米統合一体化が進み、核の共同所有などの話も出る今の状況を考えると、長門の最後を「核への無言の抗議」と受け取るのは今日的意味をもっています。私はそれだけでなく、長門は今も日米統合一体化に対して「祖国日本を守ってくれ」と訴えているのだとの思いを強くしています。
戦争と学校教育
森順子 2023年8月20日
朝鮮は、今年、戦勝勝利70周年という意義深い年。
TVでも、戦争3年間の様々なドキュメンタリーが放映された。
その中の一つに学校教育のことがあった。これまで、どの国でも、戦争と教育は相容れず、戦争時の教育は犠牲にするしかないというのが、一般的な考え方だった。朝鮮においても教育をどのようにするのかが提起されたという。すでに爆撃で全国の学校の40%は破壊された状況にあって、朝鮮が執った政策とは、抗日闘争の時代からの教育伝統を引き継いだことだ。つまり生徒がいる限り教育をしなければならないということだ。それで、学習班をいくつもつくって、教員たちは学習班を回って授業を保障する「戦時学習班」という新しい教育形態が組織された。そして、教科書とノート、鉛筆の生産も行い、教育に必要なものは、戦時中であっても優先したという。こうして、戦火の中でも学校教育事業は中断することなく行われた。
70年という歳月が経った今はどうかというと、「学校に生徒が通ってくるのではなく、子どもがいるところに学校をつくる」と、言われている。だから生徒が数人しかいない離島にも学校はあるし、確か、昨年のコロナ禍のときも一斉休校だったが、教員は学習班を回って授業を行っている。考えてみると朝鮮の教育伝統は百年近くになるわけだ。そこに貫かれているものは、現在も変わることなく引き継がれている。それは、「生徒主体の教育」だと言えるのではないかと思う。
政治評価の重要な基準の一つとしての愛国心
小西隆裕 2023年8月5日
このところ愛国心について考えている。
きっかけは、米国人の愛国心が低下しているという記事を読んでからだ。
なぜ低下しているのか。
それは、米国人にとって自分の国が愛すべきものでなくなっているからだ。
この場合、原因は二つだ。
一つは、米国が変わったこと。もう一つは、米国人自身が変わったことだ。
ウォールストリート・ジャーナル紙は、後者についてだけ挙げていた。
米国人の個人主義が強まったからだという。
もちろんそれもあるだろう。
しかし、一方で米国自体が変わったことも考えるべきではないか。
すなわち、米国の政治が米国人の愛国心に応えるようなものでなくなったということだ。
人間誰もが持つ自分の国に対する愛着、信頼、誇り、等々、愛国心に応えるような政治。
これは、政治を評価する場合、もっとも重要な基準の一つだと言えるのではないだろうか。
後期高齢者の同窓たちを想う
若林盛亮 2023年8月5日
同窓からメールが来た。
狭心症でつけていたカテーテルに不具合が生じて新しいカテーテルに取り替える手術を受けるというものだった。やはり不安があるようで無事に手術がいくことを祈ってるとあった。幸いうまく行ったようで「助けられた命を大切に、残りの人生を、目一杯、楽しみたい」とまたメールが来た。
その彼からは同窓がまた一人亡くなったことを伝えるメールももらっていたが、自分も「もしや」と思ったのかもしれない。彼は、「拉致容疑」がかけられても欠かさず私に手紙をくれていた恩師の墓参に私の長男を連れて行ってくれた人、長生きしてくれよと思う。
別の同窓はガン移転が見つかって副腎片方を切除したがやはり疲れやすくなった、あと数年は頑張れるやろうというメールももらったが、弱気になったらあかんでと言いたくなる。
数年前から狭心症のM君は、発症以前はフルマラソンやバイアスロン(水泳+自転車+マラソン)競技に参加するなどハードな運動をこなしていた人だが、発症以降はゴルフと散歩、ジム通いだけにしたそうだ。
副腎をとったI君は、学生時代のカントリー系のバンド仲間と「爺さんバンド」をいまも続けている。指が若いときのように動かなくなったそうだが年末のライブ講演を楽しみに練習もやっている。
後期高齢者になった同窓たちだが、みんな身体の故障をかかえながら老後の人生をそれなりに楽しんでいる。孫たちにも恵まれてみんな幸せそうだ。
彼らとは、いまも「若ちゃん」「コーちゃん」「せっちゃん」と子供時代のように呼び合っている。こんなことは故郷の同窓としかできないことだ。共通の故郷での思い出が絆になっている。そんな人間関係は故郷愛にもつながる。
10月には同窓会が持たれる予定と聞いている。私はメールで挨拶を送るが、一人でも多くの同窓との「再会」を果たしたいものだ。自分には故郷があると感じられる数少ない機会でもある。
ロシア音楽はロシア愛国闘争の原動力
赤木志郎 2023年8月5日
今回、戦勝70周年記念音楽公演でロシア代表団と中国代表団を迎え、ロシア音楽と中国音楽も歌われた。とくにその中でも朝鮮人歌手が歌うロシア音楽が素晴らしかった。そのいずれもがロシア愛国心を格調高く歌い上げるものだった。ロシアでの音楽公演でしばしば歌われるもので、ロシア音楽公演集をひごろ聞いている私の知る音楽だった。
その公演のロシア音楽集のみ録画して、今、それに浸っている。
元来、小学生のとき、「ともしび」をはじめ「ヴォルガの舟歌」「ステンカラージン」「カチューシャ」などを習い、ロシア音楽に親しんでいた。欧米の歌ではアイルランドの民謡が日本人の情緒に合うくらいで、ロシアの音楽が日本人に合っていると思った。「ともしび」はその代表曲で、各地に産まれた歌声喫茶の看板が「ともしび」だった。
私がとくにロシアを好きになったのは、高校生のとき「ロシア文学短編集」を読んだときだった。欧米文学と異なる人間愛、家族愛が満ち溢れていた。それからゴーゴリの「外套」、プーシキンの「大尉の娘」、ドストエフスキーの一連の作品を読んだ。
また、高校生のとき、「鋼鉄はいかに鍛えられたか」をはじめとするソ連映画も多く見た。
それでわたしはロシア文学に示されたロシア人の情愛、人間愛がロシア革命の豊かな土壌だと思った。
かつてロシア文学にロシア革命の源泉を見いだしたとしたら、今、ロシア音楽を聞きながら、ロシア音楽がロシア愛国闘争に奮い立たせていると改めて思った。とくに「起ちあがろう」「ひたすら勝利ひとつのみ」「ロシアのために服務する」などは愛国の闘いに奮い立たせる歌だ。
現在のウクライナ戦争はロシアの侵略ではなく、欧米・NATOの侵略にたいする祖国防衛戦争だと私は見ているし、ロシア国民もそうとらえている。その戦いは、米国の覇権主義と戦う世界人民の最前線になっている。ナポレオンの侵攻、ナチスドイツの侵略を退けたように、今回の欧米・NATOのウクライナ代理戦争や全面的な経済封鎖に対しかつてと同じようにロシアはかえって強国となり、それを粉砕することだろう。ロシアには愛国の伝統があるからだ。
知人によると、日本でも近くロシア音楽公演が催されるという知らせがあったが、ロシア民族の愛国心を知る機会になればと願っている。
こちらはチャンマ(梅雨)です
魚本公博 2023年8月5日
朝鮮は今チャンマ(梅雨)の季節です。これも異常気候の影響でしょうが、例年は7月中旬から始まるものが今年は6月からチャンマ入りし、それが今も続いています。降ったり止んだりの日本の梅雨に似た降り方なので、暑さも和らぎ凌ぎやすい気候になっています。
それでも晴れ間には夏の太陽が顔をのぞかせ強い日差しになり温度も上がるので農業には良いようです。周辺の農場の稲もトウモロコシも青々と大きくなっています。
私たちのところに新聞記事をメールで送って下さっている“寅”さんから「Subject;暑さボケ再送」で再送されてきた記事のコメントに「東京でも連日35度越で本当にやになります。そちらも今年は猛暑ですか」とありました。他の方々からも猛暑を心配する声が寄せられますが、上で述べたようにご心配には及びません。
それよりも、チャンマで問題なのは豪雨です。毎年7月末から8月初めにかけて必ず豪雨があります。豪雨時には目の前のテドンガンも濁流が矢のような速さで流れます。昨年は川辺の畑が水没するほどでした。最近は、台風も朝鮮に上陸する回数が増え、今後、台風と連動した豪雨が心配です。もちろん朝鮮は、これに対し河川改修や排水強化、畑の溝を深くしたりと警戒怠りなしです。
日本も7月中旬には北九州を始め各地で集中豪雨がありましたが、今は、猛暑ですね。
日本各地で40度近くまで上昇し、熱中症警戒アラートもたびたび発令されているようです。欧州でもギリシャやスペインは45度超え。中国では52度、米国では54度を記録したところも出たとか。
世界的な異常気候の中での猛暑ですが、皆さん、熱中症には十分に注意し、お元気でお過ごし下さい。
米国の愛国心低下に思う
小西隆裕 2023年7月20日
このところ、米国における愛国心の低下が著しいと言う。
2022年、米建国記念日当日、その日を非常に誇りに思うと答えた人は、1998年が70%だったのに対し、38%に止まったという。
そこには、いろいろな要因があるだろう。個人主義の深まりが大きな要因になっているのは明らかだ。
そうした中、米国政治に対する愛着、信頼、誇り、等々の低下が決定的なのではないかと思う。1%のための政治といわれる国内政治への不信、「ヤンキーゴーホーム」の大合唱に見舞われる対外政治。これでは、米国人が自分の国の政治に愛着も信頼も誇りも持てず、愛国心を持てなくなるのも当然だと思われる。
そこで思うのは、わが国のことだ。
これまで日本の政治は、われわれ日本人に日本への愛着、誇りを抱かせる方向でやられてきただろうか。
特に、戦後、米国による日本への統制が強められる中、その観点は著しく弱めさせられてきたように思われる。
それがわれわれ日本人にとって何を意味するのか。そうした中、日本人のアイデンティティが大きく弱化したことなど、深く考えるべき時が来ているのではないだろうか。
対照的な戦争への思い-朝鮮と日本
若林盛亮 2023年7月20日
朝鮮では6月25日から7月27日までは「反米月間」だ。6月25日というのは朝鮮戦争勃発(1950年)の日、7月27日は停戦協定成立の日(1953年)だ。朝鮮では朝鮮戦争は祖国解放戦争、すなわち「米帝国主義の侵略戦争に対する祖国解放のための戦争」とされている。停戦協定成立の日「7・27」は、その侵略戦争を撃退した日として祖国解放戦争勝利の日「戦勝記念日」と呼ばれ、近年、ますます盛大に慶祝されている。
今年の7・27は戦勝70周年であり、盛大な祝賀行事が予定されている。おそらく全国から老兵がピョンヤンに招請され大きな閲兵式や音楽公演などがあると思われる。
最近のTV番組では、戦闘英雄や兵士の遺した手記に基づくドキュメンタリーや老兵の語る戦闘談が特に新しい世代の若者を対象に放映されている。
金正恩総書記は祖国解放戦争時期を「偉大な年代」とし、戦争勝利記念館前の大きな「勝利像」の台座には「偉大な年代に敬意を捧げる」との直筆が刻まれている。
戦争参加者は「老兵」、偉大な年代を勝利で輝かせた老革命世代として社会的に尊敬され、老後の生活に不自由なく優待する社会的気風の中で、自身のかつての革命精神を後代に語り継ぐ「語り部」として老いたりとはいえ社会の柱としてかくしゃくとして生きている。
ひるがえって日本の場合はどうだろうか? 日本の行った直近の戦争は「太平洋戦争」とも「アジア太平洋戦争」とも明確な定義づけもなく、「先の戦争」「あの戦争」とか呼ばれている。靖国神社では戦没者の方々を「英霊」とし祀っているが、これを信じる国民は極少数派だ。
私の少年時代の記憶に戦没者を祀る忠魂碑に関する複雑な思いがある。
小学校の運動場の横に鎮守の森のようなのがあって、そこに忠魂碑、戦没者を祀る大きな石塔、慰霊塔が立っていた。戦時中は天皇に忠実な「英霊」を鎮魂する意味で「忠魂碑」として尊厳ある場所となっていたのだろう。
でも私の子供時代は「あそこはアベックが変なことをやる所だから近寄ってはいけない」と言われた。また母の実家の村の野洲川沿いの深い竹藪にはひっそりと10個ほどの墓石があって、そこに母の実兄も含め村の戦没者が祀られていた。暗い竹藪の中にある墓はふだん訪れる人も居なかった。子供心に「死んだ兵隊さんは寂しいだろうな」と思ったものだ。
「忠魂碑+男女アベック=近寄ってはいけない忠魂碑」、これが戦没者にどう対していいのかわからない戦後日本の実相のような気がしてならない。
あの戦争をどのようにとらえ、どのように総括するのか、それなしには戦没者の魂も鎮魂されない。ひいてはそれが戦後日本人のアイデンティティがあいまいな自信喪失の続くひとつの要因でもあるように思う。
もうすぐ8月15日がやってくる。これも「終戦の日」というあいまいな日のままだ。
半年経って、見る風景
赤木志郎 2023年7月20日
半年前、大病に襲われ、その後、2週間の入院および半年間の安静期間を終え、快癒して久しぶりに市内に出た。
半年前は1月の半ばで、零下10度以下の日が続いていた真冬のときだった。そして、今は7月の梅雨の真っ最中。田んぼは青々とし、とうもろこしは実をつけて伸び、それに何よりも木々が大きくなっていることに驚いた。村の近くの小高い丘は40年間も植物が育たないところだったが、今年は林になっている。日本人村は森の中にあるように緑に囲まれているが、市内まで続く道と市内も緑に囲まれているのを感じた。それが第一印象だった。冬景色だった半年前との対比のせいで余計そう感じるのかもしれない。
TV報道で緑化、園芸化にとりくみ、河川の整理を大々的にやっていることを知っているつもりだったが、そのことを実感する市内行きだった。報道によると大々的な植樹以外に河川整理などが全国的規模でおこなわれており、朝鮮全体が緑の国になるのは遠い話ではない。かつての朝鮮から見る日本は「緑の島」だったそうだが、今は、朝鮮(北半部)が緑の半島になっているのかもしれない。
緑化や環境を整備することも人間のためであり、国のためだということは言うまでもない。
その当たり前のことをたゆまず推し進めているのが朝鮮のよさだと思う。国防建設と経済建設、住宅建設と農村建設、そのなかにあっても緑化をも進めているのであった。そう考えながら小雨の中、村に帰ってきた。
麦畑の思い出
魚本公博 2023年7月20日
いよいよ猛暑の季節、皆様に暑中お見舞い申し上げます。
日本では、この7月、各地で集中豪雨が発生。私の故郷・大分県を含め北部九州で大きな被害が出たようです。その後は、高温現象が。すでに北関東では39度を記録するなど今年の夏も猛暑になりそうです。
こうした異常気象は朝鮮でも見られ、例年7月末から始まるチャンマ(梅雨)が今年は6月から始まりました。でも6月からのチャンマは、高温化を押さえ例年より凌ぎやすくなっていますし、農業にとって良い結果をもたらしているようで稲もトウモロコシも例年より青々としています。
そういう中で気付いたのは麦畑が広がったことです。「穀物生産構造を替えて、コメと麦農業を強く促進する」ことが言われており、麦栽培が広がっているようです。
麦栽培は、幼い頃の記憶に結び付いています。周囲が農村地帯で日曜農業もやっていた我が家では、冬になっての霜柱が立つ頃、浮き上がる麦を踏みつける麦踏みなどやらされたものです。そして初夏に広がる黄金の麦畑。その麦の稈(ストロー)で麦笛を作ったり、ストローで編んだカゴに周辺の木イチゴを摘んだ思い出もあります。ちなみにイチゴの英訳はストローベリーであり、飲み物を吸う管もストローです。
朝鮮の場合、寒冷地のため麦の収穫が7月になり、コメの裏作として麦を植えるという二毛作は難しいのです。しかし国家政策を実現するために各地でこれを克服する方途も立てられているようですし、近い将来、全国土的に麦畑が広がる風景も見られようになるでしょう。
日本は早くからコメ・麦の二毛作が行われ麦の生産も多かったのに、米国の食料戦略で米国の麦への依存を強要され、今では麦の自給率は10%ほどに低下し、青々と広がる麦畑、初夏の黄金の麦畑も見られなくなったのは残念なことです。
これから本格的な夏に入りますが、皆様、健康に気をつけてお元気でお過ごしください。
暑中お見舞い申し上げます。
森順子 2023年7月20日
朝鮮もエルニーニョの影響で、ポギョン(暴炎)の真っ最中です。
それで学校は、7、8月と2ヶ月間の夏休み。市内では、野外活動やサークル、泳ぎに行く子どもたちの姿も多く見かけます。朝鮮は、数年前から就学前教育の英語授業や知能教育、ロボット教育などを実施していますが、今年また、時代の趨勢に合った教育に引き上げることを強調しています。
子どもたちが、主体的に学習し探求できることに中心をおいて教育方法を絶え間なく改善しなければならないということです。英語などは、教科書だけでなく、子どもが好きな歌や、マンガのせりふを英語で覚えたり、廊下を歩くたびに英語のスピーカが話しかけ、それに答えるようになっていたりと、工夫しています。
2カ国語の習得が必要な学校では、1時間の授業時間に、30分間ずつ、2カ国語の授業をやるそうです。この方法は、2カ国語を比較できるし違いも解り早く習得できるそうです。
普通だったらちょっと考えもしないようなことです。だから、夏休みは、教員にとって、授業準備や教育内容や方法の研究など、非常に大切な時間になるのだと思います。それに、毎年、教科ごとの教育方法の発表会みたいなのがあって、そこで、評価された教育方法は、全国に一般化されるわけです。
こうだったら、朝鮮の教育水準は、どんどん上がっていくだろうと思います。そこには、教員の見えない努力と献身があり、先生たちの教育者としての誇りがあるからだと、いつもテレビを見ながら少し胸を熱くしています。
暑中お見舞い申し上げます
若林佐喜子 2023年7月20日
暑い日が続いていますが、いかかお過ごしでしょうか?
朝鮮は、6月末に梅雨に入り、7月からポギョン(暴炎=33度以上)のため託児所、幼稚園、学校は夏休みです。吉報は、検温と消毒は続いていますが、マスクの着用義務が薬局と病院を除き解除されました。初めは、なにか忘れ物をした感じで落ち着きませんでしたが、今は、すっかりなれ気分も爽快です。
梅雨とエルニーニョ現象が重なり、豪雨、暴風、ポギョンと変化の激しい日々が続いていますが、早くから、河川整備などが行われてきたせいか大きな被害もなく農作物がすくすく成長しています。力を入れているのが科学農業と多収穫で、その思いは農作業にも行き渡り、草一本無く整然とした田畑の様子に、農業通の安部さんも思わず「凄いね」とつぶやくほどです。一方、よど農場と言えば、みな文章活動などで忙しく草が茂りトホホ状態。それでも、キュウリ、なす、トマト、青じそが収穫でき食べ頃です。食事時には、好きな料理?は、焼きなす、塩もみ、みそ汁の具にはなすが一番とか、青じそとショウガをのせた冷や奴が美味しい!などの会話で盛り上がっています(笑)。
日本から送っていただいている、新聞、ネット情報、毎日、興味深くみています。最近では、「また値上げ 節約生活 もう音上げ」(「わたしの川柳」の最優秀作品)に、思わずほっこりしながらも、「う~ん、岸田政権ひどいよね」と、一人つぶやいたり怒ったり。つくづく、社会保障と雇用のあり方に問題ありと「思索」を重ねる日々・・。すでに、社会保障研究の折り返し地点なので、形にしなければとちょっと焦り気味の今日このごろです。
皆様、まだまだ暑い日が続きますので、くれぐれも水分補給をしっかり行い健康管理に留意なさって下さい。盛夏
私の「酒とタバコの日々」
若林盛亮 2023年7月5日
昔、ジャック・レモンという俳優の「酒とバラの日々」という映画があったが、私はいま「酒とタバコの日々」だ。
なにも酒に溺れているわけじゃない、溺れるほど飲めないしね。晩酌に朝鮮焼酎をコップ一杯くらいたしなむ。また一年ほど前から禁煙をやめてタバコを吸うようになった。それだけのことだが私には大きな生活の変化だ。
私は元来、酒に弱く、飲みたいとも思わなかった。興味を持つようになったのは「バーテンダー」という城アラキ原作のコミックを読んでからだ。お酒にまつわる人間ドラマ、それぞれの酒に歴史があること、カクテルという「お酒とお酒を混ぜる」あるいは「他の飲料と混ぜる」と全くちがう酒に生まれ変わる、その妙味にも惹かれた。
マルガリータというカクテルは、猟に行って誤って恋人を射殺してしまった男が、恋人への想いと償いのためにつくったというテキーラをベースにした「甘酸っぱい恋」の味、そんなドラマに思いを馳せながらこのカクテルを飲むと味わい深い。
またマティーニは「カクテルの女王」と言われるが、ベースはジン、労働者や貧民のための安酒だった酒だ。「ジン地獄」という絵画があるがそれは安酒に男女が酔いつぶれてロンドン中が地獄絵図というものだ。この安酒がワインに果実、香草の蒸留液を加えたフレーバーワインと言われるベルモットを混合すればたちまち匂い立つような「貴婦人」と化す、まさに乞食女が一晩でレディと化す「マイ・フェアレディ」の物語そのもののカクテルの妙味。
マンガを参考にカクテルをつくってみたら、これが案外イケた。仲間や朝鮮の人にも受けた。ジンくらいなら$20ほどで入手できたからジントニックなど皆に喜ばれた。もう十年も前の話だ。以降、わが「日本人村」を訪れる日本からの客人ももてなした。だから私は「BAR・裸のWAKAB.」店主兼バーテンダーを自称した。
いまはコロナ国境封鎖で洋酒は高価、高嶺の花になった。それで朝鮮焼酎を毎晩、晩酌で飲むようになった。夜10時に寝て朝3時頃に起きる、よく眠れて目覚めも良い、仕事もはかどる(気になっている)。
私と同じ下戸だった田宮が晩年、お酒をたしなむようになった。「おい! 酒は人類の一大発明だぞ」とまで言うようになった。たしかに年齢を重ねるとお酒の味がわかるようになる、これも人生の妙味だ。
タバコは去年くらいから。愛用は「高麗」(KORYO)というニコチン0.8mg、タール8mgのタバコ、「健康によい(?)」ということと濃紺色のフィルター、細身の長いタバコサイズ、ケースも淡い空色で一目惚れ、とてもカッコイイのだ。もっと若かったら女の子に「これ吸ってみない」とカッコつけるのになあという邪心まで芽生えそう。細身で長いから長持ちする。1本を二回に分けて吸えば経済的でもある。私にはちょっと高価だが他を節約すればなんとかなる。
文章に詰まったときには一服吸ってまた考える、また「上出来かな」と思える仕上がりの原稿を読み返すときなどに吸う一服の味はまた格別だ。まあ単なる自己満足かもしれないが、仕事がうまく行くならよし。
大谷選手とイノシシ
魚本公博 2023年7月5日
大谷翔平選手の活躍に今年も元気をもらっています。
とりわけ6月27日のホワイトソックスとの試合で、リアル二刀流で脅威の1試合2発の
28号本塁打と投手で7勝目は圧巻でした。これで本塁打と打点で首位を独走。三冠王も可能な好位置に。
この知らせは、メールでネット情報を毎日知らせて下さっているMさんから。その日だけは2回目のメールがあり、それで知りました。そのSubject: には、「大谷ファンなもんで、みんなに話したくて」とありました。日本でも大谷選手の活躍に気分スッキリ、元気もらっている人がたくさんいるのでしょうね。
私もその一人で、例年、野球シーズンではNHK・BSの10時40分からの「MLB」を見るのですが、今年は文章作業が山積し、中々時間をとれません。でも、その日はテレビを見て投打の活躍映像を見ました。スカッとして、文章作業もはかどりました。
そして今や31号。只々、驚嘆です。
大谷選手の活躍はスッキリ爽やかな気分になれるのですが、ここに来て、憂鬱な現象も。イノシシです。昨年も春先に出没し、よど農園の作物を荒すので困り果て、川辺の畑は放棄し、これまで被害のなかったアパート近くの畑に集中する作戦だったのですが、そこにも被害が拡大。特にさつま芋がやられ、まだ苗を植えたばかりで芋も付いてもいないのに、畝を掘り起こし食い荒します。
足跡を見ると、小さいので子どもイノシシなのでしょう。家族総出で畑荒しといったところで、心底ガックリきました。今後、夏秋の収穫期にはどうなることやらと憂鬱です。
大谷選手の活躍でそうした憂鬱もひっくり返して欲しいものです。
「利」
小西隆裕 2023年6月20日

朝鮮リンゴ、赤くなればさくらんぼのよう

狸それともアライグマ?日本人村で捕獲
このところ「らんまん」にはまっている。
朝ドラの「らんまん」だ。
朝観て、昼観て、録画したものを2回、時には3回観ている。
主人公の「槇野万太郎」には、本当に魅了される。
昨日学んだのは、「利」だった。
万太郎は、植物学者だが、決して「学者馬鹿」ではない。
人と活動する時、いつもまず相手の「利」から考える。
自分の要求を通す時、まず、それが相手の「利」に合うかどうかを考え、合うと判断して、話を進めていく。
合わなければ、合うように相手との関係を作っていく。
決して自分の「利」を一方的に相手に押し付けたりしない。
このような生活の真理を彼は一体どのようにして体得したのだろう。
ここからは私の推測だが、彼はそれを自然から学んだのではないかと思う。
虫と植物、植物と植物、動物と植物、等々、自然界はそうした無数の相互作用、助け合いによって成り立っている。
彼のように植物を愛し、自然を愛し、関心を持ってその生態を観察していたら、そうした生活の真理に気付かないはずはなく、それを愛し、それに学ばないはずがない。
「らんまん」は、観る者の想像力までかき立てながら、感動の回を重ねて行っている。
南ア・マンデラ大統領描いた映画「インビクタス/負けざる者たち」に感動!
若林盛亮 2023年6月20日
先日、BS放送で「インビクタス/負けざる者たち」という映画を見た。南アフリカ共和国の初の黒人大統領、ネルソン・マンデラを描いた映画、とても感動的な映画だった。
南アは悪名高いアパルトヘイト(人種隔離政策)によって黒人を人間として認めない800もの悪法をつくって白人植民地主義者の政権を維持してきたが、マンデラはこれと闘って28年間も(たしか)獄中生活を強いられた人だ。国内外からの圧力を受け仕方なく白人政権はマンデラを釈放、4年後にはマンデラは黒人に選挙権が与えられた大統領選で圧倒的に勝利、南ア初の黒人大統領となる。映画はマンデラが大統領として白人と黒人の共和国、南アフリカを人種間対立のない平和で豊かな統一国家としていかに築いたか、その苦闘の一端を示すもの。
映画の冒頭はこの国を表す象徴的なシーンで始まる。
舗装道路を挟んだ二つの競技場、片方は白人のラグビーチームの練習場、片方は黒人の少年たちがサッカーに興じる運動場。白人のそれは芝生のきれいに整備されたもの、黒人用のそれは土むき出しの粗末なもの。そこに刑務所から釈放されたマンデラの車列が来る。黒人の少年たちは「マンデラ! マンデラ! マンデラ!」と熱狂歓迎、片やラグビーチームの白人は憮然と車列を見る。ある白人青年がコーチに「マンデラって誰ですか?」と尋ねる、するとコーチは「釈放されたテロリストだよ」と答え、こう吐き捨てる-「覚えておけ 今日がこの国の破滅の始まりだ」と。事実、この後、内戦勃発寸前の事態が起きる。多くは白人政権の陰謀がらみだった。
この冒頭シーンだけで当時の南アがどんな問題を抱えていたかを雄弁にわからせてくれる。黒人の熱狂歓迎が白人には「破滅の始まり」に映る、そんな時期にマンデラは大統領としてこの国の統治を託されたのだ。
黒人にとって白人はこの国の人種隔離政策で富と権力を独占した「憎むべき支配者たち」、白人にとって黒人政権は自分たちを破滅に追い込む「敵対者」、こんな国の空気をどのように変え、国の統一を図るかがマンデラが大統領としてやるべき最初の重い課題だった。
この映画はラグビーを通してこれをやりとげたマンデラの闘いを描く。
黒人選手が一人というこの国のラグビー国家チームはワールドカップでも弱小チームだった。そんなチームを南アで開催されたワールドカップで優勝に導く、その歓喜を白人だけでなく黒人も共にする。そんな劇的転機をマンデラが大統領として成し遂げる。
黒人たちはラグビーチームの名称、ジャージの色、応援歌を白人時代のそれとは違うものに変えよと主張する。マンデラは「それはダメだ」と止めさせる。サッカーの世界でもそうだがチームの名称、チームカラー、応援歌(アンセム)はそのチームの歴史そのもの、もし「レッズ」と親しまれてきたリバプールのユニフォームが「赤」でなくなったら、また有名な応援歌“You’ll Never Walk Alone”が違う歌になったらどうなるか? サポーターの怒り、落胆は暴動さえ起こしかねない。私だってその心情はわかる。マンデラがそれを守ってくれたことで白人選手、サポーターたちに黒人政権への安心と共感を呼ぶ。
次ぎにマンデラは国のラグビーチームを世界最強にすることに取り組む。「負け癖」のついたチームにいかに奮起を呼び起こすか?
彼は自分の執務室にチーム・キャプテンを呼ぶ。そして人が持てる以上の力を発揮するためには? と話を切りだし自分の刑務所での体験を話す。「打ちのめされたとき自分は英国に多くを学んだ」と言いながら英国のビクトリア時代の詩に鼓舞されたこと、そしてバルセロナ五輪のラグビー競技で歌われた国歌「神よ アフリカに祝福を」にも鼓舞されたことを彼に話した。
会見を通じてチームキャプテンは大統領が白人敵視の人物でないこと、全国民を鼓舞するワールドカップ優勝が大統領の願いであることを悟る。そのためにチームの志気を高めることの大切さを学ぶ。
こうしてチームに戻った彼は、まず黒人少年たちにラグビーを教えることを仲間に呼びかける。しかし仲間たちの反応は拒否感に近いもの、だが実際に黒人少年に教える過程で白人と黒人は一緒にやっていけることを全員が実際に体験する。
また彼はチーム全員をマンデラが収容されていた刑務所に連れて行く、そこでマンデラがどのように過ごしたかを全員に体感させる。
こうした過程でチームにはこの国の白人、黒人全ての国民のためにワールドカップ優勝の決意と覚悟が育くまれていく。
そして南ア開催のワールドカップで強豪国を次々と撃破、優勝戦では最強のニュージーランド相手に拮抗した試合を展開、ついに優勝の栄光を手にする。
熱狂する会場には「神よ アフリカに祝福を」の国歌が流れる。
会場貴賓席のマンデラ大統領も歌う、観客席の黒人も白人政権時代からあるこの歌を歌う、そんな黒人観衆を見て白人は、この国が白人と黒人の国であることを肌身で感じる。
国歌では「我ら 心一つに立ち上がろう」の歌詞が流れる。
マンデラという人間の大きさを映画は見せてくれた。そして政治がどのようなものでなければならないかも学ばせてくれる。泣けてしょうがなかった、久しぶりにいい映画を見た、心から感動した。
インドネシア、父親の思い出
魚本公博 2023年6月20日
天皇夫妻のインドネシア訪問で、大統領夫人の故郷ソロに話しが及び、歌謡ブンガワン・ソロが話題になったという記事を見ました。
ブンガワンソロは、オランダ植民地時代の下、悠々と流れるソロ川に祖国への愛を託して謳った国民歌謡です。先の大戦でインドネシアに出征した日本兵が持ち帰り日本でも流行したのだそうです。
そうした記事を見ながら、亡くなった父親のことを思い出しました。
父親も大戦中、インドネシアに出征していており、もう一つの代表的な国民歌謡である「私のきれいな娘さん」(ノーナマニシャパヤンプーナ)を原語でよく歌っていました。
ノーナマニシャパヤンプーナ ノーナマニシャパヤンプーナ ノーナマニシャパヤンプーナ ラササンヤ サンヤゲー ダリマナダータンヤンキター ダリマナタンディカリー・・・・
父親は歌だけでなくインドネシアのことも色々と話してくれました。通訳もできるほどインドネシア語に堪能で、現地の人との交流も深かったようです。ちなみに、インドネシア語は日本人が一番習得しやすい外国語だそうです。
そういうことから私はインドネシアには、昔から親近感があります。60年代、スカルノ大統領が中国との関係を深める中、65年に9・30事件が起き、スハルトの逆クーデターが起きますが、その経緯を手に汗を握る思いで注視したものです。
インドネシアはバンドン精神の発祥の地。どの陣営にも属さない非同盟。主権第一で対外干渉を許さず、互いに協力して「平和と繁栄」を図る。その精神は、インドネシアはもちろん、ASEAN諸国の国是になっています。
米覇権が音を立てて崩れつつある中、主権第一で協力して「平和と繁栄」を図る、そうした新しい国際秩序が求められており、世界はそのように動いています。
インドネシアの事では、キリシタン追放令で、追放された混血女性が故郷の親族に宛てた手紙の末尾に「日本恋しや、日本恋しや、日本恋しや・・・」と連綿と綴った「ジャガタラ文(ふみ)」のことも脳裏によぎります。
戦国時代からの日本とインドネシアの浅からぬ因縁。天皇夫妻の訪問を機会に、インドネシア、特にその生き方への関心が深まればと願いながら、父親のことを思い出しています。
生きる目標
小西隆裕 2023年6月5日
このところ冲方丁著の「光圀伝」を読んでいる。
最初は「家康」から出発し、その孫である光圀を知って、家康への認識を深めようとしたのだが、読み進むにつれ、光圀自身に魅了されるようになった。
いろいろあるが、何と言っても、凄いのはその志だ。
戦国の世が終わり、侍として、人間として何を目標に生きるかの段になって、彼は、「詩歌で天下を取る」を目標にした。
もちろん、その後目標は変わっていくのだが、最初「詩歌で天下を取る」と志したのは凄いと思う。
人間、何でもよい、天下を取るほどの目標を持ってこそ事を成せるのではないだろうか。
この目標が光圀という偉人を生んだのだと思う。
しかし、それにしても、家康という祖父が在っての光圀。
家康に対する認識も深まった。
私の週末LIFE
若林盛亮 2023年6月5日
5月27日(土)から28日(日)にかけての私の週末のLIFE記録。
土曜の午後はやりかけの原稿1本、だいたい体系を立て、小題目を考えて文章の流れを構想、「よしこれでいこう」と決める。
午後6時、朝鮮体育放送の番組予告をビールを呑みながらチェック、8時43分から英プレミアリーグのLiverpool:チェルシー戦の予告、お?っやったあ! 私は熱狂的レッズ、Liverpoolサポーター。ずいぶん前の試合だが、私には生身のレッズの選手達が躍動する試合観戦は心が躍る。BS放送では全くやらなくなったから、今は朝鮮のTV放映が唯一の頼り。
夕食後、朝鮮のニュースを見て、度数30度の朝鮮焼酎をちびりちびりやりながらサッカー観戦。久々に見るレッズの選手達を見ると俄然、興奮する。攻守の切り替えの激しい展開で見応えあり、でも0:0のまま試合は動かない。お酒で少し居眠ってるうちに試合は終わってた。今シーズンの結果はもうわかってるので「まあいいか」。
居眠りの余韻のまま10時頃就寝。
日曜朝3時に起きて事務所に出て構想した原稿を仕上げる。
8時、朝食はトーストにゆで卵、アスパラ(畑でとれる)、キャベツ、キュウリ、トマトをのせたもの、飲み物は朝鮮のヨーグルトが定番。
日曜は雨になって定例のゴミ焼きは取りやめ。
9時頃に事務所に出てもう1本の原稿を構想、短いものだから「まあこれで行こう」といったところで構想を終える。
昼食はお好み焼き。
夕方6時からは、NHK大河ドラマ「どうする家康」を録画、小西さん、安部(現姓は魚本だが私たちはこう呼ぶ)さんはその場で視聴。
7時からカレー夕食、USB録画した「どうする家康」を佐喜子さんと見ながら食べる。晩酌は焼酎。
朝鮮のニュース、天気予報を見て、風呂に入る。
風呂上がりに朝鮮体育放送でやるちょっと前の欧州チャンピオンズリーグ16強戦の英チェルシー:独ドルトムンド戦を観戦、2:0でチェルシーが勝ち、準々決勝進出を決める。この結果はレッズサポーターの私には関係のないこと。
10時頃、就寝。
だいたいこんな週末の過ごし方をしている。
草の尊厳
小西隆裕 2023年5月20日
今回の朝ドラは、「らんまん」。明治の植物学者、牧野富太郎をモデルにした作品だ。
主人公、槇野万太郎は、植物学者になるために生まれてきたような人。
病弱だった幼少の頃から植物には目が無かった。
小学校も、そこではもはや何も学ぶものがないと、中退。土佐一番の大酒造主の跡取り息子として生まれたからこそできたことだが、独学の植物学、研究三昧の少年期を過ごした。
物語は、その彼が酒造り家業を姉に譲り、東京大学で植物学の研究をしようと、一度会っただけの植物学者を唯一の伝手に上京して下町長屋に居を構えたところまで進んできている。
ここまででもいろいろ感動するところはあったのだが、その中でももっとも感動したこと、それは、主人公の植物に対する態度だった。
万太郎にとって、もっとも我慢ならないもの、それは雑草や名も無き草花のことを馬鹿にし、大切にしようとしない人間の態度だった。
そういう場に出会う度に、彼は、「どんな雑草にも名前がある。もし、ないなら、私がつける」「どんな草花も、同じものは一つもない。一つ一つ、自分にしかない個性を持っている」「どんな草木も、皆、同じままではいない。今日のこの草は、昨日のこの草ではない。だから、草木との出会いは、皆、一期一会じゃ」、等々と言いながら、植物一つ一つの持つ尊厳を説き、大切にする。
こうした名も無き雑草、草木、草花に対する彼の態度が自分の祖母や姉、奉公人や友人、そしてすべての人々、引いては、自分と共に生きるすべての生き物の尊厳を認め大切にする態度に表れないはずがない。
物語は、まだ始まったばかり。これからの展開が、これまでの朝ドラにも増して楽しみだ。
私の儚はかない「夢で会いまShow」
若林盛亮 2023年5月20日
私はめったに夢を見ない人間だ。一年間、夢を見ないなんてザラだ。ところが16日の夜、正確には17日夜明け前頃、夢を見た。
どこか外国のひなびた町を誰かに案内されてある部屋に入ると、布団から顔半分を出して女の人が寝ていた。ベッドの横には二人の女性が立っていた。それがなんと小泉今日子、もう一人は柴崎コウだったか北川景子さんだったか? かもす雰囲気、イメージは柴崎コウだが顔は景子さんのような・・・
素敵な人に会える! と思ったとたん、目が覚めた。なんとも惜しい! せっかくお話できるチャンスを逃した、夢とはいえとても悔しかった。
小泉今日子は先日、朝日新聞で彼女のインタビュー記事を読んだからだろう。
記事の中に「安保法制反対デモをやるシールズの若者を見て、自分たちが若い頃、よくやってこなかったから今の若い子達にこんなことをさせている」、そんな自責感からSNSで政治的発言をやるようになった、そんな彼女の言葉に私はとても感動した。キョンキョンはスゴイ!
だから夢枕に彼女が出てきたのだろう。夢ででも私に会ってくれたのはちょっと感動!
柴崎コウも種苗法改悪に反対するSNS発信があったから彼女が夢枕に出てくるのもわかる。それに大河ドラマの「井伊直寅」もカッコよかったし・・・
でも全体の感じは柴崎コウだったけれど顔は北川景子さんみたい、これは何でやろ?
想像するに、以前、BS-TVで印象派画家ゴッホの足跡を訪ねる旅のナビゲーターを彼女がやって、景子さんもゴッホファンだと知った。ゴッホがピストル自殺を遂げた場所に立って涙ぐむ景子さん、そんな彼女に惚れた。私はこういうつい自分をさらけ出してしまう女優さんが大好きだ。女優は演技も大切だが人間性が第一! だからこの方は「さん」付けで呼ばせていただいている。「どうする家康」の信長の妹「お市さん」も景子さんがやると素敵な「お市さん」になる。
見た夢を分析すると、政治的感動ということで小泉今日子と柴崎コウ、でも柴崎の顔を景子さんにしてくれたのは、私の好きな女優を知った「夢の神様」のご配慮だったのだろう。
夢なんてただの夢、でもめったに見ない私の夢はなんか訳がありそう。ということで想像してみました。
も一回会いたいなあ、小泉今日子、柴崎コウ、そして北川景子さん! 今度会ったらゼッタイ、お話がしたい。
でも私の「夢で会いまShow」にたぶん続きはないだろう。
私の夢は儚い、予告編だけで本編はない。めったに夢を見ない爺さんの悲劇!?
コロッケとお好み焼き
赤木志郎 2023年5月20日
歳をいって食べたいと思うのは、昔、幼いときによく食べたものだ。わたしの場合、それはコロッケとお好み焼きだ。
コロッケは小学生のとき毎日の昼食のおかずだった。近所の肉屋で売られているものだ。1個7、5円だった。「今日もコロッケ、明日もコロッケ」と、コロッケの歌を口ずさみながら、美味しく食べていた。
お好み焼きの店は町の到るところにあった。神戸はメリケン波止場があるようにメリケン粉(小麦粉)の主な輸入港であり、小麦粉を使ったたこ焼き、お好み焼きの店が数多くあった。多くはお婆さんの内職の店だった。当時、1枚15円で小遣いのお金で食べることができた。
コロッケは揚げるので油を多く使うために自分では作らない。作ってもらうか、食堂で注文するしかない。3月8日の婦人デーに女性の代わりに男性が料理を作ってくれるというので躊躇なくコロッケを頼んだ。お好み焼きはキャベツと豚肉さえあれば簡単に作れる。今は新鮮なキャベツを手に入れることができるので、久しぶりに自分で作って食べた。美味しかった。
食べると子供の頃を思いだす。お好み焼き屋はいろんな人と交わる社交の場でもあった。同級生のお母さんから文集に載ったわたしの詩が良かったと言われたこと、どこかのおあ兄さんがはやく結婚しろと言われて怒って代金を払わず出ていったことなどなど。
歳をいって食べたいと思うものが幼い時よく食べたものになる理由は、郷愁にあるのだと思う。
小さなママ犬
森順子 2023年5月20日

一人ぼっちのパパ犬
今年の春は、なぜ、こんなに冷えるのかしら。
4月始めは、暖かい日が続き、少しずつ動けるようになったのですが、もう5月中旬なのに、また冬眠したくなるようなこの頃です。この気候に対応できていないので困ったもんです。
生活のことを言えば、いつも私たちを和ませてくれている小さいママ犬が、2回目の妊娠をして、4月に出産だったのですが、ママ犬の踏ん張りが足りなかったみたいで、ママ犬と胎児共々、死亡してしまい、皆もがっくりきています。勝ち気なママ犬の後ろに、おとなしいパパ犬がいつもついて歩く光景は、微笑ましいというか、心に残るくらいです。今年の始めくらいまでは、猫もいて、パパ犬と一番じゃれ合っていたのが、猫も家出をしてしまい、ママ犬もこんなことになって、パパ犬は、ひとりぽっちなので、もうはしゃぐこともできず、よく佇んでいる姿をみます。そんな姿は、やはり、寂しく映ります。動物でも伴侶が、いなくなったことが分かるのでしょうか。
故郷-帰りたい 帰りたいなあ
若林盛亮 2023年5月5日
「デジタル鹿砦社通信」に私たちは2回/月の寄稿を、また毎月末日、私の「ロックと革命in京都 1964-70」連載をさせて頂いている。その「デジ鹿通信」に書家、龍一郎さんの見事な筆致による「今月の言葉」が掲載される。
「4月の言葉」に心が動いた。
「“故郷” ふるさとの桜は 今年も 美しく 咲いているだろうか 帰りたい 帰りたいなあ」
私の故郷、滋賀県の草津には毎年、春ともなれば町の上高く流れる天井川、草津川の桜並木に見事な桜が咲き誇り、さながら花のトンネルをなす。
幼い頃は両親に連れられてお花見をして「これはお爺ちゃん達が植えはったんやで」と教えられた。自我に目覚めた青春期、花のトンネルを「特別な同志」とくぐりながら、ぼんぼりに浮かぶ夜桜の魔力に魅せられて魂が急接近。故郷の桜には安穏、波乱、恋、いろんな思い出がつまっている。私が故郷を離れても何十回と桜は変わらず春になれば鮮やかな花を付けたことだろう。
天井川は大雨以外の日は水が流れない。川原は子供の頃はかっこうの草野球場になった。打ったボールが土手の草むらに飛び込むとみんなで大探しをやった。当時、1個の軟球は子供には貴重品、見つかるまで必死に探したものだ。
草むらに小屋を作って自分たちの「隠れ家」にした草深い土手の堤防、あの草むらが目に浮かぶ。いまは整備されてすっかり変わったことだろう。
台風シーズンには豪雨の激流に一変、土手が切れれば町の上から大洪水がなだれ落ちてくるのだから台風の日は怖い天井川に一変した。いまは水路を変えて公園化されたと聞く。
でもあの天井川は草津のシンボル、故郷を想うときは必ず草津川の情景、そこでの思い出がまず浮かぶ。
今年は10月に中学の同窓会が開かれると友から聞いた。
私も友らも75歳を越えた後期高齢者、年々、同窓も一人二人と数が減っていく。癌の闘病中、という友もいる。だから今のうちにと持たれる同窓会だ。
「帰りたい 帰りたいなあ」・・・友らの顔が浮かぶ。
とても行きたい同窓会、せめてメッセージででも友らと会いたい。
元気ないいメッセージを送れるように、日々精進を励もう。
龍一郎さんの書を見て、そんなことを考えたりした。
衰退する地域
魚本公博 2023年5月5日
今回の統一地方選は、投票率も40%台であり、議員の「なり手がない」ことによる無投票も増え、全般的に低調のまま終わりました。
この低調さをマスコミは「選挙制度に問題がある」と分析しますが、そもそも、歴代自民党政権の地方政策は、新自由主義の「選別と排除」の論理で、力のある中核市にカネ・モノ・ヒトを集中して、弱小自治体は「切り捨てる」というものであり、その結果ますます地域が疲弊したことが、この低調さの背景にあることを見逃してはならないと思います。
BSの旅番組を見ても、地域の疲弊ぶりを感じます。とりわけ山間地帯の狭い谷間にある数軒ばかりの集落の人影もない「現代の姥捨て山」のような風景には胸が痛みます。市街地でのシャッター街も増えましたね。鉄道旅の風景では乗客はガラガラ、ワンマンカーも増え、無人駅も増えています。漁港でも、前は30隻あったんだが今はうちを入れて10隻だよ、みたいな話しが聞かれます。
地域の「祭り」も地域が衰退する中で、その維持も大変なようです。それでも皆でワッショイ、ワッショイと神輿を担いだり、山車を引いて盛り上がる姿は、活気があります。
やはり、人間は力を合わせて一つのことを共同で成し遂げるとき活気づくのだと思います。そういう人々の心の中にある共同性への希求、それを引き出し地域の共同体を作っていく。それが地域を活性化するカギになるのではないのでしょうか。もちろん、そのためには共同性を否定し共同体を破壊する政府の新自由主義的地方政策を止めさせなければならないことは言うまでもありませんが。
「家康」(安部龍太郎)前編(全8巻)を読み終えて思ったこと
小西隆裕 2023年4月20日
家康ものにはいろいろある。家康を肯定的に描いているものの代表作は、やはり何と言っても山岡荘八の「徳川家康」だろう。
しかし、安部龍太郎の「家康」には、それとは違った味があると思う。山岡のが「思想」だとすれば、安部のは「政治」ではないかと思う。
その中でも圧巻は、スペインによる覇権との攻防だ。信長の「本能寺の変」、秀吉の「バテレン追放令」、等々を通して描かれる当事者たちのスペイン覇権への対し方は、現時代の米覇権への対し方にも通じていて、実に興味深い。
当時の当事者たちは、何を中心にスペイン覇権に向き合ったか。信長は、何よりも日本という国をこういう国にしなければという自分の「理念」を大切にしたのではないかと思われる。だからスペイン覇権をはね除け、スペインから見離された。近衛前久にとって、中心はどこまでも「朝廷」だったし、キリシタン大名にとって、それは「キリスト教」だった。彼らがスペイン覇権に接近したり敵対したりしたのも、従順であったのもそのためだと思う。これに対して、秀吉はどうか。彼にとって中心に置かれていたのは、やはり自分の利益、自分の権力だったのではないかと思われる。彼が「バテレン追放令」を出したのも、後にそれを引っ込め、スペイン覇権に従属しながら、それと一体になって朝鮮から中国への覇権を狙ったのもそのためなのではないかと思う。
では、家康はどうだったのか。家康の場合、信長に準じるのだろうが、それは、少し違うような気がする。同じ「理念」でも自分の頭の中で練り上げられた「理念」と言うより、武士や領民、多くの人々、皆の思いや要求が反映され、込められた「理念」と言った方が近いのではないか。
江戸時代が欧米や中国などどこの覇権の下にも入ることなく、日本独自の大衆文化の花が開いた260年にわたる長期に渡る安定期になったのも決して偶然ではないように思う。
「租界で花咲いて租界で散った」-和田妙子・「上海のマヌエラ」
若林盛亮 2023年4月20日
「をんな千一夜」-前々回の日本人初の女性映画監督、坂根多鶴子に続き今回は和田妙子、戦前、上海西洋地区租界で「マヌエラ」としてその名を轟かせたダンサーのお話し。彼女は戦前の朝鮮半島生まれ「外地育ち」の方。
短歌をたしなみ画家をめざしたけれど見合い結婚させられ夢かなわなかった彼女の母親が娘だけは「自分と違う生き方をしてほしい」と自由に生きるよう支えた。そのおかげもあって和田妙子は朝鮮の女学校卒業後、東京の文化学院に進学の予定が松竹歌劇団のレビューを見て衝撃を受ける。そして歌劇団入団、しかし恋多き彼女はいろいろ紆余曲折も経て中国に渡り大連を経て当時の魔都、上海租界へ。
「一流のダンサーになって西洋租界地のショーで踊りたい」とユダヤ人亡命ダンサーからスパニッシュダンスの指導を受け、日本女性であることを隠し国籍不明の「マヌエラ」としてショーに出るようになり、彼女のダンサー人生が花開く。
彼女はカルメンやボレロを踊り、またたくまに「上海のマヌエラ」としてスターになった。そのうちハリウッドからある映画の主演ダンサーの話があって、ところが渡米直前に日本軍の真珠湾攻撃が起き日米開戦でそれは中止に、その後も上海で踊り続けたが敗戦で全ては終わる。
戦後は米軍キャンプなどで踊るものの米兵の卑猥なヤジに嫌気がさし踊ることを辞めて結婚、その後は踊ることはなく喫茶店やナイトクラブ、日本料理店などを経営。
「租界で花咲いて租界で散った。私の踊りはそんな踊りだったのかもしれない」
この言葉を遺し「上海のマヌエラ」こと和田妙子さんは2007年に95歳でお亡くなりになった。ちなみにこの和田妙子の妹の娘が女優の内藤洋子、その娘、喜多嶋舞も女優、波乱に満ちた叔母の血を受け継いでいるのだろう。
「租界で花咲いて租界で散った」和田妙子、「上海のマヌエラ」だが、日本人であることを隠し中国大陸で有名人になった女性といえば「李香蘭」の山口淑子がいる。満州の奉天で生まれ、幼い頃からの父親の教育で彼女は中国人並みに流ちょうな中国語が話せた。これが彼女の運命を決める。
彼女は満映所属の中国人女優「李香蘭」として数々の国策映画に出演、また歌手としても絶大な人気を誇るスターとなった。彼女の演じる「中国人女性」は強い日本人男性に惹かれ日本人に訓化されていく従順な中国人、それは中国民族を侮辱するものだった。日本敗戦後、「李香蘭」は「漢奸」、中国人でありながら国を裏切り外国の手先になった者として国民党政府下で死刑判決まで受ける。が、日本人を証明する戸籍謄本が危機一髪で届き、それが彼女の命を救った。
戦後の日本で山口淑子(その後、再婚して大鷹姓に)は女優引退後、自民党「アジア・アフリカ派」国会議員、政治家として活躍し、中国はじめアジア・アフリカの発展途上国、旧植民地諸国と日本の親善友好に半生を生きた。金日成主席とも親交があったことで朝鮮で今も愛される日本人女性でもある。
「上海のマヌエラ」も「李香蘭」も前々号で書いた日本人初の女性映画監督、坂根多鶴子も中国大陸で「花咲き、そして散った」女流アーチストたち、素晴らしい才能も国が道を誤ると永遠の花を咲かせることができないという苦い教訓を私たちに残した。
芸術や科学に国境はない、しかし芸術家や科学者は自分の国とは無縁ではいられないということもまた事実。この3人の女性の波乱の人生から学べるのは、そういうことだと思う。
3.31-”yodo-go”の日
若林盛亮 2023年4月5日
1970年3月31日、私達は“yodo-go”に搭乗、羽田を飛び立った。金浦空港での3泊4日を経て4月3日、順安国際空港がわからず石田機長の知る戦前からあった美林飛行場に着陸、私達はピョンヤンの地を踏んだ。
「労働者国家」(社会主義国家とは呼ばなかった)を国際根拠地にして軍事訓練を受け、その年秋の「七〇年安保決戦」で首相官邸占拠・前段階武装蜂起を「よど号赤軍」が担い貫徹する、それが目的だった。
この「よど号赤軍」の目論見は現実によって破綻が明らかになった。そこから私達は新しい出発を開始して現在に至っている。
あれから53年、私は76歳、日本では後期高齢者と言われる年齢になった。故郷の同窓達はみななにがしかの仕事をして年金生活者となって孫に囲まれていい爺さん婆さんになっている。でも私はまだこれといった仕事を何もしていない。だから引退ということもない。
生涯現役、頭と身体が動く限り仕事を続けるのがyobo-yodoのLIFEだ。
仕事は「ピョンヤンからアジアの内の日本を考える」こと、精神労働、文筆活動だ。しばらくは私達のHP「ようこそ よど号日本人村」や「救援」紙くらいしか文章掲載の場がなかったが、昨年あたりから「月刊 日本」、「紙の爆弾」、「デジタル鹿砦社通信」といった日本の媒体に掲載の場が少し広がった。
いま日本は対中対決の最前線だとか「東のウクライナ」になるという大変な時代を迎えている。ますます「アジアの内の日本」を訴えていく私達の仕事が問われる時代になったというのが実感だ。もっともっと仕事をしなければと思う。
今年、10月には故郷の中学の同窓会が持たれると便りがあった。そのときに私にもメッセージが求められる。みんなは「若ちゃん、北朝鮮で何やってるんやろ」と思ってるはずだ。だから「私はこんなことをやってます」と懐かしい故郷の同窓達に言える仕事をしなきゃなあと、ちょっと焦る気持ちもある。
エデンの東
赤木志郎 2023年4月5日
ジェームス・ディーン主演の「エデンの東」は有名な映画だが、気になりながら一度も見てなかった。最近、録画したものを借りて見ることができた。父親の愛が欲しいという葛藤、そして兄弟愛などを描いている名作だ。そもそも「エデンの東」に興味をもっていたのは、韓国ドラマで同じ題名の作品を見たからだ。韓ドラの方は父の遺言とおりに家長として弟を守る兄弟愛で貫かれている、波瀾万丈の主人公の生涯を描いている。まったく違う内容なのに。同じ題名なのは、エデンの東という聖書に出てくる言葉の意味からとったのであろう。聖書には「カイン 兄弟アベルを殺せり 去りてエデンの東ノドの地に住めり」とあるという。主人公のジェームス・ディーンは「お前も去るべきだ」と忠告される。もうひとつどういう意味かよく分からないが、少なくとも韓国ドラマの「エデンの東」では、兄弟を殺すのではなく兄がとことん弟を愛し守り、最後には弟をかばって銃弾に倒れた。
両方の映画とドラマを比較して、兄弟愛というものを考えざるをえなかった。私は6人兄弟で兄3人、妹2人に囲まれて育った。それぞれ考え方や生き方はまったく相異なるが、それでも兄弟の絆があると思っている。長兄が京都で入院している時、病院に居候しながら京大の周りを散策し、次兄は最初の給料でジャンバーを買ってくれたし、赤軍派に入るため上京したとき穿いていたのは次兄が買ったジーパンだった。三番目の兄が一番会話を交わした兄だが、大学合格したときに近くの裏山に誘い出したのはその思いやりの表れだった。しかし、現実には兄弟間でいろんな問題をかかえている。それは結局、兄弟愛の不足から来るものだと今、考えている。
肉親にたいする愛を考えさせる二つの映画とドラマだった。
山菜が芽吹く季節ですが
魚本公博 2023年4月5日
様々な花々が一挙に咲く季節ですが、今年は遅れ気味です。こういう時は、最初に咲くレンギョウやツツジだけでなく、アンズ、スモモ、ユスラメ、ボケ、ライラックなども同時に咲くので、殊の外、美しい「北国の春」になります。
そうした中、フキノトウが芽生え始めました。天ぷらやみそ汁の具にして食べています。皆にも配りました。
そしてナズナ。日本でも春の七草の一つで「七草粥」などにして食べていましたが、今はどうなのでしょう。こちらではナズナはレンイと言って、春先によく食べます。春先の芽生え始めた頃の根付きのものを大量にみそ汁の具にします。苦みがあって独特の美味さがあり、健康にも良さそうなので好物です。
ノビルやタラの芽も食堂で出ます。そして皆が好物のアスパラも芽吹き始めます。春先の野草や木の芽は何でも食べられるとかで、休みの日には、握り飯とミソを持っていって野外で、それらを食べるのも楽しみの一つです。
今、日本では、世界的な食糧危機が予想される中、「食の安定・安全を守れ」の声が高まっています。米国の食糧メジャーや遺伝子組み換え作物で悪名高いモンサント(現バイエル)などがGAFAMと手を組んで世界の食を支配しようとしており、彼らがバイオ技術を駆使して開発する昆虫食、人造肉、バイオ鮭などの魚類、バイオ野菜への安全性に疑問が持たれているようです。
ロックと革命 in 京都 1964-1970<06>
裸のラリーズ ”yodo-go-a-go-go”── 愛することと信じることは……
若林盛亮 2023年3月31日
◆「裸のラリーズ」脱退
1968年の5月頃、私はバンドを辞めることを水谷、中村に告げた。「同志社学館での出会い ── ジュッパチの衝撃の化学融合」から約半年が経っていた。
それは中村の高校の同窓というドラムの加藤君が入って練習場も桂の彼の家に移った頃、「裸のラリーズ」がミュージシャンとしての本格活動に入る時期でもあった。
その頃、学生運動は佐世保闘争の高揚を経て東大医学部闘争の激化から東大卒業式は祝典中止に追い込まれ、後に東大全共闘結成に至る。中国は文化大革命の真っ最中、パリでは世界を揺るがすフランス五月革命の胎動が始まっていた。
1968年という熱い政治の季節の開始を告げる時期、私は居ても起ってもおれない気持ちだった。
私はミュージシャンとなること、ベースギター練習に打ち込むモチベーションを持てなくなっていた。このままでは本格的にバンド活動を開始するみんなに迷惑をかけるだけ、私は脱退の意を水谷、中村に告げた。彼らは私の意を理解し、それを快く受け入れてくれた。彼らも心に「革命のヘルメット」を宿す人間だった。
辞める時、水谷が「それ僕にくれないかなあ」と言っていた私のお宝、細身の五つボタン、黒のコーデュロイ上着をプレゼントした。ベース・ギターもバンドに譲った。それらは政治転進の私には不要のものだった。
こんな風にミュージシャンとして何の貢献もないまま私は「裸のラリーズ」を去った。
その後の私はデモや政治集会に参加、組織に属さない孤独にもがく日々が続いたが1969年1月の東大安田講堂死守戦で逮捕、起訴後の拘留を経て秋に保釈後、ようやく赤軍派に加入、翌年3・31「よど号ハイジャック闘争」で渡朝に至る。このことは別途、触れるとしてその後のラリーズとの関わりについて少し書いておこうと思う。
2019年、誰知ることもなく逝った水谷孝、その死はHP「Takashi MIZUTANI 1948-2019」の立ち上げで皆が知ることとなった。‘90年代初頭の活動停止後、どこで何をしていたのか、家庭を持ったのかどうかさえ世間で知る人はいない。「裸のラリーズ」だけを遺して神秘に包まれたままこの世からふっと消えた水谷、実に水谷的な人生全うの仕方だ。彼は自分のことを全く語らなかった人だが水谷亡き今、私の知る彼のことを少しでも書き残しておきたいと思う。
◆脱退後、そして「よど号」渡朝後の「水谷と私」
バンドを脱退してからも水谷、中村らとは会えば「やあ、どうしてる」という関係は続いた。
ある日、「ゴールデンカップスにゲバルトをかけよう」との水谷からの召集令状を受けた。相手は秋の同志社学園祭に出演するゴールデンカップス、学生会館ホールでやる前座がそのゲバルト舞台ということだった。
私は誰かにハモニカを借りて出演、黒セーターに黒ジーンズ、赤い布きれをネクタイ風に首に巻き付けた「左翼」スタイル、そして自衛隊の戦闘靴で決めた。この時、琵琶を持って参戦という変わり者がいたが久保田真琴(夕焼け楽団)だったように思う。例によって事前練習も打ち合わせもない「裸のラリーズ」式ぶっつけ本番、私は水谷の即興的な唸るギターに合わせハモニカを延々吹きまくった。文字通りのアドリブ。いつ終わるか果てしもない即興演奏、どう終わったかも記憶にない。
「ゴールデンカップスにゲバルトをかける」 ─ きれいなお決まり音のグループサウンズ撃破の轟音とアドリブ演奏 ─ 自分たちの音楽理念で挑む!これが水谷式のゲバルトだ。ホールの聴衆はあっけにとられたことだろう。ゴールデンカップスが兜を脱いだかどうかは知らないが、前座をわきまえない果てしのない轟音アドリブ演奏はさぞかし「迷惑」ではあっただろう。
「裸のラリーズ」公式アルバムの“’67-’69 Studio Et Live ”の最初に収録の“Smokin’ Cigarette Blues”という曲がある、あれが学園祭でのゲバルト出演、アドリブ演奏であろうとほぼ確信している。この曲を聴くと騒音の背後で唸っているハモニカ風の音が私の記憶の中の感覚、水谷の轟音ギターに応じイメージが膨らむままに吹いていたあの即興感覚が蘇る。水谷が精選したたった3枚の公式音源、その一曲にラリーズの原点、「オリジナルメンバーによる唯一のもの」としてこれを入れてくれたのだとしたら、それは私への水谷なりの「義」なんだろうと勝手に感謝している。いまは確かめる術はないが……
その後は激化一途の政治闘争の渦中にあって水谷、中村らと会う機会はなく、「裸のラリーズ」も私の頭からは消えていった。
渡朝後のピョンヤンで「その後のラリーズ」を知ったのは‘79年の『ぴあ』11月号に掲載されたイベント紹介記事、青山ベルコモンズ「裸のラリーズコンサート」。告知にはサングラスの水谷の写真が!「おお、まだやってんだ」とアングラバンドとして生き残ってたことが正直嬉しかった。その時は「まあ、細々とやってんだろうな」くらいの感覚だった。
二度目は‘90年代初期? ピョンヤンで会ったテリー伊藤と一緒に訪朝の前衛漫画家・根本敬さんから「幻の名盤」なんとかで「裸のラリーズ」テープ、“’67-’69 Studio Et Live”をプレゼントされたこと。この時も「アングラの名盤に入ってんだ」、そこそこ健闘してるじゃないか程度の認識だった。
そんな私の認識を大きく変えたのは、2000年代に入ってのピョンヤンでの英労働党EU議員、Glyn Fordとの出会い。彼から「貴方達の中にギターやってた人がいるよねえ」と言われて、もしかして私のこと?日本でバンドやってたことがあると話すと、彼から“Les Rallizes Denudes”じゃない? 「実は自分の友人にファンがいる」と聞かされた。
これには正直、驚いた。「へえ~、海外にまでファンがいるんだ!」 ── 世界的バンドになったのか!これは仰天の事実だった。以降、G.Fordとは訪朝の度に会うようになり、ネオナチ反対運動をやってる彼の友人、「裸のラリーズ」ファンの依頼ということで私のサインを送ったりするようになった。G.Ford自身はローリング・ストーンズ愛好家、東大留学経験で宇井純とも親交あったという私とほぼ同世代、英プレミア・サッカー同好の士でもある。
世界的支持者といえば、あのレディ・ガガが“Les Rallizes Denudes”ロゴ入りTシャツ写真姿を彼女のインスタグラムに掲載、知人から送られたその数枚を見たがとてもカッコよかった。超ビッグなレディ・ガガを惚れさせた水谷の凄さを見せつけられた思いだった。
訪朝した雨宮処稟さんからも「ラリーズ初代ベーシストですよね」と言われた。彼女の著書の中にプレカリアートの一人が「部屋を閉め切って布団を被って轟音ラリーズを聴く」話があった。“生きづらい”若者には「救いの轟音」なのだとラリーズの功績を再認識させられた。
労働者ユニオン代表だった小林蓮実さん、派遣で働く彼女の友人にもラリーズ支持者がいるとも聞いた。
2010年代にFさんという「裸のラリーズ」熱烈支持者の女性から手紙やメールでラリーズの詳しい情報を得られるようになり、彼女からの「ロック画報」No.25特集号で「その後のラリーズ」の全貌をほぼつかめ、「水谷の偉業」を知ることになった。そのFさんは‘13年に表参道付近にある「Galaxy ── 銀河系」で「裸のラリーズ・ナイト」を主催、私がメッセージを送ることになった。根本敬×湯浅学対論も持たれ、21世紀に入っても冷めやらぬラリーズ支持者の熱気を感じたものだ。
こうした人々との交流の中で「ラリーズ」公式音源、映像ほか“yodo-go-a-go-go”など非公式音源も入手、ピョンヤンにいる私の中に時間と空間を越えて「裸のラリーズ」が蘇った。
結成50周年の2017年秋には、椎野礼仁さんの仲介でBuzz-Feed Japan、神庭亮介記者の電話取材を受け、私のラリーズ体験を語ったが、それはネット配信されけっこう反響があったと神庭記者から伝え聞いた。
結成50年を経て取材が来る、活動停止後20余年も経たバンドの記事を待つ熱狂的支持者がいる。布団を被ってラリーズを聴くプレカリアートの若者がいる。レディ・ガガがロゴ入りTシャツ姿を
インスタグラムに載せる。「裸のラリーズ」サポーターは百人百様だが、バンドは彼らの胸に永遠に生きている。
それもこれも水谷孝のなせる業、偉業だと痛感させられる。
「誰のものでもない自分だけのものを」! そんなバンド「裸のラリーズ」を水谷はこの世に産み遺していったのだ。
◆“yodo-go-a-go-go” ── 愛することと信じることは……
英国製海賊版とされるアルバム“yodo-go-a-go-go”、でもこれには水谷が関与していると言われている。私は「水谷の関与」を確信している。
確信の根拠は、まずアルバム・タイトルに“yodo-go”を選んだこと、またジャケット写真に「よど号ハイジャック」を想起させる「煙が上がる駐機中の飛行機」を配したことだ。「よど号」メンバーがオリジナルメンバーにいたことは知られているが、わざわざ“yodo-go”タイトルの海賊版を創る物好きはいないだろう。
それにこのアルバムには私が参加したであろう演奏“Smokin’ Cigarette Blues”が収録されていることも水谷の関与を臭わせるものだ。
私が何より「水谷の関与」を確信するのは、アルバムの裏ジャケットに記された「謎のメッセージ」にある。
日本語表記には「溺れる飛べない鳥は水羽が必要」と記されているが、小さなローマ字表記ではそれが“Oboreru Tobenai Tori wa MIZUTANI ga Hitsuyo”と「水羽」を“MIZUTANI”に置き換えてある。これは水谷らしい謎かけだ。
私はこれを「溺れる飛べない鳥」には「水谷」という「水羽」が必要、と解釈している。つまり「溺れる飛べない鳥」のために「水谷」は在る、飛べるかも知れないし飛べないかも知れない、でもせめて溺れないように「水羽」くらいは提供することはできる。それが水谷の「裸のラリーズ」、「飛べない鳥のための革命」なのだ、と。
「愛することと信じることはちがう」、これは水谷の歌詞に出てくる言葉だ。「おまえの言葉の中に愛を探したことは いつのことだった!」とか「いまではおまえを信じることはできない」そして「僕の腕の中におまえは死んでいる」、そんな歌詞をいろんな楽曲で水谷が歌っている。
歌詞によく出てくる「おまえ」は「革命」を指すと評した人がいる。
1969年から‘70年年初冬に同志社放送局のスタジオで収録されたCD“MIZUTANI/ Les Rallizes Denudes”には轟音ノイズのこのバンドには珍しいフォークっぽい美しくも悲しみをたたえたメロディに乗せて上記のような歌詞がいろんな曲で歌われている。
このアルバム収録時のことをギター参加の久保田真琴が「ロック画報」(ラリーズ特集号)で語っている。少し長いがその頃の水谷を知る上で重要な当事者証言だから引用する。聞き手は、ラリーズ・ファンでもある音楽評論家の湯浅学。
<久保田 もう、学校もぐしゃぐしゃな時代でロックアウトされてたんだけど、キャンパスでバタっと出会ってね。……それで、聞いたら、まあ、「つかれちゃった」と。たぶん、学生運動のことでいろいろあったんだろうと思うんだけどね。
湯浅 ……・
久保田 う~ん……だからよど号の事件はいつだっけ?
湯浅 70年の3月31日です。
久保田 ええ~、そうなんだ。じゃあ、もう、よど号が行く前にいったん解散してたんだ。
湯浅 みたいですね。そのあたりに分かれ目がどうもあったらしくて。
久保田 だから、彼はやっぱりミュージシャンを選んだんだな。まあ、そういうことですよ。そう……そうか、私はなんか、頭の中では、あの録音はもう、よど号が行っちゃった後っていうイメージがあったんだけど、違うんだね。>
同志社での“MIZUTANI/ Les Rallizes Denudes”収録直前の1969年は1月の東大安田講堂落城以降、全国の大学のバリケードは警察機動隊によって解体され、拠点を失った学生運動は混迷期に入る。立命全共闘だった『二十歳の原点』の高野悦子さんなど多くの自殺者が出た年でもある。混迷突破をめぐる党派内部の混乱もあって1968年にはあれほど熱かった政治の季節、革命の前途は一転してうすら寒くも暗澹となりゆく時期、しかし余熱はくすぶっていた。
赤軍派はそんな余熱を革命の熱気に換えようという組織だった。ある公演舞台(京大西部講堂?)で水谷の歌うマイクスタンドの前に「赤軍派」のヘルメットがぶら下がってる写真があるが、彼が心を寄せていた可能性はある。でも赤軍派拠点だった同志社キャンパスは久保田の言うように「ぐしゃぐしゃな時代」、水谷に何があったか知る由もないが「つかれちゃった」という状況にあったのだろう。私はこの年のほとんどを安田講堂逮捕後の獄中にあって現場を知らない。
1969年の京都、水谷周辺の時代の空気感、それが水谷の歌う「愛することと信じることはちがう」という季節感なのだろうと私流に解釈している。
それは私にもある程度、想像はできるあの時代のひりひりした空気感だ。
案の定、時代は「連合赤軍の同志粛正」、「中核・革マル戦争」のように新左翼諸党派の「内ゲバ殺人」へと流れていった。革命は何のため? 誰のため?を忘れた革命、党派利害第一、党利党略に翻弄され「いまではおまえを信じることができない」革命に堕ちて行く。
「僕の腕の中にお前(革命)は死んでいる」 ── 水谷はミュージシャンとして「溺れる飛べない鳥のための革命」を自分の使命とし、「裸のラリーズ」で水谷の革命をやる、そう心に決めたのだ。
雨宮処稟さんの著書に出てくる「布団を被ってラリーズの轟音を聴く」プレカリアートの若者は、そんな水谷の言う「溺れる飛べない鳥」の一人なのだろう。
「愛することと信じることはちがう」、それは革命とは言えない。「愛することと信じることは同じ」と言える革命はきっとあるはずだ。あきらめずに地面を掘り続ければ、必ず水は出てくる、私もあの時代を生きた一人、今もそれを追求途上にある。
だから私は“yodo-go-a-go-go”裏ジャケットに記された謎かけのようなメッセージを私に対する水谷の決意表明だと受けとめ、ならば私は私の革命を続ける責任があると肝に銘じる。
「裸のラリーズ」の楽曲で私のイチ推しは“yodo-go-a-go-go”所収の名曲“Enter The Mirror”だ。“’77 LIVE”にも同曲があるが断然こちらがいい、私にとっては珠玉の名曲、「私の裸のラリーズ」だ。
この“Enter The Mirror”を聴きながら「愛することと信じることは同じ」革命を追求する責任が自分にはあるのだということを私は忘れないようにしている。
「鏡よ鏡 天国でいちばんカッコイイのは誰? それは“裸のラリーズ”」 ── 天国にあってもそんな水谷孝であろうことを確信しながら……
追記
“Enter The Mirror”にまつわるお話しとして……
水谷との関連でぜひ触れねばならないが収まりどころがないので「追記」にそれを書く。
「オルフェ」という1950年代の古いフランス映画がある。詩人ジャン・コクトーの創った映画だ。私には珠玉の名曲”Enter The Mirror”はこの映画を想起させる。
鏡の外は現実の人間世界、鏡の中に入ればそこは「死者の世界」、「死に神の女王」は「鏡の外」の世界の詩人を愛してしまう、それは「鏡の中の世界」では許されない御法度とされる行為、しかし「鏡の中」の法廷で「死に神の女王」は詩人への愛を否定せず自分の愛を貫く、そして「死より恐ろしい刑罰」の待つ刑場へと向かう、毅然と美しく!
コクトーの詩を好んだとされる水谷、“Enter The Mirror”は「死に神の女王」を意識した楽曲、私は勝手にそう解釈している。私は水谷がこの「死に神の女王」に自分を重ね合わせているのではないかと思えて仕方がない。(つづく)
ロックと革命 in 京都 1964-1970
〈01〉ビートルズ「抱きしめたい」17歳の革命
〈02〉「しあんくれ~る」-ニーナ・シモンの取り持つ奇妙な出会い
〈03〉仁奈(にな)詩手帖 ─「跳んでみたいな」共同行動
〈04〉10・8羽田闘争「山﨑博昭の死」の衝撃
〈05〉裸のラリーズ、それは「ジュッパチの衝撃」の化学融合
〈06〉裸のラリーズ ”yodo-go-a-go-go”── 愛することと信じることは……
(初出:デジタル鹿砦社通信)
「をんな千一夜」-日本人初の女性映画監督、坂根田た鶴子づこ
若林盛亮 2023年3月20日
「選択」誌に「をんな千一夜」という連載がある。書いているのは女性伝記物では定評のある松田妙子。「選択」主要記事をメール送付頂いている椎野礼仁さんに強いてこの欄を送ることを頼み込んで毎月、読むのを楽しみにしている。
私は自立心旺盛な女性、強い女性の人生にとても興味を惹かれる。
「ならあっちに行ってやる」の長髪高校生時代から私を理解し背中を押してくれた恩人達にはそんな女性が多かったからだろう。「戦後民主主義」の日本で男性は高度成長の波に乗ったが、女性の社会的進出には壁があり、職場での扱いは「結婚するまでの腰かけ」的存在、料理や裁縫、お花や茶道など花嫁修業に励むのが若い女性の役目とされた風潮の中、運命の自己決定権に目覚めた女性は「戦後日本はおかしい」の私に似た境遇にあった。
恩人達には「女でも実力次第」が通用する作家や演劇をめざす女性が多かったが、「をんな千一夜」に登場する女性らにもそんな人が多い。これまで作家の樋口一葉、文筆家・社会運動家の平塚らいてう、伊藤野枝、菅野須賀子、女優の川上貞奴などが取り上げられた。
3月号は坂根田鶴子、日本で女性初の映画監督となった人物だ。
明治37年生まれの坂根田鶴子は同志社女子専門学校英文科(後の同志社女子大)入学を果たすも、父の後妻の反対で中退を強いられ心にもない結婚の道を、結局それも破綻、そして勇躍「それなりの仕事をしたい」と映画監督の道を選ぶ。
有力者の父の紹介で入社した日活で異例中の異例として女性でありながら助監督として溝口健二監督の下に配属される。
坂根は決意と覚悟を示すため、長い黒髪を切り、美しい着物姿と決別、ハンチング帽とズボン姿で助監督の仕事に臨んだ。映画界の女性といえば女優と髪結いくらいという時代だった。
大物の溝口監督でさえ現在の中学校も出ていないという当時の映画界で学識のある坂根の才能は際だち、溝口監督は彼女にシナリオ作成、撮影、編集まで頼るようになり彼女は監督の右腕にまでなった。
そんな彼女に監督の話が持ち上がると周囲の空気は一変、「溝口と肉体関係を持った対価だ」とまで陰口をたたかれる。しかし男性の価値観で支配された映画界を変えたい一念の坂根はそんなことに負けはしない。
しかし実際に撮影に入るとスタッフの嫌がらせはさらに増し、結局、思うような映画を撮れなかった。彼女の初監督作品「初姿」は批評家に酷評される。
このままでは監督になれないと彼女は記録映画に転進、さらには昭和15年、大陸に渡り満映に入社、それは女性でも監督になれるという条件があったから。ここで彼女の才能は一挙に開花、次々と大作を発表する。
「男装の麗人」とも謳われた当時の彼女を知る女性の映画関係者は「草原のロケで堂々と指示を出す坂根さんの姿は眩しかった」と述懐している。
しかし敗戦で彼女の志は中途挫折を強いられる。戦後の映画界で満映出身者を「アカ」と見る傾向もあって、松竹に入社してもスクリプター(記録係)の仕事しか与えられず、日本初の女性監督は不遇のうちに生涯を終える。
戦前の日本で女性初の映画監督として苦節の末の栄光と失意、波乱の生涯を送った坂根田鶴子、精いっぱい志す道を生きた彼女にとても敬愛の念を感じた3月号の「をんな千一夜」だった。
暗中模索の青春時期、夢に向かう互いを励まし合った恩人達のその後、女流作家、演劇女優の道はどんなだっただろう? 結果はどうだったのか? いずれにせよ悔いなく生きたことを願い信じたい。
山口正紀氏の生き様
赤木志郎 2023年3月20日
同世代の市大出身者が次々と亡くなっていく。70歳後半だから無理もないが、やはり寂しい。
山口氏は私より1年くらい後輩で、大阪市大卒後、読売新聞記者となり、20年前に辞職し、冤罪問題など社会問題で鋭い告発をおこなってこられた有名なジャーナリストである。読売新聞を辞職したのは、朝鮮の拉致問題非難一色の報道を批判したことで社から「記者職」を剥奪されたのが契機だった。昨年暮れ12月7日に亡くなった。肺ガンを抱えながら、筆を奮ってきた闘志の塊の人だ。
「レイバーネット」誌に連載されたコラムを集めた『言いたいことは山ほどある』(旬報社)が3月に出版された。
山口氏は私たちの田中義三とも交流があったという。田中義三遺稿追悼集に山口氏の追悼文が掲載され、そこに詳しい。田中が獄中から連日、手紙で人々に訴えていたことに胸を打たれたそうだ。田中との交流をつうじて「よど号」に良い印象をもっていなかったが改めたそうだ。山口氏は帰国支援の集いに参加され、そこで私と大学時代に「論争」したことがあるという話をされたことがある。私自身、後輩と話す機会が少なく、山口氏と会った記憶がない。わざわざそういう話をされたのは、過去は過去として共に手をとっていこうという気持を感じた。しかし、それに応えなかった。後悔といえば、そのことがずっと胸にひっかかっていた。
山口氏は「私は人権を侵害するために記者になったのではない」と冤罪事件に関わってきたのは、氏の正義感がどれほど強いものかを示している。ほんとうに惜しい人を亡くしてしまった。
異郷の地であれ、心から氏のご冥福を祈りたい。合掌。
よど農園縮小
魚本公博 2023年3月20日
3月も末になり、まだまだ夜は零下の日もありますが、日中はすっかり春です。浚渫船も来ました。長い冬の北国では、春が一挙に訪れます。これからツツジ、レンギョウなどの花々が咲き乱れる「北国の春」になります。
そうした中、よど農園をどうするか思案中です。というのも、昨年は川辺の畑は春先にはイノシシに荒され、夏の大雨時期には冠水し、今でもその時の粘土質の泥が10センチほどの厚さで固く敷き積もったままだからです。
それに歳のこともあります。私もこの3月19日で75歳、後期高齢者の仲間入りです。この歳になると、さすがに若いときのようにバリバリというわけには行きません。
それで、宿所に近い2ヶ所に畑を縮小し、川辺の畑は基本的に放棄しようと考えています。完全に放棄すると原野に戻ってしまうので、皆に好評で手軽なアスパラガスやフキの畝は維持して、それを広げ、他は管理の容易な里芋やサツマ芋の畑にしようと思っています。
よど農園縮小を考えながら思うのは日本農業についてです。農業従事者の平均年齢は68歳。BS放送でも70過ぎの高齢者がトラクターに乗って、まだまだ「現役」という姿を見かけますが、いずれ「退役」は必至。心配なのは、そうした隙に米国外資が入り込んでくることです。何としてもそれを退け、日本農業を守って欲しいと思うこの頃です。
曹操の恋
若林盛亮 2023年3月5日
いま私は吉川英治の「三国志」を読んでいる。その中に「曹操の恋」という一節がある。
魏の覇王、曹操(そうそう)は捕虜とした蜀の関羽に恋をする。関羽の勇猛さばかりでなく義に篤あつい忠義の士風にとことん惚れ込んだ。曹操は彼を貴賓のごとく遇し徳によって我がものとしようとする。しかし関羽は自分の義を貫き主君、劉備玄徳の元に去ってゆく。そんな関羽にさらに曹操は恋を深くする。
男同士の恋というのは確かにあると自分にも思い当たった。
かつて私も男に恋をした。
恋人は水谷孝、中村武志。
彼らは「裸のラリーズ」結成の盟約を結んだ男たちだが、あの時私たちは確実に恋をしていた。当時の私は女性など眼中にもなかった。
同性愛とかそういう肉体関係とは縁遠い男同士の恋、いわば心の震えるような恋、魂の接近、触れあい、融合・・・??
3人は10・8羽田闘争「山崎博昭の死」に象徴される「ジュッパチの衝撃」の化学反応によって結ばれた仲だ。そしてバンドの結成、日本のロック界を革命する志で結ばれていた。でも単なる「同志」でもない、やはり恋人としか言いようがない。
互いに魅せられていた。言葉でよく表現できないが、水谷も中村もとてもカッコイイ、私にとっては「男の中の男」。
水谷は男にも女にもない中性的な風貌に真ん中分けの長髪がよく似合ってたし、中村は切れ長の目に白いもち肌のふっくら顔に目までかかるフワッとくせ毛の長髪がカッコよく、3人のなかでは女性に惚れられるタイプ。着こなしもそれぞれが独特の雰囲気を持っていた。
とにかく見目形、魂・・・全てにおいてひたすらカッコイイ。
出会った日以来、3人は音楽もやらないでいつもつるんでいた。ボブ・ディラン初恋の人、スーズ風に言えば、「その頃、3人は離れるのがいやになっていた」。
喫茶店でお話しをしたり、会話が楽しいとか言うのでもない、一緒にいるだけで周りの空気は一変、会話などなくても心と心は通じ合う「黙示録」バンド、とても不思議な関係。
3人がいてこその「裸のラリーズ」、それぞれがかけがえのない存在だった。
私はその恋を捨てて政治運動に走ったが、今でもあの恋を忘れない、不思議な懐かしさで当時がそのまま甦る。
別れて以降、水谷孝は「裸のラリーズ」を生涯貫き、中村武志は名を中村?きょうと改め「平成の浮世絵師」と言われた写真家となって、それぞれがそれぞれの「義」を生きている。
そんな彼らにさらに私は恋を深くした。水谷、中村はいついつまでも「若林の恋」人だ。
世界女子バレーボール大会でのセルビアの闘い
赤木志郎 2023年3月5日
TVで世界女子バレーボール大会を中継していた。準決勝でのイタリア対ブラジルでの試合も見ていてはらはらするほどの激戦だったが、決勝でのブラジル対セルビアの試合もそれに劣らず激戦だった。最後までどちらが勝者になるのか分からなかった。ブラジルは従来、女子バレーボールで強者として知られていたが、セルビアも強者だった。最終的にセルビアが優勝した。
セルビアはハンドボール、バスケットボール、水球など球技が得意な国だ。民族意識が強い国で、第一次世界大戦勃発の契機となったオーストリア皇太子暗殺事件を起こしたほどであり、最近では昨年のNATOにたいするロシアの軍事作戦で反NATO、ロシア支持の数千人のデモが行われた国だ。民族意識が強いせいか、球技でも世界の強豪となっている。
そういう意味で、私はセルビアを応援したい気持で世界女子バレーボール大会の決勝戦を見ていたら、なんとブラジルを圧倒しているのである。人口もそれほど多い国ではない。
国が強いかどうかは、人口の多少、領土の大きさ、経済力も左右するが決定的には、民族自負心、民族意識がどれほど強いかにかかっているのではないだろうか。そして、その民族意識、自負心は国の在り方にかかっている。
日本の場合、スポーツでニッポン意識が盛り上がっているが、政治は米国には何も言えない。これで自負心を持てというのは無理だろう。
浚渫船よ早く来い
魚本公博 2023年3月5日
今年は暖冬で例年なら、まだまだテドン江も凍結したままなのですが、もうすっかり溶けました。ツツジやレンギョウのつぼみも大きくなって、春の訪れを感じます。とは言え、まだ土は凍りついたままで、クワを打ち込んでも跳ね返され、当分、農作業は無理ですが。
テドン江の氷が溶けると待ち遠しいのは浚渫船です。浚渫した砂をコンクリートに使うためです。一つの浚渫船を中心にして何艘もの運搬船が随伴する船団がいくつも行き来する風景は中々のもので、その出現を今か今かと待っています。
今年、浚渫船の出現がことのほか待ち遠しく思われるのは、今、平壌や全国各地は新たな建設ラッシュだからです。
昨年は平壌市の南端にあたるソンシン地区に80階の高層アパート数棟を中心にした新市街が完成しており、ファソン地区の新市街地も完成段階にあり今年から第二段階1万世帯の建設が始まります。平壌の北方に位置するソポ(西浦)地区にも4000世帯の新市街が建設されます。
平壌市の建設では、住居だけでなく、カンドンに大温室農場も建設されます。
更に付け加えると、新住宅建設は区域ごとに自力でなされており、私たちが市内に出るときに通るチャンスウォン地区でも古い建物が壊され、新住宅の建設が準備されています。
感心するのは、こうした建設の先頭に青年が立っていることで、青年組織である社会主義愛国青年同盟の全国的な建設への呼びかけに、すでに10万人超の青年が応じています。
ソポ地区の建設には、これまでのような人民軍建設隊ではなく青年だけの建設隊(白頭山英雄青年突撃隊)が担当することになっています。
そうした若々しい息吹を感じながら、浚渫船よ早く来いと、その出現を待ち望んでいるこの頃です。
「家康」
小西隆裕 2023年2月20日
寅さんこと杉山寅次郎さんからメールで安部龍太郎の「家康」を送っていただいた。新聞広告で「家康」第8巻(明国征服計画)が発刊されたのを知り、お願いした。
スペインが秀吉を動かして朝鮮半島を通り明を攻めさせ、自分は南から攻めて中国全土を征服する計画を立てたのに家康がどう対したのか安部龍太郎の説を知りたかったからだ。
ところが寅さんは、8巻ならぬ第1巻の最初から送ってきて下さった。
それで送られてきた第1巻を一気に読んだのだが、それが今放送中の大河ドラマ「どうする家康」と重なり大変面白い。
家康が戦国時代を終わらせ、中世から近代への転換点をいかに切り開いたのか、それが家康の人間としての成長とともに高い説得力を持って描かれている。
中でも納得がいくのが、家康の人の言動を深く推し量り、そこから学ぶ力が人並みはずれていたことだ。自らの祖母源応院の自決とその遺言が自分に伝える遺志を読み取る段などは圧巻だ。
しかし、それにも増して納得なのは、自らの家の子郎党、三河の人々への家康の深い愛情だ。桶狭間での敗北の後、大樹寺にわずか28人の手勢とともに追い込まれた時、28人を助けるため、自らが腹を切ろうとしたことなど、三河侍の結束が固かったのは、そのためだと思う。
これから家康がどのように成長し、いかに天下統一、スペイン覇権との攻防をしていくか楽しみだ。
あんたの生まれたのは2・26事件と同じ日
若林盛亮 2023年2月20日
私はこの2月26日で76歳になる。
誕生日で思い出すのは母の言葉だ。
「あんたの生まれたのは2・26事件の日、それにヴィクトル・ユーゴの誕生日と同おんなじなんやで」
たしか小学4、5年生くらいの頃だ。
ヴィクトル・ユーゴのことは著書「ああ無情」の主人公ジャンバルジャンが義賊的な人くらいしか知らなかった。
でも2・26事件のことは陸軍青年将校が義憤に駆られて起こしたクーデターが失敗、首謀者たちが銃殺に処されたことなどイメージが強烈でけっこう鮮明なものだった。だから自分の誕生日は「2・26事件の日と同じなんやで」という母の言葉が強烈に印象に残った。
「大義のために死を賭して起つ」という2・26事件の主人公たちの行動がとても高尚なことで、それが私の誕生日と結びついていることがなにか誇らしかった。
それは高3になってビートルズ風長髪で異端児的に進学校ドロップアウト以降も、その後、ドラッグでらりっていた時期も常に私の意識下にあったように思う。
そんな頃、幕末の志士への憧れから久坂玄瑞の伝記的なものも読んだ。
久坂は長州藩攘夷過激派による無謀な武力クーデター企図を止めようと努力した説得がならず、同志たちを見殺しにできずついに自身も蛤御門の変に加わり戦い敗れて自害した人物だ。
そんな生がすごく美しく思えた。いつか自分も・・・と。その頃の実際の私の現実とは遠く離れてはいたけれど。
政治に目覚め東大安田講堂死守戦逮捕のとき、のちに赤軍派に加入、よど号ハイジャック闘争に参加するとき、「自分の生まれたのは2・26事件の日」という無意識の意識はあったと思う。
母はなぜ私にあんなことを言ったのか? 「寄らば大樹の陰やで」と私を案じ言い聞かせていた母が・・・
母亡き今はそれを確かめる術すべはない。
私なりに「人として正しく生きなさい」という母の願いと期待であると心に留めておこうと思う。
「尼僧物語」のオードリーはとても素敵!
若林盛亮 2023年2月5日
「永遠の妖精、オードリー・ヘップバーン」、中学生の頃、私はオードリーに恋した。
4才上の姉に連れられて私はよくアメリカ映画を観に行ったが、「ローマの休日」のオードリーを見て瞬時に心を奪われた。
王女様のたった一日のはかないローマの恋が若林少年の感涙を誘って「妖精」オードリーは私の永遠の「恋人」になった。
以降、私はオードリーの映画はすべて観た。
76歳になる私だが、いまもオードリーは私の「永遠の妖精」だ。
先日、BS放映の「尼僧物語」を観た。オードリーも素敵だったが、映画もとてもよかった。
尼僧をめざすオードリー、彼女の夢はコンゴに行って熱帯病に苦しむアフリカの人々を救うことだが、当時の苛酷な熱帯ジャングルの地で看護師を担えるのは自己犠牲をいとわない修道女だけだったからだ。
修道院では神の僕としてイエス・キリストのみに仕える厳しい戒律を絶対のものとして受け入れ、そこに人間的感情をさしはさむことを禁じられる。ゆえに様々な葛藤にぶつかるが、オードリーはコンゴの地での看護をめざし修道女の道を極め、ついにアフリカ熱帯林に足を踏み入れる。
しかしそこでも修道女と看護師という二つの立場の葛藤に苦しむ。祈祷の時間は厳守、たとえ手術中であろうと場を離れドアの前ででも祈祷を強いられるなど様々な看護場面での葛藤に悩む。修道女の戒律は絶対的。でもそれにも耐えていくオードリー。
看護師としても人間としても第一級のオードリーは患者やアフリカ現地の人から慕われ人気者になる。でもそれは修道女としての「評価」とは次元の異なるもの。
そしてナチスによって理不尽に殺された父の死(おそらく反ナチ地下組織で医療活動中)、しかし戒律は敵を憎む心を許さない。
日々、人間的良心と戒律との狭間で揺れる自分はどうしても良心を押し殺すことができない。ついにオードリーは修道院を出る決心をする。
彼女の決心を翻そうと修道院長はこう説得した。
「あなたは尼僧であり看護師ではありません。医療より信仰生活が大事です」と。
この言葉でオードリーの決心は揺るがないものとなる。そして長年、研鑽を積んだ修道院を決然と去る。
修道女の道服から平服に着替え立ち去るオードリー、修道院から去りゆく彼女をドアからロングショットで捉えたラストシーンは主人公の決然たる意志を象徴する感動的なシーンだった。
「神の僕ではなく、人のために生きる」!
オードリーは実生活でも、この映画の主人公のように生きた。晩年、彼女はユニセフ親善大使としてアフリカの子供たちのために生涯尽くした。
オードリー・ヘップバーン、彼女は私の「永遠の妖精」、人間としても尊敬する人物だ。
国名の呼び方
赤木志郎 2023年2月5日
サッカーワールドカップの時に感じたことだが、国名の呼び方が日本と朝鮮では異なるのがいくつかあった。モロッコは朝鮮ではマロコだ。それでマロコがすごい活躍しているのねという話題のときに、「マロコってどこの国?」という人の話が出て、「モロッコのことだよ」で疑問がすぐ解かれた。他にも、「セルビア」が朝鮮では「スルビア」、「クロアチア」が「フルバツカ」。ワールドカップの試合に出場していない国では、「ハンガリー」が「マジャール」というのがある。
国名の呼び方は、当事国の要求に従うのが国際ルールになっていると思う。かつてイギリスの植民地だった「ビルマ」が「ミャンマー」になったのも現地の国名がそれだからだ。「セルビア」と「スルビア」の違いは単に発音の仕方の問題だと思うが、「クロアチア」と「フルバツカ」や「ハンガリー」と「マジャール」の違いはどうなのか、気になる。
また、地域名では香港を「ホンコン」、澳門を「マカオ」と呼ぶのも気になる。中国内地の人にはまったく理解されない呼び方だ。植民地だった呼び方の名残がまだ日本に残っている。
一番問題なのは、朝鮮を「北朝鮮」という呼び方だ。10数年前までは「朝鮮民主主義人民共和国」と呼んでいたが、安倍晋三元首相が呼称を「北朝鮮」に替え、マスコミにも強制した時から今日に至っている。それは朝鮮敵視政策をとる姿勢の象徴だった。中国を「支那」というのと同じだ。それに比して、伊勢崎賢治氏が昨年12月10日「琉球弧を平和の緩衝地帯に」講演会で「朝鮮民主主義人民共和国(D.P.R.KOREA、朝鮮)」と呼んだのは印象的だった。
経済制裁に軍事的威嚇などの敵視政策をとりながら「無条件的な首脳会談」を言うなどは、相手に刃を突きつけて「話そうじゃないか」というのと同じだ。少なくとも国名を正式名称で呼ぶのは最低の礼儀だというのは言うまでもないと思うが。
ボブ・ディラン「激しい雨が降る」を実感する新年
若林盛亮 2023年1月20日
お正月休みにボブ・ディランのライブ動画を観た。
圧巻は奈良、東大寺大仏殿で行われたフルオーケストラをバックにしたライブ公演、曲目はプロテストソングの名曲「激しい雨が降る」。
1962年にあったキューバ危機体験を歌ったものだ。
キューバにミサイル基地建設のためのソ連軍艦艇を阻止しようと米海軍が海上で待ちかまえた一触即発の危機、世界は米ソ核戦争の恐怖に震えた。米国では生徒たちが机の下にもぐる核戦争訓練を学校でやった。
私が小学生の頃、米国がビキニ環礁で水爆実験をやって近くにいた日本の漁船、福竜丸が被爆、船員の久保山さんが死亡した。「死の灰」が日本にも及ぶ「ビキニの雨」に当たるとハゲ頭になるといわれ雨が降ると本気で心配した。キューバ危機時の米国民の恐怖はその比ではなかっただろう。
ボブ・ディランはイタリア留学中だった恋人スーズに手紙を書き送った。「ソ連の艦艇がキューバに近づいている」とケネディ大統領が発表した夜のことを綴ったものだ、
「夜通しフィガロに陣取って世界が終わるのを待った。真剣にこれで終わりなのだと思った。・・・・あの夜で世界が終わると思ったとき、僕はただ君と一緒にいたいと思った」
「激しい雨が降る」は以下のような歌詞で綴られている。
♪ どこへ行っていたの、青い目の息子よ・・・墓場の口に1万マイル入っていた
・・・・
♪ 何を見たの、青い目の息子よ・・・小さな子供が手に剣や鉄砲を持っているのを見た
昨年末に閣議決定された「安保3文書」、ここには陸上自衛隊に「スタンドオフミサイル部隊」の新設が書かれた。要するに中国や朝鮮に届く中距離ミサイル部隊が日本にできる。米国の要求は「核搭載の中距離ミサイルの日本配備」だから、安倍元首相の主唱したNATO並みに「米国の核共有」が実現すれば、日本の自衛隊基地は核戦争基地に一変する。
これは仮の話だが、キューバ危機の事例で立場を逆転して考えれば、「核ミサイル基地建設阻止」の軍事行動を中国や朝鮮がとったとしてもそれを非難する権利は米国や日本にはない。
「安保3文書」実現はキューバ危機のアジア版、「日本危機」という火種をこの地域にもたらすものになる。
これはすでに現実になろうとしている。「安保問題の権威」と言われる人物がこんなことを言い出した。
「被爆国として非核の国是を守ることが大事なのか、それとも国民の生命を守ることが大事なのか、国民が真剣に議論すべき時に来た」
「激しい雨が降る」はこんな歌詞で終わる
♪ それで激しい 激しい 激しい 激しい
♪ 激しい雨が降りそうなんだ
まるでいまの日本のことのようだ。
どうする家康、どうする日本
魚本公博 2023年1月20日
今年の冬は異常な暖かさです。例年だと1月の小寒から大寒までは零下10数度の極寒の日々が続くのに、今年はせいぜい零下数度で日中は零度を超えます。モスクワは零下60度という寒さ、これがアジアに移動するそうで、今後どうなるか分かりませんが、異常は異常。かつてなかったことが起きる、ありえないことが起きる、時代もそうなっているのかも知れません。
実際、今年は岸田政権による「国防費倍増・反撃能力保持」に対して平和と暮らしを守る闘いが「かつてなかった」規模と激しさで燃え上がるのではないでしょうか。
そういう中で、大河ドラマ「どうする家康」が興味を引きます。それと言うのも、大河ドラマを契機に色々な歴史番組でも家康を取り上げているのですが、そこでは260年の平和な世の中を作った家康ということが強調されているからです。
「どうする家康」の2回目も、桶狭間の戦いで、今川軍が敗北した後、駿府に帰ろうとした家康が松平昌久に攻められ、大樹寺に逃げ込み切腹しようとしたところを登譽上人に厭離穢土・欣求浄土、すなわち平和な世の中を作るために生きよと説得されるという場面でした。
それにしても、「どうする家康」とは、今年の世相に合う、うまい題目です。本当に今、「どうする日本」が問われているし、私たち一人一人にも「どうする俺たち」が問われていると思います。これからのドラマの展開が楽しみです。
朝ドラを見ながら・・
若林佐喜子 2023年1月20日
雪の多い冬と言われていますが、昨日(15日)も5センチほどの積雪があり、雪景色が続いています。
衛星テレビで、毎日、見ているのがNHKの新旧の朝ドラ2本です。
今の朝ドラは、タイトル「舞いあがれ」。パイロット志望の主人公のお話かと思っていたら、
先週から、中小企業の再建話になりました。時代は、2008年のアメリカ発のリーマンショックの直後で、主人公の舞ちゃんは、航空会社の就職内定が決まったものの1年延期に。実家のねじ工場も注文件数が減少し資金繰り難になり、さらに父親(社長)の急死で倒産の危機に陥ってしまいます。従業員の工場愛と仕事への誇り、そんな従業員あっての会社であり、絶対につぶすわけにはいかないと大奮闘する舞ちゃんとお母さん。日本で圧倒的に多いと言われている中小企業、大阪の下町の実相を少なからず反映しているのかなと興味深く見ています。
もう一本は、再放送の「本日も晴天なり」。こちらは、戦前、戦中、戦後の話しです。特に
印象に残ったのは、昨年12月5日の放映内容で、戦後の日本国憲法発布の日の出来事でした。満州で兄は帰らぬ人となった主人公の元子の「これで、戦争は2度とおこらないのよね、あんちゃん。誰も死なないのよね」との言葉。折しも、日本では、「敵基地攻撃能力」を盛り込んだ安全保障関連3法が閣議決定されようとしていた時期。私は、元子のその言葉に、「そうだよね、それはないよね」と思わずつぶやいてしまいました。
新年に入って、早々に米国詣での岸田首相。先日の新聞の川柳に、「国民の支持より大事、米国の支持」とありました。本当に、国是よりも、「国民の命と暮らし」よりも、米国との約束、要求が大事な岸田政権のようです。一体、どうやって「国民の命と暮らし」を守れというのか、と怒り心頭の新年、1月の今日この頃の私です。
年賀メール
小西隆裕 2023年1月5日
年賀状ならぬ年賀メール。
それが悪くない。と言うより、大変良い。
昨年もそう思ったが、今回はその良さが深まったように思う。
新年、正月の気分そのままに書ける。
いただいた年賀メールに反映された相手の正月の様子、気持ちを知りながら、こちらの様子、気持ちを織り交ぜ、楽しく書ける。
何より、リアルタイムというのが良い。
何でもそうだが、会話調に、正月の挨拶も心を接近させて、相手を思いながらやるのが良いと言うことだろう。
アメリカン・ミュージック・アワードを観た
若林盛亮 2023年1月5日
私は近年、毎年末にあるアメリカン・ミュージック・アワードを観るようにしている。アメリカで年間の各部門の最優秀賞を決める一大音楽イベントだから世界的にも注目されているものだから、私は数少ない新しい音楽情報を得る機会として観ることにしている。
今回のを観た感想は、一言でいってあまりさえないものだった。
前回、2021年度のは、韓国のポップグループ、BTS(防弾少年団)人気のブレークで若い人を中心に会場も大いに熱狂した音楽イベントになった。新人賞受賞のオリビア・ロドリゴというまだ十代、新進気鋭の女性歌手も注目を集めた。私も彼女の曲に新鮮な感動を覚えたものだ。
ところが今回、2022年度は、最高賞にはライオネル・リッチというかなり古参のしぶい歌手が、そして年間最優秀アーチストだったかにはテイラー・スウィフトが選ばれた。テイラー・スウィフトも好きな歌手だが、まだ若いと言えば若いけれど、どちらかといえばもう古参に属するアーチストだ。彼女の受賞の挨拶も前回のような「熱」がない平凡なものだった。
まあ言うならば「無難な人」が選ばれたという感じで、サプライズも感動もなかった。
一言でいって「新しい熱」というものが感じられなかった大会というのが私の印象だ。
いま「アメリカの民主主義が危機」と言われる時代だが、音楽というところにも「米国文化の衰退」が現れるようになったのかなあとも思った。
2022年のアメリカン・ミュージック・アワードを観てもそんなことを考えさせるほど、今のアメリカは、かなりヤバイところに来ているのだろう。
2023年、新年に思う
赤木志郎 2023年1月5日
年末から電気ガス代の値上げ、物価高に苦しむ人々の声が届く
この30年間、実質賃金は下がり続けるなか増税の話
そして、炊き出しに並ぶ人の群れ。
そのうえ、コロナ禍の放置で次々と知人からコロナ感染の知らせ
そのうえ防衛費を2倍にし敵攻撃能力を備え、戦争準備を整えている
なぜ中国と朝鮮を敵国とするのか、隣国と仲良くできないのか
敵愾心を煽り、悪いニュースばかり垂れ流す政府とマスコミ
今や、半植民地、植民地だったかつての中国、朝鮮ではない
米国の言いなりになって、日本が再びアジア諸国と銃を構えるのか
たとえ異郷にあれど、心はいつも日本に
聞こえてくる、闘いの開始の音が、敵基地攻撃能力に反対する若者の声が
その声に呼応し、私も頑張ろう
まだまだ元気だ、力を尽くしていこう
それが新年の決意だ
明けましておめでとうございます
魚本公博 2023年1月5日
新聞の読者欄に、年賀状を書きながら「おめでとう」と書くことに戸惑いを感じるという一文がありました。物価高が生活を直撃し、軍事費増大、増税、年金削減、社会保障費削減などの話しが飛び交う中、「おめでとう」などと言えば顰蹙を買うのではないか相手に失礼になるのではないかということです。
昨年末の清水寺での「今年の一字」は「戦」でした。その中にはワールドカップ「戦」の「歓喜」もありましたが、ウクライナ「戦」によるロシア制裁や対中対決「戦」の中で、軍事費倍増、反撃能力、台湾有事、日米共同軍事演習とまさに「戦」の1年であり、それが生活を直撃した生活苦との「戦」の一年でした。
そして今年は、昨年末に閣議決定された軍事費倍増・反撃能力強化に着手する年となり、一層きな臭さを増し、生活苦を強いられる年になりそうです。
今、ネットなどで若い人たちを中心に軍事増強反対の声を高めているとか。今年は、「戦」を「闘」で阻止する、そういう年にしたいものです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
今年の大河ドラマは「どうする家康」だとか。私は、それを聞いて、「どうする私」「どうする俺たち」が問い掛けられているように思いました。「どうする私」「どうする俺たち」、私たちも生活苦が深刻化する中で命と暮らしを守るために高まる軍事増強断固反対の声を自身のものとして共に「闘」っていく、そうした決意を新たにしています。こうして、来年は心から「明けましておめでとう」を言える年にしたいものです。どうか今年もよろしくお願いします
ワールドカップと「国」
小西隆裕 2022年12月20日
今回のワールドカップを見て、思うところがあった。
それは、「国」だ。
メッシ、ネイマール、ロナルドなど世界の名手たちのこのワールドカップに懸ける思いを知って思ったのが、彼らの自分の国に対する思いの深さだった。
彼らは世界的な大会の常連だ。
サッカーの世界的な大会と言えば、ワールドカップにも勝る水準のプロリーグ世界一を決める大会などもある。
しかし、その彼らがワールドカップの優勝に懸ける思いは、それにも勝る格別なものであるようだ。
その思いが果たせず、涙する彼らの姿を見る毎に、「国」というものの持つ人間にとっての意味について改めて思ったワールドカップだった。
メッシ最後のW杯、女神はメッシに微笑んだ
若林盛亮 2022年12月20日
メッシはやはりメッシ! 勝利の女神はメッシに微笑んだ。
W杯優勝決定戦、アルゼンチンVSフランスは予想通りの大激戦、2:2で延長戦、そこでも3:3となり、PK戦にもつれ込む展開になったが、メッシのアルゼンチンが4:1のPK戦でフランスを制した。
世界的名手メッシは過去4回、W杯に出場したがアルゼンチンは振るわず、不甲斐ない試合も続いて、国民からは「メッシはアルゼンチンのためには闘っていない“名手”だ」と批判さえ受けていた。彼の所属したスペインの名門クラブ、バルセロナではヨーロッパ・チャンピオンに何度も輝き、メッシ個人はパランドール(世界最優秀選手賞)を7度も受賞していた。だから母国からそんな非難もあがるのはある意味、仕方なかった。
私見では、メッシ頼みの戦術、メッシが得点できるようにチーム戦術を組んだことが、他の選手の個性や創造性を殺していた面があったのだと思っている。チームのすべての選手がそれぞれの個性を生かし、それがチーム全体の戦術となっていなかったのかもしれない。もちろんメッシは特別な存在だから、彼を中心に動くチームになるだろう。でもみんながメッシしか見なくなったら、チームが生きないし、相手チームもメッシさえ押さえればよいとなる。
今回のアルゼンチン・チームはメッシを中心としながらも他の選手も生かす、メッシは自身も得点するけれど、攻撃を組織し他の攻撃的選手の得点もお膳立てする、そんな風になっていたと思う。
今回のアルゼンチンの優勝はメッシを中心とした組織、アルゼンチン・チームの勝利! そう思う。やはりサッカーは組織プレーの競技だ。
前半2点をリードしながら後半、フランスに2点の追撃を許した。その2点目は攻撃に移る途上のメッシが持ったボールを奪われてカウンター攻撃を許した結果、手薄になった防御陣を突かれてエムバベのボレーシュートを許すことになった。メッシは試合を延長戦にしてしまった自分の責任を痛感していたことと思う。
しかしここからがメッシの本領、自身最後のW杯で母国に必ず優勝をもたらす! この決意と覚悟で延長戦に臨んだはずだ。
それが延長戦後半での相手ゴールキーパーのはじいたボールを冷静にゴールに流し込みメッシは試合を3:2にした。しかし不運にもフランス選手のシュートがアルゼンチン選手の肘に当たり、ハンドの反則でPKをフランスに与え、再び同点に追いつかれた。
ここでもメッシは不運に泣いたり落胆したりしなかった。アルゼンチンの選手もメッシの覚悟と意志を感じたはずだ。
最初にPKを蹴ったメッシはボールと同方向に動いた相手キーパーのタイミングを外すややゆるやかなキックでゴールを決めた。強いキックだったら止められたかもしれない。これはメッシの冷静さ、「自分が必ず決める」という強い心の現れだろう。
「アルゼンチンのためのサッカーをしていない」と言われてきたメッシだが、十数年の歳月をかけ自身、最後のW杯で悲願の優勝を愛する母国に捧げる偉業を成し遂げた。
母国の首都ブエノスアイレスの広場には数十万の群衆が歓喜に湧き、SNSでは「メッシは神だ」の声が上がった。
私は女神の存在を信じている。
女神は正しく強い愛と志を持つものには必ず微笑む。
愛国の心を見、学ぶ
赤木志郎 2022年12月20日
朝鮮ではインド映画をよく放映し、DVDでも販売している。最近では、「チャン氏の女王」があった。チャン氏王族の嫁になった女王が王亡き後も一族を率い、イギリス侵略者にたいし徹底的に抵抗し、最後は炎に包まれて死んでゆく話だ。インドの大地、人々、伝統を踏みにじる侵略者を絶対許さないという強烈な愛国精神で貫かれている。他のインド映画でも愛国者をテーマにした映画が多い。民衆の中での強烈な愛国精神が根付いているのだと思う。
私はかつて学生運動の頃、「愛国」がもっとも嫌いな言葉だった。「愛国」が嫌いだったのは、愛国をスローガンに国民が侵略戦争に動員されたという怒りからだった。また、そこには個人の自由のために反抗する米国式の個人主義に影響され、国とは自分を拘束するものとらえる側面があったかもしれない。
ハイジャックの時これで日本の拘束から解放されると思いながらも、日本から離れようとすればするほど日本のことが愛おしく感じるのだから、我ながら不思議な気持だった。
それから数年経って、愛国について考えるようになった。それでインド映画で描かれる愛国者、さらにはロシア祖国防衛戦争、中国抗日闘争、朝鮮の革命と建設の愛国者の姿に刺激を受けてきた。
しかし、もっと重要なことは日本の愛国者から学ぶことだと思う。日本の侵略戦争に反対し反戦闘争を繰り広げた槇村浩はその筆頭だと思う。また、自民党でも石橋湛山、松村一人、米国に在日米軍撤退を要求した重光葵、芦田均も愛国者だと思う。東北大震災のとき津波のため避難を呼びかける放送を津波に呑み込まれるまでおこなった女性アナウンサーも立派な愛国者だ。国の運命を憂い、国民のために闘う人だけでなく、日本人はみな国を想う心をもっている。国のために税金を納めなければと思う人、さびれゆく故郷を発展させようと苦心する人、伝統文化を継承発展させようとする人、職場を守り責任を果たそうとする人、子供を産み立派に育てようという母親の心も愛国の心だ。そうした平凡な人々にある愛国心を学んでいくことが私の課題だ。
今年もお世話になりました
若林佐喜子 2022年12月20日
 雪景色の日本人村
雪景色の日本人村
-300x261.jpg) 凍るテドン河(12.20撮影)
凍るテドン河(12.20撮影)
早いもので、もう師走、年末です。
シニアになるほど時の流れを早く感じると言いますが、本当のようです。
5月12日、最大非常国家防疫体制が発令され、私たちyobo yodoも外出禁止に。一日2回の検温で37.5度以上の場合は家で隔離。数日、熱が続いた仲間があり、全員PCR検査を受けましたが、みな陰性で安堵。毎日テレビに映し出される防疫指令部のリ・ヨンチョル氏の詳細な報告と対策解説に一喜一憂の日々でした。8月10日に、非常防疫体制の勝利宣言。その数日後、外出中の市内でマスク義務の解除が発表され、通りでも、バスの乗客たちも、たち寄ったテソン百貨店でもみなマスクなし。人々の打ち勝った達成感と喜びに満ちた風景、私もとまどいながらマスクをはずし、かなり感動してしまったことがつい昨日のようです。
そして、11月16日、朝鮮では1961年に「全国母親大会」が開かれ、その日にちなみ、「オモニ(母)の日」で祝日です。息子のような案内人からお花と「おめでとうございます。いつまでもお元気でいて下さい」と書かれた祝賀カードをもらいちょっと感動。出かけた市内のレストランでも「オモニ チュッカハンミダ」と声をかけられ、出される料理もオモニファースト、ミニチョコケーキにアイスクリームのサービスまで受けて、お腹も心も一杯になって帰途につきました。ミョンチョル案内人は、奥さんに「子供たちを立派に育ててくれてありがとう」とメールメッセージを送っていました。その日、奥さんと息子夫婦たちは、孫の保育園の音楽公演発表会に行き、開演の挨拶までした孫娘の姿に大喜びだったそうです。すくすく成長している孫娘を囲んでの一家団欒の様子が目に浮かんでくるかのようでした。新しい生命、後代のためにあらゆる苦労も楽と考え、愛と情を捧げる母親に対する社会的尊敬と期待のこめられた「オモニの日」。色々、考えさせられた一日でもありました。
12月の誕生日に届いたお祝いメッセージ。そこには、自分が親になって親の責任と重さを実感したとしながら朝鮮での日々への感謝の言葉が記されていました。よど号の子供として様々な苦労を乗り越えてきた娘、息子たちもパパ、ママに・・。どおりで私もばぁーばになったはずだと改めて自戒と自覚。
この一年、かりの会・帰国支援センターの山中幸男代表をはじめ、毎日、日本の新聞、出来事など、故郷、祖国のたよりをメールで送って下さった皆様、心よりありがとうございました。一日も早いコロナの収束を願いながら、再会できる日を心待ちしています。日本も今年の冬は寒さが厳しく、雪も多いと聞いています。どうか、くれぐれもお身体ご自愛下さい。では、皆様、良いお年をお迎え下さい。
追記)
この間、朝鮮でもW杯放映があり、特に家で視聴していたアジュモニ、ハルモニたちのサッカー熱が高揚。ダントツ人気はメッシュだそうです(笑)。
森保監督に「ごめんなさい」、でも・・・
若林盛亮 2022年12月5日
日本がドイツ、スペインに勝った!
これは私にはサプライズだった。なぜなら私は森保監督では勝てない「予選突破は不可能」と断言していたからだ。その理由は森保監督に一貫した「日本の戦術」というものが見えず、アジア予選でも基本メンバーを固定して「これが日本サッカーだ」というものを示していないと感じたからだ。
ところが今回のW杯は、その森保采配が見事に当たって強豪ドイツ、スペインを撃破し、グループ1位通過で16強入りを果たした。だから「ごめんなさい」と森保監督に謝りたい。同監督の相手に合わせて試合戦術を組み立てるという采配が見事に当たったからだ。
強い相手には前半は無理な攻撃に出ず相手の攻撃に耐え後半わずかなチャンスに勝負を挑む。これがドイツ戦でもスペイン戦でも劇的な逆転劇を呼んだ要因だろう。
そして後半に投入された攻撃的選手たちのわずかなチャンスをものにする強いモチベーションがそれを可能にした。ドイツ戦では相手のわずかなスキを突いて攻め上がった堂安律の思い切りのいいシュート、そしてほとんど角度のない位置からあの「世界のノイアー」GKの手の届かないゴール右上に決めきった浅野琢磨のゴール、それを演出した南野。スペイン戦でも堂安は同様の素晴らしいゴール、ゴールラインを割りそうなボールを諦めずに追ってライン数ミリというぎりぎりでクロスを上げ田中碧のゴールを演出した三苫君は素晴らしい。スペインのGKはラインを割ったものと判断、出たボールを取りに行こうとゴール中央を開けた、開いたところに三苫からの浮いたクロスボールが入りそれを田中碧が楽々と決めた。
サッカーというのは何が起こるかわからない競技、一瞬のスキが勝利にも敗北にもつながる。日本はそれを勝利に、ドイツやスペインはそれを敗戦にした。圧倒的にボールを支配されても相手に混乱とスキが現れた瞬間を見逃さず、それを勝利につなげる。これが予選で強豪国を倒した日本の若き選手たちの活躍だったと思う。
強豪相手にひるむことなく勝ちに行った監督と選手たちを凄いと思う。
でもこれからには不安が残る。
サッカーは「相手に合わせる」だけでは勝てない、「チームとしての戦術」、「これが日本サッカーだ」というのがなければ「怖いチーム」になれない。いつも「奇跡」が訪れるわけではない。
だから森保監督には「ごめんなさい」、でも・・・というのが正直、いまの私の立ち位置だ。次のクロアチア戦ではそれが試されるだろう。
日本の16強進出は素直に嬉しいし、次のクロアチア戦にもサプライズを期待している。でもどこか冷めた目で見ている節がある。
残念ながら私のサッカー愛国心は燃え上がるまでにはなっていない。ひねくれているのかもしれないが・・・
こんな嬉しいことはない
魚本公博 2022年12月5日
サッカー、ワールドカップで日本は、強豪ドイツ、スペインを破って決勝トーナメントに進出。それにしても、奇跡のドイツ撃破の後に「まさか」のコスタリカ戦敗北。そして、再び「まさか」のスペイン戦勝利、手に汗を握る「まさか」の連続で、こんな嬉しいことはありませんでした。
実は、BS放送では録画放送しかやりません。コスタリカ戦、スペイン戦は放送もありませんでした。それでスペイン戦もラジオを聴いた仲間の「勝ったらしいよ」「勝ったよ」という言葉で、勝ったとは思ったものの自分の目で確かめるまでは不安でした。ところが、その日は、他の試合の録画放映ばかりで、ようやく12時50分のニュースで見て、「まさか」が本当であることを確信出来た次第です。
試合の映像は朝鮮の放送でようやく見ることが出来ました。後半の連続ゴールは圧巻でした。とくに堂安選手のシュートは、まるで神業。伊藤選手からのヘッドでボールを受けるや、二人のディフェンスの隙間をかいくぐっての絶妙なシュートでした。
私は、常々、日本サッカーの良さは、俊敏性にあると思っていましたが、堂安選手のこの動きはまさに、それでした。2点目も三苫選手のラインギリギリからの折り返しが起点になりました。ドイツ戦での浅野選手の抜け出しなど、まさに忍者のような俊敏さを随所で見ることができました。
森安監督の高い位置からのプレス戦術も、その俊敏さに裏打ちされて効果的でした。選手たちは、指揮官の意図を理解し、選手同士で時間をかけて互いに欠点を指摘しアイデアを出し合って互いの動きを確認し合ったといいます。
日本の良さと言われる組織性ですね。今回のWCでは「一丸」という言葉を耳にします。控えの選手も一丸となって。サポーターも一丸となって、その応援振りに、楽しそうだと飛び入り参加する外国人も多かったとか。そして日本中が一丸となって応援しました。
それにしても、選手たちの自信に満ちた眼差しや動きが印象的でした。森安監督もインタビューで「自信をもってやってきたことが勝利に繋がった」と語っていました。選手の良さを引き出す指揮官の戦術、それを選手個々人が話し合って自身のものにする。こうして日本人の特徴や良さを上下が一致して作り出す。そこに新しい日本像、若者像を見た思いがする、それが一番嬉しかったことです。
衰退が言われる日本ですが、これからの主役は若者です。若者たちが、日本人の特徴、良さを発揮し活躍できるようにする、そこに衰退脱出のカギがあると思います。
ノーベル賞を採った大隅良典さんと共にオート・ファジーの研究をした吉森保さん(大阪大学大学院栄誉教授)は「日本は、才能は豊かな国だ」と若者への期待を述べながらも、国の人材育成の戦略のなさを危惧していました。確かに、今のような米国一辺倒では、日本のための戦略、人材育成など立てようがありません。若者の才能を活かす、国の主体的で一丸となった取り組み、そうした政治の実現が問われていると思います。
明日は、8強進出をかけたクロアチア戦。森安ジャパンが自信をもって更なる高みに挑戦し、その活躍に日本中が、とくに若者が励まされる。そうなることを願っています。
日本政治が翻弄されている
小西隆裕 2022年11月20日
山際、葉梨、今、寺田。
経済再生相、法相、そして総務相。
前二者はすでに辞任、もう一人もその可能性がでてきている。
三者連続となると、岸田政権自体が危うくなる。
迫りくる解散総選挙。
安倍国葬から旧統一教会、そして閣僚の不祥事・任命責任問題。
立て続けの「問題」は、自民党政権自体の崩壊を十分に予告している。
時あたかも、「米中新冷戦」、ウクライナ戦争と世界大動乱。
今、日本政治に問われているのは、政治と政局の動きに翻弄されない冷徹な目とこういう時こそ事態を大きく動かす革新的で戦略的な叡智と行動力なのではないか。
政治に関わるすべての人に、与野党の枠を超えて、そのことが問われているのではないかと思う。
海の彼方より、熱いエールを送らせていただきます。
天然の「かわゆ~い」-天真爛漫の童女
若林盛亮 2022年11月20日
9月に「スター誕生」で書いた女性歌手チョン・ホンランの歌をここんとこ毎朝、朝食時に聴いている。今年9月9日の共和国創建74周年の大音楽公演、野外ライブの動画をUSBに取り込んだので、それをTVに差し込んで聴いている。
この最後、フィナーレを飾るのが「ウリ・ウィ・クッキ」、“わが国旗”だが最初の場面は無数の光の粒が夜空に舞い上がるドラマティックな動画シーンから始まる。
このシーンのっけに出てくる童女が実にかわゆ~い、思わず見とれてしまう。
みそっ歯のふっくら顔の3~4歳の幼女、その子が掌てのひらに集まった無数の光の粒を見つめ、それが徐々に舞い上がっていくのを見上げていくその短い時間、その子の表情の微妙な変化が実にかわゆいのだ。
掌の光の粒を見つめる時は目をやや下げ気味に、目の前を光の粒が舞うときは目を大きく見開き、舞い上がっていく時は上目遣いに光を追い、そして画面は一転、頭上から童女が両手を広げて高く舞い上がった光の粒を見上げる姿をドローンカメラがとらえる。夜空に舞い上がった光の粒がまるでこの子を祝福してるみたいなシーン。
もうこれだけで一つのドラマ!
その間の彼女のやや厚ぼったい目とみそっ歯気味の口、その両者の動きの微妙な変化が実に絶妙。これは言葉で言い表すのは難しい。画面を見てもらう他はない。
これぞ天然の「かわゆ~い」、天真爛漫!
光の粒が舞い上がるシーンは後でコンピューター処理されたものだろう。だから実際の現場では光の粒が舞い上がるなんてことはない。だからこの童女のシーンは演技を教えられてやったものだ。
でもこの女の子は演技なんかしていない、本当に光の粒が舞い上がっていくのを不思議な夢見るような気持ちになって見ている。
おそらくカメラマンか映画監督が「さあこれから光が上がっていくよ~」とか撮影しながら彼女に伝えているのだろう。でも童女は光の粒が自分の掌に本当にあって、それが徐々に舞い上がっていくのを「心の目」で見ていて、いやもしかしたらこの子には本当に見えているのかも知れない。だから不思議な光の粒の舞がうれしくてしようがないのだ。
19歳の女性歌手チョン・ホンランさんは天然のスター、アイドルだが、このみそっ歯童女の天真爛漫も天然の「かわゆ~い」だ。
いやはや天然というのはそら恐ろしい。それは天才とはちょっと違う、文字通り天然、自然ににじみ出てくるものなのだろう。
リズム
赤木志郎 2022年11月20日
音楽の要素として音の高低と長さ、そしてリズムがあると思う。私が感じるのはリズムの重要性だ。文章を書いていても、気にいった文章はリズム感があり自分でも乗っていることを感じる。だめな文章はまるでリズム感がない。
さらにリズムが重要だと感じたのは、最近の朝鮮の音楽からだ。「熱情の歌」と「この空、この大地で」は、それまでの歌とまったく異なる軽快なテンポで、若者に大受けする歌だった。9月の共和国創建を記念する公演で歌われた。まず速いテンポの「熱情の歌」で盛り上がり、次の「この空、この大地で」でさらに盛り上がり、会場を揺るがすほどのアンコールを求める歓声を受け、2度目の歌でさらに絶頂へと向かった。これほどの盛り上がりは、50年間朝鮮に滞在していて初めて経験するものだと思う。
この二つの曲を毎日のように聴いているが、リズムが決定的だという私なりの結論に達した。この二曲が印象的なのは、歌のリズムが人々の感じるリズムと一体となって共鳴しているのだと思う。とくに、新しいものに敏感で生気はつらつとした若者の心にぴったり合うものだ。
話は昔のデモになるが、デモでのリズムは「安保反対! 闘争勝利!」というように2拍子だった。日本の祭りの「ワッショイ、ワッショイ」というのと同じリズムだった。このリズムで一歩一歩前進していくというイメージだった。朝鮮では3拍子で踊るときのリズムがそれである。同じ3拍子でも、今の朝鮮の新しい歌のリズムは斬新ではるかはやい。早足で歩くテンポだ。
時代は速い速度で進んでいる。人々のもつリズムも速くなっているのだろう。そのことを考えると、私も老いたとはいえ、リズムが合わなければ時代から取り残されてしまう。人々の気持ちや感性を理解、共鳴できなくなる。そう考えると、この二曲を聴き、口ずさんでいくことの重要さを感じるのであった。
「心の複雑骨折」重ねて「自然治癒力」を
若林盛亮 2022年11月5日
読売新聞の「編集手帳」という小さなコラムにはときどき面白い記事が載る。
先日、「ふむふむ」とうなずける言葉に出会った。
「心の複雑骨折を繰り返しながら自然治癒力を身につけていくのが人生というものかもしれない」(夏木いつきエッセイ集「瓢箪から人生」より)
人間の心というのはとてもナイーブ、鋼鉄でできているわけではない。だから心は骨折もする。自分の心がいいと思ったことも失敗や挫折もする、その繰り返しを「心の複雑骨折」というのだろう。
人生75年の私だが「心の複雑骨折を繰り返しながら」というのはよくわかる。
私も人生門出の青春期から脱線、逸脱を繰り返してきた。でもそれは自分を知り社会を知る得難い体験でもあった。
アメリカンドリーム、高度経済成長に浮かれる戦後日本にどこか違和感のあった団塊世代第一号の私は、高校時代に受験戦争までやって自分は何をやりたいのか? 何をやるべきか? 心は揺れに揺れた。何もわからないままただ流されていくのが怖かった。だからいったん流れから外れてみようと思った。以来、私は進学校からドロップアウト、社会に背を向け、ひとまずは脱線人間になった。
でもそれで何かが解決したわけじゃない、「いったい僕は何をやってるんや!?」という場面に数多く出くわした。
幸いそんな自問の時期に私は学生運動に出会った。おかしいと思う社会に真っ向から挑み社会変革に活路を求め、これに正面からぶつかっていく学生たち、それに比べ社会に背を向ける皮肉屋の自分は卑怯で良心のない人間に思えた。私の心はそう反応した。
しかし勇躍決心して始めた「戦後日本を革命する」というのも思ったほど簡単じゃなかった。失敗、敗北も数多く体験し今日に至っている。
でも脱線や逸脱、失敗と敗北の過程で幾多の「出会い」があって、それが私を救ってくれた。
こんな言葉がある。
「人間は鋼鉄よりも弱い、でも人間は鋼鉄より強い。なぜならば鋼鉄は自己の酸化過程(錆び)を自分で防ぐことができないが人間にはそれができるからだ」
この言葉は「心の複雑骨折を繰り返しながら自然治癒力を身につけていくのが人生というもの」に通じる言葉だと思う。
人の心は鋼鉄じゃない、でも柔らかいからこそ古い自分にこだわらず「いったい僕は何をやってるんや?」と自問もするし、痛い批判や必要な栄養分を取り入れる柔軟さを持つ。そんな柔軟な強さ、自力更生力を持つのが人の心というものかもしれない。
古い自分からの脱皮を繰り返しながら「骨折した心」の自然治癒力を身につけていく、それが人生というものなのだろう。
ロミオとジュリエット
赤木志郎 2022年11月5日
私はシェークスピアの作品が格別好きだ。ハムレット、オセロ、じゃじゃ馬馴らし、一二夜、真夏の夢の物語などなど。ところで先日、日曜日に朝鮮のTVで「ロメオとジュリエット」を放映していた。シェークスピアの作品は、セリフが軽妙で意味深長でしかも喜劇的なのでそれを味わいたくて見入ってしまった。作家井上ひさし氏もシェークスピアの戯曲でのセリフに魅入られたと書いてあったが、とのことがよくわかる。
「ロミオとジュリエット」は数多く映画化されている。この日、放映されたものはその中でも原作に忠実な作品だった。短い数日間の話を息を詰まらせるような速いテンポですすめ、あっという間にクライマックスに至った。完成された映画だと思った。
高校生のときにソ連映画の「ハムレット」を見、こちらで衛星TVを通じて「じゃじゃ馬馴らし」「一二夜」や「オセロ」を見た。とくに「一二夜」が素晴らしく本を取り寄せたくらいだ。久しぶりにシェークスピアの作品の映画を見、またこのような作品の放映があればと思った。
「ヤンキーゴーホーム」、久しぶりに聞きました
魚本公博 2022年11月5日
今、欧州各地で「戦争やめ、国民の生活救え」のデモが起きています。ロシア制裁でガス、石油、電気、食料などが高騰している中、これから「凍える冬」到来を前に、このままでは、大量の凍死者を出しかねないという切迫した状況の中で、国民生活に目を向けることなくロシア制裁を主導する米国、それに追随する現政権への怒りのデモです。
そうした中、イタリアでのデモのスローガンに「我々にはガスブロムが必要だ、ヤンキーゴーホーム」があったという記事を見ました。
「ヤンキーゴーホーム」、久しぶりに聞いた言葉ですが、子供の頃はよく耳にしたものです。当時は、アメ公、メリケン野郎などと共に普通に使っていました。子供の頃とは50年代ですが、周囲には、米国との戦争で戦死した人の家族もあり、別府には進駐軍も居ましたから、米国への反感が隠然としてあったのだと思います。
政治スローガンとしても50年代に盛んだった内灘闘争や砂川闘争などの米軍基地反対闘争では「ヤンキーゴーホーム」が言われました。その後の60年安保でも使われていたし、70年安保の頃でも残っていたと思います。
その後、日本を離れたので、「ヤンキーゴーホーム」がどうなったのかよく分かりませんが、最近では、とんと聞かなくなりました。その言葉が戦後77年にもなって、日本を遠く離れたイタリアで出現したことに驚きました。
物価高騰は日本も同じです。それに加えて円安が国民生活を直撃しており、生活苦は今後益々過酷になるではないでしょうか。一度は消えたかのような言葉ですが、その内、日本でも復活するのではないかと密かに期待しています。
「女性服展示会」と「アイスクリーム工場」
森順子 2022年11月5日
朝鮮では、始めてだと思いますが、いま、「女性服展示会」が、開催されています。
500以上の工場や企業所から出品されたものが、大規模なスペースに華やかに飾られていて、デパートの何十倍という広さのようです。何と言っても、女性たちには大盛況です。季節ごとの様々なデザインの服だけでなく、ハンドバック、靴やハイヒール,帽子や化粧品もあり、販売もされるといいます。最近は、男性でも黒ではなく、明るい色や淡い色、チェックのブレザーを着ている人もいるので、デザインや色も前より洗練されていますが、この展示会で、また新たな女性服の流行が見られるかもしれません。
次の変化は、「テソンサンアイスクリーム工場」が、操業したこと。街では、どこでもアイスクリームは売っているのに、こんな大規模工場を建設すると・・・。
まだ、コロナのために、封鎖は完全に解かれていないし、当然、経済的困難もある朝鮮ですが、人民生活向上を掲げ、軽工業や消費品生産に拍車をかけています。その現れの一つが、今回の女性服展示会やアイスクリーム工場操業だと思います。困難な状況でも自力更生によって、人々の生活は以前より文化的で豊かになり、それが目に見え実感している人々の表情は、やっぱり、とても明るく感じられます。
来年のソフトバンクに期待する
小西隆裕 2022年10月20日
プロ野球、パリーグの日本シリーズ出場権をソフトバンクは逃した。
シーズン中、あと一勝で優勝だったのにその一勝が獲れず、二位。
三位までの三チームで日本シリーズ出場権を争う、クライマックスシリーズでも、二、三位によるファーストステージで勝ちながらも、一位のオリックスとのファイナルステージで、接戦の末、敗退。
小学校時代の大半を福岡で過ごした私にとって、チーム名が西鉄からダイエー、ソフトバンクに変わろうと、ライオンズからホークスに変わろうと、福岡をフランチャイズにするチームが一番だ。
そのソフトバンクの敗退のダメージは簡単ではない。
まして、当の選手たちのショックはいかばかりかと思いきや、ファンの前で敗北の挨拶を終えて帰ってくるキャプテン柳田の顔にはなんと笑みが浮かんでいるではないか。その敗北の弁も、「投げるのも打つのも向こうの方が上でした」というもの。
柳田だけではない。選手会長の今宮も「オリックスのピッチャーはすごかった。それに勝てなかったと言うことです」の弁。
これが一昨年までの常勝ソフトバンクの主力選手が万年Bクラスだったオリックスに敗れての弁なのか。
今年だって、彼らが自分らの勝利を信じていたとしても何の不思議もない。
それが、自分らが至らなかった、だから負けたのだとはなかなか言えることではないと思う。
それをあっさりと言えたとは・・・。
これは、意外と展望があるのかも知れない。
今から、来シーズンのソフトバンクが楽しみになってきた。
ギター先生の叱咤-“自分に不利だからと避けてはいけない”
若林盛亮 2022年10月20日
ギター教室に1回/週、通い初めて半年、その間、コロナ禍で1ヶ月の中断があって、国立音大出身の先生から約5ヶ月の指導を受けたことになる。
ようやく複雑でない限り、たいていのコード(和音)は弾けるようになったし、ロック調の弾き方も習った。いくつかの曲は歌いながら演奏できるまでになった。
いま「禁じられた遊び」を練習している。ギター練習では日本でも初心者がまずやる曲だ。でもけっこう難しい。
楽曲の途中から6本の弦を人差し指で押さえながら中指、薬指、小指を使って同時に2本の弦を抑えるところになるとお手上げだ。
まず6本の弦を同時に押さえるというのができない。私は元来、指が短く太い、だから人差し指で6本の弦を抑えても二つの関節部分のどこかが浮いて抑えきれない弦が出てくる。だから音が濁って「ぶお~ん」、いくらやっても「ぶお~ん」・・・。ましてや他の指も同時に動かすとなるとそれは至難の業だ。
それで家で練習するときに6弦同時押さえをやめて「自分にあった簡単なやり方」でやることにした。するといちおう最初から最後まで「禁じられた遊び」らしい演奏にはなった。
それでギター先生に「こういうふうにやってみました」と練習成果を披露した。最初から最後まですらすら弾けた。弾いた後で自分は指が短くて6本同時押さえはいま無理だから「自分なりの方法を考えた」「当面はこれで行きます」というようなことを言った。
当然、ほめられると思ったが、先生はしばし間を置いて、意外にもこう仰った。
「アンテンミダ(だめです)」!
それは断固とした語調。
「自分に不利だからとやるべきことを避けていてはだめです」と先生は話を続けた。
「わが国は小さくまだ発展途上、しかも制裁で必要なものが入ってこない。だからとい
って人民生活向上は難しいと迂回路を取るんですか?」と。
これには私も反論できない。
「だから貴方も指が短いと嘆くんじゃなく、楽曲の要求通り基本に忠実にやるべきです。必ずできるようになります」と先生は私を励ましてくれた。
その日は基本通りに6本の弦を押さえるやり方のレッスンを何度も受けた。浮いてしまう人差し指は先生の指で押さえてもらったりしながら・・・。
いちおう形はなんとかできるようなったがギター音は相変わらず「ぶおん」! 濁った音のまま。でも先生は形通り演奏できると「オルソーッ(そうだ)!」と拍手してくれる。
この先生は教え方は厳しいけれど心根はとても優しい、拍手に愛情がこもっている。
私はこのギター先生を「竜之介」と心の中で呼んでいる。あの小説家、芥川龍之介になんとなく風貌が似ている、面長で大きな眼がぎょろりと光るところなどはそっくり! 日本の「竜之介」よりも柔和な印象だが・・・。芥川龍之介も自分の文学には厳しい態度で臨んだ。
朝鮮の「竜之介」を私は師とし厳しい指導にも食らいついていこうと思う。
「皆さん、頑張ったね」と思う、この頃
魚本公博 2022年10月20日
最近、同年輩の方々の訃報に接することが多くなりました。この10月には、三遊亭円楽さんが亡くなりました。円楽さんは、学生運動出身者だと聞いて親しみを覚えていた人でした。ほんの数ヶ月前にも、岡田准一さんが司会する番組に出演していて、学生運動のアジテーション(演説)は、高座でのお客さんとの間の取り方に通じるものがあるとして、「ここに参集した労働者、学生、市民の皆さん・・・」と語りかけるところから始め、聴衆の反応を見ながら演説するのだ、みたいな話しをして、岡田さんから「相当やってましたね」と突っ込みを入れられていました。まだ72歳だったそうで、突然の訃報に驚きました。
彼の死に際して、雑誌「紙の爆弾」の鹿砦社を主宰する松岡さんからデジタル鹿砦社通信に載せたご自身の記事が送られてきました。「六代目三遊亭円楽さんの死去に想う」という題で、円楽さんの、かなり詳しい活動暦が紹介されていました。それによると円楽さんは1968年に青山学院大学に入学して学生運動に参加し、所属はブント(共産主義者同盟)だったそうで、私たちと同じです。その記事には、学生運動に参加して後に芸能人になった人として、北野武、新谷のり子、松原智恵子、市原悦子さんらの名前もありました。
確かに、そんな時代だったのですね。あと、一般には関心が薄いでしょうが、同年輩でバイオリニストの佐藤陽子さんの訃報もありました。ソ連時代のロシアで学んだ人なので、ロシア人への親近感をもち、ソ連社会への見識などにも独特のものがあって、高校生の頃、「いいな」と思った人でした。
松岡さんは、「このところ、私と同じ歳か、ちょっと上の世代がどんどんなくなっています。訃報を聞くたびに『明日はわが身』と思わざるをえません」と結んでいました。
新聞に訃報が載るような人は、いわば「功なり名を遂げた」人ですが、学生運動を経験した後の苦節たるや、大変なものだったでしょうね。そして、名もなく亡くなられた方々も大勢いるわけです。日本での社会人生活を知らない私としては、円楽さんの訃報に接しながら、そうした苦節の人生に、「皆さん、頑張ったね」と思うこの頃です。
近況たより、驚くことばかり
若林佐喜子 2022年10月20日
銀杏や楓が色づきはじめた晩秋の日本人村です。
実りの秋、食欲の秋、私の間食もアイスクリームから「ペクミティギカジャ」(白米せんべい)の生活にとチェンジ。さらに、よど農場で収穫した里芋と大根、ごぼうの入った豚汁や鍋うどんと温かい料理の日々です。最近は、美味しい国産のうどんが出回り、パッケージにも「ウドン」との表示。数年前、市場でたどたどしく「中国産麺、イッソヨ?」と尋ねると、販売員が「イエ、ウドン」と差し出すのでした。「ええ?!」朝鮮語でも「ウドン」なんだと、変に感心するやら、販売員と一緒に大笑いしたことを思いだしました。
10月に入り、コロナ禍対策は、これまでの公共での検温と消毒にプラス個人での朝夕2回の検温と外出時のマスク着用になりました。ちなみに、日本人村では私が検温の担当ですが、最近は、みな朝夕、自分から知らせてくれます。また、先週の買い物日、天気が良いのにたくさん着込んだ寒がりのAさんは、ある商店での検温が38度でお店に入ることができませんでした(涙)。37度以上は入店禁止です。自分と周囲の人々の健康、国家の安全を守るためとみなが自覚し、本当にやることが徹底しています。
そして、一番の驚きは、大規模なリョンポ温室農場の竣工式ニュースでした。280万平方メートルの敷地に、850余棟の温室がずらりとたち並び、1000余世帯の特色ある近代的な文化住宅と学校、文化会館、総合サービス施設などがあります。地方の野菜生産基地の現代化、集約化、工業化の実現ということですが、咸鏡南道、特に咸興市は、経済と科学技術発展の重要都市ですが、冬が長く寒さが厳しい土地柄で野菜もよくできません。そのような土地に世界一大規模な野菜温室農場を建設するのですから、その胆力と大胆さ、勤労者の生活向上への思いと温もりが伝わってくるかのようで、もう驚きの10月でした。今後、すべての道(日本では県)に建設していく予定だそうです。
虫がいなくなった
小西隆裕 2022年10月5日
最近、虫がいなくなった。
窓を閉め忘れても、夜、蚊に悩まされることがなくなった。
それにハエも蛾もパンク虫も、みんな皆いなくなってしまった。
50年前、朝鮮に来たばかりの頃、夜、蛾が網戸一杯、ぎっしりと群がっていたのが懐かしい。
この世界的現象について、先日、あの養老孟さんがラジオで語っていた。
原因はいろいろ言われているが、農薬なのか都市化なのか、何なのか分からない。
ただ、これが人類にとって、生物全体にとって良くないことなのは明らかだ。
虫を食って生きている動物が、いや植物も、いかに多いか。
植物の受粉ができない。土壌の回復ができない。
虫がいなくなって起こる弊害は計り知れない。
朝鮮のテレビで最近、有機農法の勧めが頻繁なのに少し胸をなで下ろしている昨今だ。
身重になった愛玩犬、シロちゃん
若林盛亮 2022年10月5日
「村」にはテリヤ系雑種とプードル系雑種の小さな愛玩犬がいる。テリヤ系とは安部(現姓は魚本、私たちは使い慣れた安部で呼んでいる)の見立てだから実のところはわからない。
このテリヤ系には安部が「シロちゃん」と名付けた。とても可愛いい。私が近づくとゴロンと寝ころんで「おなかをさすって頂戴」となる。それでおなかをなでてやると気持ちよさそうに目を細めてなんとも言えない恍惚とした表情になる。
このシロちゃん、ちっちゃな犬なのに賢くてリーダーシップもある。いつもプードル系を従えて村を徘徊、夜になるとアパートの安部の玄関前の靴脱ぎシートで休む癖がついた。それで私がいつも「カラッ!(出ていけ)」と追い出しているが、またいつの間にかプードルを連れて、時には猫も引き入れてくる。夜明け前出勤でアパートを出る私の顔を見ると、申し訳なさそうに目線を下げてすごすごと出ていく、プードルもそれに続いて出ていく。自分が叱られるようなことをやっているという自覚はあるのだろう。シロちゃんは賢い!
そのシロちゃんが妊娠した。おなかをなでてやるとき、いつもより乳首が大きくなってやや黒ずんでいる異変に気がついたが、最近は一目で身重とわかるようになった。歩くときも足取りが重くなった。少ししんどそうだ。裏返しにしておなかをさすると子供がいるのがわかる。
そうかシロちゃんはママになるんだ! でもちっちゃな身体を見ていると子供がママになったような奇妙な感覚。父親はプードル、いつも仲睦まじくじゃれていたからいつの間にか恋が芽生えたのだ。犬の恋ってどんなもんなんやろう? とつい想像したくなる。
でもテリヤとプードルの夫婦、いったいどんな子供が出てくるのか楽しみ、みんなの関心もその一点にある。10月中旬には出産とのこと。私たち爺さん婆さんらは孫でも迎える心情、みんなで身重のシロちゃんの健康を気遣って「エエ子を産むんやで」と声かけをしている。
食欲の秋
魚本公博 2022年10月5日
食欲の秋、市場でもサツマ芋、栗、柿、リンゴ、ブドウ、キウイなどが出回っています。街中のキオスク風の売台(メーデー)でも、焼き芋(クンコグマ)や焼き栗(クンバム)が売られています。
焼き芋は、日本のように石焼で作るのでねっとりと甘みが出て非常に美味いです。栗は有名な平壌甘栗の本場ですから、これも美味い。それが大量に出回るので値段もタダ同然の安さです。
そしてブドウとキウイ。私もよど農園の一角で育てています。キウイは、数年前に20個ほど実ったこともあるのですが、零下20度を越えると地上部は凍死してしまい、ここ数年それが続いて、今のところ収穫ゼロです。南部のケソン(開城)辺りでは、1mほど土を掘った石垣でキウイの凍死を防止しているそうで、ちょっと小型ですが国産のキウイとして市場にも出回っています。
ブドウも何年も前から育てているのですが、あまり手入れもしないので、夏場は草に埋もれ、中々大きくなりませんでした。そこで一念発起して昔の温室跡に移植したものが大きくなって、今年は、50個以上の房を付けました。しかし、異常気候のせいでチャンマ(梅雨)が2ヶ月近く続き、雨に弱いブドウは、粒も小さく、色も悪いまま。もう少し様子を見ようとしているうちに実が落ち始め、あわてて収穫して、食堂で皆に出しました。ちょっと心配だったのですが、「結構、甘いじゃない」の声にホッとしました。
これから10月、食欲の秋も最盛期です。好物の柿もこれから大量に出回ります。夏痩せするタイプの私にとって、ありがたい体力回復の季節です。
5500台の農機械
森順子 2022年10月5日
テドン江の向こうは、まだ、黄金色した稲穂が揺れていますが、地方では秋の刈り入れが始まっていて、今年は大きな台風もなくよかったなと思っているところです。
そしたら、数日後、農機械が黄海南道(穀物生産の中心地)に送られたという報道があり、5500台の各種、農機械が20キロにも及び列をなしている、その光景には、声が出るくらい驚きました。確か、農村革命が言われてから、まだ一年くらいしか経ってないのに、この大きな変化を、朝鮮の人も思ってもなかったようです。
朝鮮では、農業生産の科学化、現代化、情報化して、農産作業の機械化を高い水準で実現すること、そして、同時に農村の住宅建設を基本とすることが今の課題です。とくに、地方の住宅建設が目を引きます。地方、地域の特性に合った住宅が全国各地に次々と建設され、入居時の様子は、よく放映されます。「あすは、新しい家に入れると思うと寝れなかったわよー、農事を今以上に・・・」というおばさんたちの声、そこには、農村が現代的に改変され、その変化を実際に見て、肌で感じていることが伝わってくるようです。
5500台の農機械は、改めて、この国の潜在力を感じさせる出来事でした。
味方のエラーに対して
小西隆裕 2022年9月20日
山本由伸。今、日本で最高の投手だと言って良いだろう。
その彼が、高校の時は大した選手ではなかったらしい。一応、都城高校のエースだったらしいが、これといったこともなかったようだ。
試合中、急に投球が乱れ、ダッグアウトに戻ってきてからもブスッとしている。試合は大負け。
試合後、監督が山本に言ったのは、「エラーした奴を怒ってはならない。逆に皆に感謝しろ。それができない奴は勝てない」。
それを黙って聞いていた山本は、次の日からがらっと変わったようだ。
それから10年近く、その時のことを山本も監督もよく憶えているという。余程印象深かったのだろう。
今、山本は、味方がエラーしても、怒ったり、腐ったりしない。逆に皆を励ましながら、投球のギアを上げる。その後ろ姿を見て、チームの集中力も高まる。
こうして投手はエースになり、チームは強くなっていくのだろう。
スター誕生!建国74周年・音楽公演の大舞台で
若林盛亮 2022年9月20日
朝鮮の建国節前夜の9月8日、金正恩総書記夫妻を迎えての音楽大公演夜間ライブがあり、それがTVで放映された。
場所は最高人民会議(国会)前の大広場、革命博物館横の駐車場スペースにもなる広大な敷地、優に数万は入りそう。そこに大舞台が設けられ、バックの議事堂全体がスクリーンになるような配置。日本でよくある野外ライブのような会場との一体感の出る光と映像、そして音の一大ショウ形式の音楽公演だった。
TVで観たそのライブ公演は圧巻、これまで観たどれよりも凄かった。ここではとても書き尽くせないので、とても印象的だった出来事、一つだけに触れようと思う。
その女性新人歌手の名前はチョン・ホンラン、朝鮮では珍しい眉毛が隠れるおかっぱ頭がまず目を惹いたが彼女の歌う歌、歌唱力も凄い、大胆かつ伸びやかでエレガントかつ活気ある振りの仕草も迫力をもって迫ってくる。
“新しい世代がこれからの国の主人、素晴らしい国に盛りたてていこう”的な歌では、伸びやかな肢体をパンツ・スーツに包み、天に向かって指を突き上げ歌い踊る、歌の切れ目で手のひらを軽く振って歓呼の観衆に応える余裕、一連のそれらがとても自然。
この子は天然の大スター!! 正直、そう直感した。
爺さんの日本人が感動するのだから朝鮮の大学生や若い人の反応はもっと強烈、彼女の歌は終始“ウオーッ”の歓呼に包まれ、歌に合わせてみんなで上げた手をゆらゆら、身体もゆらゆら、手の国旗もひらひら、まさにライブの醍醐味を象徴するような興奮のるつぼになった。
これは古い世代が目をむくような現象ではない。実際、会場にいた老齢、中年、男女を問わずみなが相応に身体を揺すっていた。
歌の内容も“前世代の精神を受け継いで私たちも・・・”的なもの、だからこのチョン・ホンランさんは若者だけじゃなく古い世代も支持する「全世代型のスター」になるだろう。
若手歌手中心のこの舞台は他の歌手への歓呼も凄かった。それだけ迫力あるライブだった。でもこのチョン・ホンランさんのは別物、すべてが天然でとてもカッコイイ-誰のものでもない「チョン・ホンラン式」!
まさに“スター誕生!”、すなおに私は感動した。
毎日、聞く音楽
赤木志郎 2022年9月20日
7・27戦勝記念日、戦勝記念館の前で催された音楽会で新しい三人の歌手が登場した。これを録画し、歌手別に編集し、それを毎日、聞いている。とくに気にいったのは、チョン・ホンランの「エップニ」(可愛い子ちゃん)だ。しかし、ムン・ソヒャンの「戦士の歌」、キム・リュギョンの「人生の栄光」も劣らず良い。そして、チョン・ホンランの「誰が教えてくれたか」を含め、四曲を毎日、聞いている。
同じ歌を唄ってもモランボン楽団の歌手とはまた異なった趣がある。声量といい深みが感じられる。
とにかく演出がすごい。踊りやバックの大型スクリーンを使っての、単なる音楽公演ではなく一大エンターテイメントに仕上げている。しかも、数万人の観客の多くは大学生、革命学院生などの若い人だ。一緒に手をふりあげ、歌手と観客の一体感をもりあげている。
このビデオを毎日、眺めていたら、今度は9・9節(共和国創建日)の公演があった。場所はマンスデー議事堂(日本の国会にあたる)の前の野外。議事堂の白い壁を巨大スクリーンにしたてている。
主役はチョン・ホンランとキム・リュウギョンだった。最初はキム・リュウギョンが真っ赤なドレスを着て暗闇の中でスポットライトを一身に浴びて「共和国創建宣布の歌」を独唱するところから始まった。こんな始まり方は初めてだ。キム・リュウギョンは「祖国と私」「今日もその日のように」と少し重い歌を全身で唄い上げるのが特徴だ。
一番、出番が多かったチョン・ホンランは「私を呼ぶ声」「党よ私の母よ」などの叙情的な歌もあるが、軽快なテンポの歌がぴったりな人だ。「熱情の歌」「この空この大地にて」がそうした若い人に合う軽快な歌だ。とくに「この空この大地にて」は大歓声のアンコールを受けて二度歌った。こうした大々的な公演でアンコールはめったにないことだ。多くの歌は祖国愛をテーマにした歌だが、「この空この大地にて」はこの祖国で自分の夢を実現しようという現在の発展していく現実に合う歌だった。だから、若い人の歓声がすごかったのだろう。おそらく結婚式などで踊りながら歌うその姿を真似する人が出てくるのではないかと思った。
会場がかつての劇場ではなく、野外なので大人数の人々が参加でき、そこに若い人たちが圧倒している。かれらの熱狂的な声援を見て、祖国戦争(いわゆる米国との朝鮮戦争)や祖国建設の戦いが、若い人たちに継承されている姿を見る思いだ。
最後に一言、放送されるのは編集されたものだが、この編集技術もどんどん発展している。公演といい、撮影・編集技術といい、発展する朝鮮の現実を見せている。
しばらく、朝鮮の新しい歌手の歌に夢中になりそうだ。チョン・ホンランの歌を集めた動画を作成し、今日も聞き入っている。
奥歯よさようなら! そしてありがとう「私の奥歯ちゃん」
若林盛亮 2022年9月5日
朝鮮の祝日だった8月25日、家でお好み焼きを食べているときにガキッ! と音がして奥歯が真っ二つに割れた。
病院で診てもらったが、「抜きましょう」となって医者が「親からもらったもの、いいですか?」と了解を求めたので「ええですよ」と私は応え、すぐに抜歯した。前に固いものを噛んで少し欠けた歯だったので腐蝕が進んだのだろう。割れているので少し手間がかかったが、コロンコロンと抜いた奥歯が容器に落ちる音がした。終わって血に汚れたガーゼの中の奥歯のかけらをつまんでみた、記念に持って帰ろうかなと思ったからだ。「汚いものだから捨てましょう」と医者は言った。私は心残りだったが「奥歯よさようなら」をした。なんとなく感傷的になって「ありがとう“私の奥歯ちゃん“」と心でつぶやいた。
思えば70余年間、私と苦楽を共にしてきた「私の奥歯ちゃん」だ。
幼児の頃は奥歯まで生えそろった私を両親が健康であれ、と祝福してくれたことだろう。
けっこう虫歯だった私は小学生の頃、歯医者によく通ったものだ。奥歯の臼歯をガリガリと削る音がとても怖かった。
高3のとき、ビートルズ風長髪を見とがめた体育教師から「女の子の授業はあっちだ」と言われ、「ようし、ならあっちに行ってやる」! むらむらとわきあがる反抗心で奥歯をきりりと噛みしめたことを「私の奥歯ちゃん」は覚えているだろう。
東大安田講堂で逮捕、長期拘留後、帰った京都で私の恩人がやってくれた「出所祝い」の遠足、心尽くしの「おにぎり」はひとしおおいしかった。激動の時代、赤軍派参加直前のつかの間の安らぎのひととき、その格別の味も「奥歯ちゃん」は忘れてはいないはずだ。
それから半年の後、私はよど号ハイジャックの機内に、金浦空港で重武装の韓国軍に囲まれたとき、奥歯がきりきりする緊張も経験した。
朝鮮に来てからは「無償医療」の恩恵を受けて悪い歯の治療を受け、虫歯の奥歯をブリッジにしてから私は歯の悩みから完全に解放された。以来数十年、頑健な奥歯は私の健康と仕事を支え続けてくれた。
「奥歯ちゃん」は私の人生を共に歩んだ名もなき私の友、隠れた恩人だ。
そんな「私の奥歯ちゃん」の歴史を「ありがとう」の気持ちで振り返る契機を与えてくれたのが古希過ぎてやった今回の抜歯、「奥歯よさようなら!」、75歳の「よど号LIFE」であります。
お盆を迎えて
赤木志郎 2022年9月5日
8月お盆やすみにお墓参りもできないので、思い立って家族の写真や手紙を3日間かけて整理し、読み直してみた。
そこには家のようすが詳しく書かれてあった。父が私の手紙を受けるたびに涙をながしていたこと、祖母が私の写真を部屋に飾り、しばしば私の話をしていたということ。妹がいつかは朝鮮に行きたいと書いてあったことなどなど。私は家族の愛情をたっぷり受けていた。
しかし、私は親不孝者だ。父母、祖父母の死に目にあっていない。生前に孝行らしいことを一度もやっていない。むしろ、心配ばかりかけてきた。ときどき父母や祖父母を生前に近くの温泉にでも連れていったならと思う。
もし、孝行をできるとしたら、息子、孫として恥ずかしくない生き方をすることだ。それしかない。しかし、それが一番大切なことかもしれない。そう自分を慰めながら、父母と祖父母、兄と妹の愛に応えていこうと思った。
泥土堆積、そしてイノシシ出現
魚本公博 2022年9月5日
今年のチャンマ(梅雨)は、異常でした。朝鮮の場合、日本で弱化した梅雨前線が北上してチャンマになるため、期日も7月終わり頃に、しばしば大雨になる程度なのですが、今年は、7月初旬から始まったものが、8月下旬まで続き、それも豪雨続きでした。とくに8月初旬には、ピョンヤン辺りは、それほどでもなかったのですが、上流域で大雨が降ったらしく、目の前のテドン江が増水、水位が2、3mも上がりました。そのため、川辺の畑が水没。水が引いた後に行って見ると、粘土質の泥が10㌢ほどにも堆積し作物も埋まっていました。朝鮮に来て50年来、こんなことは初めてでした。
その上に何とイノシシが出現。サツマ芋が掘り返され、その他にも、スコップで削りとったような穴があちこちに。そこには、豚のような足跡があり、イノシシの仕業と分かりました。これも50年来なかったことです。
それで、最早、今年の農作業はあきらめるしかないという状況です。まあ、細々と大根やホウレンソウの植え付けはやりましたが、来年は、どうなることやら。
異常気候は世界的なもので、中国の四川省では、40度を越える日々が続き、川の水が干上がり川底が見えるほどだとか。パキスタンでは大水のために、幅100キロにもなる巨大湖水が出現したとか。日本でも、梅雨前線が止まり各地で大雨被害が出ました。
泥土堆積、イノシシ出現で、来年の心配をするなどと、言っておられませんね。
マスクレス
小西隆裕 2022年8月20日
マスクのない生活、二年ぶりだ。何かおかしい。何かを忘れたような感じだ。特に、ピョンヤン市内に行く時など、忘れ物をしたような感じで、心が定まらない。
もうかれこれ一週間以上になるのに、いまだにそうだ。
マスクレスの生活。
高校時代、野球部の脱衣室で誰かが「今日はやる気レスだ」と言っていたのを思い出した。この六十数年間、一度も思ったことも頭に浮かんだこともない言葉だ。
人間の脳というものは一体どうなっているのだろう。
8月15日に出たホタル
若林盛亮 2022年8月20日
蒸し暑い夜、事務所からアパートに戻る途中でホタルを見た。
たった一匹、飛びもしないで草むらで小さな光を放っていた。
ここ2、3年見かけなかったが6月頃に数匹が青白い光を放ちながら飛んでいたから「今年はホタルが出るんだ」と期待したけれど、それ以降またまったく見かけなくなった。だから炎暑と豪雨の夏だったから今年もだめだろうなと思っていた。その矢先のことだったのでとても貴重な光に見えた。
ところがそれ以降、またホタルは見なくなった。
あの一匹のホタルは何だったのだろう?
思えば、ホタルが出たのは8月15日だった。朝鮮では祖国光復(解放)の日、日本では敗戦記念日(公式には「終戦記念日」)だ。
だからあの夜現れたたった一匹のホタルは、何かを訴えるために光を放っていたようにも思えてくる。
ホタルといえば、野坂昭如原作の「火垂るの墓」、高倉健の映画「ホタル」がある。
「火垂るの墓」はアニメ映画やドラマで観た。アニメ映画では戦災孤児の兄妹が餓死、兄の死後、彼の持っていた妹の骨の入ったドロップ缶から青白い光を放つ無数の火がゆらゆらと天空に舞い上がっていくシーンが感動的だった。
一方、「ホタル」は朝鮮人戦闘機乗りが特攻出撃後、一匹のホタルとなって現れるという映画でその部下だった高倉健が朝鮮人パイロットの恋人だった田中裕子と結婚後、長い歳月を経て朝鮮人特攻パイロットの両親を訪ねて韓国に渡るという映画だった。
あの戦争でいまだ鎮魂されない霊魂が無数にあるのだ。
8月15日にたった一匹、飛びもしないで草むらで密かに青白い光を放っていたあのホタルは何を訴えていたのだろう?
今年の8月15日は、ウクライナ事態や米中新冷戦を受けてわが国が「東のウクライナ」化へと傾斜を強めているさなかで迎えることになった。いまあの戦争の教訓、非戦の国是は風前の灯火だ。
あの日に見たホタルはいまだに鎮魂されない無数の霊魂が何かを訴えていたのではないだろうか? そんなことを考えさせる青白い光だった。
今年も元気もらってます
魚本公博 2022年8月20日
大谷選手が8月10日の対アスレチックス戦で、投げては10勝目をあげ、ホームランも25本と大活躍です。
当日は、号外も出たそうです。多難山積の日本で、みんなが大谷選手の活躍に元気をもらっているようです。ネットでは「ヤバすぎ」「やっぱ凄い」「スーパーヒーロータイム突入」などのコメントが並んだとか。
実は、昨年の8月20日の「よど号ライフ」にも「がんばれ大谷翔平」と題した文章を載せています。昨年は、ホームラン王争いで、毎日のようにホームランを打つので、それを見ては、やる気が出るという内容でした。
今年は、ホームランは、それほどではなく、11時からのMLBニュースでも、がっかりということが多かったのですが、リアル2刀流で、投げては10勝目、打っては投手大谷を援護する25号ホームランという活躍に、久しぶりに溜飲を下げた思いをしました。
感想もよかったです。ベーブルースに並ぶ104年ぶりの偉業達成にも「単純に二つやってる人がいなかっただけ。二刀流があたり前になれば、もしかしたら普通の数字かもしれません」と謙遜。そして、「もっともっと三振がとれるよう頑張ります」「もっともっと打ちたい」という前向きの姿勢。
これからも頑張ってほしいです。心配なのはケガですが「あまり先を見すぎてもしょうがないので、ちゃんと寝て、いい明日を迎えられるよう頑張りたいと思います」ですから大丈夫でしょう。
その日の新聞は「内閣改造」の記事もありましたが、あまり変わり映えしませんね。スポーツでは大谷選手や完全試合の佐々木朗希選手など若者の活躍が目立ちますが、政治の世界でも、もっともっと若い人が出てくればと思います。
新規発熱者ゼロ
小西隆裕 2022年8月5日
今日は8月2日。午後8時のテレビニュースの時間に出てきた、お馴染み、国家非常防疫司令部、リュー・ヨンチョルさんは、今日も新規発熱者ゼロを発表した。
これでもうかれこれ一週間以上、「ゼロ」が続いている。
昨日完治した人の数は49人。
これまでの発熱者総数、477万2813人中、477万2644人が完治したという。
残り169人。
なのにまだわれわれの検温は続いている。
これくらいやっているからこそ、つい数ヶ月前に一日の新規発熱者数が40万を超えていたのがウソのようになった。
南山の青い松
若林盛亮 2022年8月5日
私のギター教室はまあ順調に進んでいる。何よりも先生とうまく行っている、と言うより「ギターは技術じゃない音楽だ」という人だから何となくウマが合う。音楽を愛する点で通じ合うものがある。
「感情を込めて歌いながら! ギターは下手でもいいから」と先生が言うので、朝鮮の歌で私の好きな歌にギターのコード(和音)進行を付けてもらって練習するようにした。
「南山の青い松」という歌だ。歌詞はこんな感じ。
南山の あの青い松が
雪霜に埋もれ 千辛万苦に耐えて
陽春を再び迎え 甦生することを
友よ わかるか
作詞作曲は金日成主席の父君、キム・ヒョンジク先生(朝鮮の人はそう呼ぶ)、この方は独立運動闘士であると共に「明新学校」という学堂を開いて後代教育に尽くした人でもある。この方の生涯を描いた歴史小説が「歴史の夜明け道」、題目の通り夜明け前の道を歩きその途上で倒れた不屈の独立闘士、それがキム・ヒョンジク先生だ。
朝鮮に来た当初からなんとなく心惹かれ愛唱歌の一つになっていた。おそらく「夜明け前の道を歩く」という心情に通じるものを感じたのだろう。
この歌を歌う度に「雪霜に埋もれ」ても、いつか「陽春」を迎えるのだ、それまでは千辛万苦なにするものぞ! 若かりし頃はこの歌を口ずさむと心が奮い立ったものだ。
先生が付けてくれたコードに従ってギターをボロロンとつま弾きつつ歌う、歌に乗ってくるとギター音までが迫力を帯びだしその相乗効果ですごくいい感じの演奏になる。いまの私の技量水準で最高の音! と思える演奏になる。
少し自信が出た頃、先生の前で「南山の青い松」演奏と歌を披露した。
先生は「ベリー・グッド」、すごくいいなどと英語も交えて拍手してくれた。そして言った「これをみんなに聴かせよう」と言い出した。最初に「ピョンヤンの理髪師」アジュモニをスマホで呼んだが仕事中、ということで「じゃあ練習が終わったらカラオケ場でやろう」となった。私は「みんなを呼ぶのはやめてほしい」「先生に歌唱指導を受けたい」と言った。
結局、私はその日、先生からカラオケ場での歌唱指導となった。
まず私の歌を聴いて先生は「もっと感情を前面に出しなさい、高らかに歌うところはもっと高らかに・・・」などと言いながら「ただ突っ立って歌うのじゃダメ、感情をそのまま動作で大きく表しなさい」、動けと強調。自分がやってみるからと実演してくれた。
「千辛万苦に耐えて」では胸に手を当て表情は慟哭するかのように、「陽春を再び迎え」では天を仰いで手を広げたりといった具合に舞台狭しと熱演してくれた。
私は少しオーバー・アクションだなと思ったが、本当にこの人は音楽を愛してるのだと再認識した。
ちょっと変わった先生だが音楽愛で結ばれたいい師弟関係になれそうだ。
私のギターも今は「夜明け前」だが未来は明るくなりそうな予感がする今日この頃。
これが私のギター教室の現在地であります。
ふるさとの海
赤木志郎 2022年8月5日
 よど農場のぶどう
よど農場のぶどう
 可愛い朝鮮リンゴ
可愛い朝鮮リンゴ
暑中、お見舞い申し上げます。日本ではとくに今年は猛暑だったとか。
平壌の今年の夏は雨が多かったです。7月下旬から梅雨入りし、それからずっと雨天続き。例年より雨が多いのは確か。暑くて湿気がある。冷房ももっぱら湿気を除くためでした。
子供たちの夏休みは8月15日まで。2週間ぶりにプールに行ったら、子供を連れた家族づれで一杯。「子供が王様」の国なのか、無我夢中で遊びまくっている。ゆっくり水中歩行をやっている場合ではありませんでした。
途中、休みながら、私も子供の頃、プールや浜辺で泳いで遊んだことを思いだしました。近所の浜辺、そしてプール、須磨の海の家などなど。「われは海の子」という歌にあるように海に囲まれた日本人にとって海はなくてならない故郷のようなものだと思います。
小中学生のときには、近くの和田岬に行って、写生などしました。その後、埋め立てられ、海も汚れてしまいましたが。
高校生のとき移った高台に位置している須磨の家では、窓から海が見えました。台風のときにはものすごい高波がうち寄せるのが見え、静かな海のときの日の出はなんともいえない美しいものでした。海に囲まれて育った私には、海が故郷への思い出と繋がります。
朝鮮に来て2年目か地方を参観したとき、元山(ウオンサン)の浜辺で潮の匂いをかいだ瞬間、懐かしい日本の海を思いだしました。続いて、ハムフン市の海水浴場に行ったときには、ボートを狂ったように一人で漕ぎまくっていました。
それは若かりしの頃のこと。今は、じっと静かに青い海を眺めてみたい。いつか日本の海を。
ケージャンの日に思ったこと
魚本公博 2022年8月5日
朝鮮も暑い日が続いています。朝鮮では倒れ伏すような暑さということで、7月から8月にかけて、初伏、中伏、末伏があり、これを三伏と言い、この日に犬肉を食べる習慣があります。先日、日本のSさんに資料を送ってもらおうとメールしたのですが、末尾の挨拶に「昨日は中伏、ケー(犬)ジャンを食べる日でしたが、日本で言えば土用の丑の日、ウナギでも食べてお元気で」と書いたところ、「犬食文化」の資料を送ってくれました。
それによると、「犬食文化」は、世界各地にあり、欧州でもドイツやフランス、スイスなどに根強く残っているそうです。世界では年間2000万頭から3000万頭が食べられており、その多くはアジアだとか。
それで欧米の動物愛護団体が犬食をアジアの悪習として「犬を食べるなど野蛮だ」と非難しています。これに対してアジア側は、これは文化だ、あなたたちは、犬は食べるなと言いながら牛、豚は平気で食べているではないかと反論しています。
いわば、食の文化論争ですね。日本は、犬食文化圏ではありませんが、食の文化として鯨肉食やイルカ漁が非難されています。
「犬食文化」を巡る論争について、フード・ジャーナリストの川路力哉さんは、「まずは、異なる文化の存在や背景を認めることが重要だ」と述べていますが、これが大切だと思います。
「戦勝の日 7、27」
森順子 2022年8月5日
「世界でいちばんつよい国」という絵本がロングセラーになっているらしいです。自分たちの暮らしほど素敵なものはないと信じている大きな国。その大きな国の大統領が、次々と世界を征服していく話。絵本では、小さな国に攻め込んだ大きな国の兵隊は、小さな国にすっかりなじんでしまい、小さな国をぶんどったつもりの大きな国の大統領も・・・。
ところで、7月27日は、朝鮮の「戦勝の日」です。今年は69周年になります。
毎年、この日は全国からの老兵たちが集まる行事があります。もう90歳前後のおじいちゃん、おばあちゃんだから見るからに大変そうですが、歴史の体現者、証言者の話は、やはり違います。力が入った張りのある声と内容に胸を打たれます。老兵世代は、共和国の存亡と
発展の礎を築いた世代。もっとも厳しかった1950年代、老兵世代が発揮した勇敢性や精神は、次の代に引き継がれる国の遺産なのです。老兵世代が、そうであったように、次世代のために奮闘していこう、というのが、今の朝鮮の人々の姿です。
絵本「世界でいちばんつよい国」の感想を書いた方の最後には、本当に勝つのは大きな国とは限らないだろうと言われていますが、そうだと思う。それは、国が大きいかどうかや、武器があるからで、決まるのではないのだから。
安倍国葬
小西隆裕 2022年7月20日
ラジオのニュースを聞いていたら、「安倍国葬」という報が飛び込んできた。
「ちょっとやりすぎではないか」。それが最初の感想だ。
もちろん、死人に鞭打つ気はない。
しかし、この間の報道は、「美化」もいいとこだ。
それが政治的目的を持ったものなのは言うまでもない。
この「国葬」への反対闘争が組織されていると聞く。
まったく異議なし。目には目を、歯には歯を。
「アベノミクス」「安保法制化」・・・
安倍が日本国の前に犯した特大級犯罪を暴き出し、
「国葬」を日本政治の転換を考える一大契機に!
それが一番ふさわしい安倍の葬儀のあり方だと思う。
人生に 無駄なものなどなにひとつない
若林盛亮 2022年7月20日
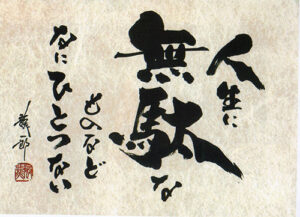
月刊誌「紙の爆弾」、「デジタル鹿砦社通信」への寄稿などなにかとお世話になっている鹿砦社社長の松岡さんから一枚の書が送られてきた。
「人生に 無駄なものなどなにひとつない」
逞しくも見事な筆致、骨太の書、作者は龍一郎という書道家、同志社神学部卒業の方だ。最初の赴任先の福岡で荒れる小学6年のクラスを見事に立て直し、卒業を前にピカソの反戦画「ゲルニカ」をクラスみんなで描き上げ、卒業式前夜に式場に飾ったがそれは撤去された。龍一郎さんのクラスの生徒達はこれに抗議の国歌斉唱ボイコット、生徒達がそれぞれに「ゲルニカ」を描いた決意を述べたという。それを問題にされた龍一郎さんは懲戒処分になった。いまは書道家として活躍される一方でアフガンで非業の死を遂げられた医師、中村哲さんの遺志を継いでペシャワール会の事務局の仕事をやっておられるという。
「人生に 無駄なものなどなにひとつない」
龍一郎さんの座右の銘であろうこの書に私は共感、というよりわが意を得たり! と大いに共鳴するところがあった。
ここ10年の間、「よど号欧州拉致」えん罪払拭のためもあって私たちは「拉致疑惑と帰国」「追想にあらず」「1970年-端境期はざかいきの時代」と三本の手記を書いたが、それは私にとって自身の人生を振り返るまたとない機会となった。
高校3年時、教師にビートルズ風の長髪をみとがめられ「ようし、ならあっちに行ってやる」と進学校、受験戦争をドロップアウトしてはみたものの行く当てや明確な志があったわけではなかった。当時は高度成長下の日本で受験戦争に勝ち抜くことは常識だった。でも私はおかしいと思うことに自分がずるずる流されていくのが怖かった、理由はそれだけだった。
その後は転がる石ころのように流転の人生の大学4年間だった。傍目はためには「あいつは何やってるんや」、親のすねかじりのただのずぼら学生、遊び人、「無駄だらけの青春」だったろう。私の胸の内もけっして穏やかではなかった。
ポール・ニザンの言う「二十歳が人生の最も美しい時期だとは誰にも言わせない」! の心境だった。
青春期は自分の運命開拓の出発点、ある意味、思案に暮れる時期、未熟だから脱線、逸脱もある。
でも「なら、あっちに行ってやる」の契機、自分の原点さえ忘れなければ、二転三転、転がる過程での人との出会いを幸運につなぐこともできる。私の場合、最終的に「10・8闘争-山崎博昭の死」という新しい学生運動に出会うことによって「あっちに行ってやる」以来、社会に背を向けてきた自分が恥ずかしくなって再び社会と向き合う新しい自分に脱皮できた。
ずいぶん遠回りの人生で恥ずかしくもなるが、「しゃあないやろ、それでいいのだ」とも思う。
人生には脱線も失敗もある、でもどんな人にも自力更生力がある。そのうえで出会いは大切、自分を振り返ることのできるもの、それは人でも書物でも実体験でもいいというのが私の総括だ。
瀬戸内寂聴さんは言った「若い人は恋しなきゃだめ、でも失恋することが何よりも大事よ」と。
「人生に 無駄なものなどなにひとつない」のだ。
素晴らしい書を残してくれた龍一郎さんに感謝!
無窮花(ムグンファ)
赤木志郎 2022年7月20日

今年は蒸し暑い夏だ。日本では短い梅雨が終わったあと、40度にもなる暑さが続いているという。朝鮮ではちょうど梅雨の期間で蒸し暑さが際だっている。猫も一日中寝そべっている。家でも事務室でも冷房をかけている。
散歩していると、秋を知らせる無窮花(日本語ではムクゲ・木槿)が一つの木に一杯の花を咲かせているのを見つけた。日陰の場所だからだろう。無窮花(ムグンファ)は朝鮮語名であり、毎日、次から次と咲き続けるので無窮の花という名前があっている。朝鮮に来た頃、初めて見る花で、しかも、鮮やかな花を咲かせ続けるので非常に目立った。朝鮮で愛でられる花だ。夏から秋へと咲き続ける花で、この花を見ると秋の近づきを感じる。朝鮮では8月15日を過ぎると空気がさっと変わる。だから、一ヶ月足らずすぐ秋だ。
今は暑い、暑いと言っているが、秋は目の前だ。季節の移り変わりの速さを感じる。
今年は、動乱の時代の始まりだと言われている。その中で、時代の速いテンポに追いつけないでいることを感じる。時代はたゆみなく進んでいる。それに応じた理論活動を行わなければと自らを戒める思いだ。
ミコとシロ
魚本公博 2022年7月20日

食堂で飼っている猫と犬。今までもしばしば飼っていましたが、あまりなつきませんでした。ところが、今、飼っている猫と犬は、人への警戒心がまったくありません。食堂での食事後に餌を上げる人はもちろん、誰にでもなつくのです。それに二匹ともお互いにじゃれ合って仲がよい。最近の日本のテレビのペット動画では、犬、猫がじゃれ合う場面も見ますが、実際に見たのは初めてです。
この間、雨が続き、アパートの玄関に入り込むようになっていたのですが、先日の夜、ドアの隙間から部屋の中に二匹が入ってきました。猫は堂々と我がもの顔で、犬は尻尾をふってうれしそうに。それがおかしくも可愛くもあって、ソーセージの切れ端をあげました。それから一層、なついて、食堂に行くたびにナデてやると喜びます。
あまり情が移ると、後々困るので、適当な距離感でやっています。
先に2月2日の「ニャンニャンの日」に際して、私が幼少の頃、日本で飼っていた猫のことを書きましたが、猫は、その時のミコと同じ赤猫なのでミコと呼び、犬は、Tちゃんが飼っていて、帰国の際に引き取って飼っていたシロに似た小型の愛玩犬なのでシロと呼んでいます。二匹のじゃれあっている姿、夕だまりに寝そべっているミコ、朝、私を追って、事務所までやってくるシロに思わず笑みが浮かび癒されているこの頃です。
気を緩めずに
若林佐喜子 2022年7月20日
暑中お見舞い申しあげます。
例年より早く、先月末から梅雨に入りました。今年の特徴は、短時間に大量の雨をもたらす豪雨現象。ですので、河川の整備や田畑の水管理などへの具体的な注意と対策がとられ、テレビのニュース時間、特に天気予報では健康管理への注意と農業対策などが詳しく報道されます。稲やとうもろこしの成長期なので、心配するのみですがついつい私も身をのりだして毎日見ています。よど農場は、きゅうり、ねぎ、大根が食べ頃で、青じそもすくすく育ち蒸し暑い日の「冷や奴」の薬味などに重宝しています。
気を緩めずにと言えば、感染症対策、国家防疫体制です。国家非常防疫司令部のリュ・ヨンチョル氏の発表によれば、14日現在、一日の発熱者は全国で500余人、総完治者は99,975%、治療者は1120人。厳格で安心感が伝わってくるヨンチョル氏。その日の強調点は、「強度強く安定した状態だが、全世界的な感染状況のなかで、国家と人民の安全を守るために厳しい防疫秩序をたて、検査、検診を少しの隙間もなくしっかりやりぬかねばならない」と言うことでした。
私たちは、週一度の買い物と若林、赤木さんはギター教室、プール通いをやっていますが、マスクの着用、どの店、どの場所でも体温検診と手の消毒を行います。また、毎日、午前、午後の2回の検温と担当機関への通報をやっています。
本当に、気の抜けない生活ですが、しっかりのりきって行きたいものです。
日本の皆様も、感染防止と熱中症対策、体調管理にくれぐれも留意して下さい。
サボテン
小西隆裕 2022年7月5日
私は、自慢ではないが、生き物を飼ったり、育てたりしたことがない。
78歳を間近にして、一度もない。
私の実家では、犬や鶏を飼っていたが、私自身がそれに責任を持ったことはない。
朝鮮に来てからも、私の部屋に生き物がいたりあったりしたことはない。
花を花瓶にさしたこともない。
そのきっかけは長年使ってきた湯沸かしポットがついに壊れてしまったことだ。
それでポットが置いてあった小テーブルの上が空いてしまった。
それで接待員の女の子が事務所を小植物園のようにしている鉢に目を付けたという訳だ。
それで見た目にもよく、手間もかかりそうもないサボテンに白羽の矢を立て、黒田さんを介して手に入れた。
と、それからいくらも経たず、当の女の子が手の平に乗りそうな小さな丸いサボテンをコンピュータから出る有毒放射線を吸収してくれるからと持ってきてくれた。
週に二度水をやれば、それでOKだということだ。
という訳で、今私は生まれて初めて、自分の部屋で生き物とつき合っている。
週二度の水やりを忘れたことはない。
「ギターの生命は音楽」-先生の教え
若林盛亮 2022年7月5日
6月の末、ギター教室の月謝金支払いのために「先生」に連れられてレジに行った。ちょうどそこに「ピョンヤンの理髪師」アジュモニがいて「先生」に「この生徒さんいかが?」と訊いてきた。「なかなか優秀、ご老人だが手も頭もよく動く」と先生は「生徒」をほめた。私は「いやアジュモニのおかげで頭の格好がいいというだけのことです」と「先生」のお世辞を茶化した。
ギター教室に通い始めて2ヶ月だが、5月はコロナ最大非常防疫体系実施のため1回しか行けず、実質、約1ヶ月の授業を受けたことになる。最近、ようやく指が動き出し、少しきれいな音が出るようになった。
いまの課題はひとつひとつのコード(和音)はなんとかできるがいくつかのコードを流れるようにつづけて演奏できない。特にアルペジオという分散和音を親指・人差し指・中指・薬指を交互に使う奏法は難しい。
ひとつのコードから次ぎに移るときに弦を押さえる左手が気になってどうしても右手で弾く音が中断してしまう。私は正確に弾くためには仕方がないと思って、そういう練習の仕方をやっていた。宿題点検でこれを見た「先生」は「ダメッ」と言った。私は正確に音を出すためには「いまのレベルでは仕方ないでしょう」と抵抗した。すると「マイ・ティーチャー」はこう仰った。
「私たちは音楽をやっているのです。ひとつひとつの“音”や“コード”では音楽はできません」そして続けてこうも言った-「ギター演奏するときは音楽として音が流れるように、その歌曲の調子を口ずさみながら中断なくやることが重要」なのだと。そのためには「失敗しても下手でもかまわない」のだと。
「先生」の言いたいことは、要するにこういうことらしい。
ギターは技術ではない音楽性が生命なのだ、だからミュージシャンの心を持ってギターを弾くことを心がけなさい!
続けて先生はこう言った。
「貴方は75歳だが頭もまだよく動く、これくらいはいくらでも身につける力があります」と。「いやいや・・・」と謙遜を装った私もついその気になっている。「先生」はモチベーションを持たせるのがうまい。
最後にこう付け加えた。
「弦を押さえる左手に気をとられて右手の指の動きをいい加減な我流でやってはいけません。ちゃんと規定通り交互に動かす癖をつけなさい、これは音楽をやるためですよ。」
今日、学んだのは「ギターの生命は音楽」ということだ。技術習得に気を取られてミュージシャンの心をなくしてはいけない、「音楽をやるためにギターを学ぶ、その初心、忘れることなかれ」! これが「先生」の言いたかったことなのだろう。
久しぶりの水泳
赤木志郎 2022年7月5日
久しぶりにプールに行ってみた。海に行ったのはもう数年前だ。コロナ禍でなにかと行動が制約され、身体を動かす機会がすくない。それで運動不足を解消するために前からプールと考えていた。とくに水中歩行が良いと訪朝団のOさんから勧められていた。行ったのは外人クラブのプールだ。
人はあまりいないはずだと思っていたら、20人ほどいた。外人ではなくほとんど朝鮮の人だった(私は外人だが)。しかし、皆、20代、30代ぐらいだ。私だけが75歳の老人だ。
海のすぐ近くで育った私は水泳が好きだ。喜んで飛び込んで見たものの、昔のようには手足が動かない。平泳ぎで懸命に手を掻くが前に進まず、だんだん沈んでしまう。深さは170センチくらい。長さ30m以上もあるこのプールは外人用なのか深い。立つこともできない。あわてて横の取っ手に手をかけた。しかし、上る力がない。梯子のあるところまで移動して上った。
縦長のプールの他に子供用のプールが二つある。一つは温水で噴射バブルもついてある。背中や腰に水を叩きつけることができる。ここは立つこともでき、水中ウオーキングもできる。それで、ほとんどこの温水プールに入っていた。
水中歩行運動は上半身くらい水につからないのが良いのだが、子供用プールでも胸まで水がつかる。歩くのには股関節の痛みをまったく感じないが、進むのが大変だ。手足の筋肉がひどく弱っていることを実感した。それを何回かやって終え、サウナに入り、身体を洗って出てきた。まるで全身の垢をとったようだった。老人がいないせいか、係りの人たちは非常に親切にしてくれる。最後に靴を履くのにも椅子に座っていた他の人をどかせ、私が楽に靴をはけるようにしてくれた。
財布が許せば、プールの二楷にある喫茶店にも行きたかったが、運動不足の解消という目的をひとまず達成したので帰途についた。その日は10時間くらいぐっすり寝込んだ。翌日、太股や腕が痛く、全身運動になったのを感じる。来週も行こう! 老人よ身体を鍛えておけ、その日のために。
国を挙げてのゼロコロナ政策
小西隆裕 2022年6月20日
-300x300.jpg) 国家防疫司令部(朝鮮中央テレビより)
国家防疫司令部(朝鮮中央テレビより)
 16日の状況
16日の状況
朝鮮のテレビで毎日報道されるコロナ感染状況を見ていると、日毎の全国新規発熱者数が急速に減少し、6月18日現在、1万人台になっている。一頃、40数万人を超えた頃から見ると著しい改善振りだ。死者は、このところ連日、ゼロだ。
私の周りの人たちを見ても、高熱で苦しかったという人たちも、隔離から戻ってきた後は、若干の後遺症がある人も含め、皆元気で仕事をしている。
一方、検温は、徹底している。私たちに対しても、PCR検査と陰性判明の後にも、日に二度、時間を決めて、検温とその結果の通知は今も続いている。幸い、発熱ゼロだ。
もちろん、ピョンヤン市内に出かける時の二重マスク、市内の建物や何かの催しに入る毎の検温、手の消毒は、いつものように完全に励行されている。
国を挙げてのゼロコロナ政策、このまま行けば、近い将来、完全収束の日を迎えられるのではないだろうか。
6月の意気消沈、あと一歩及ばずのリヴァプール
若林盛亮 2022年6月20日
6月の私はけっこう落ち込んでいる、というか意気が上がらない。
私の愛してやまないサッカー英プレミア・リーグの古豪、リヴァプールがリーグ優勝と欧州チャンピオンズ・リーグ(UEFA-CL)優勝をあと一歩というところですべて逃したから。
リーグ優勝は首位のマンチェスター・シティ(マンC)とわずか「勝ち点1」差でリーグ最終節まで首位決定がもつれ込む展開。その最終節で奇跡が起こる気配の展開に。マンCが今なお「リヴァプールの永遠のキャプテン」と称されるジェラードが監督として指揮するアストンビラに0:2で負けていて、このまま行けば他会場のリヴァプールが勝って逆転優勝、それも「永遠のキャプテンの功労による」というドラマとなったはず、ところが後半に入ってたったの5分間でマンCが3得点で逆転勝利。優勝をほぼ確信しかけたリヴァプール・サポーターは声を失った。
またUEFA-CLはリヴァプールが一方的に攻勢を仕掛ける中、相手のレアル・マドリッドは一度訪れたカウンター攻撃のチャンスを決め、片やリヴァプールの猛攻はことごとく2m近いレアルGK、クルトワの神がかったファインセーブに会いこれまた1:0の惜敗。放ったシュート数でいえばリヴァプールが23本(枠内9本)で圧倒、レアルはわずか3本しかも枠内シュートわずか1本、それを得点につなげたのだからこれも神がかっている。合理的、科学的な眼からすればレアルに勝ち目はない、それでもリヴァプールは試合に負けた。これで14度目のUEFA-CL優勝というレアルの歴史、勝利の伝統、そのDNAがチーム個々人に浸透、科学では読めない「神がかった」勝利をものにしたのだと言われている。サッカーはやはり人間がするもの、そういうものかもしれないが、リヴァプール「命」の私には受け入れがたい結果だ。
結局、世界最高峰と言われる英プレミアリーグ、UEFA-CL共にチャンピオンにあと一歩が及ばなかった。
サポーターという立場から離れて客観的に見ても今季のリヴァプールは世界最強、最高のチームだった。かつてドイツの地で香川を一流選手に育てたクロップ監督が7年をかけ築き上げた「芸術作品」とも言えるのが今季のチームだった。
前線、中盤、最終ラインとどこにも隙のない百戦百勝の戦力、そして洗練完成された戦術はチームに浸透、また国内と欧州で4つのカップ戦を闘い今季は63試合をこなすというハードシュケジュールで主力を休ませても戦力ダウンしない陣容、そこにはプレミア・リーグ先発こそ希だったが他の英国内カップ戦で貴重なゴールを上げ続けた南野君の活躍もあった。
だからこの「クロップの芸術作品」、最高最強のこのチームに世界最高峰の優勝カップ2つを掲げてほしかった。来季はもうこの顔ぶれは少し変わるだろう。だからとても無念残念だ。
「サッカー及びでない」人には「何をぐだぐだ言うてるんや」となるのだろうが、「これほどのチームが何で??」という無常感、無念感、とても気持ちのコントロールが難しい。
でも地元のサポーター、リヴァプールの市民達は国内の他の二つのカップ戦を制した「おらが街のチーム」を熱烈に歓迎、歓呼した。それはこのチームが世界最高、最強で「クロップの芸術作品」であることを知っているからだろう。ここまでの苦難の道のりを知るからこそ、このチームへの地元の人々の心からの賛辞なのだろう。
私も気持ちを早く入れ替えて来季に備えよう。たかがサッカー、されどサッカーなのであります。
ロシア音楽
赤木志郎 2022年6月20日
私は古いと思われるかもしれないが、ロシア音楽が好きな方だ。小学生の頃、当時流行の歌声運動、歌声喫茶の雰囲気のなかで担任の先生から教わったものだ。灯火、カチューシャ、カカリンカ、ヴォルガの舟歌、ステンカラージン、走れトロイカ、アムール河、仕事の歌などロシア民謡や革命歌だ。当時、フォークダンスも流行っていて、高校生の時レコードと携帯蓄音機をもって近くの山でその集まりも催していた。
ところで、朝鮮でもロシア音楽をTVで時々放映する。DVDで販売しているのも少なくない。そこで流される音楽の主流は、ソ独戦争を歌った唄だ。かつて私が親しんだロシア民謡はそれほど多くない。
戦争から77年も経つが、朝鮮のTVで放映されるロシア音楽公演ではロシアの観客たちが目に涙をためながら口ずさんでいる。それほど深い傷跡を残した戦争だったのだ。ソ独戦争を題材にした唄では、「勝利の5月」を歌ったものもあるが、犠牲になった無名の英雄たちへの追憶が圧倒的だ。なかには数百名の遺影を掲げた場面もあった。2千万人が犠牲になったというから、十人に一人が亡くなったことになる。その厳しい戦いで勝利し、かつ復興をとげたのがロシアだ。
ところで、ロシアがウクラナイで軍事作戦を行っているが、プーチン大統領は「これは欧米との戦いだ」と位置づけている。NATOの東方拡大によりロシアが欧米覇権の脅威にさらされていると感じ、ウクライナに中立化をもとめて軍事行動を起こした。それで、「Z」マークを掲げているように、それが愛国の戦いであることを強調している。かつての侵略と戦う祖国防衛戦争ではないが、今は、「欧米民主主義」を掲げた欧米の覇権策動に反対し祖国を守る戦いという意味で共通点をもっている。
だから現在の欧米諸国による経済制裁に屈することはないと思う。そもそも制裁で人間が屈すると考えるのは、人間にたいする冒涜だ。撤退したマグドナルドの店の代わりに、自分たちのハンバーガーの店を開いたように、欧米とは異なるロシア風の経済をかならず建設すると思う。
ソ独戦争で犠牲になった無数の英雄たちを追憶する数多くの歌を聴きながら、そう考えた。
高専についての思い出
魚本公博 2022年6月20日
朝日新聞のGLOBE版に高専の記事がありました。
高等専門学校のことで、中学卒業後の5年間の一貫教育で技術者を養成する日本独特のシステムが世界の注目を浴びているのだとか。すでにタイやモンゴル、ベトナムに、そのシステムが輸出され、エジプトなどアフリカ諸国でも誘致の声が高まるなど、今やKOSENは、SUSHI(すし)、KOBAN(交番)に続く国際語なのだそうです。
この記事を見ながら、高校進学の頃に大分高専のことが話題になったことを思い出しました。その頃、大分は、大分市を流れる大野川、大分川河口付近を埋め立てた大分臨海工業地帯を建設していた頃で、それに合わせて大量の技術者が必要になるということで大分にも高専ができ、ちょうど我々の学年が中学を卒業し高校入試を控えた1963年に最初の入試が行われたわけです。
当時も成績が良くても家庭の事情で大学進学はあきらめざるを得ないという「親ガチャ」がありましたが、大学に行けなくても大学に匹敵する技術を学べ、大卒と同水準の資格を得ることができるというので話題になったのです。私の中学からも、そうした生徒が20名近く受験していました。
私は大分の進学校に進み列車通学していたので、同じく列車通学する中学で同窓だった高専生と乗り合わせることがあり、高専では先生は教授であり、クラブ活動も盛んで、学び甲斐があるなどという話を聞いたこともありました。
今、工業高専は全国51校に5万人の学生が学んでいるとか。かつての「モノ作り大国」の栄光も消え失せてしまった日本ですが、「モノ作り」は経済の基礎です。「新しい資本主義」では人材育成に力を入れるとなっていますが、どうも、その人材は、アイデアとか流通、投資分野とかに片寄っているように見えます。日本経済の再生には、やはり「モノ作り」人材育成こそが大事です。政府は高専など「モノ作り」人材育成に力を入れるべきですし、彼らがもっと夢をもてるような政策を打ち出して欲しいものです。
朝鮮のコロナ対策
小西隆裕 2022年6月5日
とうとうきた。コロナ禍の発生により、朝鮮全土に最大国家非常防疫体系が布告されたと言う。
われわれも「村」から一歩も出てはならないことになった。
しかも、われわれの「村」(管理所)の所長さんもピョンヤン市内に行っていて、感染したらしい。高熱で伏せており、所長さんと接触した料理士や接待員も同様だと言う。
それで、われわれの行動範囲も、アパートと事務所の間だけということになった。
さらに朝と昼、一日二回の検温とその一回毎の通報が義務づけられた。
食事も完全自炊。そのための食糧供給も食堂からなされた。
となると、われわれも心許ない。この間、買い物のため、全員、市内に出ている。
それで、PCR検査を頼んだ。検査は当日。そして夕刻には結果判明。全員陰性だった。何もかもスピーディだ。
それから2週間。長期戦を覚悟していたところ、突然の非常防疫体系解除の報せ。その日の昼12時をもって、ピョンヤン市内にも出られるという。
ただし行動範囲は、市内のみ。出る時は、マスク二枚着用のこと。手洗い、うがいの厳守励行。人々が集まって何かやること、だからバレーも禁止。
久し振りのピョンヤンは、やはりいつもより閑散としていた。商店や市場も、人も物もいつもより少な目。
馴染みの売り子のおばさんも熱が出て大変だったと言う。女性と老人、子どもの症状が重かったとか。
しかし、この収束速度は凄い。
普通、こうした感染症の大爆発での原則は、検査、隔離、治療の励行だと言われるが、400万近い有熱者大爆発に対応する検査薬も、薬も、施設も不足している。
そこで採られた対策が、検温と自宅隔離、解熱剤およびビタミン剤などの給付と有熱者家族への食糧など生活用品の給付、そして都市など必要な各単位の封鎖だったようだ。
そのために人民班と病院、医学生、薬局、薬剤師、党と政府機関、軍隊までが発動、動員された。
その一方、生産など通常の業務で必要な仕事はすべて、いつも以上の強度と気勢で遂行されている。
これは、一言で言って、一つの共同体の組織戦だ。最高責任者である金正恩総書記を陣頭とする共同体一丸となっての整然としたコロナ対策がこの迅速なコロナ禍の収束を生み出しているのだと思われる。
もちろん、コロナ禍が完全に収束したという宣言はまだ出されていない。しかし、われわれの周りの人々の落ち着いた笑顔は、この禍の近い将来での完全収束を確信させてくれる。
音楽教室に鳴り響いた「友よ」のギター
若林盛亮 2022年6月5日
朝鮮のコロナ事態が好転してギター教室も再開、散髪もできなかったのでまずは「ピョンヤンの理髪師」のお店に行って、音楽教室に顔を出した。
理髪師アジュモニの家庭は息子も夫も発熱はなく無事だったとか、私のギターケースを見て「やってはるんですね」とニコッと笑った。一人前になったらギター教師を紹介してくれたこの恩人にも1曲プレゼントしなきゃならんかな・・・
さてほぼ1ヶ月ぶりとなった音楽教室、授業開始前に「この間、時間があったからこんなもんをやってみました」と岡林信康の「友よ」を我流で弾き語りしてみた。宿題のコード練習だけでは単調なので日本の古い教本「趣味のギターレッスン」にあった「友よ」の楽譜コードを参考に弾き語りを練習したので少し先生のアドバイスもほしかった。
「エエ曲ですねえ」と先生は言って楽譜を見せてくれというので日本の教本を見せた。すると先生はたちまち「友よ」を演奏しだした、それは見事なものだった。どんな歌かと聞くので、若い頃の闘いの歌だと歌詞を説明した。先生はとても気に入ったようで、「今日はこれをやってみましょう」と言った。
この人はなにか芸術家肌特有の熱を持っている、授業そっちのけ、つまりちょっと気まぐれなところもある。
「もう一度やってみなさい」と言うので和音をガシャガシャかき鳴らすだけの我流の奏法でやった、先生は私に従って演奏しだしたが、けっこうグーな「友よ」のギター・ハーモニーが教室に響き渡った。われ知らず乗った、それはバンド時代を思わせるノリだった。
終わって先生は言った。「そんなやり方ではこの歌がかわいそう」、自分のやった奏法を教えましょうと。エ~ッ! それって玄人のやる奏法でしょ!
でその日は、アルペジオ奏法を教わった。和音を数個の音に分けて弾く奏法で3本の指を使う要領を習った。やっとギター弦を押さえる左手が動くようになったとこなのに、右手の指運びまでやることになった。人差し指、中指、くすり指を交互に連続的に動かす・・・口には出さなかったが「んなあ~、ムチャや」、とても「レッスン2」でやるようなことじゃない。
結局、ほぼ1時間はその練習だった。要領がイマイチわからないし指が思うように動いてくれない、「ノー、この指」と先生は私の指をいちいち正す、「そんなん言われてもすぐ動くわけないやんか」と言いたいがこの先生に口応えは無駄。
先生は「友よ」の楽譜のコード進行を見て「数学に公式があるように音楽にも公式があります」と説明。D-G-Aというコード進行は「D:主和音(Tonic)-G:次属和音(Subdominante)-A:属和音(Dominante)」という公式を教本に書いてくれた。そこに今日の日付まで書き込んだ、「この日に学んだことを記憶に残すためにね」だとか。
芸術家というのは少し分けのわからないところもある、でも言うことにはちゃんと「理」が通っている。
終わって「みっちりしぼられた」がその日の感想だ。でも帰ってアルペジオをやってみたらそのうちなんとか法則通りに指が動き出した。たしかに和音がきれいな分散音で響く。「理」に従ってやってると思うと、なんだか確信も湧いてくる。
あの音楽教師、少しわからないところもあるけど興味深い人物ではある。いつか二人でギターのデユオ、コラボレーションをやってみたいな、とか空想、妄想も広がっていく。
自力更生、考えさせられました
魚本公博 2022年6月5日
 夜明けの「村」
夜明けの「村」
この間、コロナ対策のため、日本人村から外出できませんでしたが、29日に外出禁止が解除されました。それで6月1日に、久しぶりに市内に買い物に出かけました。一ヶ月ぶりの外出で驚いたのは、周辺の農場では、田植えがほとんど終わっていたこと。トウモロコシも随分大きく育っていました。
外出禁止で困ったのが「よど農園」で植える苗のこと。いつもなら、トマト、ナス、キウリ、唐辛子などは、市場で苗を購入していたのですが、これが入手できなくなりました。そこで、自力更生で苗をと思い立ちアパートのベランダで苗作りしてきました。外出禁止・接触禁止の解除で管理所の人たちからも幾分、分けて貰えそうで、自作の苗との併用で何とかなりそうです。
今、日本では、物価高騰、特に食料品の高騰が起きています。最近の気候変動やコロナ禍での輸送停滞による供給不安から世界的な食料価格上昇が起きていたところをウクライナ危機で、それがさらに助長されているわけです。
これまで「カネを出せば買える。それが一番、安上がりで、効率的」とされてきましたが、それが通じなくなっています。これからは逆に「少々値がはっても自力でやるのが一番」となっていくのではないでしょうか。エネルギーでも太陽光や風力、地熱による自力解決が今まで以上に注目されていくと思います。
対外依存体質の日本ですが、食糧高騰を契機に食の自力更正、そこから全ての分野で自力更生への志向が強まることを期待しています。
最近、もっとも呆れたこと
小西隆裕 2022年5月20日
最近、生活していて、もっとも呆れたのは、ラジオでウクライナ戦争関連のニュースを聞いていて、マリウポリのアゾフスターリ製鉄所の地下に立て籠もっているアゾフ大隊副司令官がインターネットで米国テスラ自動車CEOイーローン・マスクに助命嘆願したとの報道を聴いた時だ。
これまでも、製鉄所の地下に1000名にのぼる市民がいるとの報道を聴いて、市民を「人間の盾」にするこの悪名高いネオナチ部隊の卑劣さを思っていたが、市民を解放せざるを得なくなった後に、やることは、全員玉砕か白旗を立てての投降かどっちかしかないと思っていたところに、「貴方しか私たちを救える人はいません」というこの助命嘆願。
その相手が自分たちの大統領、ゼレンスキーでなく、イーロン・マスクだったとは!誰がウクライナの最高責任者であるかを自ら告白、露呈するこの嘆願には呆れ果てざるを得なかった。
75歳の手習い-ギターを始めたわたし
若林盛亮 2022年5月20日
「最初期のメンバーでミュージシャンとして通用するのは水谷さんだけ」
「僕らはミュージシャンになりたかった訳ではなくて、バンドをやりたかった」
これは京都新聞(5/14)に掲載された「裸のラリーズ」結成期の盟友、いま「耽美派写真家・中村?きょう」を名乗る中村武志の言葉。私も「日本の音楽シーンを革命する」というバンドの志に共鳴したけれど「ギター小僧」になる気はなかった。だから担当のベースギターも課題曲のベースパートだけ覚えて「バンバッバババッ」とやっただけ、「元ロッカー」と言われるのはいささか気恥ずかしい。
そんな私が古希を過ぎて心機一転、前にも書いた「勧誘されたギター教室」に5月から通うことにした。「ギター爺さん」をやってみようかなと思ったからだ。
初日、音楽教室の先生は私をテストした。
ピアノでメロディラインを演奏して「いまのメロディを音符で暗唱しなさい」、あるいは「パパパンパパッパパッ・・・」などと手拍子で叩いたリズムを「いまのをそっくり真似してください」といった音感とリズム感のテストから入った。少しは自信はあったが爺さんになって認知力の衰えは隠せない。ちょっと焦ったが先生からは何の評価もなし。「音楽力」はだいたい把握できたということだろう。
レッスン-1は、基礎として初歩的な和音コードとメロディラインの奏法を。音符もC、D、A、F・・・という風に音楽記号を覚えなさい、と。「弾き語りができる程度でええんですけど」と私が言うと「いや、音楽理論の基礎、ギターの奏法、姿勢の基礎は最初からきっちりやること」「いいかげんにやるよりその方がよっぽど早道なのです」と先生は容赦がない。
国立音大出身、ピアノから管楽器、弦楽器、ドラムとなんでもできる先生は言うことに揺るぎがない。素人だから、老人だからと手加減はしませんよ、ということらしい。
もしかしたらこの人、とてもいい先生なのかもしれない、そんな予感がする。これはワクワクものだ。
突然のオミクロン株事態で「ギター教室」はレッスン1だけで当面おあずけ状態に・・・、「基礎が大事ですよ」の先生の言葉を胸に練習課題はしっかりやっておこう。
訪朝団再開の折にはお披露目しますのでみなさんお楽しみに! と自分にプレッシャーかけときます。
5月半ばに
赤木志郎 2022年5月20日
5月下旬になったにもかかわらず、それほど気温があがらず朝夕は寒いくらいだ。とても風薫る季節とはいえない。しかし、朝、事務所に出るとウグイスが鳴いて迎えてくれる。子のウグイスなのか「ホーホケキョ」の「ケキョ」の部分を繰り返している。もちろん、ホーホケキョと鳴くウグイスもいる。
家の窓際に置いてあった日日草やアロエの植木鉢を、管理員が土を入れ替え、形もきれいに整えてくれた。そのお陰で日日草は多くの花を咲かせ、目を楽しませてくれる。それまでは、滋養分の不足で花があまり咲かなかったのだった。緑の葉が茂るだけでも良いと思い、花が咲かないことに気にかけなかったが、やはり花が咲く方が良い。
そんなのどかな日々に新型コロナ流行の報道が降って湧いた。消毒と検査、隔離と治療が大々的に行われはじめた。世界的な流行が3年目を迎えても感染者ゼロで、安心していただけに私も驚いた。なんとか抑え込むことができるよう願っている。
沖縄闘争、今こそ
魚本公博 2022年5月20日
この5月15日は、沖縄の「本土復帰50周年」でした。東京と沖縄に分かれての式典でしたが、本土のそれが自民党政権(佐藤内閣)による復帰実現を祝うものだったのに対し沖縄での式典は、「素直に復帰を喜べない」というものでした。その原因は、一言で言えば、「基地問題」です。本土復帰は、平和憲法への復帰であり、その下では米軍基地もなくなるのではないかという期待。それが裏切られた失望が如何に大きなものだったか。
そればかりではありません。今では台湾有事の際には沖縄が最前線になるなどと言われ、反撃能力(敵基地攻撃能力)保持や核共同所有の基地にまでされようとしています。
世論調査で「基地の負担が重すぎる」と答えた人が沖縄、本土共に80%を越えています。沖縄の人は、基地集中の苦しみを本土の人も分かって欲しいと言いますが、それを分かろうとする本土の人も増えているようです。ウクライナ事態を契機に、軍事力強化や改憲の声が高まる中、沖縄の現状が他人事ではなくなっているからだと思います。
時代の流れでしょうか。沖縄の戦い、勝たなければなりません。勝たなければ反動にも傾きます。今、日本はそういう岐路にあると思います。
当日、「紙の爆弾」を発行する鹿砦社代表の松岡さんから「デジタル鹿砦社通信」が送られてきました。そこには、71年からの沖縄返還協定調印→批准阻止闘争は60年代後半の戦いに匹敵するほどの盛り上がりを見せたとしながらも、「私たちヤマトンチュは当時、沖縄返還の意味を理解するのに十分ではなく、ともかく『返還はよかった』という意識はなかったか」と自問の言葉もありました。その時には朝鮮に居た私たちですが、「本土復帰50周年」に際し、沖縄の人々と心を一つにして、戦いを継続しなければならない、との思いを強くした今年の5・15でした。
パソコンの前に置かれたサボテン
若林佐喜子 2022年5月20日

すっかり深緑の季節になりました。
昨年の12月、日本人村の代表団を迎える宿所内に創られたミニ植物園。その後、植木鉢のカクタス、ゴムの木、麒麟花などはすくすく成長し、この4月の春に、事務所の各人の部屋にサボテンの植木鉢がプレゼントされました。植物は健康によく、特にサボテン類は眼の疲労回復に効果ありと、孫娘のような建物管理の彼女がせっせと手入れをしてくれたものです。
まず、この2月に根付いた植木鉢が宿所から事務所の衛星室(応接室)に移動。彼女、いわく、「水やりも科学性が必要、自分がやるから」と、私に水やり禁止令が出ました(涙)。傍らでみていると、米のとぎ汁を大きめのマグカップに1杯、週2回ほど。確かにケイランは生き生きと育ち花をつけるまでに見事に成長、サボテン類も青々と。植木鉢は窓際のみならずテーブルの上にも飾られ、さらに、廊下の鏡の前には少し大きめの鉢植えが置かれ、さながら事務所、応接室が植物園になった雰囲気です。
各人の部屋のパソコン前に置かれた大小のサボテン。今日もみなの眼の保養と疲労回復に大いに貢献してくれています。植物は心身の癒しですね。
さて、朝鮮は、5月13日からコロナ感染者発生のため特別防疫非常体制がとられています。テレビで毎日、国家非常防疫司令部による新規発熱者数や対応での留意点などが発表されています。一日も早く平穏な日々に戻ることを心から願い、私たちもしっかり防疫体制を厳守して、乗り切っていきたいと思います。
朝鮮の人物紹介番組が面白い
小西隆裕 2022年5月5日
朝鮮のテレビを観ていて、最近面白いのは、各階各層人物紹介番組だ。
実に多様な人々が出てくる。多収穫農民もいれば、独特な教授方法で注目されている学校の先生もいる。技術革新を組織した水産企業所の責任者もいれば、創意創案のユニークな労働者もいる。著名な大学教授、体操選手もいれば、山林保護の名もなき英雄もいる。
とにかく各階各層、有名無名、様々な功労者がその周りの人々とともに出てきて、インタビューに答え、その仕事と生活を画像で伝え、その思いと信条、工夫と苦闘の数々を教えてくれる。
長さは様々だ。15分から30分、全編に流れる解説と音楽、それがうまく調和して観る者を感動させてくれる。
それを、最後に字幕で出てくる作家、編集者、演出、撮影、録音、解説、等々それぞれの担当者が一つのチームをつくって、ドキュメンタリー作品として完成していっている。
私自身、そこから朝鮮の社会主義建設について、その一端を学ばせてもらっている。
「試合開始7分」の拍手と“You’ll never walk alone”大合唱
若林盛亮 2022年5月5日
再三、この欄で語ったように私はサッカー英プレミア・リーグ所属のリヴァプールFCサポーターだ。
先月19日にリヴァプールのホーム・スタジアム、アンフィールドで行われた対マンチェスター・ユナイテッド(マンU)戦で奇妙な光景が展開された。試合開始7分にホームのリヴァプール・サポーターから1分間の拍手とチームのアンセム(応援歌)“You’ll never walk alone”(おまえは独りじゃない)大合唱が起きたのだ。これがこの試合に欠場したライバルチームのエース・ストライカーに対して行われたものだということで一躍、世界の注視を浴びた。
実はマンUのエース、メッシと並び世界的名手であるクリスチャン・ロナウドが夫人に男女の双子が誕生したが男児が死亡したことでこの試合を欠場していた。これを知ったアンフィールドのリヴァプール・サポーターがロナウドの背番号「7」にちなんで試合開始7分に1分間の拍手と“You’ll never walk alone”大合唱でライバルチームのエースに同情と励ましを送ったのだった。
これに感激したC.ロナウドは「ひとつの世界…ひとつのスポーツ…ひとつのグローバルファミリー…ありがとう、アンフィールド」と自身の公式インスタグラムに綴った。
リヴァプールとマンUとの試合は「ナショナル・ダービーマッチ」とも言われる全英国的関心を集める注目のカード、互いのクラブの名誉と意地を賭けた激しい競技になるが、今回、リヴァプール・サポーターの見せたライバルチーム・エースへの心からの「儀式」は特別な感慨を呼び起こす。
リヴァプールという英北西部港町の労働者階級のサッカー・クラブから発祥のこのチームの歴史には苦難、困難を共にしてきた人間達の歴史がある。
1980年代はこの港町が寂れ多くの人が職を失った。ライバルチームのサポーターたちはリヴァプール・ファンが“You’ll never walk alone”を歌い出すと“You’ll never get a job”(おまえらには仕事がない)のヤジで応えたという。
このサッカークラブには「ヒールズボロの悲劇」の歴史もある。競技場に押し寄せたファンでスタンドのフェンスが壊れて多くの人が圧死、犠牲になったが、警察側調査で事故の原因はファンの乱暴な行為によるものと烙印された。しかしリヴァプール・サポーター達の長期に渡る名誉回復のための闘争によって競技場の管理責任のミスによるものとの判定を得て、ようやく犠牲になったファンたちの名誉が回復された。アンフィールド競技場にはその記念碑が建てられ、毎年その悲劇の日には試合前に1分間の黙祷が捧げられる。
このように悲しみも喜びもチームとサポーターが一体となって乗り越え共にしてきた歴史が、このクラブに特有の人間性をもたらしていると私は思う。それがライバルチームのエースの不幸に「試合開始7分」の拍手と“You’ll never walk alone”大合唱で対するという態度に自然に出たのだと思う。
私はこのリヴァプールというクラブがますます好きになった。今年は史上、誰も未達成の4冠制覇も不可能ではない。私は“You’ll never walk alone”を歌い続ける!
有元幹明さんの思い出
赤木志郎 2022年5月5日
4月23日に「有元幹明さんを偲ぶ会」が大阪にて催された。200名もの大勢の人々が参席されたそうだ。長年、大阪における労働運動、平和運動、日朝友好運動を担ってこられた人だけあって、その労苦と人柄を多くの人が偲んだと思う
私が有元さんを知ったのは、92年頃の社会党の日朝友好の船で数百人の訪朝団が来られ、大阪の港地区を中心とする労組活動家たちと会った時だった。話の中で、有元さんが自分たちを代表する府会議員だということを聞いたときだった。そんな人がいるんだとその名前が刻み込まれた。
それから「浪速の翼」訪朝団を率いたりしてたびたび朝鮮に来られた。同じ大阪の労働運動の津嶋茂夫さんと一緒に市内事務所に来られたこともあった。また、浪速の翼訪朝団の方と会うときに話をする機会があった。私自身、それほど多く、また深く話を交わしたことはなくわずかな思い出しかないが、印象的なものをいくつか。
その一つは、事務所に来られ帰国を前にした子供たちや女性らを前にして「マイ・ウェイ」を歌いあげたことだった。自分の道を行く、その歌は有元さん自身の信念の歌であり、また私たちへの励ましの歌だったと思う。高らかに唄い上げたその歌声を今でも忘れることができない。
二つ目は、2012年だと思うが、他の訪朝団と高麗ホテルで食事しているとき、近くに有元さんらが居られて、食事後、話を交わすことができた。そのとき、「平壌宣言10周年を迎えるのに、日朝正常化がまったくすすんでいない」と嘆息されていた。日朝関係が極度に悪化していく時期であり、その中で日朝友好運動を担われて苦労されたと思う。
三つ目は、浪速の翼訪朝団の団長として来られた時だった。団員一人一人を紹介し懇談が終わって別れる時、私に「(大阪で開かれた」金正日国防委員長追悼式に金子さんが子供たちを連れて来ていた」と労るように話してくれたことだった。緊迫していた当時、追悼式に訪れた帰国した女性、子供たちの姿が目に浮かぶようだった。
このような断片的なエピソードのなかでも、大阪の日朝友好運動を担われた責任感と苦渋、人を思いやる人情を深く感じさせる。今になって後悔することは、有元さん自身の話をほとんど聞いていなかったことだ。いつも自分のことを話すのではなく、人の話を受け止めておられたと思う。偲ぶ会に参加できていたら、有元さんの生涯について少しは知ることができただろう。そのことが残念でならない。きっと天国にて私たちの闘いを今でも見守っておられると思う。ありがとうございました。合掌。
就寝前の読書
魚本公博 2022年5月5日
就寝時にはベッドで仰向けになって本を読みます。そのうち眠くなってポトンと本が落ちて、もう寝ようと睡眠に入るのが最高に気持ちいいです。ところがコロナ禍で外国からの郵便物は受け付けていないので古い本しかありません。それで過去見た本を読み返したりしてきましたが、それも底をついてしまいました。それで今は19年まで送られてきていた文藝春秋や中央公論といった雑誌を読み返しています。
これが中々面白い。この間、16年から19年までの文藝春秋の芥川賞の受賞作を見ました。今は年2回の発表でダブル受賞もあるので全部で10以上になりますか。「何とまあ感覚的な」という印象でしたが、これも時代の趨勢なのでしょうね。
そういう中で、文芸春秋に佐々木朗希投手のことが出ていました。テーマは「潰さない」ということで、高校時代の甲子園出場をかけた県大会決勝戦で大船渡高校の國保監督が登板させなかったことについて、「潰さないで大事に育てる」英断と評した文章でした。そこでは高校野球では、そういう監督は少ないとあり、高校野球界として潰さないことを真剣に考えるべきであり、「春の選抜」もなくすべきだという意見なども紹介していました。
佐々木選手は、今年4月、28年ぶり、20歳という最年少で「完全試合」を達成し、次の登板でも8回までパーフェクト、あわや、世界でも例のない連続「完全試合」かというところで井口監督が交代させたのも、「潰さない」ための英断だと評価する声が高かったです。
数年前の雑誌記事ですが今に通じるものも多く、結構、面白い就寝前の読書です。
チョンソ君の来訪
森順子 2022年5月5日
 お見事!
お見事!
 美味しいかな?
美味しいかな?
明日から5月になるというのに、この一週間は、なんて寒いんでしょう。とくに朝方は冷えているので、体調維持とカゼに気をつけるこの頃です。
それでも、やっぱり春です。今年もチョンソ(エゾリス)が、やってきました。3階の我が家にまで上ってきて、いつも窓のガラスに顔をくっつけて、中を覗いています。目が合ったら一瞬、固まってしまったチョンソ君。それから、リンゴの皮やヘタを置いたら、3日に一回くらい、朝、7時ごろ訪ねて来るので、こちらも「おはよう」のあいさつをして、一日がはじまるといった感じです。ところが、いつだったか、チョンソ君ではなく、鳥(名前は?)が来て、リンゴの皮を放り投げて地面で食べ始めるのを見て、チョンソ君より一枚上手な相手がいたなあ、と感心したのですが、その後は、チョンソ君が、いつもより早く来るようになったり、交互に来たりと、奪い合いも喧嘩もせず互いにうまくいっている感じです。
こんな光景が見られるのだから、春は、やっぱり一番いい季節。体も心もほぐれる毎日を感じられるよい季節です。今は、世界の報道を見ても聞いても、気持ちは重くなり胸が痛いことばかり。日常のちょっとしたことでも、心をほぐしてくれることがあるのは、人間生活で大切なことだと思うので、チョンソ君の来訪にも感謝したいです。
出現した新市街
小西隆裕 2022年4月20日

街の風景-300x149.jpg)


4月15日、キム・イルソン主席の生誕110周年の記念の日、皆でバスに乗って、ピョンヤンに食事に行った。
日和もよく、市内はそぞろ歩く人々がかもす慶祝の明るい雰囲気が漂っているように見えた。
今日のお目当ては、普通江畔につくられた800世帯新市街の車内からの見物だ。
つい1年前には、柳の大木でこんもりと覆われていた丘が様々な形の階段式住宅群に一変していた。
外からはうかがい知れないが、内部はこれまでの住宅とは次元が違う画期的なものだ。二日前、竣工式のテレビで家の中を観て驚いたが、この超高級住宅に住めるのはこれまでの功労者たちだという。それも党と政府の幹部は一人もいない。私たちの村の修理にいつも来てくれる労働者の人も住めるようになったようだ。
食事の後、今度は、もう一つこの1年でできた一万世帯新市街地に行ってみた。
バスから降りて、散歩をしながら観たが、まず降りたところにそびえ立つ80階建てアパートのどでかさに圧倒され、次にアスファルト・メインストリートの両側に立ち並ぶ、一、二階に商店や食堂など各種施設が入った、様々な高さと形、色のアパート群、そしてその通りを行き交う人々のにぎわいに心が和んだ。家族連れなど、そぞろ歩く人々の顔が4・15慶祝の気持ちとともに新居を得た喜びに明るく爽やかだったのは、私の気のせいではなかったと思う。
「朝鮮の新しいミサイル発射!?」の太陽節
若林盛亮 2022年4月20日
4月15日は朝鮮では太陽節、金日成主席の生誕日、今年は生誕110周年ということで「民族最大の慶祝日」として祝われている。
この日、私たちはみなで市内に外食に出かけた。市内の目抜き通りは花の植木いっぱいの装飾、「花のプロムナード」、着飾った市民の家族連れで街はにぎわっていた。
私は案内のミョンチョルさんに「昨日の夜、閲兵式やらなかったんですか?」と訊いた。日本の報道では太陽節には軍事パレードをやる、その兆候が衛星写真でも見えるとあったが、朝鮮のニュースにもなかったし市内の様子はどうもやった気配がないからだ。
返ってきた答えは「新しいミサイル発射をやりましたよ」!?
「エーッ、ミサイルまた発射ですかあ」と驚く私にミョンチョルさんは言った。
「TV報道でもあったでしょ、普通江地区階段式住宅の竣工式。それが朝鮮の新しいミサイルですよ」。
「はあ??」の私にミョンチョルさんは言った、「あのTV報道を見て涙が止まらなかった」と。
この普通江地区、元は金日成主席の私邸のあった丘陵地帯で、その跡地を「一般人民が住む住宅地区に」、それも「最上級の住宅区域」にという金正恩総書記の想いがあって、それが実際に実現したからだと彼は言った。特に感動したのが、そこに住む人が幹部など「特別な人」ではなく長年、真面目に働き功労があったと職場で評価された普通の人民、勤労者が入ることなのだ、と。入居者の職種も教員やアナウンサーもいれば溶接工や道路管理工もいるとか様々だという。「階段式住宅」、すなわち二階もある200平米の日本で言えばまあ「億ション」、ここに国のために真面目に汗を流した普通の勤労者が入る。これがミョンチョルさんの言う「朝鮮の新しいミサイル発射」、彼の感涙をさそい、世間をアッと言わせる出来事だったのだ。
ここからは余談。
竣工式の後、金正恩総書記が手を取り合って家庭訪問した女性アナウンサーは私たちもよく知る方だ。私たちの間では「天知シゲ子さん」で通った人、「よど号」で来た当初から朝鮮のTVに出ていて日本の俳優「天知茂」に似ているというので田中義三がそう名付けた。いわば朝鮮で「青春時代を共にした仲」、馴染みの方だ。
この方には会ったこともある。日本で柴田泰弘が逮捕された‘88年にTV朝日の取材を受け日本と宇宙中継でつなぐため小西さんと私が朝鮮中央放送局を訪れたとき、廊下の窓ふきをやっていた「お掃除おばさん」が「どっかで見たことあるよな」と二人で言い合ったが、それがあの「天知シゲ子さん」だったのでびっくりした。そんなこともあって私たちには「長年のお友達」のような方だった。
この「天知シゲ子さん」、日本でも独特の語り口でけっこう「有名人」と聞いている。今年、79歳というから小西さんより一つ上、私たちと同世代と言えなくもない。
だから金正恩総書記に手を取られて自分の新居を見て歩く高齢の女性アナウンサーの喜びが他人事とは思えない・・・「よかったね天知シゲ子さん」と言いたくなる。
丘陵地にあるこの住宅地域は、運河地帯、普通江の美しい景色を一望できる楼閣のような住宅区という意味で「景楼区」と名付けられた。
これを書いていた17日夕方、「新しい誘導弾発射」! の中央放送ニュースが入った。まさかミョンチョルさん、このことを知っていて「朝鮮の新しいミサイル発射」と言ったんじゃないでしょうね。ニュースを聞いてこのタイトルは合わなくなったかなと思ったが、ミョンチョルさんを信じてそのままにしました。
1万世帯高層アパートと功労者アパート完工
赤木志郎 2022年4月20日
暖かい日差しに包まれる4・15を迎え、恒例の「春の祝典」が連日、放映された。中国、在中同胞、ロシア、ベトナムなどの芸術団がオンラインで参加しており、その水準の高さに驚いた。一方、国内の人々による人民音楽祭典も各劇場でおこなわれている。そうした華やぎの中で今回とくに人々の耳目を惹いたのは、1万世帯高層アパート群と功労者アパート完工式だった。
1万世帯高層アパートは、5年間で5万世帯アパートを建設する最初のものだ。それが市内の中でもすこしはずれた近郊に建設されていく。つまり、平壌市内に五つの市街地区が新たに建設されるという話しだ。市内にある高層ビルから1万世帯アパート群を眺めたら、近郊に高層アパート群が忽然と現れたという印象だった。すでに2期目の1万世帯高層アパート群の建設も開始された。それ以外にも、市内中心部で古いアパートが壊され新しく建設する工事もあちこちで行われている。皆が近代的アパートで暮らせるという住居問題を完全に解決するということだ。
それが単なる夢でなく、現実のことであることを今回の一万世帯高層アパートの完工式が示した。だからこそ、人々の大きな関心を惹きつけたと思う。
早速、四月一五日にその二つのアパート群を見にいった。八〇階アパートのそばに車をつけたが、余りに高いので見上げるのに首が痛くなるほどだった。
都市だけではなく、農村でも近代的住居、公共施設を備えた「農村建設」が開始された。すでに白頭山のふもとの三池淵郡に都市と変わらない立派な建物群が建設され、市に昇格した。それを模範にしてその建設経験を生かし全国に拡げていく闘いが開始されたという。日本人村の近くにも「共産主義へ行こう!」とスローガンが掲げられた。
そういう意味で、全国到るところで建設ラッシュだ。
もっとも厳しい経済制裁を受けて自力更生に困難な闘いの意味合いがあったが、今や、自力更生が自分の力で自分の思うままに建設していけるという明るい展望の意味に変わっている。
世界が戦乱と物価高、コロナ禍で騒々しい中において、朝鮮の社会主義建設がひときわ輝いているように思う。
私も励まされました
魚本公博 2022年4月20日
4月15日の太陽節、当日は、市内で食事でしたので当日の街の風景を見ることができました。印象深かったのは、花です。どのアパートや商店の前にも花壇がしつらえられ、各アパートの窓辺にも花鉢がおかれ、どこもかしこも花で一杯でした。ソンシン地区の新住宅街にも行き、80階の高層アパートを仰ぎ見て来ました。
15日から土日にかけて3連休でした。その最後の日曜日には、BSで田中陽希さんのグレート・トラバースを見ました。100名山踏破から200名山、300名山と続いたものを人との触れあいをテーマに再編集したものです。
その中で八ケ岳の天狗岳に向かう場面がありました。そこで出会った中年の女性の挨拶、「私、ガンにかかって手術を受けて退院したところなのよ」。そして「陽希さんの頑張る姿を見て励まされました」と。最後に「頑張ってください。私も頑張りますから」と涙ぐんでの挨拶。陽希さんも「さようなら、お元気で、行ってきます」と挨拶を返しながら、カメラに向かって「前から不思議に思っていることなんですが、何なんでしょうね。僕は自分がやりたいことをやっているだけなんですけどね」と感じ入った様子でした。
何かを追求して生きる生き様に、人は勇気を得、励まされる。そして、それがまた自身の励みになるということでしょうか。
3.31のイベントに国際電話で参加して
小西隆裕 2022年4月5日
「『よど号』ハイジャックから52年 3・31 救援報告の集い」が東京で開かれた。私たちも、当事者として国際電話で参加させていただいた。
第一部で活動報告が山中さん、井上さんの方からあった後、第二部、「国際情勢について語る」の途中からの参加だったが大変有意義な時間を過ごさせていただいた。
討論が幾人かの論者によってなされた後、国際電話がつながり、こちらの発言が求められた。司会の椎野さんの要求は、ウクライナ問題、5分間でというものだった。
それで、私が皆を代表して、あらかじめ用意したウクライナ問題の本質と日本にとっての意味について手短に話した後、朝鮮の問題も、ICBMと貿易が完全に遮断された中での自力更生の闘いについて簡単に話させていただいた。
話の内容が日本のメディアなどで言われているのと大分違うので、質問や反論、異論が出されるのは覚悟の上だった。
ところが驚いた。私の発言を受けて討論された共同通信OBの福島さんは、私の発言に同意されながら、実にすらすらとウクライナ問題の本質を解明されたのだ。全く異議なし!素晴らしい!の一言だった。一緒に聞いていた皆からも拍手が湧き上がった。
その後、電話口に出られた早見さん、足立さん、新崎さんも皆、多かれ少なかれ、賛同だった。
いや、これは実に嬉しいことだ。
心が通じることの喜びをいただいた3・31のイベント。
本当に有り難うございました。
「またギターをやってみようか」-音楽教室に誘われた私の春
若林盛亮 2022年4月5日
3月の終わりに散髪に行った。私のひいき、いつもの「ピョンヤンの理髪師」アジュモニ(おばさん)の理髪店だ。散髪が終わって、みんなが商店廻りに行った車を待って玄関横のソファで読書中の私に、たったいまロシア人の少女を見送ったばかりの渋い感じの男性が声をかけてきた。
「あの~音楽教室をのぞいてみませんか」? 物腰は柔らかいがえらく単刀直入・・・
「はあ?」と不審顔の私に「音楽を好まれてるようなので、チョッと」とにこやかなその応対ぶりについ引き込まれて後をついていった。
「ピョンヤンの理髪師」のいるところは、コロナ禍で外国人の行けるサービス施設が限定されている中でもピョンヤン市民のみならず私たち外国人も出入り可能な総合サービス施設。サウナ、プール、食堂の他にも朝鮮語教室や音楽教室もある。ピョンヤン駐在大使館員の子女などがこれらの「教室」に通っており、土曜日の午後などはこうした外国人子女が多くやってくる。
その男性は私を音楽教室に招き入れると自分はここの音楽教師だと自己紹介しながら「ギターはお好みですか?」と聞いてきた。「はあ・・・まあちょっと。でも若いときに少しベースギターをやっただけだから、爺さんになってもう指がよく動かない」と答えた。
「まあよろしい、じゃあ私が少しやってみますから聴いてください」と演奏を始めた。「アルハンブラの想い出」を演奏してくれたが指さばきはとても堂に入ったもの、さすがはプロ、「うまいですねえ」と思わず拍手した。
「6ヶ月もやれば、誰でもこれくらいはできます」と教師は断言調、「1時間半の授業を1週間に2回、後は私の与える課題をやればよろしい」と次は熱心な勧誘。ついほだされて「う~ん、そうですなあ」と肯定的な答え方をしてしまった。正直なところ、心は動いた。
私はかつてロックバンド「裸のラリーズ」結成に関わりながら‘68年の政治の季節にはバンドへのモチベーションが低下、「日本音楽界にゲバルトをかける」と語り合った水谷、中村両「盟友」にバンドのこれからという時期に脱退を告げた人間だ。政治に転進以降は「二度とギターを持つことはあるまい」となんとなく心に決めた。それが不義理をした「盟友」への私の倫理感のようなものだった。
支援者から贈られたギターは私の家の倉庫に眠っている。でも音楽への興味がなくなったわけではない。政治一本できた私だが人生晩年期を迎え、またギターをやってみようか、作曲だってできるかも・・・という野心も少し芽生えている。
いま正直言って迷っている。ギター練習をやる時間をどう捻出するか、それに授業料も日本の常識からは破格の安値だが、私にとってはけっこうな出費だ。
どうってことないことだが、まあそんな悩みの4月の春、私の「よど号LIFE」。
でもどうしてあの音楽教師が私に声をかけてきたんだろう? 「音楽を好まれてるようなので・・・」というのも何でわかったんやろ? 教室にあったピアノや管楽器などではなくギターを持ち出してきたのもなんか「訳あり」だ。
よう~く考えてみると、「ああ、あのピョンヤンの理髪師かあ」!
いつか理髪中の雑談で「近頃、頭のてっぺんが薄くなりましたねえ」と言われて、「若い頃はアジュモニほどの黒々としたロングヘアーやったんですけどね」と答えたが、昔、バンドをやったことがあるという話もしたことに思い当たった。
きっと理髪師アジュモニがあの音楽教師に私のことを教えたのだ。そう言えば、アジュモニが「ここに音楽教室もありますよ、やらはったら?」とも言うてたな。コロナ禍国境封鎖で在留外国人も激減、大使館の子女などが通う音楽教室にもかなり空きが出てきているのかもしれない。
「ピョンヤンの理髪師」のアナザーサイド、手の込んだ客の勧誘ぶりはまことに商売上手、商売熱心! 新たな発見でありました。
さて75歳になった若林爺さん、どうしたもんじゃろのう・・・
見直した日本映画
赤木志郎 2022年4月5日
昔から私は洋画ファンだった。日本映画はスケールが小さく、細々した題材で、型にはまったものが多いと洋画を好んだ。大学生のときは年に100本くらい見ていた。しかし、所謂名作、大作ものは好きではなかった。商業主義が鼻につくからだ。だから、マカロニウェスタンやソ連映画、インド映画が好きだった。
もちろん日本映画にも秀作はある。岡本喜八監督の「喧嘩エレジー」は最後に主人公が北一輝を訪ねていこうとする場面が革命闘争に立ち上がることをイメージしていたと私は思った。
BSで放映されるのは「007」シリーズなど過去、何回も放映されたものであり、ほとんどが米国製映画で観るべきものがないと思っていた。土曜日のBS12の洋画劇場だけがそうした映画と頃なる秀作をときどき放映してくれるので、毎週、チェックしている。でも、月一回程度しか見ることがない。
ところで最近、BSで松竹東急というチャンネルができ、そこで夜、日本映画でグランプリ最優秀作品を放映してくれるようになった。そこで第一回目の「事件」という日本映画を久しぶりに見た。以前にも見たことがあるがほとんど記憶になかった。しかし、今回、見直すと、構成、演技、展開など完成度が非常に高い作品だったことに驚いた。恋人の姉を殺した事件の裁判のなかで隠された真相がしだいに明らかになっていくストーリーだ。思わず引きこまれていった。以前は、放映時間の制約で30分以上もカットされたものだったが、今回、全編を見ることができて余計に印象深かったのかもしれない。日本映画の水準の高さを知らされた思いだった。
最近、アカデミー賞をとった「マイ ドライブ・カー」が話題になっているが、かつての構成と展開、名演技のすべてを備えた映画作品が生まれているのか、知らない。制作費がかかるからもう無理なことかもしれない。日本映画の優れた伝統を生かしてもらいたいものだ。
エゾ・ウコギ
魚本公博 2022年4月5日
3月、朝鮮では「植樹月間」でした。市内に出かけるたびに市内各地で植樹風景を見かけました。私も、よど農園の周囲を花木で美化しようと、ツツジやレンギョウ、ボケ、ライラックなどを移植してきました。そういう中で今、目をつけているのがエゾ・ウコギです。
エゾ・ウコギは、北海道に生えるウコギの一種ですが、絶滅したと思われ「幻のエゾ・ウコギ」と言われていたものが数年前に再発見されたのだそうです。
実は、私たちの村の谷間に、ウコギに似た木が生えていて、葉がきれいなので農園近くに数本移植していたのですが、ヤツデの一種だと思っていました。ところが昨年、BSでエゾ・ウコギの映像を見たのですが、その木にそっくり。それがエゾ・ウコギ(近似種かもしれませんが)だと分かりました。それで、3月は過ぎましたが、エゾ・ウコギをもっと移植しようと思っているというわけです。
ウコギは、朝鮮で有名な強壮滋養の朝鮮人参に成分が似ているそうです。特に野生の人参は「人参は歩く」と言われ、幼苗を発見して、大きくなるのを待っても、見失うほど発見が難しく高価です。封建時代には、野生人参1本で「家が建つ、船が買える」と言われるほどだったとか。今でも、国際シンジケートで、良質の物は数千万円から1億円もするそうです。
2002年のワールドカップ日韓共同大会で、韓国では、その高価な人参が全国から寄せられ選手が使ったとか。そのとき、ロシアではウコギを使った強壮剤を利用したそうですが、「人参よりも効果がありそうだ」と言っていました。
ウコギは木皮を朝鮮人参のように煎じて飲んだり、若芽を浸しものや和えものにしたり、飯に炊き込んだりして食べます。エゾ・ウコギがウコギと同様の効果をもつのかどうかは分かりませんが、何しろ「幻のエゾ・ウコギ」、効果はありそうです。今年は、若芽を沢山採って皆に食べてもらおうと思っています。
「盆栽型」と「栽培型」
森順子 2022年4月5日
教育は「盆栽型」教育と、「栽培型」教育とに分類することができると言われたのは、折原浩氏(東大名誉教授)です。「盆栽型」とは、外から圧力を加えて変形していく教育、つまり「「盆栽」を作成するように「鋳型」にはめるように教育すること。「栽培型」は、植物を栽培するように枝を伸びたいように伸ばしていく教育、人間が成長したいように、また成長できるようにするために、肥料を施したり害虫を駆除したりすることが教育の役割だということです。教育の意味を問うとき、「盆栽型」と「栽培型」という分類は、分かりやすく、内在しているものを引き出すことが教育であるということだと思います。
日本では、これまでの詰め込み、暗記優先という教育から、新しい能力開発を主とする学び方、教え方に力を入れた教育に変化していっています。この変化自体は、引き出す教育、「栽培型」教育の方向だと思います。朝鮮でも同じです。教育、すなわち、人材育成は「人材農事」だと言われ、思考を主とする知能教育方法の改善や革新のために奮闘する教員の話や姿をテレビでは、よくやっています。それを見ていると、一人一人を生かす教育方法をいかに編み出し、生徒の能力をどう見つけ、どういう教育方法が合うのか。それを常に探求している教員の役割こそが本当に重要だと感じます。
日本ではタブレットが大きな役割をしていますが、教育は一方通行、すなわち教え込むことではないから、教員数を増やし、教員の力をもっと発揮できるようにすることだ、そうしてこそ「栽培型」教育となり質も上がるのではと思っています。
覇権国家米英の汚さ
2022年3月20日 小西隆裕
連日、「ウクライナ」で明け、「ウクライナ」で暮れている。
それにしても、日本のマスメディアの報道は凄まじい。
ここぞとばかりのプーチン叩き、ロシア叩き、返す刀で中国叩きだ。
そこで強調されるのが日本の軍事力強化。
挙げ句の果ては、核の「共有」論まで飛び出してきた。
そこで思うのは、米英覇権国家の狡猾さだ。
もともと今回の戦争の根因は、米英によるウクライナの対ロシア・フロントライン(最前線)化にある。
ゼレンスキー政権の完全な米英傀儡政権化、ネオナチ政権化。
ウクライナ軍隊の米国製最新兵器による武装化と米軍による訓練。
そして、ウクライナのNATO加盟の推進。
今回、ロシアのウクライナ軍事侵入の際掲げられたスローガンがウクライナの非ナチ化、非武装化、中立化だったのは、まさにそのためだ。
この「軍事侵入」に対して米英覇権国家がしたことは何か。
国連での対ロシア非難決議の主導。
国際決済秩序(SWIFT)からのロシア銀行の排除など経済制裁。
米英系メディアを総動員してのプーチン・ロシア攻撃、中国攻撃。
その上で、米英自身のロシアとの軍事衝突は巧妙に避けられている。
廃墟と化したウクライナ。
その影でほくそ笑む米英覇権国家。
日本が「ウクライナ」から学ぶべきは、何よりもこの構図ではないだろうか。
「春を謳歌」のピョンヤンの3月、私の3月
2022年3月20日 若林盛亮
春はあけぼの・・・
3月になると「村」前の大同江の氷もようやく溶けて「やうやう明けゆく」東の空に昇る朝日が映え水面みずもはあかね色に染まる、この風情ふぜいや「いとおかし」、清少納言になったようなとてもアートな気持ちになる。
ピョンヤンでは春を感じるのは陽気的には寒さが和らぐ2月だが、景色的には3月だろう。野山の雪も消え地肌が見えるというのが朝鮮の春感覚、下旬になると朝鮮ツツジ、れんぎょうが花咲きはじめ辺り一面を彩色する。
3月8日は国際婦人デーで祝日、市内では音楽公演や辻々で舞踏会と街はカラフルなチマチョゴリ一色になる。男達は恋人や奥さん、女性同僚に花束やカードを贈る。私のひいきの「ピョンヤンの理髪師」アジュモニは、旦那さんと子供から食事会の招待を受けるのよ、と言っていた。
この日、よど号が降り立った飛行場に隣接する美林競馬クラブで行われた市民公募の馬術運動会は異色のものだった。
政府要人も夫人同伴で参加、着飾った多くの市民が家族連れで食ったり飲んだりしながら競馬、障害物競技などの馬術やアトラクション公演を楽しんだ。
中でも異彩を放ったのが農場員参加の競馬ならぬ「競牛」、男達が大きな牛の背中に乗って鈍重な牛に鞭を当てながら「速さ」を競うユーモラスな姿が市民の笑いをどっと呼んだ。TVを見ながら私も思わず笑ってしまう。
3月10日からは協同農場では苗床作業が始まった。
一方、サッカー・フリークの私にとって3月は英プレミアリーグが終盤に向け熾烈な順位争いの佳境に入る季節。
私の応援するリヴァプールFCは現在2位、1位のマンチェスター・シティ(マンC)に肉迫中。その勝ち点差は「6」(一試合勝てば勝ち点「3」)だったが、14日の試合でマンCが引き分けになって勝ち点「1」に終わり、他方12日の試合でリヴァプールは2:0でブライトンを下したために勝ち点差は「4」に縮まった。リヴァプールは未消化試合が一つあるため、これに勝てば勝ち点差は「1」となってさらに急迫する。そして大一番は4月初旬のマンCとの直接対決、これでライバルをたたきのめせば首位逆転奪還! プレミアリーグ優勝がほぼ確実になる。
他に欧州選手権(UEFA-CL)でもすでに8強進出、また英国内カラバオカップ戦では優勝したので、残るFAカップなど4つあるカップ・タイトル全制覇も夢でない。これは誰も成し遂げたことのない歴史的偉業となる。
たかがサッカー、されどサッカー、私にはゴージャスな「夢見る」3月である。
ウクライナやオミクロン株蔓延中で大変やのに何を呑気なと言われそうだが、リヴァプール「命」の私はひたすら“You’ll never walk alone”(応援歌)を歌うのみ。
とにかくピョンヤンも私も今年の3月は春を謳歌している。
春眠暁を覚えず
2022年3月20日 赤木志郎
-300x300.jpg)
早春の気配(蕗のとう)

掘り起こされたよど農場
大同江の氷も完全に溶け、春になった。ぽかぽかする暖かさではなく、まだ寒気が残っているが春は春だ。本格的な春は4月なかば。
暑苦しくなった毛布も洗い、布団を干し、シーツも洗って一新した。これから冬物の服を整理していなければならない。
家のガラス戸がよく閉まらない箇所やベランダのドアーなど、管理所の人たちが修理してくれるのも春だ。
春になって、身体が緩んでいるのを実感する。困ったのは、眠気がすることだ。いつもなら、午前中が一番、集中できる時間帯なのに、朝から欠伸がなんども出る。まさに、春眠暁を覚えずだ。しばらくすると慣れるだろう。
凍った道もなくなり、歩行運動も再び始めなければならない。土の中で冬ごもりした虫たちがはい出る「啓蟄」の節気もすぎた。
春はあらゆる意味で活動の開始の時期だ。しっかり準備をし、本格的な活動に備えていこう。
「見捨てない」、それが大事なのだと思います
2022年3月20日 魚本公博
今年の3月11日は、東日本大震災11周年となる日でした。2万人もの犠牲者を出したあの大惨事。まだまだ仮設住宅で生活する人があり、原発被害で避難生活を余儀なくされている人は3万8000人もいるとか。まだまだ復興途上なのですね。
ちょうどその頃、BSで六角バンドの六角さんが各地で列車旅する「呑み鉄 一人旅」で、三陸海岸鉄道に乗って旅をする番組を見ました。
三陸海岸は大震災の津波の被害をモロに受けた地域です。列車の車窓からの風景、途中下車しての街の様子など興味深かったです。どこも立派な防潮堤が、その高さは10数メートルに達するとか。でも市街地は、新しく立てられた建物もまばらという所が多かったです。
新聞記事を見ても、被害地は、どの街も人口は半減し、かつての賑わいを取り戻すのは難しそうです。牡鹿町の人が「牡鹿をゴーストタウンにしたくない」と言っていましたが、どこも、そういう状況なのでしょうね。
一方、東北では「仙台圏の一人勝ち」ということが言われています。山形市を含む仙台とその周辺で構成される圏域にヒト・カネ・モノが集中し、他は衰退するという現象です。
効率第一の新自由主義的な発想によって、「すべては救えない」として、末端の弱小自治体や集落は切り捨てるという考え方の結果です。そうではなく、どんな人にも価値がある、どんな地域にも価値があるのであり、どんな人も見捨てない、どんな地域も見捨てないという考え方が大事なのだと思います。
三陸鉄道の車内では、震災復興の応援歌として歌われた「花は花は花は咲く・・・」の歌が流れていましたが、最後の「・・・私は何を残しただろう」のフレーズが妙に頭に残る今年の3・11でした。
早春の香りのなかで
2022年3月20日 若林佐喜子
先日(13日)、よど農場の一角で蕗のとうを5個みつけました。朝晩は肌寒い日もあり、枯れ葉の中の凛とした緑の蕗のとうは、早春の気配、力強い生命力を感じさせてくれます。中にはちょっと可愛すぎる感のものもありましたが、早速、天ぷらにして香りとほろ苦さを味わいました。その後、日中は16度の日もあり、しばらく青々とした蕗のとうを味わえる日が続きそうです。よど農場はきれいに掘り起こされ、種まきをまっている状態です。
ピョンヤン市郊外でも、温かい陽射しのなかで苗代づくりがはじまりました。テレビのニュースや天気予報の時間には、苗代づくりの様子や何日からいつまでが最適期などとの報道があったりしてすっかり営農モードという感じです。昨年は、7月末にポギョム(暴炎)日が続いたり、秋の収穫前に雹(ひょう)が降るなど大変でした。温暖化をはじめ異常気象現象を予想しての苗代づくり、まずは、丈夫な苗づくりが多収穫を保障するための大切な第一歩ということのようです。
最近、日本の新聞記事で、「温暖化=気温上昇、一見すると『恩恵』に見えるが、農業の未来はそう単純ではない」という内容を見ました。温暖化現象で、東京の八王子市で南米の亜熱帯地方原産の果物(パッションフルーツ)の名産品化、北海道での温暖化地方のぶどう栽培による高級ワイン作りの成功。今後は、愛媛・和歌山県の特産である温州ミカンの適地が東北まで北上し、又、現在、東北で栽培が盛んなリンゴは北海道が最適地になるだろうということです。それで、農林水産省は2015年に適応計画を策定し、青森ではリンゴに変わる桃の栽培が奨励されはじめているが、先人の苦労の結果であるリンゴ農家の思いは複雑とのこと。品種改良で気候への対応を進めてきた作物の代表が米である。しかし、新しい品種の作付けには莫大な資金が必要であり、農家個人のみでは対応できないので、国全体で対応を考えることが不可欠だ!ということでした。
記事を読んで最初は、朝鮮でもみかんやレモンが収穫できれば良いのになぁーと思いました。しかし、穀物生産量を決定的に増やすことが要求されている朝鮮では・・。だから、現在、「食料問題の円満な解決、農業生産構造を変えて災害性異常気象の影響を克服するための根本的な鍵は種子問題を解決すること」という課題が強調され、その解決に力が入れられているんだと強く納得した次第でした。
早春の中、苗代づくりを目の前にしながら、朝鮮でも日本でも今年は大きな自然災害、被害がなく豊作を迎えることができますようにと、心から願わずにはいられませんでした。
「ウクライナ」に思う
2022年3月5日 小西隆裕
今、日本のメディアは「ウクライナ」一色だ。
ロシアに対する非難で満ちている。
そこで二点、疑問に思うことがある。
一つは、米国のイラク侵攻の時との違いだ。
「イラク」の時は、これほど米国に対する非難で満ちていただろうか。
この違いはどこから来るのだろうか。
米国の侵攻は正義で、ロシアのそれは不正義だからなのか。
そこでもう一つ、今回ロシア軍がなぜウクライナへ侵入したのか、その理由がほとんど語られていないことだ。
米国の時は、「イラクの大量破壊兵器隠匿」が前面に掲げられた。
しかし今度は、ウクライナのNATO加盟への動き、それが米ソ冷戦終結時のNATO不拡大の約束違反であること、それを米国が後ろからロシア包囲、封じ込めの目的で操っていることなど、ロシア側の言い分は後方に追いやられている。
問題は、こうしたメディアの動きが日本にとって良いことなのかということだ。
唐十郎、「越境する紅テント」
2022年3月5日 若林盛亮
以前、「よど号ハイジャック」を扱った「アナザーストーリーズ」というNHK番組で「越境する紅テント」と題する状況劇場の唐十郎のドキュメントをやった。
1960年代後半期、唐十郎の「紅テントの状況劇場」は寺山修司「天井桟敷」と双璧をなすわれわれの世代の前衛的存在、紅テントのあった新宿花園神社は聖地のようなものだった。
私が「裸のラリーズ」というバンドを水谷、中村らと結成した背景には、唐十郎に刺激された側面もあったと思う。当時は演劇界での新しい試みが日本のロック音楽よりも先行していた。身の程知らずかもしれないが私がある種のライバル意識を持った人物、それが唐十郎だ。
番組によれば、唐十郎は少年時代に強烈な体験を持ったという。「焼け跡時代」と呼ばれる敗戦直後の東京、上野駅周辺は戦争孤児や家を焼き出された一家が飢えとの厳しい闘いをやっていた、野坂昭如の「火垂の墓」のような餓死した孤児の死体が毎日のようにころがっていた時代だ。また「オカマ」と呼ばれた男娼が夜の街を徘徊していた。
唐十郎少年には逆境にめげずに生きる人たち、「オカマ」、反社会的というレッテルを張られた人々の逞しさが「何ともきらびやかなもの」に見えたという。これが彼の演劇人としての原点だ。
大学生となった唐十郎は新しい演劇を志す。当時はチェーホフの「桜の園」だとかロシアや西欧戯曲の翻訳劇主体の取り澄ました「新劇」が演劇界の主流だった。ある意味、「新劇」は軍国主義に代わる自由と民主主義という「戦後民主主義の象徴」でもあった時代だ。それに唐十郎は反旗を翻す。それは彼の同世代とも言える「時空を越える黒」ファッションのデザイナー山本耀司、彼の言う「ファッションは飾り立てるものかもしれないが、人の眼を欺いてはいけない」に通じるものだろう。
敗戦の混乱から戦後日本は高度成長期に、人々は経済的な豊かさを求める時代になった、だがそこになにか割り切れない疑問、空虚を感じたのが私たち戦後世代の若者だ。こうした時代の空気の中から「戦後日本の常識を破る」という志を実践したのが唐十郎であり、寺山修司、山本耀司だった。
唐十郎は劇場という固定空間でやる演劇を否定、野外のテントを劇場とし、テントの一部を開くと現実の都会風景と一体になるという演劇空間を創造した。自ら脚本を書いた「腰巻きお仙」「ジョン・シルバー」などの演目は若者の度肝を抜く芝居、舞台と客席が一体となった熱気みなぎるテントの中は幻想と現実渾然一体の不思議空間となった。まさに新しい演劇革命の出現だった。
「余談」だが、私の友人に京都の劇団研究生がいた。その人は劇団で準主役を射止め私より先に「俳優の卵」から一歩前に出ていた人だった。私がよど号ハイジャック直前に京都に行った時、「恩人に別れ」をと電話を入れたが家人から「東京に行った」と聞いた。おそらく従来の「新劇」的な所属劇団に飽きたらず「新しい演劇」の激震地、東京に活躍舞台を求めてのものだと直感した。更に一歩前へ、「戦後日本の常識」を破りたかったのだろう。唐十郎らの演劇はそんな磁力を持っていた。
「越境する紅テント」と題したアナザー・ストーリーズは唐十郎の別の一面も紹介する。
唐十郎は、看板女優である妻の李礼仙が韓国籍のため当時の沖縄公演時にビザが出なかった不条理体験を契機に、「二都物語」と題する脚本を書き韓国ソウルに始まり東京で終わるという演劇を企画。だが当時の韓国はパク・チョンヒ親米軍事独裁政権下の国、拷問を伴う学生運動、民主化闘争への苛酷な弾圧の国、そして日本文化はいっさい禁止、常識では唐十郎の公演は到底不可能となる国だ。しかし彼は断固、ソウルでやる決心を変えず金キム芝ジ河ハに連携をつける。金芝河は「死刑判決」を二度も受けた民主化運動の象徴的存在、KCIAの尾行や監視を受ける中、金芝河の助けでソウルの大学での野外公演を唐はついにやってのける。これに私はとても感動した。
日本にいた頃は、ただ「前衛演劇の旗手」程度の認識だったが、この番組では志のためには危険も敢えて冒す、そんな気骨を持った人だったのかと再認識させられた。
80歳を越えた唐十郎は今も脚本を書き続け「紅テント」は「唐劇場」となって生き続けている。「戦後日本の常識」に抗い、それを乗り越えようとした戦後世代として政治と演劇と活動舞台は異なっても唐十郎同様、私はその志と気骨だけは持ち続けたいと強く思った。
いま「アメリカに追いつけ追い越せ」の「戦後日本の常識」に赤ランプがつく時代、かの山本耀司は「ファッションで政治を主張する」と頑張っている。時代は私たち戦後世代に老骨に鞭を打てと呼びかけている。
緊迫するウクライナ情勢
2022年3月5日 赤木志郎
最近は、ラジオやテレビ、新聞でまずウクライナ情勢に釘付けになっている。ウクライナは、「鋼鉄はいかに鍛えられたか」の舞台であり、「戦艦ポチョムキン」が反乱を起こしたオデッサがあり、かつて反革命と革命の激しい戦闘が繰り広げられてきた。そして、ナチスドイツのソ連侵攻でまっさきに占領され、大きな犠牲を強いられた地域である。そして、この十数年間は米国のオレンジ革命策動が繰り広げられ、ナチス信奉者らの国会突入で親ロ政権が転覆され親欧米政権が樹立されて、クリミア半島のロシア併合、ドネツク州・ルガンスク州の親ロ武装勢力の独立と抗争など、欧米の覇権策動とそれに抵抗するロシア勢力の争いが繰り広げられてきた。
それゆえ、ロシアの行動は米国の覇権機構であるNATO拡大に反対する非常手段だといえると思っている。ロシアにとってはウクライナはロシア民族の一部であり、兄弟国であったし、ロシアと国境を接した大国として、その国にNATOが進出することは直接の脅威となり許すことはできなかったということは理解できる。
戦闘と交渉が続いているが、今後、ウクライナの国民がどのような決断を下すのか注視してみたい。
ネコの思い出
2022年3月5日 魚本公博
2月22日は、ニャンニャンの語呂合わせでネコの日だとか、BSでは岩合光昭さんの「世界猫歩き」などネコの番組が多く放映されていました。
私も子供の頃、ネコを飼っていました。小学生5年の頃、夏休みには毎朝集落の子供が集まってラジオ体操するのですが、そこまでの通り道の傍の麦畑に捨てられていた子ネコを拾って帰ったものです。三毛猫と赤ネコで、三毛ネコはミケと名付けて妹が、赤ネコはミコと名付けて私が飼うことになりました。
母親が室内で飼うことを嫌って追い出すので、昼間は外で、夜は室内というような飼い方でした。田舎の家なので庭も広く周囲は田畑でしたから、食事も室外、排泄も室外でした。子を産んでも捨てることなく飼っていたので、多いときには8匹ほどにもなりました。
朝鮮でもネコを何回か飼ったことがあります。最後は2000年の頃、子供がどこからか貰ってきたキジ猫で名前はミカ。あまり私には懐かなかったのですが、子供が日本に帰ってからは二人きりで、まあ仲良く過ごしていました。夜になると布団に潜り込んできて、鼻をくっつけてくるのですが、ネコの鼻は冷たくて、そのたびに目覚めるので閉口しました。雄猫だからか、ある時、出て行ってしまいました。
朝鮮でも犬やネコを飼いますし売ってる市場もあります。犬はテリアとかプードルなど愛玩用ですが、ネコは在来種だけです。日本の在来種と比べると、朝鮮のネコは爪も歯も鋭く、警戒心も強くて野性味があります。
日本のBSで放映される愛らしいネコを見ながら、ミコやミカなどをなつかしく思い出したニャンニャンの日でした。
2月は春です
2022年3月5日 森順子
「2月は春です」という歌があります。この歌のように2月の中旬になると陽ざしが暖くなり春の気配を感じますが、この冬は雪も多く、月末になっても朝の気温はマイナス10度くらいの日が続きました。やっと3月になり春だよね、とほっとしているところです。
今年の朝鮮は、5カ年計画の2年目の年。2月の朝鮮は、祝日も多くありましたが、とくに今は、建設の新しい高揚期と言われています。5カ年計画は、市内では5万世帯の建設ですから毎年、いろいろなデザインや型の住宅や施設が建てられるだろうと思います。昨年、完成した1万世帯も特色あるようです。超高層アパートは、遠くからですが、これまでにない現代的な建物に見えます。12日にはファソン地区に昨年同様、1万世帯の住宅と街の建設が始まり、また、建築部門の大きな講習会なども開かれました。そして、引き続き、北方のハンフン市には、大規模温室農場建設が着工されました。この温室は10月の労働党創建記念日までの230日あまりで完工するため、建設場は戦闘的気迫で沸きたっていると言います。来年になれば、また、朝鮮の姿は、今年より、もっと大きく改変されると思います。
自分を信じた金メダル、平野歩夢
小西隆裕 2022年2月20日
北京オリンピックはまだ終わっていない。
しかし、今までのところだけでも、日本選手の活躍は、これまでのどの冬季オリンピックにも勝るものだったと言えるのではないか。
それは、メダルの数だけではない。選手の活躍が印象的だった。
特に圧巻だったのは、スノーボードの平野歩夢選手の「金」だ。
二度ある試技の中の最初、彼が挑戦した五輪史上初の大技、「トリプルコーク1440」は、目を見張るものだった。だが、採点は、91・25。
本人だけでなく、観ていた者誰もが納得できるものではなかった。
ソチ、平昌、過去二回のオリンピックでいずれも「銀」だった彼は、今回も二位、またもトップに立てなかった。
そして最後の試技、彼は怒りを力に換えた。スノーボードに乗って飛び上がり斜めに縦に3回、横に4回転(1440度)する夢の技、「トリプルコーク1440」を最初の試技にも増してさらに完璧に決めた。得点は、96・00、断然最高点、文句なしの優勝だった。
平野歩夢、24歳。彼は、「自分を信じ、戦い抜けば、必ず結果はついてくると確信している」そうだ。
この信念が、平昌以後毎日、普通日に25回から30回が限度と言われる練習を60回、時には肝臓の破裂、膝の靱帯損傷という大怪我を同伴しながら貫徹させた、力の源泉だったに違いない。
われは詩のかみ(神)の子なり!-「恋する一葉」を見た
若林盛亮 2022年2月20日
BS-NHK放送に「プレミアム・カフェ」という過去の放送の中から反響の大きかったものを取り上げる番組がある。題目を選んで私はときどき視聴、先週は2004年制作の「恋する一葉」を見た。
ドキュメンタリー・ドラマと銘打った「恋する一葉」だが、「平成の女子大生がたどる明治の青春」と副題にあるように、舞台女優をめざし演劇科に通う女子大生マナミの夢と現実の間で揺れる平成時代の青春が樋口一葉の人生をたどる姿と同時進行する。
かつて私が政治活動入り立ての頃、互いに「卵からの孵化」を励まし競い合った京都の劇団研究生の「俳優の卵」がいてこのドキュメンタリーの主人公がどうしてもその友人とだぶって見えた。
21歳、4回生になったマナミは女優になる夢をあきらめかけている。大学の先輩たち、演劇科卒業生120人中、劇団に入ったのはたった10人、それもフリーターやバイトをしながらの俳優生活という現実。折しもこの頃は就職氷河期、いわゆるロスジェネ世代のマナミ、中学、高校時代からの演劇への夢は動揺渦中、「社会人としてやる演劇」と親の保護下にあっての学生時代の「夢としての演劇」とは覚悟が違うという「現実」をいやがおうでも痛感、かといって就職活動する気にもなれない、ただばくぜんと「小説家になろうかな」とも考え始めている。
そんな彼女だったが、大学の劇団で「恋する一葉」の脚本が上がり、一葉役をマナミがやることになった。役作りのためにもマナミは「明治という新しい時代の新しい女性」一葉の人生をたどろうとする、それは彼女にとって自分を見つめ直す旅でもあった。
一葉の父は貧しい農民出身だが駆け落ちした村の娘(一葉の母)と暮らす幕末期の江戸で金をコツコツ貯め士分を買い取り、明治になって下級官吏となる人物。一葉は幼い頃から利発で小学校4年で中退するが首席の秀才、父は娘の才能を見込み荻之舎という歌会学校に入れる。そこでも一葉の和歌は最高位の評価を受け、彼女は自分の文才に目覚める。父の死後、母と妹との3人の家計を助けるべく作家を職業に家族の暮らしを支える決心をする。
そのときの作家への決意を一葉は日記にこう記している。
「我れは人の世に 痛苦と失望とをなぐさめんために うまれ来つる詩のかみの子なり」!
「詩のかみ(神)の子」とはたいそうな自己評価だが、命ある限り「われはこの美を残すべく」とも記し一種の使命感に燃えていたことは真実だろう。
一葉を知る人は早くから類い希な彼女の文才を認めるが、しかし現実は甘くない。彼女は知人からの借金や質屋通いを続け貧苦に耐えながら作家人生を歩んで行くことになる。
一葉が女流作家として世間から認められるのは、24歳の若さで結核で病死する直前の2年間、22歳頃からのことだ。この間に「たけくらべ」「にごりえ」「大つごもり」など「一葉文学」として後世に讃えられる名作の数々を一気に生みだしていった。
その頃、一葉の住む狭い6畳間はさながら「文学サロン」を呈していたという。島崎藤村、幸田露伴、泉鏡花など後の文豪となる錚々たる文学青年多数が一葉に自分の将来の夢を託して集まってきたと言われる。でも一葉はそれを冷めた眼で見ていた。「いま清少(納言)や紫(式部)なりとはやしたてるなり 私がなにを考えているかも知らず」と。ただ女と言うだけで面白がっている「文学青年」たちを「心ない人」と切って捨てている。
そんな中で一葉の作品を「泣きて後の冷笑あざわらい」と評した斉藤緑雨という「毒舌批評家」青年がいた。「逢えたるはただの二度なれど 親しみは千年の馴染みにも似たり」と、「本当のことを言ってくれたのはこの人だけ」だと緑雨に恋心まで寄せた(ようだ)一葉。
こうして一葉の作家人生は晩年になってやっと花開くものではあったが、それは逆境にあっても挫けない強い信念、意志力がなせる業。番組では瀬戸内寂聴さんが「彼女は幸せだったんじゃないかと思いますよ」とマナミたち演劇科学生に語る。
さて一葉をたどる旅の果てに「平成の女子大生」マナミの下した結論は・・・?
「恋する一葉」舞台本番を前に化粧室で一葉になりきった自分に向かって彼女は静かにつぶやく。
「女優になってやる」!
まさに一葉は「詩のかみの子」! 「われはこの美を残すべく」、それを平成の時代にやり遂げたのだ。
オミクロン・コロナの大流行
赤木志郎 2022年2月20日
日本でコロナウイルスの感染が急速に広がっているという。これまで身近な人が感染したことがなかったが、肉親や支援者の方がまたたくまに感染し、驚いている。ワクチン二度接種していても感染するのだから、まったく安心できない。一日で10万人、とくに十代、二十代の子供、若者の間で感染が広がっているという。オミクロン型は重症化する率が低いと言われるが、感染者の急増で重症者も増えるし、治療設備のパンクで死亡する人も増えている。
人の往来を制限すれば経済活動が支障をきたし、その制限を緩めばコロナが再び流行するというジレンマを断ち切れないで繰り返している。新型コロナはたえず新しい変種株を生み出すのだから、ゼロコロナを目標にした対策と医療設備の拡充を抜本的に講じなければならないのでなかろうか。生命と健康を守り、不安から解放することこそが先決だと思う。そのうえで正常的な社会経済活動も可能となる。
その場その場の対応ではなく、制限と解除のジレンマに悩まされるだけでは根本的な解決ができない。海外からの入国者を緩和するというのも場当たり的な対応だ。ゼロコロナ戦略のもとでの抜本的な対策を講じなければとつくづく思う。コロナ専用の病院を作る話がときたま出るが、作られたことがない。
正しい戦略なく右往左往するのを繰り返すのはもう止めさせなければと思う。
デーボルムの日に
魚本公博 2022年2月20日
15日はデーボルムでした。旧暦の正月、最初の満月の日です。朝鮮では祝日で、この日は一年の豊作や家内繁栄を祈願して、コメ、麦、キビ、粟、小豆を炊き込んだ「五穀飯」を食べたり、一家で食堂に出かけて会食したりします。
それで我々も、市内の食堂に出かけました。食堂では結婚式をやっていたり、家族で会食するたくさんのお客さんで賑やかでした。
最近、市内に出ての楽しみの一つは、住宅建設の状況を見ることです。今、ピョンヤンではソンシン、ソンファ地区の1万世帯やポトンガン河岸住宅区、その他、各地で新住宅区の建設が進み、文字通り建設ラッシュです。
ソンシン、ソンファ地区は、ピョンヤンの郊外にあるので近くで見る機会がありません。それでも80階という数棟の高層アパートは遠くからでも見ることができます。
新住宅地区は、金日成主席の生誕日である4月15日の太陽節を契機に一斉に入居が始まるそうです。その頃には現場に出向いてしっかり見ることができるでしょう。新住宅は、園林化、知能化などが言われていますが、日本で言われるグリーン化、デジタル化でしょうか。それがどういう形になっているのかも興味がわきます。
また、新しくファソン地区でも1万世帯の建設が始まります。太陽宮殿から空港に向かう高速道路の辺りです。住宅建設は地方でも進んでおり、今後、地方に出かける時が楽しみです。
豊作を祈願するデーボルムですが、農業だけでなく、住宅建設や工場建設など、それも全国的な建設が進められており、今年は豊年の年になりそうだと朝鮮の人は言っています。中天に輝く満月もことのほか美しい朝鮮のデーボルムでした。
気になること・・
若林佐喜子 2022年2月20日
日本で4月から成人年齢が18歳に引き下げられます。関連して児童養護施設入所者についての新聞記事がありました。大方、18歳、高校卒業と同時に退所して就職し、23%が「家計は赤字」、就労者のうち44%が非正規労働とのこと。特に気になったのが、政府が無利子の貸付案を提示していたことです。無利子であっても返さなければならず、本人にとってはとても大きな負担であり、根本的な解決になりません。
さらに、昨年、「親ガチャ」と言う言葉が話題になり流行語大賞にノミネートされました。しかし、それが決して戯言(ざれごと)ではないという事実が現存しているということです。昨年末の内閣府より「令和3年 子供の状況調査の分析 報告書」で明らかになりました。(東洋経済 education 2/15)
全国的調査が実施されたのは初めてであり、その内容を詳細に分析しています。強く印象に残ったことは、シングルマザーの世帯は過半数以上で貧困率が高く、一方、父母の学歴が高い世帯ほど貧困層の割合は低いということです。結局、保護者の経済状況が子供の学習環境に大きく影響しているのです。この状況を放置しておけば、経済的に豊かな保護者の子供は学習環境に恵まれ、その結果、子供も豊かになる可能性が高い。「貧困層」世帯の子供は学習環境に恵まれず、その結果、進学の機会も狭められ子供が豊かになる可能性は低くなる。つまり、「貧困の連鎖」が生まれやすいということです。未来を担う子供たちは日本の宝であり、機会の平等が保障されなければならないと思います。
北欧の国々では大学まで無料です。また、リカレント教育(再教育)、成人教育とも言われていますが、日々発展していく高度な知識、技術を学びなおせるように政府が公費で保障する制度が整っています。
日本では、国公立大学でも学費が4年間で約400万円です。また、大学を出ていなければ正社員になれないともいわれているのが現実です。
岸田政権、行き過ぎた新自由主義から脱却し、成長と再分配に力をいれるとのことですが、現実は、「子供家庭庁」の創設でもわかるように、まず自己責任と家族、地域の互助であり、政府の責任、負担は最後のようです。
「政策提言」を完成して
小西隆裕 2022年2月5日
私たち6人共同で取り組んだ「東アジアからの政策提言 米中新冷戦、問われる戦後日本政治の転換」をようやく書き終えた。9月に「アジアの内の日本」コーナーに発表した闘いの対決点まで含めると、約半年の長丁場だった。
その過程で、菅政権から岸田政戦への政権交代があった関係もあって、それに合わせて、こちらの研究も若干の変更、深化が要請された。
そうした中、安保防衛や外交、経済、地方地域、教育、社会保障など、各人の自らの専攻分野の研究が深まると同時に皆が集まってやる討論が良かった。同じ、「新冷戦体制」づくりとの闘争でありながら、違う角度から研究でき、担当者の研究に役立つだけでなく、自分自身と皆の研究のためにも大いに役立つようになった。
6人の平均年齢は優に70を超えた。だが、こういう共同作業は悪くない。
できあがった「政策提言集」を見ても、その筆致は結構若々しい。
後は、「まな板の鯉」。サイト読者のご審判に委ねるのみだ。
50年前、私はバリケードの中にいた
若林盛亮 2022年2月5日
若林盛亮 2022年2月5日
「50年前、私はバリケードの中にいた」
鹿砦社の松岡利康社長から送られてきたデジタル版「鹿砦社通信」にあったご本人の言葉だ。
松岡さんは70年同志社入学組、「遅れてきた全共闘世代」に当たる。
松岡さんは同志社版全共闘である「全学闘」の中心にいた人、1972年に学費値上げ反対闘争を学生大会で決議しバリケード封鎖を貫徹、逮捕された人だ。その闘いは多くの学生の支持を受けながら機動隊のバリ解除と闘い、退潮期の当時としては画期的盛り上がりをみせた闘いだった。
「少なくとも私は、この50年間、時にだらけたり時に絶望したり、いろいろなことがあったが、その闘いを貫徹できた矜持を持って生きてきたつもりだ」
こう松岡さんは語っている。おそらくこれが松岡さんの人生の原点なのだろう。
私にも同様の体験がある。
1970年1月の東大安田講堂死守戦の闘いだ。
18、19日と二日間に及ぶ闘いだったが、私は講堂内部を任された同志社部隊の持ち場を勝手に離れて東京の学生達のバルコニーでの闘いに合流した。そこには1月の寒空の下、機動隊の放水の中で闘う多数の学生がいた。寒風の中で放水を浴びるのは辛い、ましてや交代時、一つの石油ストーブを囲んで暖をとった後、まだ湯気の立つジャンパー姿のまま再び放水の待つバルコニーに出ていくのは容易なことではなかった。でも誰も「もういやだ」という人間はいなかった。
これは私の貴重な体験だった。この体験があったからその後の逮捕、起訴で8ヶ月に及ぶ長期拘留にも耐えられた。そしてそれ以上の覚悟が問われたよど号ハイジャック闘争も貫徹できた。これは紛れもない事実だ。
寂聴さんは「青春は恋と革命」と言った。異性に恋するのが恋愛なら政治に恋するのが革命だ。恋とは誰かに何かに必死になることだ。青春期は未熟、だから必死になっても「失恋」することが多い。でも必死になればこそ「失恋」から教訓も得て前に進める。
あの時代は「明日のジョーの時代」だと言われる。叩かれても叩かれても立ち上がる「明日のジョー」、松岡さんも私たちも、そしてあの時代を生きた同世代はいまも闘いをやめない。
今は「戦後日本の転換」点にあると言われる時代だ。
ベトナム反戦、反安保、学園の民主化を掲げ、戦後日本の矛盾を問い闘った世代が老いたりとはいえ、あの闘いの決着をつけるときに来ている。新しい世代にあの闘いの失敗は失敗として認め教訓を伝えつつ闘いは新しく継承発展されなければならない。
もうじき「よど号」ハイジャック52年になる3月31日を迎える。この日を「明日のジョーの時代」を生きた世代が、原点を確認しつつ今日的意義があるような「戦後日本の転換」を語り合える場にできないか考えている。
なんとか若い人、新しい世代にバトンを継ぐ場にできないか、みなさんと考えていきたいと思う。
春のきざし
赤木志郎 2022年2月5日
1月20日の大寒が過ぎると、最低気温がマイナス15度以下になる日がなくなった。そして、2月1日の旧暦の正月。この日、どさっと雪が降りつもり、雪が以前のようなさらさらしたものでなく湿り気のある重い雪だったので、衛星アンテナの掃除が一苦労だった。雪の変化からも春に一歩ずつ近づいているのがわかる。
まだ寒くても春が近づいているのが分かるのは、まず光からだろう。旧正月を新春というようにその頃から眩しい光が溢れる。
暦では旧暦(陰暦)が季節感をぴったり表していると思う。そういう意味では、季節感に敏感な日本人にとって新暦とともに旧暦を併用しカレンダーに示し、旧暦に由来がある祝日も旧暦に従ったほうが良いのでないかと思う。
8月15日のお盆も元来は旧暦の日をさし、新暦では10月ごろになる。田舎に帰って墓参りするなら旧暦ではなくてならないはずだ。七夕の日も旧暦の7月7日であって、新暦の7月7日ではない。1月15日の成人の日も旧暦の1月15日の最初の満月の日のことだ。それを新暦にそのまま移し、おまけに日曜日の休日に合わせて、成人の日とした1月15日の由来がまったく分からなくなっている。
こういうことになったのは、明治維新直後、明治5年に突然、旧暦を捨て、太陽暦に変更したためだ。いわゆる、「万国公法」に合わせるためだったそうだ。
新暦は時を正確に刻む意味で便利なものだ。しかし、効率第一だけで考えるのでなく、成人の日など数多くの祝日が土日の休みの日との関係で毎年、変えてしまうのはどうかと思う。自然の時を刻む暦という大切な性格から、旧暦に由来する祝日は元来の旧暦に合わせるべきだろう。そうすれば、もっと季節感を深く味わえるのではなかろうか。旧暦の正月を迎えながらそういう思いに耽った。
まるで浦島太郎ですが
魚本公博 2022年2月5日
BSの旅番組でバナナマン日村が私の故郷・別府でグルメ探しをするものがありました。「別府にきちょるけん○○食べてかんと」(別府にきてるから○○食べていかなければ)と大分弁で書いたパネルに、通りがかりの人に○○を推薦してもらい食事するという趣向です。
正確に言えば「食べてかんと」は「食べちいかんと」ですが、関西風なまりが入って、「食べてかんと」になっているのかもしれません。別府は昔から移住者が多い所で、戦前は、北九州からの移住者が多かったのですが、戦後は関西からの移住者が増えましたから。
これまでテレビで紹介される別府の風景は、「別府の湯けむり」の鉄輪地区のものが多かったのですが、この番組では、別府駅周辺の繁華街が写っていて昔とは随分違っていましたが、なつかしかったです。
別府のグルメと言っても、ラーメンとか、しゃぶしゃぶとかで、郷土食という感じではありません。元来の郷土食では、「団子汁」(すいとんのようなもの)やブリの切り身を使った「お茶漬け」、具をオムレツ風に閉じた大分風「お好み焼き」などありますが、そういうものは、出て来ず、ちょっと残念でした。
興味を引いたのは、冷麺。本場、朝鮮で作るのと同じように製麺器に小麦粉、そば粉を錬った塊を入れ押し出した麺を使ったものでバナナマンも、これまでの冷麺とは全然違うとご満悦でした。
「別府グルメ」、大観光地なので全国から腕に自慢の料理人が集まってくるのでしょうが、全国共通のものを地元の食材で美味しく作り、本場の手法を取り入れて差別化を図るなど、苦労がしのばれます。
久しぶりの別府、街の様子も言葉も食べ物も昔とは違いますが、考えてみれば私の知ってる別府は50年前のもの。まるで浦島太郎ですが、別府の今を見ることができ、うれしかったです。
朝鮮でも幼稚園からの英会話
森順子 2022年2月5日
朝鮮の小学校は数年前から、子どもの資質と個性を伸ばす目的で多様なサークルをつくりましたが、一番の人気サークルは英語なのです。今では試験的に幼稚園でも英語教育を実施し、小学校では、中国語と英語の2カ国語を行っている学校もあります。私たちの知り合いの孫娘も、まだ2歳だというのに、ABCD・・・から始まる「英語のうた」まで、うたうのですから、さすが英語は世界共通語だと再認識させられます。
日本でも英会話ができれば、と思う人は少なくないはず。NHKの朝ドラ「カムカム・・・」などは、主人公と英語とのつながりが見どころですが、もしかしたら隠れた主役は英会話かもしれないと思えるくらいです。
ラジオでの英語講座の講師40年という先生は、英会話とは英語で会話することだが、日本では、それを越えた様々な意味合いや思いが込められてきた、戦後の日本人が抱いたアメリカへの強い憧れがあり、それが英会話に凝縮されていると言っていましたが、そうなのかも知れません。でも今は、アメリカンドリームも崩れ去り色あせた国となったアメリカを認識していましたが、日本人のアメリカに対する親近感度が、とても高いのは意外でした。これも英会話効果かしら。日本人も欧米人のように、じゃんじゃん意見を言い、臆せず、恐れず、より大らかに英会話と向き合おうということでしょうか。
そのためにも、まずは日本語できちんと意見が言えることが前提。日本語会話の力も磨き、自分の考えをもち英語で発表できる英語学習者になることでしょう。
素晴らしいラブソング-「Fields Of Gold」
若林盛亮 2022年1月20日

日本人村2022/1/19撮影
新春、日本も世界もオミクロン蔓延で苦しむモノクロトーンの中、少しカラーなお話を。
最近、素晴らしいラブソングに出逢った、それは「Fields Of Gold」。1980年代以降活躍した「ポリス」というバンドのリーダー、スティングが作った歌。
彼が移住した英南西部の町に広がる大麦畑を風がそよがせる、それはまるで風が大麦を愛してるようだった、この光景からこのラブソング「Fields Of Gold」が生まれた。かのビートルズのポール・マッカートニーが「この曲が僕の作った曲だったらよかったのに」と嫉妬したというが、歌詞もメロディも素晴らしい! の一言に尽きる。遙か遠い昔の恋を想う歌だ。
♪ 軽々しい約束はしないが・・・
でも残された日々 僕たちは
黄金の世界を歩もう
これだけは誓おう ♪
たいていの初恋とか青春期の恋は成就しない。人生途上の青春は未熟、サナギが蝶になるために脱皮をするように恋も脱ぎ去らねばならないときが来る。これは多くの人が経験する青春の法則みたいなものだろう。青春とは試行錯誤の時期、だから青春期の恋は熟成にはほど遠く永遠というわけには行かない。「軽々しい約束はしない」、いやできない。
寂聴さんは恋の必要を説きながら「でももっと大事なことは失恋することよ」という素晴らしい言葉を遺してくれた。「失うこと」で得られるものがあるということだ。ある意味、青春とは失恋の繰り返しなのかもしれない。
何も男女の恋だけに限らない、理念や信条、行動にしてもそうだ。恋して「失うこと」、脱皮を繰り返して人は成長し大人になる。
だから青春期に誰かに、何かに恋をすることはとても大切なことだと思う。
♪ きっと君は僕を想う
風が大麦をなでるとき
嫉妬する空の太陽に言うんだ
黄金の世界を歩んだと
輝く世界を歩んだと
二人の黄金の世界 ♪
歳月を経て遙か遠い昔の恋をこのように想える人は幸せだ。
何かに恋をするとは何かに必死になること、「黄金の世界を歩んだ」と「空の太陽に」言えるような時間を過ごすことだ。
若い人にはそんな恋をしてほしいと思う。失恋してもいいから・・・
キムチ
赤木志郎 2022年1月20日
周知のようにキムチは朝鮮料理には欠かせないものだ。冬の漬け物としてかならず食卓に出る。朝鮮に住むようになってキムチを頂くが、唐辛子のからさが馴染めず、かなり長期間食べなかった。日本にいた時白菜漬けは好きだったが、キムチはちょっという感じだった。
唐辛子の入っていないキムチもある。白キムチだ。唐辛子が南米から入ってくる(17世紀)前の元祖キムチだ。日本の白菜漬けに似ているが、発酵の程度が異なる。かなり漬け込んでいて発酵もきつい。商店で各種キムチが販売されるようになったので白キムチも入手できるようになった。時々、購入している。
ところで、私たちの村の食堂で漬け込んだ今年のキムチが抜群に美味しい。家に持って帰って食べているくらいだ。発酵の程度がちょうど良いようだ。寒さがきついのも影響しているみたい。冷蔵庫に保管すると美味しいのに食卓の上に置いたままだそうでもないからだ。
今年のキムチは唐辛子もよく合っている。キムチの赤い汁も美味しい。で、この冬、雑煮にもキムチを入れ、朝食にもパンとキムチを食べ、毎日、キムチづくしだ。やめられない。なぜ、ちょっと酸っぱいキムチが好きになったのか。健康からなのか、そんな気もするか分からない。
未来のデザイン
魚本公博 2022年1月20日
朝日新聞の1月1日一面は「未来のデザイン」。プロローグから始まり、野生、仕事、いのち、つながり、グリーンと続いた記事は6日で終わりましたが、まとまりがなく、とりとめのない不思議な特集でした。
問題意識としては、13世紀に起きた欧州の人口の3分の1が死亡したとされるペストのパンデミックで労働人口が激減し、農奴による荘園制が維持できなくなり、農民の土地私有を許す封建制度に移行したように、コロナ禍でこれまでのシステムが維持できなくなって新しい社会が到来するということがあるようです。
これについては、長崎大の山本太郎教授の「パンデミックは不条理な死を引き起こす。死の原因を社会の矛盾に求め、その矛盾を問い直す動きが起きる」という言葉を引用して、それは感染症による変化というよりも、すでに始まっていた変化の加速だととらえると解説しています。
事実、コロナ禍では、貧困層ほど打撃を受けました。多くの人が「死ねと言われているようだ」という状況に追いやられ、自殺者も急増しました。
ところが特集は、デジタル化で仕事の仕方が変わったとか、困難な中でも「頑張っている」人たちを紹介し、こうした小さな取り組みの中に未来があるのでは? という感じで終わってしまいました。
問われているのは、コロナが暴き出した社会的矛盾です。戦後社会の矛盾、戦後民主主義の矛盾などであり、少なくとも新自由主義による格差拡大の矛盾と、その解決を描く「未来のデザイン」こそが問われていると思います。
今年は、そういう根本的な変化をどうデザインするのか。そいうことが問われてくるのではないでしょうか。サイトでも、そうしたことを発信していきたいと思います。
簡単で、栄養満点のサムゲタン(参鶏鍋)
若林佐喜子 2022年1月20日
-300x200.jpg)
サムゲタン(参鶏鍋)
雪の多い日が続く、今日この頃です。早いもので、新しい年が始まってすでに半月がたちましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
近況報告が遅れましたが、今年の新年会のメイン料理はサムゲタンでした。丸ごとの鶏の中に、インサム(人参)、もち米、なつめ、くり、五葉松の実、銀杏などを詰めて長時間、煮込んだ朝鮮料理です。レストランでもなかなか食べられませんでしたが、昨年、パック入りの箱で店頭に並ぶようになりました。私たちも、今回、味わうのが初めてで、みな興味津々でした。パックの封を切り土鍋に移してあつあつに煮立ったら、食べごろです。肉がとろっと柔らかく、味も濃厚で美味しい。小骨もそのまま食べれる(軽く噛むとぼろぼろと砕ける)ので、カルシウムの固まりを摂取しているという感じです。元来は、とても手間と時間がかかる料理なのに、パック入りは実に簡単で美味しく、みな大満足でした(笑)。
大きなお皿に山盛りの豪華な海老、バター味付けのホタテ貝などなど。デザートの国産のスイカは「これまでで一番甘い!」との声が出るぐらい甘かったです。クリームあんみつとお汁粉もあったのですが、みな、もうーお腹が一杯で、これ以上は無理とお汁粉は翌日に・・。よく食べ、お腹がいっぱいの新年会でした。
「金」
小西隆裕 2022年1月5日
昨年を表す漢字一文字は、「金」だった。
オリンピックの金メダルラッシュ、大谷翔平や藤井聡太の金字塔から来たようだ。
納得だ。
ところで、この「金」に共通しているものがある。
それは、「若者」だ。
今、若い人たちが元気がいい。
そこで思うのは、デジタル社会、デジタル時代だ。
どうもこの「デジタル」というやつは、若者と結びついている。
ここ朝鮮でも、IT社会、IT経済、いや政治も文化も、その根幹を若者が背負っているという気運のようなものを感じる。
われわれじいさん、ばあさんも負けてはいられない。
が、これもわれわれの世代の「個性」だと思うのがよいような気もする。
「黒船の時代」の新年に「よど号」映画がやってくる!
若林盛亮 2022年1月5日
ピョンヤンの新年は、例年のごとく金日成広場での野外音楽公演と打ち上げ花火で明けた。広場を埋め尽くす数万の観衆の歓呼は圧巻だった。私たちはTV視聴。
こうして幕を開けた新年に届いたメール年賀、その一つに「おっ」と思うのがあった。
「今、一番やりたい題材は『よど号ハイジャック事件』。これはもう本当にいろんな要素があって面白いんです」とネットのインタビューで堤幸彦という映画監督が語ったという情報。
その面白さの根拠は「翻弄される日本政府の情けなさや、裏にあるアジアの政治体制、アメリカの動向などもテーマになってくる」ということらしい。
この「面白さ」を今、取り上げるべき理由を堤監督は次のように述べている。
「今は、いろんな意味で黒船の時代なので」と。
この「黒船の時代」と今の時代相をとらえているところが興味深い。
周知のように今、日本は「米中対決の最前線」とされ新年から岸田政権は「米中新冷戦体制」づくりを本格化させることが予想されている。しかしながら中国と深い経済関係にある財界、あるいは専守防衛放棄と攻撃武力化を押しつけられ最前線の「尖兵」とされる自衛隊内には動揺が走っているであろうことは容易に想像されることだ。これは「黒船来襲」に匹敵する米国による「戦後日本の泰平の夢」を破る一大事件だ。
「よど号」の時も日本政府は右往左往させられた。
その最大の原因は「よど号乗客」に米CIA要員がいたからで、米国は絶対にピョンヤンへ行かせてはならないと圧力をかけてきた。それが福岡空港に着陸させたり、韓国に誘導させたりとなった「よど号の迷走」の基本要因だった。
これは鳥越俊太郎氏の独占スクープ「よど号ハイジャック事件、40年目の真相」やNHK「アナザーストーリー」取材で明らかにされた事実だ。番組では当時の韓国軍空港管制指令官を勤めた当事者本人が米軍の指示で「よど号」を38度線を越えたかに見せかけてソウル金浦空港に誘導したと証言している。
膠着状態の金浦空港で乗客代表の方が機内の無線での金山駐韓日本大使とのやりとりで「なぜ早くピョンヤンに飛ばせないのか」と詰問したところ金山大使は「韓国側の事情もあるので」と逃げたが、事の真相は米国の圧力があったからだった。
堤幸彦監督の言う「翻弄される日本政府の情けなさ」とはこのことだろう。
今まさに堤監督の言う「黒船の時代」、「戦後日本の泰平の夢」をうち破るような黒船来襲で日本の動向を左右する決断が日本国に問われる時期。改憲、敵基地攻撃能力保有と日本の進路を左右する問題が米国から突きつけられている。
だからこの新年は「黒船」にどう対処するかが日本国民に問われる時となる。
堤幸彦監督の「よど号ハイジャック事件」映画がこの問題に一石を投じるものになることを願うばかりだ。当然、圧力、妨害はある、映画会社、TV会社は腰が引けるだろう。それを想定し堤監督はこう語っている。
「理解ある若いプロデユ―サーと組めないか、模索しているところです」
堤監督、なんとかこの映画を世に出してください!
行く先のない年賀状
赤木志郎 2022年1月5日
コロナ禍により朝鮮が郵便物を遮断して二年経った。困ったのは年賀状だ。メール住所がある人はメールで出せるが、メールを使わない人もいる。そこで、メールで国内から年賀状を出してくれるよう依頼をした。
ところで、その返事では、依頼した宛先の大塚美春さんは昨年、亡くなったとのこと。大塚美春さんは植垣さんの救援活動をし、「悪党通信」などを保障した人だ。連赤事件の集いにも参加していた。「田中義三さんとのお別れ会」でピアノ独奏してくれた。
私は大塚さんと二〇年間も毎年、年賀状と暑中見舞いを交換してきた。大塚さんの独特な知的香りに魅了され、励まされていた。それが途絶えるとは・・・。
今年は連赤五〇周年となる年。大塚さんにとって連赤はどうだったのか。一言、聞きたかった。しかし、微笑んで何も言わないだろう。もがき苦闘した若い魂たちをその微笑みで優しく包んでくれているのだろう。私はそう思う。
行く先のない年賀状は天国に舞い上がったのだろうか。どうか安らかに、大塚美春さん。合掌
お餅を共有する私たち
魚本公博 2022年1月5日
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
年賀状の定番の文句ですが、そんな麗しい年賀状の習慣も最近はネットで発送に変わっているそうですね。それって、年賀状画面にして送るのですか、それとも文字だけですか。
それはともかく。今年も年末から正月にかけて、雑煮三昧でした。
年末にCool Japanで「餅」をテーマにして、そこでも雑煮が取り上げられていましたが、雑煮は地方ごと地域ごとに特色があり、何千あるのか分からないほど多様なのだとか。
私は大分県出身で家では丸餅に醤油味で食べていましたが、関東圏の四角餅の雑煮などは今でも不思議な感じがします。
朝鮮でも餅はよく食べられます。酒で発酵させて鈴の形のようにし餡(あん)を入れた蒸餅。四角にして煮豆やゴマをふりかけたもの。餃子のような半月形にして餡を詰め油を塗った松餅(ソンピョン)など色々あります。日本で言えば、餅菓子のようなものでしょうか。
日本とちょっと違うのは、餅米だけでなく粳(うるち)米を使うこと。中国でも粳米を使った餅が多いとか。その上、小麦粉を使った月餅(げっぺい)も餅だそうですが、「餅は餅米で作ったもの」とシンプルに神髄を生かして、雑煮のように具や汁で多様化するなどは、日本文化の特徴を表しているようで面白いです。
餅は、中国と周辺の国々など東アジア特有の食べ物だとか。米中新冷戦で対中国だけでなく、対朝鮮、対韓国と敵意を煽っていますが、食という根元的なところでの近さ。そういう近さで周辺の国々と仲良くする。それが本来の姿だし、そこに日本の未来もあるのではないでしょうか。
「新冷戦」「新冷戦」の一年だった
小西隆裕 2021年12月20日
「米中新冷戦」で明け、「米中新冷戦」で暮れた一年だったように思う。
別に、日本から送られてくるニュースや読み物が皆そうなっていた訳ではないのだが、私の頭がそうなっていたように思う。
そのため、ついに国内から、たまには別のテーマで原稿を書いてくれという苦情が来るまでになった。
私の頭では、いつも角度を変え、新しいテーマで書いているつもりだったのだが、読まされる方にとっては、たまったものではないのだろう。「新冷戦」という文字を見ただけで、「またか」となってしまったに違いない。
おかげで、「新冷戦」についての考察は深まったのではと思うが、それが自分の考えに閉じ籠もってしまった側面が出、「新冷戦」自体をもっと大きな視点、現実に即した視点から捉え返すという点では問題だったかも知れない。
少なくとも、苦情が来たのは総括の要ありということだ。
歓呼の観衆に背を向けた名将
若林盛亮 2021年12月20日
スティーブン・ジェラード、サッカー・ファンなら誰もが知る名前だろう。朝鮮のスポーツ専門チャンネルでも「世界の名手」の一人として紹介される世界的なサッカー選手だった人。
何を隠そうこの私が敬愛してやまない人でもある。部屋には彼の背番号「8」ユニフォームを飾っている。
ジェラードはそのサッカー人生すべてを英プレミア・リーグの古豪、リヴァプール一筋に捧げた選手、KOPと呼ばれる熱狂的なサポーターからは「リヴァプールのレジェンド(伝説)」「永遠のキャプテン」と絶大の尊敬と愛情を集めている人だ。私もジェラードがいるからリヴァプールの熱烈なサポーター、和製KOPになったようなものだ。
現役引退後、スコットランドのレンジャーズという古豪クラブで指揮を執る監督に就任、わずか2年で首位を独占していた強豪セルティックの牙城を破りこのチームにリーグ優勝をもたらした。選手としてだけでなく監督としても名将であることを遺憾なく証明。
そして今季、最下位付近をさまよい不振にあえぐアストンビラの監督としてチーム再生を託され、ジェラードは英プレミア・リーグに帰ってきた。すると就任後、たちまちチームに3連勝という奇跡を起こさせるマジックをやってのけた。
12月11日、このアストンビラが彼の古巣リヴァプールと対戦した。それもリヴァプールのホーム・スタジアム、アンフィールド競技場で。
試合当日、敵将としてアンフィールドに帰ってきたジェラードに対し、会場を埋め尽くした数万のリヴァプール・サポーターは熱烈なスタンディング・オペレーション(総立ちで拍手)で自分たちの英雄、レジェンドを迎えた。これにジェラードは手を振って応えた。
ところが試合は1:0とリヴァプールの勝利に終わり、ジェラードは敗将となった。試合後、リヴァプール・サポーターはジェラードのチャント(賛歌)を歌い出した、彼への崇敬の念を込めて。ところが当のジェラードはチャントの観衆に挨拶も返さず背を向けたまま素っ気なく競技場を後にした。
惨めな敗戦に悔しい思いでいっぱいのチームの選手達と自分は一心同体、「私はアストンビラの監督・ジェラードなのだ」! こう言いたかったのだろう。
この光景を思い浮かべる私のジェラードへの崇敬の念は倍加した。選手としても監督としても、そして人間としてジェラードは超一級の人だ。
これからはアストンビラも応援しようと思う。
ジェラードは永遠なり!
ちょっと不愉快
魚本公博 2021年12月20日
最近、日本の新聞やテレビでやたら難しい英語に出会うようになった気がします。ギフテッド(特異な才能がある)、フード・デリバリー,PPP購買力平価、働くインセンティブ、DX(デジタル・トランスフォーメーション)、VR(仮想現実)、コンペティション(競争)、クローズド・キャプション・・・。よくわからず聞き流しているので、ここに記すこともできない言葉がたくさん。
先日、新聞で見たのは、ギグワーカーという言葉。説明ではフリーランスで働く人のことで、ネットを使って仕事の委託を受けて働くような人のことを言うらしい。ところが私はフリーランスというのは、小規模な商売などをときどきやるような働き方を指していう言葉だとばかり思っていました。
一事が万事、そうした感じで、自分なりに、こんな感じなんだろうなで済ませている。辞書で調べようにも、今持っている辞書には全くなく、どうしようもない。
言葉が分からないと時代においていかれそう。色々な格差がいわれますが、これでは言葉格差じゃないかと思ってしまいます。
今、教育では、グローバル人材の育成が叫ばれ、英語力強化に力がいれられているとか。それもあって、英語の氾濫なのでしょうが、時事番組で、親米的な人たちが、やたら、こちらの分からない英語を得意顔で使うのを見ると、親米こそ時代の最先頭と言ってるようで、ちょっと不愉快になります。
米中新冷戦でアメリカ側につく、というのが、こういうところにも表れているのかもしれません。昔はこうじゃなかったと年寄りじみたことは言いたくありませんが、何とかならないのかと思います。
よど号ライフも、今年はこれでおしまい。次は新年の1月5日。それまで皆さん、よいお年をお迎えください。
「オミクロン」株の出現と国の責任
小西隆裕 2021年12月5日
オミクロンというコロナ変異株が現れた。
今度はこれまでの変異株にも増して悪質だと言う。
感染率、重症化率が高いだけではない。
これまでのワクチンが効かないようだ。
日本に来たナミビアの外交官は、オミクロンにかかっていたのだが、ファイザーのワクチンを二度接種していたと言う。
これは大変なことだ。
これまでのコロナ対策のゼロからの見直しにさえつながりかねない。
折しも、日本ではコロナ感染率が下がっている。
今こそ、国は「ウィズコロナ」から「ゼロコロナ」へ、コロナ対策のあり方そのものの根本的転換に踏み切る時なのではないだろうか。
それが国としての国民への責任だと思う。
ピョンヤンの理髪師-その3「私のサービスはこれよっ」!
若林盛亮 2021年12月5日
11月末の陽射しのうららかな日、床屋に行った。ひいきの例の「ピョンヤンの理髪師」のお店。
店に入ると先客が二人もいた。しばらく外でぶらぶらしてから店に入った。まだ先客の一人が理髪中だったので待合室で待った。
手持ちぶさたでテーブルを見ると、カップ入りのポップコーンが置いてあった。前にも薔薇茶のおもてなしを受けたので、これでもかじりながら待つかと理髪作業中のアジュモニ(おばさん)に「これ食べてもいいの?」と聞いてみた。「だめ、それはお客さんのもの、食べちゃいけませんよ」とたしなめられた。
客が帰って理髪台に座ってから「どうも失礼を。前にお茶をごちそうになったから、てっきりアジュモニのサービス精神かと思って・・・」と弁解した。するとアジュモニは「あっはっは」と笑って、「私のサービスはこれよっ」! とハサミをチョキチョキさせて振った。
私のような短髪のカットは長髪よりも手間がかかるのだそうだ。他の店ではまずバリカンでざっと短くしてからハサミで手を入れていくことが多い。でもこの理髪師アジュモニは裾刈だけバリカンでやって後は全てハサミでていねいに刈り込んでいく。
私の場合、丸刈りはもちろん若者風の角刈りになってもいけない、丸みを帯びたカットにするのがコツなんだとか。散髪中に私の頭を右っ、左っとか「まっすぐ立てて」とか鏡をにらみながら丸みを帯びたカットに余念がなく、ハサミをたんねんに動かし続けている。それもとてもスピーディ。
できあがりを鏡で見せて「ほうら、穏やかないいハラボジ(お爺ちゃん)になったでしょ」とハサミを持って鼻を高くするポーズ。それがとてもチャーミング、「私の究極のサービスはハサミ」! という意思表示。
またまた「ピョンヤンの理髪師」のプロ魂を見せつけられた。
このアジュモニはいつも私に新鮮な驚きをくれる大切なピョンヤンの友人。
お粥
赤木志郎 2021年12月5日
歳とともに好みが変わるようだ。以前はご飯が好きだったのに、最近は自炊するときもっぱらお粥を作っている。水を5倍ほどいれ、噴いてから、鍋のフタをとって10分ほど煮る。最後に卵をかきまぜ、具をいれる。具は煮ジャコであったり、納豆、ソーセージだったりする。そしてネギをいれて出来上がり。味つけのため醤油をかけたりする。簡単でホカホカのお粥が頂ける。
沸き立つお粥を眺めてみると、こうした料理法は弥生時代から多くあったのではないかと思った。米はご飯だという定式みたいに考えてきたが、ご飯でも混ぜご飯があり、お粥はもっといろんな具を入れて煮ることができる。そうするとバリエーションが増える。
中国料理ではお粥が米料理で最高のものとして位置づけられ、祭日に手のこんだお粥を作る習慣があるという。日本では関東ではほとんど食べず、関西で冷や飯をお粥にする習慣があるという。
私は、消化に良いし作るのに簡単なのが気に入って始めたが、知識不足でさまざまなお粥を作れないのが残念だ。本にはいろんな粥の作り方が書かれてあるが、慎重な私はなかなか取り組めない。これから寒い冬、もっと工夫していろんな具を入れ、あつあつのお粥で過ごしたいと思っている。
このシステムは守って欲しい
魚本公博 2021年12月5日
BS朝日の番組「魚が食べたい」を時々見ます。副題は「地魚さがして3000港」。漁港が3000もあるとは驚きですが、島国、日本ならの光景でしょう。実際、番組で見ても、地方の小さな浜辺のいたる所に漁港があります。
感心するのは、その流通システム。旅番組で欧州の漁港が出てきますが、朝、漁船が港に帰ってくるころ人々が集まってきて、岸壁で売り買いするようなのがほとんどです。世界三大漁場を控える北欧でも港の近くに朝市のような市場が立って、そこで売るようになっている程度です。
日本の場合は、ほとんどの漁港に市場があって、そこで競りに掛け、ただちに流通経路に乗せ、その日のうちに全国に配布するシステム。世界の料理人がうらやむ、そのシステムで寿司や魚介類を特色とする日本料理も成り立っています。
番組で出てくるのは、ほとんどが沿岸業の漁港ですが、その漁のシステムもなかなかのものです。早朝に出漁する時間が決まっていて、出発の合図で一斉に港を出て業場に向かうとか、前日にくじ引きして漁場を決めるとか、自然保護のためにA班、B班に分けて一日交代で出漁するとか共同的で規律的です。禁漁期日もよく守られていて、伊勢エビなどは解禁期日があり一日の漁獲作業も2時間。時間になると、さあ時間だと終わって時間厳守です。
今後、世界の食糧難が予想される中、アマゾンなどが日本の海産物市場に目をつけているとか。ネット販売で新鮮な魚を直接食卓にというわけですが、そうした米国企業の思惑に負けず、日本のよきシステムを発展させながら守っていってほしいと思います。
今年もお世話になりました
森順子 2021年12月5日
もう今年の終わり月がきました。一年が早いです。コロナで代表団は、ここ数年訪朝できず日本からのお客さんには会えず話ができないことは、私たちにとってやはり痛手です。でも国内の方たちからは、新聞や書籍やいろいろな情報を毎日のようにメールで送ってもらっています。それも、もう何年も毎日のように継続してくれていることにも頭が下がります。いつも自国が身近に感じられるのも支援してくれる方々がいるから、そのおかげで考えることも話もいつも日本のこと。また、今年、一番うれしいことは、支援者をはじめ私たちの知人や身内が、誰一人感染せず元気にいてくれたことです。思い出せば、私たち皆、心配と不安のなかで過ごしていたんじゃないかと思います。来年もどのような状況になるのか分かりませんが、国内の皆さんが健康で元気に過ごされることを祈りながら、よい年をお迎えください。
ミニ植物園が登場
若林佐喜子 2021年12月5日
日本人村の柿の木も根っこにわらを巻いてもらい冬支度です。
代表団を迎える宿所の部屋にミニ植物園?が登場。小さい鉢植えのきりん花、ゴムの木、カクタス、ケイランなどが置いてあります。
建物の管理をしてくれている孫娘のような彼女が、植物は鑑賞用にも良いし、健康、特に目の疲労回復に良いとせっせと増やしてくれているのです。植物好きな安部さんの植物も大分、加わっているようですが・・(笑)。根づかせて各部屋に置いてくれるとのこと。私は、すでにミニサボテンと葉の模様を楽しむケイランを貰い受け、事務所の窓際に置いて癒し気分に浸っています。
朝鮮では、ここ数年、菊の花、バラ、ガーベラ、ユリ、カーネーションなどの花をはじめ色々な種類の観賞用の植物が街角のキオスクで売られています。先日の「オモニの日」にも、そんな色とりどりの生花の花束を抱えた人々の姿を多く目にしました。我が日本人村、ミニ植物園もまだまだ種類が増え、yobo yoboたちの健康とリラックスに貢献してくれそうです。
2日に、5センチ程の積雪がありました。一緒に雪かきもしてくれる孫娘のような彼女、ミニ雪だるまとウサギもつくり携帯で写真撮り。ついついほっこり気分にしてもらっている12月の私です。
感染力の強いオミクロン株が世界をはじめ日本でも発見され、水際対策、防疫体制が強化されていると聞いています。何かと忙しい師走、感染防止対策、寒さ・健康管理にくれぐれも注意し、乗り切られることを願っています。
二つの選挙に思う
小西隆裕 2021年11月20日
二つの選挙とは、もちろん、先の自民党総裁選と総選挙のことだ。
この二つの選挙がどうなるかは、いつもの選挙以上に関心があった。
そして結果は、思っていた以上だった。
危惧していたことが倍以上になって返ってきたという感じだ。
国民の思いに応えるというのは簡単ではない。
今、日本に問われていることを国民の思いに沿うようにどう訴えるか。
それをスローガンとして政策としてどう掲げるか。
それがよくできないと、いくら候補者の一本化をよくしても勝てない。
その真理を改めて思い返させてくれたのが今回の選挙だったのではないか。
闘いはこれからだ。
「改憲」をはじめ、「米中新冷戦体制」づくりとの闘いが待っている。
寂聴さんは人間臭い革命家・仏教者、素晴らしい人
若林盛亮 2021年11月20日
瀬戸内寂聴さんが99歳で亡くなられた。
作家・瀬戸内晴美が出家して尼僧になり京都嵯峨野の尼寺「寂庵」で仏法や人生を語り、反戦平和の活動にも熱心だったということなどで寂聴さんは少し気になる存在ではあった。でも彼女の本を読んだことはないし、それほど関心もなかった。だがこの間、訃報を伝える新聞に掲載された多くの人が語る寂聴さんの波乱の生涯、そして人生への真摯な姿勢に正直いって心を動かされた。
寂聴さんの波瀾万丈の人生は敗戦を出発点とする。寂聴さんは戦争で母を亡くしてもいる。
「正しい戦争と教えられ、それを信じてきたが、戦争に負け、自分の愚かさに気づいた。これからは自分の心で感じたことだけを信じて生きていこうと決めた。それが私の戦後の革命だった」
「私の戦後の革命」! このきっぱり言い切った言葉にとても感動した。
「戦後の革命」の第一歩として寂聴さんは夫の教え子だった青年と恋に落ち、よき妻、よき母を捨てて、憧れだった文学の世界に進んだ。父親からは「どうせ鬼になるなら大鬼になれ」と言われ、この言葉を胸にその道を迷わず突き進んだ。
寂聴さんは作家「瀬戸内晴美」として、時代に翻弄されながらも自我に目覚めた女性たちの人生を小説という形にしていった。主人公は、無政府主義者・大杉栄の妻として憲兵隊に虐殺された女性解放運動家の伊藤野枝、大逆事件で死刑になった菅野スガ、新橋の芸者から尼僧になった高岡智照など古い時代観念に流されない信念と潔い生を貫いた女性達だった。
しかし人気作家となった「瀬戸内晴美」は理想とする文学とはほど遠くなっていく。そんな自分を叱咤し「バックボーンとなる思想を身につけたかった」と51歳になって仏教の世界に飛び込む。これが尼僧「寂聴」としての新しい人生の始まりだった。
波乱に満ちた寂聴さんの人生、それは書き続けるための革命だった。
寂聴さんは語る。
「まだお母さんともしゃべれない幼い娘を捨てて文学の世界に飛び込んだから、書き続ける責任がある。私は幸せになっちゃいけないの」
この言葉は私にはズシンと重い。
私は高3の頃に自我に目覚め、寂聴さん風に言えば「これからは自分の心で感じたことだけを信じて生きていこうと決め」、優等生であることをやめた。敗戦で戦後日本は価値観が180度変わって大人達も混乱していた。親や教師、大人の言うことに従順だった自分がただ流されるまま生きていくことが怖くなった、ただそれだけのことだった。でも私は寂聴さんにとっての「文学」というような自分の目標を持てずにいた。だからあっちに転がりこっちにぶつかりしながら、ようやく学生運動に巡り会いよど号ハイジャックで朝鮮へ飛翔、と続く紆余曲折の「私の革命」の果てに今日に至っている。
「私の革命」の道はまだ遙か遠い。「私は幸せになっちゃいけないの」と言い切れる無私の境地にはもっと遠い。でもこれまで出会った幾多の恩人達、不義理を重ねた人たちに報いるために私にはこの道を歩き続ける責任がある。
絶えず自分を叱咤するのよ! 改めて寂聴さんに教えられたように思う。
寂聴さんは若い人たちにこんな教えも遺している。
「青春は恋と革命」「100冊の本を読むよりも1回の恋」
いいお婆ちゃんになってこんなことを言えるのはいいなあと思う。人間臭い革命家・仏教者の寂聴さん、なんて素晴らしい人なんだろう。
古希を過ぎて寂聴さんのような方を知ったことを幸せに思う。寂聴さん、どうかあの世から私を監視してください。
母の日
赤木志郎 2021年11月20日
先日16日に朝鮮での母の日があった。第一回母親大会が開かれた日だ。日本や国際的には5月の第二日曜日を母の日とし、赤いカーネンションを贈るのが慣わしになっている。
この日、市内に出てみると、花束をもった人たちが行き来している。食堂は母親を囲んでの家族づれで湧きかえっていた。TVを見ると母の日一色だった。劇場でもその舞台がもたれていた。3月8日の国際婦人デーが主に職場で祝われるのにたいし、母の日は文字通り息子娘たちが祝う。
しかし、私が母を慰労したことはない。むしろ、大学1回生のとき母を亡くしたとき、多くの学友が葬式にきて私を慰めてくれたことのほうが大きい。家には小中高時代の友人たちが葬式に来てくれた。そのうち遺影の前でS君は詩吟を詠ってくれた。S君は小中学校時代の親しい友人だった。そのなかの一句「一億人の母がいようとも自分には一人の母しかいない」というのを今でも記憶している。大学ではクラスの級友は一升瓶をもって来て生協の一室で慰労会を開いてくれた。私は飲みつぶれてしまった。一升瓶を抱えてやってきた級友の姿を今でも覚えている。
級友たちが慰めてくれればくれるほど、私は母の苦労を察し、なにかしてやれたのか、心配ばかりかけただけではないかと悔やむしかなかった。その悔やみは歳月を重ねるほど深まっていく。
だから、母の日に人々が祝っている姿を見ると羨ましく思うのである。そして、できるだけ祝ってあげてと願うばかりだ。
ケツメイシ
魚本公博 2021年11月20日
秋も終わりに近づき、黄色に紅葉した銀杏の葉も一挙に散ってしまいました。朝には零度以下になることもあり芝生にも霜がおりて、いよいよ冬到来の季節です。
よど農園も最後の収穫。とは言っても大根、ホウレンソウ、ゴボウくらい。それとすっかり枯れた里芋も根の部分は凍結するほどではないのでまだまだ収穫可能です。そして、ケツメイシ。正確にはケツメイシは漢方薬としての名であり植物名はエビスグサと言うそうですが。
ケツメイシは飲む目薬と言われます。最近、目のかすみなど視力低下で、パソコンの字が見にくくなって、これはいかんと、市場で買って飲んでいたもの。炒ったようには見えないので、植えれば芽吹くのではないかと思い春になって試しに撒いてみたところ、芽が出ました、成長すると1・5mほどの高さになり黄色い花が咲きました。それが長さ20㌢太さ5㍉ほどの細長い豆のようなサヤになり、その中に3mmほどの黒い種がぎっしり詰まっています。これを採って乾燥させて実だけを収穫。二畝ほどしか植えなかったのですが3升ほどにも。思ったより大量に採れたので、皆にも分けました。
このケツメイシ。インドではコーヒーの代用にするとか。確かに煎じると黒い液で苦みがあり、コーヒーっぽいです。気のせいか覚醒作用もあるようで飲むと頭もすっきりします。なかなか良いので、来年はもっと作付け面積を広げようと思っています。
日本もこれから冬。季節の変わり目には、とかく体調を崩すもの。コロナ禍の中、体に気をつけてお元気でおすごし下さい。
青い朝鮮人参
小西隆裕 2021年10月20日
最近、朝鮮の市場に「オクラ」が出回り始めた。野菜売り場の片隅に遠慮がちに売りに出されている。
森さんが見つけて教えてくれた。それで買ってみた。
それを十本くらい刻んで粥の中に入れ、みそ汁や卵を加え煮込んで食べると絶品だ。
トロッとしていて滋養分があり味も良い。
それで売り場のおばさんにどういう名で売り出しているのか聞いてみた。
すると、ただ「栄養食品」としか言わない。
それで二,三回買った後、どんな名を付けたか聞いてみた。
すると、「プルンインサム(青い朝鮮人参)」と言うではないか。
言われてみると朝鮮人参に形が似ている。それに健康食品だ。
なかなか良い名を付けたものだ。
この「プルンインサム」が朝鮮の人たちの食卓で人気を博するようになる日も近いかも知れない。
「AI No Katachi」-愛のカタチ
若林盛亮 2021年10月20日
「AI No Katachi」(愛のカタチ)という歌をご存知だろうか?
歌っているのは世界カラオケ大会で優勝したという海蔵かいぞう亮りょう太た君、若い歌手だ。「J-MERO」というBS番組で偶然、耳にしたがとても心にしみいる歌だった。だから録画に採って何度も聴いている。
認知症の女性と家族をテーマにしたと言われるが、病に記憶を蝕まれていく母にそっと寄り添う中熟年の息子や娘の想いを歌にしたものだろう。
「AI No Katachi」はこんな歌詞から始まる。
“桜舞い散る 春待たずして/ もしもあなたが この世を去ったら/ 実り黄金こがねの 秋待たずして/ あたしは あなたを追うのでしょう“
出だしからの美しい言葉としっとりと歌い上げる高音域の亮太君の歌唱力が聴く者をぐいぐいと歌の世界に引き込んでいく。歌詞を彩る美しい日本語の響き、音韻がさながら言葉の霊となって認知症の母と子が心で交わす愛の世界を紡いでいく。
春の夕暮れ、裏通りへと散歩に出かけた「あなた」を「あたし」は庭の錆びたベンチで待つのでしょう
冬の夜、夢を諦めきれず北へと旅に出る「あなた」に「あたし」は毎夜、北に向かい「おやすみ」を言うのでしょう
このような歌詞がしっとり続いた後、亮太君が歌い上げるこの曲のクライマックス!
“あなたが教えてくれた事・・・/ それは本当の「愛のカタチ」“
これは説明するまでもない誰もが心にひっそりと宿す「母の愛」そのもの。
私はよど号で朝鮮に渡って10年もしないうちに母を亡くした。別に認知症だったわけではないが、この歌が母への想いを代弁してくれているように思える。
末期大腸癌に病んだ年老いた母、その母は最期を看取ることもできない不肖息子の送った「朝鮮人参」をとてもありがたがっていたと姉から聞いた。
私の母は「受験戦争」に背を向ける私を「寄らば大樹の陰やで」と心配した。学生運動に飛び込んだ私に「おまえがやらんでも他にやる人はいっぱいいるやろう」とも言った。そんな母だが私のすることに反対したことは一度もなかった。朝鮮に渡って以降は日本の訪朝団に託した手紙に「(朝鮮で)お世話になっているんやから感謝の心は忘れてはいけない」と書いてくれた。
心配はするが信じる、それが私の母の「本当の“愛のカタチ”」だったのだろう、そう思う。
この歌は最後をこう締めている。
“幾年いくとせ老いて あたしの記憶を/ 病が徒いたずらに食らえども/ 愛子まなごの名を忘れ 我が名を忘れ/ それでもあなたを忘れません“
幾年老いた私も母を忘れないだろう。
吉幾三さんの新曲「涙…止めて」
赤木志郎 2021年10月20日
BSTVで吉幾三特集があった。吉幾三さんの歌には「かあさん」「娘に」「酔歌」「津軽平野」など肉親への情愛をこめた歌が多い。そして、女性の感情を歌った「海峡」「雪国」がある一方、愉快なラップ調の「俺さ東京さいくべ」「尽くさんかい」がある。「酒よ」は酒場の片隅で故郷に帰りたくとも帰れないで酒を寂しく舐めていた労働者から話を聞いて作った歌だそうだ。
こうした様々な人の心の底に渦巻く気持を歌いあげているのが特徴だと思う。
最近、といっても三年前に作詞作曲された「涙・・・止めて」という曲をこの番組で初めて聞いた。
涙止めて世界中の涙を 夢を見たいこの先の夢
過去と未来みんな背負って 歩きだそうこの手つないで
やがて笑うみんなが笑う そんな地球を私は見たい
水と緑に覆われた日本 この国でみんなが生きていくのなら
かつて子供の頃、覚えた反戦歌は、戦後直後に作られた、先の第二世界大戦を思い浮かべる歌だった。戦災を蒙って戦争のない国をめざし立ち上がろうという感じだった。「心の歌」「原爆許すまじ」などなど。今ではまったく耳にしない。そんな歌があったのかと思われるくらいだ。ベトナム戦争当時、反戦歌が多く歌われたが、外国のもので私には馴染めなかった。
この歌は、現在の戦乱がたえない現在の世界、戦争の危険性がある日本のことを歌っている。だから、新鮮に感じたのだろう。
何回も聴きながら、日本という国を非戦平和国家にし世界から戦いをなくし平和を希うという人々の切ない願いが込められていると思った。
「非戦平和国家」こそ日本国民の願いであり、日本の使命と役割だとつくづく感じさせられた。
落ち穂ひろい
魚本公博 2021年10月20日
この間、朝鮮は寒波が張り出してきて急激に気温が低下。それまで最低気温も10度以上はあったものが、一挙に数度になり17日の日曜には零度にまで下がりました。よど農園の里芋も一挙にしおれ、まだまだ大きくなることを期待していただけに残念でした。
この日、市内に出かける機会があったのですが、周辺の農村地帯では稲の刈り入れも終え、脱穀準備に大忙しでした。そうした中、農場員や農業支援の子供達が落ち穂ひろいをしているのを見かけました。テレビなどでも「稲刈り戦闘をよくやろう」「一粒のコメも無駄にせず取り入れよう」と呼びかけていて、そのための稲穂ひろいなのです。
その風景を見ながら、昔、故郷で見た稲穂ひろいの風景を思い出しました。私の故郷は当時、別府の市街地に隣接する農村地帯で、住民の中には、土地を持たず、市内に働き場所をもつ人たちも住んでいたのですが、稲刈りの頃、そうした人たちの何人かが稲穂ひろいをするのです。何でも、集めると一升瓶ほどにはなり、生活の足しになるのだとか。幼少の頃、そうしたオバさんたちの稲穂ひろいを手助けした記憶があります。
以前、BSの歴史物で、昔、日本の農村では、村に住む土地を持たない人のために、農民はわざと落ち穂を残す習慣があり、ある地方では、勝手に稲刈りをしてもよいように小さな田圃ごと稲を残す習慣さえあったということを知りました。
貧しい人のための、弱い立場の人のための庶民のセーフティーネット。人々が助けあう共同体の中で自ずと生まれたシステム。何かほっこりする話しです。今では、そういう習慣も消えてしまったのでしょうが、それだけに、国が人々の命と暮らしに責任をもつという意味が問い直されているように思います。
メディアジャックの「乗客」にされて
小西隆裕 2021年10月5日
この間の日本のテレビ、ラジオ、新聞などメディアは、さながら、自民党の総裁選のため、連日、ハイジャックならぬメディアジャックされた観があった。
われわれも、その予想や分析、評価に熱中していた。言ってみれば、メディアジャックされた飛行機「日本号」の乗客にされていた訳だ。
総裁選は、岸田氏の予想を大きく上回る圧勝に終わった。国民的人気が高いと言われ、党員票での圧倒的優勢を言われた河野氏の惨敗。河野氏の票を大幅に食ったと言われる高市氏の出馬。
選挙後、岸田氏を真ん中に満面の笑みで主席壇に居並んだ安倍、麻生、甘利、いわゆる3Aの面々。2Fと言われる二階氏の憮然たる表情。
「日本号」がどこに着陸させられたかは明白だ。
「乗客」であるわれわれも黙っていてはならないと思う。
京都の思い出に出会う
若林盛亮 2021年10月5日
BS放送では京都の神社仏閣、古都の歴史、四季の風景、京都料理などを紹介する番組が多い。
私にとって京都は学生時代、青春の思い出のいっぱい詰まった町だ。
常連バイトでお世話になった「貸し物屋」という京都三大祭り、和服や華道各流派の展示会といった京都ならではのイベント、地鎮祭や学校の文化祭など催し物の会場設定をやる仕事があって、天竜寺や東福寺、東寺など主な神社仏閣はなじみの仕事場として記憶に残るところだ。
ある日、貴船きぶねという鞍馬くらま山麓にある夏の京都の避暑地の紹介番組があった。
水の神様が祀られているという貴船神社があって、谷間を流れる貴船川は鴨川の源流の一つだが渓流に沿って川床をしつらえた料理旅館がずらり軒を連ねる観光スポットでもある。
貴船祭りの際に紅白の幕張り、床几やテントの設営をやったが、京都にはこんな渓谷風景があったんやと感動した仕事場、それが私にとっての貴船だ。
あのとき職人のおっちゃんたちと休憩時間に吸ったタバコの味が忘れられない。思い出すのがタバコとは不思議だが、たぶん汗みずくで働いた後、シャツのポケットから取り出したじとじとに濡れたタバコの味が格別だったからだろう。「Bちゃん(=Beatles;私の愛称)、こうやるんや」と親しく私に仕事の要領を教えてくれた人情家のおっちゃん達はもういないだろうなと思うと少し寂しい。
新撰組ゆかりの地として紹介された三条大橋、鴨川にかかる橋桁あたりの風景も当時のまんまの姿で残っていた。
あの橋の下で「小説家志望の詩人」を誘って乞食のおっちゃん二人組とやった酒宴の思い出がよみがえる。二人のお乞食さんが近くの木屋町飲屋街から集めたポリタンクいっぱいの残り物ごちゃまぜビール、その味はなんとも言えなかった。朝目覚めて比叡山あたりから昇る朝日をみんなで眺めたが、「満州の太陽はもっとでっかいぞ」と言ったおっちゃんの言葉が忘れられない。満州引き揚げ者のおっちゃん二人の様々な想いのこもる言葉だった。
私の学生時代はある意味、放浪の時代、京都のあちこちを彷徨し、仕事もし、人に出会い仲間らと語り合った。
番組で紹介される京都にはそうした発展途上の青春にいろんなことを教えてくれた記憶が凝縮されている。
だからなぜか故郷の近江の風景より京都には思い入れが深い。
秋夕の月見
魚本公博 2021年10月5日
9月21日は中秋の名月でした。朝鮮では秋夕(チュソク)の日と言って、墓参りの日で休日です(もう一つの墓参りの日は4月5日頃の清明節)。中秋の名月の日は、旧暦の8月15日になります。お盆ですね。盆は丸いということで満月を意味して付けられたのだと思いますが、朝鮮でも「膨らんだ」という意味でボルムと言い、満月を意味しており、似ています。先祖供養の日であるというのも同じですね。
明治になって太陽暦を取り入れる際、旧暦の日時をそのまま当てはめたため、元来8月15日は満月の日だったのが必ずしも満月にならいのは残念な気もします。
中秋の名月では、ススキに月見団子が定番ですが、地方によっては里芋をそなえ、それが原型のようです。そこで私は、中秋の名月には、里芋をふかして食べることにしています。その日はあいにくの雨、小降りになった頃をみはからって、よど農園に行って里芋を掘り、何とか間に合わせることができました。夜もしばらく雨天でしたが11時頃に晴れ間が広がり、名月を見ることができました。
中秋の名月を仰ぎ見ながら亡き父母や故人を偲ぶ。今年は雨天の後の晴れ間に出た月ということもあって、妖しいほどの美しさで、いつにも増して身に染みる月見となりました。
最近のこと
森順子 2021年10月5日

160個の栗
9月、気になったことは台風ですが、昨年のような被害に見舞われず全国的に万全な取り組みもされ無事に過ぎそうです。残るは稲刈りを待つだけです。このまま気候がよければいいのですが。
もう、道ばたには秋桜がいっぱい。市内に行く高速道路の両側に列をなす秋桜が寂しくない秋を感じます。数日前は、アパートの下で皆と栗焼きしました。もちろん栗は村の栗の木です。すごい煙に覆われましたが初めての経験で秋の日の午後の思い出と癒しになったようです。
日本では、緊急事態宣言が解除されることと、もっぱら総裁選のことばかり。4人の候補者の人物評価の話が私たちの中でもよくでますが、どっちにしろ・・・。それより11月には6波が来ると誰もが言うのに解除とは、こっちの方が気になります。
明日は総裁選挙ですが、「ともかくコロナに勝てる人」「命を守ってくれる人」、国民の目線に立てば、これが総裁の条件だと思うのですが・・・。

あっという間にお腹の中に
10数年ぶりの卓球から
若林佐喜子 2021年10月5日
空一面に広がった鱗雲に魅せられ、ちょっと気分も爽やかな9月末のある日。
村に来ていた案内人のミョンチョルさん、わがyobo yodoたちと卓球を10数年ぶりにやりました。すでに帰国しているわが次男とやったのが最後のように記憶しています。
朝鮮の人たちは、みな卓球が上手です。どの学校、どの職場にも卓球台があり、住宅地の広場の一角にもコンクリートの卓球台があるくらいです。
何しろ10数年振りなのとyobo yodoなので、思うように身体が動きません。カットされた玉は受けられず、打ち込みをやろうとすると気があせり外に出てしまう(笑)。ダブルスで組んだ人にカバーしてもらいながら3回戦やりました。1セット目は負け、2セット目はジュースの接戦勝ち、3セット目はあっけなく負けました。
久しぶりに卓球をやりながら、思い出すのは小学校時代の事でした。田舎の学校で一学年一クラスの全校生徒150名弱の小さな学校です。お坊さんの先生が体育担当で、サッカー、ドッジボールなども人数的に男女混合です。高学年の教室の一角には卓球台があり、体育の授業だったのか、放課後やったのかは定かでないのですが卓球をやりました。また、全校生徒で近くの川原から石を運んで作った「仲良しローラースケート場」まであった校庭が、懐かしく目に浮かびました。
今の子供達の置かれた状況を考えると、当時は、なんとも牧歌的でのんびりした時代だったと思わずにいられませんでした。
同窓生
小西隆裕 2021年9月20日
母校、都立小石川高校を卒業してから、実に58・5年振りの対話だった。
クラス会をZOOMで開くので参加できないかというメールが来て、ZOOMではできない旨返信をしたのに対する向こうからの電話だった。
相手は、クラス会の幹事をやっているのだろうM君。
電話越しに聞こえてくる声は、どこか聞き覚えのある、まさしくM君のものだった。20分と20分、計40分間、同級生だったTさんと結婚したM君のこと、他の皆のことなど、時間はあっと言う間に過ぎ去った。
正直言って、M君とは高校の時、それほど親しかった訳ではない。しかし、時間が経つのを忘れて、話は尽きなかった。
たったの3年間。77歳の私にとって、半生の26分の1に過ぎない。しかし、それが鮮やかによみがえってきて、それより遙かに大きな比重を持って思われた。
話が合う合わない、昔仲が良かったかどうかなど関係ない。あの時一緒に居たというただそれだけで十分心が通じ話が通じた。同窓生とはそういうものなのだろう。
「自分の軸足を持ちたい」という「M」さんへ
若林盛亮 2021年9月20日
私たちのツイッター、yobo_yodoの9月更新分に質問が来た。
「成人し、少しずつ社会が見えてきて自分が正しいと信じていたことに疑問を感じる機会が増えました」とあるので、たぶん成人して間もない若い人からのものだ。
「今まで北朝鮮は自由がなく恐ろしい国だと思っていたので、皆様のウェブサイトでの氷みづのお話や船に乗っている花嫁さんの写真にとても驚き」、与えられてきた情報を鵜呑みにしてきた自分の未熟さを実感したのだそうだ。
「M」さんと名乗る彼女は(勝手に女性と推定)「日本の未来である子供達を守る仕事に就きたい」と考えており、自分の間違った認識や信念のために子供を傷つけたらと不安になる、だから「情報に振り回されるのではなく自分の軸足を持った人間になりたい」と私たちに助言を求めてきた。
「今後一人の大人として生きていく上で自分の芯を作る為にはどの様な事が大切でしょうか」?
とても難しい質問だ。私としてはMさんにいま言えることだけをツイットした。
「貴女が思う『おかしい』、その疑問の解答を求め続ける誠実さではないでしょうか」
一言でいおうとちょっと抽象的になった。ウェブサイトも閲覧されているようなので、自分の体験談も交えてもうちょっと砕いた返信にしてみた。
私も大学生になる前、自分が正しいと信じてきた「常識」、進学校の優等生やいい大学に入るため受験戦争に勝つことに疑問が芽生え、また物心つく頃から羨望の的であった「アメリカン・ドリーム」が色あせたものに見え始め、親や教師、大人たちから言われてきたことが「何かおかしい」と感じるようになった。でもその答はわからなかった。でも「おかしい」と思うことにずるずる流されていくことの方が怖くて、そこから一歩、距離を置くようになった。
私は「M」さんのように「日本の未来である子供達」のための仕事に就くというような明確な目標はまだ持っていなかった。だからあっちにぶつかりこちらに転がりしながらやっと社会と向き合うべきだと悟り学生運動にたどりついた、それが大学4年になるとき、とても遅い「覚醒」だった。そして「赤軍派―よど号で朝鮮へ」となって今日に至るも私の自問自答は続いてる。
「M」さん的に言えば、それは「自分の芯、軸足」を持つための人生遍歴だったように思う。
いま思えば、敗戦直後の大人たちも皇国史観の軍国主義日本から突然の米国式の民主主義日本への180度価値観転換に頭が混乱していた。敗戦の教訓も自分の頭で考え抜かれたものじゃなかったと思う。戦後の日本社会はその出発点から「自分の軸足」が確固としなかった。このことは私たち戦後世代を経ていまの若い世代が日本社会の「常識」に疑問を感じ「自分の軸足」を持てないで悩むことにいまだ影響を与えていると思う。
こういった私の想いを込め、「疑問の回答を求め続ける誠実さ」とちょっとカッコつけすぎのツイットをした。言葉を換えれば「自問自答を続けることではないでしょうか」と伝えたかった。
これまで正しいと思ってきたこと、自分の「常識」に疑問が芽生え始めたこと自体が「軸足を持った人間」への第一歩の始まり、そして「おかしい」への回答を求め続けること、またその過程での学びと人との出会いを大切にすること、失敗さえも力に変えていく努力を続けること、「ではないでしょうか」とだけは言える。
貴方が日本の未来である子供たちのために誠心誠意、精進努力を続けられんことを願うだけです。
玄界灘の向こうから「M」さんを応援しています。
お世話になった人々
赤木志郎 2021年9月20日
長らく宿舎の周りを丁寧に手入れしていたオジサンもいつのまにかいなくなった。定年の60歳を越えていたからいつかは引退すると思っていたが・・・。よく宿舎の周りの雑木を刈り込み、綺麗にしていた。ここは大同江が見下ろせるからどんなに良いかと話していたことが印象的だった。
これまでそれこそ多くの人々にお世話になった。朝鮮に来たはじめの頃は、解放直後の民主改革経験者、朝鮮戦争参加者が多く、異口同音に「米兵が世界で一番弱い」ということを聞かされたのが印象的だった。いわゆる革命第二世代と呼ばれる楽天的で元気な人々だった。
つぎに朝鮮戦争後育った世代だ。ちょうど私の1,2歳上になる。復興時期なので苦労して育ったのが分かる。日本の戦後世代と似ている。
管理関係の労働者も最初は日本から親元を離れ異郷に訪れた若者として息子のように対してくれた。そうした人々もいなくなり、比較的長く世話になった運転手の方々も皆、引退した。
今や、皆、年下の人ばかりになった。管理するおじさんたちもどんどん若返ってくる。日頃接している市内の商店、病院の人たちもそうだ。孫のような人たちは、私を若返えさせてくれる。
しかし、昔、世話になった人たちは去っても、その情は日本人村の到るところに残っている。村や家のあちこちを見ても、その箇所を修理してくれたことを思いだす。風の便りで病死したという話をきくときもある。しかし、彼らの情は私たちの胸に残っているのだと思う。
先人の知恵、学ぶべし
魚本公博 2021年9月20日
今年の猛暑、ビールが美味かったです。ビールには枝豆。この単純にして簡単な枝豆がビールのつまみには最適。BSなどを見ていると外国人にも「あれは美味い」と好評のようです。
枝豆は大豆を青いうちに採ったものですが、よど農園で大豆を栽培するのがことのほか難しい。原因はキジ。我々が住む日本人村は、動物保護区(禁猟区)の一角なのでキジの天国なのです。アパートの周辺にも我がもの顔で歩き回っています(ちなみに、四つ足動物だけでもノロ(小型の鹿)、タヌキ、キツネ、リス、シマリスなどがいます)。
このキジの大好物が大豆。畑に植えても、必ず探しあてて食べてしまいう。そこでビニールで覆っても、鶏のような頑丈な足で隙間を作って入り込み食べてしまう。それならと苗を家で作って移植する方法でやってみたのですが幼苗も食べられてしまう。無念やるかたない。
そこで、一念発起して、やってみるかと思い立ったのが、昔、管理の人たちが直撒きした大豆畑に木の枝を刺し、そこに糸を張り巡らせてキジを防止するやり方。以前から考えてはいたことなのですが、あんな細い糸で囲っても、やられちゃうだろうなと、あまり気乗りしなかったもの。
やってみたら、それが大成功。どうもキジは細い糸が張られているような所は怖がるらしく、糸を張った場所には警戒して近づこうともしません。かくて、3mほどの畝2本に植えた大豆に実が鈴なり。今年の夏は(と言っても8月になってから)枝豆が大量に採れました。皆にも配って、喜ばれました。
イヤー、あんな細い糸を張ってもと半信半疑でやったことですが、先人の知恵、学ぶべしを思い知らされた枝豆でした。
肌で感じた「時代の転換」
小西隆裕 2021年9月5日
先日、外交評論家、孫崎享さんの講演を受けて、同氏との電話を通しての対論に「アジアの内の日本の会」を代表して出演させていただいた。さほど広くない会場には、コロナの中、40名ほどの人々が集まり盛況だったようだ。
講演の内容は、米朝問題、米中新冷戦問題、それについて私の方から質問するかたちで対論は進行したが、その過程で電話線につないだスピーカーから聞こえてくる会場の人々の声に感じ入った。
一言で言って、「時代が変わったなあ」という感慨だ。
「米国が中国に負ける」という孫崎さんの話がごく当たり前のように受け入れられている。
一方、米国が唱える「民主主義VS専制主義」がもはや何の力もないイデオロギー、古い戯れ言として受け止められている。
時代の転換は、人間の意識を超えて進んで行く。
この間の米国の衰退、没落、コロナ禍でのその露呈が生み出した、この時代の進展に改めて驚かされた一日だった。
夏の終わりは・・・
若林盛亮 2021年9月5日
夏の終わりはさみしい。
8月も下旬ともなれば秋風を思わせる涼風を肌に感じ始める。あのボギョム(暴炎)と言われた真夏の炎暑が懐かしくなるから不思議だ。
故郷の滋賀にいた頃、琵琶湖の海水浴場の砂浜に人気がなくなる季節、「海の家」、貸しボート屋などが寂れていくサマを思い出す。高校のヨット部活時、艇庫のある浜の隣が柳ケ崎水泳場だったが、寂れた桟橋や客もないかき氷屋の店先で「氷」の旗がひらひら風に揺れている風情は何とも言えないワビの世界を想わせたものだ。
さみしいと言えば、「村」前の大同江をあれほど頻繁に往来していた砂利運搬船、浚渫船がこのところめっきり減った。市内の1万世帯ニュータウン建設、丘陵地の8千世帯階段式住宅建設が完成段階に入って骨材の需要が激減したからだろう。これは季節とは関係がない。
夏の終わるこの季節、他方では私の密かな楽しみの始まる季節でもある。
これからは何と言ってもリヴァプールの季節! 英サッカー、プレミア・リーグの新シーズン開幕の季節だ。
昨季は防御陣の主力3人が負傷長期離脱で「苦難突破シーズン」、それでも最終的には3位にこぎつけた。だから今季はリーグ制覇、優勝が私の悲願、だから必勝祈願のシーズン開始となる。
ところで今季は優勝争いが大混戦になる気配濃厚。これまではマンチェスター・シティのみがライバルだったが、今季はチェルシー、マンチェスター・ユナイテッドも監督交代や新選手補強でライバルとなりうる強力な陣容を整えている。四つ巴のデッド・ヒートになりそうだ。
案の定、リヴァプール第三戦はチェルシーと1:1、ドロー(引き分け)試合になった。相手チームに出されたイエロー・カード(警告)二枚、レッド・カード(退場)一枚というのが試合の激しさを物語っている。
サッカーとなると話が止まらないのでここまで。
とにかく深く静かに私が燃えたぎる季節が始まったことは確か。
DAZNが放映権独占でBS放映は皆無になったので、速報は椎野さんから、詳報はわがサッカー師匠からいただく。この方たちも忙しくなる季節に入る。
かんにんしてな、おおきにやで。
やる気の源、大谷翔平
魚本公博 2021年9月5日
私の一日の生活パターン、夜はプライムニュース、深層ニュース、報道1930などBSの報道番組を見るのですが、最近はこれに11時からのワースポMLBが加わります。そこで一番の楽しみは大谷翔平選手の活躍ぶり。ダイジェスト版ですから活躍場面だけを見ての省エネ視聴。
ホームラン場面や投手で力投の場面を見ては、気分すっきり。そんな日には溜まった原稿書きも「よーし今日は徹夜だ」とばかりにやる気が出ます。我ながらミーハーというか単純だとは思うのですが。
日本人選手が大リーグで活躍しているのが嬉しいということですが、インタビューなどで垣間見る大谷選手の人柄にも好感がもてます。一言でいえば「野球愛」。自分の好きな野球を自身が楽しみながら、それを喜んでくれる観客や支えてくれるチームへの感謝も忘れない。そのための自己管理の努力などなど触発されることも多いです。
そうした大谷選手を通して、今の日本の若者像に触れる思いも。今の日本は様々な面で困難な問題が山積。それを解決し切り開くのは若い人たち。日本の若者はやりますよ。そうした期待を抱かせてくれるという意味でも「やる気の源、大谷翔平」です。
8月が終わって
森順子 2021年9月5日
五輪競技も応援できたし、今年は高校野球も開催でき、とってもよかったです。日本の深刻なコロナ状況を思うとネガテイブになりますが、選手や球児の躍動する姿で少し救われたような気持ちになれました。
ピョンヤンでは、一万世帯建設中です。もう今年の末までには入居できるようです。この短期間に、また新しい町が生まれ高層住宅がそびえ立ち緑化も進み、どんどん進化していくピョンヤンを感じています。また、今年は、2万人という青年たちが山に海に開発地に建設現場にと、いわゆるしんどい単位に志願したのです。28日は青年節、市内では祝典に参加する青年たちが乗ったバスに手を振る多くの人たちを見かけました。
朝鮮では、困難期を乗り越えたのは、青年たちの志願から始まったという歴史があり、それが今でも引き継がれていて、「青年強国」と言われるのも青年たちに対する国の信頼なのだと思います。皆、自分の故郷を離れるのは寂しいけど、と言っていましたが、国つくりに青春を捧げたいという、まさに頼もしい青年たちです。「若い人が元気な国、朝鮮」を感じた8月でもありました。
オバケひょうたんで、パガジを
若林佐喜子 2021年9月5日
朝晩は涼しく、日中には赤トンボを見かける今日この頃です。
よど農場はすでに実りの秋、枝豆、ゆりの根、ニガウリ、ジャガイモ。一番の収穫は、なんと言っても「ひょうたん」です。日本のひょうたんと違って楕円形で、朝鮮では、水くみ用の容器(パガジ)として使います。

オバケひょうたん8月中旬撮影
今年のひょうたん、一番大きいのは周囲が104センチ!です。 アパートの下の畑に行くたびに、よくこんな大きなひょうたんがぶら下がっているものだと感心しながら見守っていました。先日、皆様にお知らせしようとカメラとメジャーをもって畑にいくと、草むらに落ちて割れているではないですか。「ええ!2個とも? この間、お天気が悪かったせいかな」と。一人ではとても運べず思い悩んでいたら、偶然、管理人の人に出会い2人でアパートの前までやっとの思いで運びました。その日の夕食時に安部さんに話すと、「実は自分が切った」とのこと。な~んだ、どうりできれいに二つに割れていたのだと納得の私でした(笑)。
さて、オバケひょうたんですが、ばかでかいパガジを作って宿所に置き、支援者の方々が来られたときにお見せしようということに・・。
その日本の支援者の方々のご尽力で開催された8月29日のイベント、孫崎享氏と小西隆裕さんの電話対談。受話器ごしですが、日本の皆様の懐かしい声と熱気溢れる会場の雰囲気が電話を取り囲んでいた私達にも伝わってきました。会場の「スペースたんぽぽ」は、日本の友人がメールで送ってくれる「テント日誌」に出てくる名称なので勝手に親しみと懐かしさを感じていました。コロナ感染拡大の中で、会場の準備や当日の感染防止対策に苦労して下さった皆様、参加者の方々に心から感謝しています。
一日も早くコロナが収束し、帰国支援センター山中代表をはじめ支援者の方々を日本人村にお迎えできる日が来ることを改めて願った9月です。

癒しのひととき
オリンピック
小西隆裕 2021年8月20日
今回のオリンピックはもう一つ関心を持てなかった。だから、テレビのスイッチを入れる指先にも力が入らなかった。
しかし、一旦観始めると違ってきた。出場している選手たちのオリンピックに掛ける気迫が乗り移ってきたかのように。
プロの選手たちも、いつもとは違って見えた。米国との決勝戦、1点差の攻防の中、ピンチをキャッチャーフライで切り抜けた時、甲斐が落ちてくるボールを押し戴くように捕って跪いたのが印象的だった。
国を背負うと選手たちも重くなる。見る方も気が入る。人間にとって、国とはそういうものなのだろう。
Sailing(帆走)-風を読み風を操る
若林盛亮 2021年8月20日
夏のせいか、「Sailing」という歌を最近よく聴いている。
ロッド・スチュアートという英ロック歌手の歌だがバックを王立フィルハーモニック交響楽団の荘重な楽曲が支え、その素晴らしいメロディラインがSailing、人生という航海を悠々たるドラマチックな音楽として歌い上げている。
船は行く 船は行く/帰るんだ/海を越え/船は行く/嵐の海を/君のそばへ/自由へ
飛んでいく 飛んでいく/鳥のように/空を越え/僕は飛ぶ/雲を抜け/君のもとへ/自由へ
途中はさまれる歌詞は
「死にそうだ/泣き続けて/君のもとへ/なにがあろうと」
とあって、その航海は思うようにいかないこと、でもなんとしてでも「君のもとへ」たどりつくのだと人生の紆余曲折も歌いこんである。
あっちに転びこっちに転びの自分の人生体験を重ねることもできる歌だ。
Sailingといえば、高校時代にSailingクラブ、ヨットの部活をやった。競技自体に興味はなかったが、夏の広々とした琵琶湖を思いのままSailingする爽快さは忘れられない。
帆船とは風を帆に受けて風下にしか進まないものと思ってたら、風上に向かうものだということを知った。飛行機の翼の原理、丸みを帯びた上部と平坦な下部を過ぎる風が走る距離の差によって生まれる分力が浮力と推進力を生む原理を風にふくらむ帆に応用したものだ。風上に向かって40度角に進むときに最も速くヨットは走る。
風を読み風を操る操舵でどこにでも行ける!
かつて堀江謙一さんが「太平洋ひとりぼっち」、小型ヨットで太平洋横断をやった。当時、「琵琶湖ひとりぼっち」、琵琶湖周航くらいはできそうだと私でも夢想できた。
人の人生と同様、国の運命も時代の風を読み風を操れば順風満帆、時代を読み間違えば国の舵取りを誤る。
日本が「米中対決の最前線を担う」、そして「台湾有事は(日本の)国家存立危機事態」だから米国と一緒に台湾防衛のために中国と戦う日本にすべきだという声が上がっている。しかし時代の風は「米国についていけばなんとかなる」という「戦後の常識」がもはや通用しないことを見せている。
今日は8月15日だ。
沖縄特攻で散った戦艦大和の士官の一人は遺書に「新生日本が世界史の中で正しい役割を果たす日の来ることをのみ願う」と書いた。私たち戦後の日本人には新生日本を託して散った先達の念願をなんとしてでもかなえる責務がある。
Sailing?日本の舵取りのためには時代の風を読む正しい眼力を養うこと。
そして風を操り嵐の海を突き抜け行くんだ?「君のもとへ/なにがあろうと」!
いつにも増して重い「8・15」でした
魚本公博 2021年8月20日
今年の8・15、いつにも増して重く感じる8・15でした。それは、五輪強行によるコロナ禍の急拡大。「最早、打つ手なし」とも言われる状況、まさに「コロナ敗戦」と重なる「敗戦記念日」だったからだと思います。
その「全国戦没者追悼式」。94歳という最高齢で参加された長尾昭次さんは、コロナ禍の中、参加をためらう気持ちもあったそうですが、兄が戦死し自身も陸軍少年飛行兵で「仲間には特攻で死んだ者もいる」として、「特攻で亡くなった人たちを思えば、私たちに何ができるか」との思いを抱いての参加だったとか。
そして言います。「(政治家も含め)戦争だけは絶対避ける考えをもっていただきたい」と。遺族を代表して追悼の辞を述べた兵庫の柿原啓志さん(85歳)は、「自分たちのような遺族を作ってはならない」と述べておられた。
これに対し、菅首相は「積極的平和主義の旗の下、国際社会と力を合わせながら・・・」と。積極的平和主義とは、「米国と共に戦争する国」を目指した安倍前首相が使った言葉。国際社会とは米国。そして今、米バイデン政権の唱える「米中新冷戦」で日本はその前面に立たされようとしている。
菅首相の言葉は、遺族の方々の思いを真っ向から否定し押しつぶすもの。一体誰が、どうした政治が「敗戦」をもたらしたのか。「コロナ敗戦」を見るにつけ、政治の無責任さを思わずにはいられません。
「二度と戦争してはならない」「二度と遺族を作ってはならない」。この言葉の重みがいつにも増して胸に迫る8・15でした。
「照ノ富士」(2)
小西隆裕 2021年8月5日
つい四ヶ月前、「こういう力士にこそ横綱になってほしい」とこのライフ欄に書いた照ノ富士が本当に横綱になった。
春場所で優勝して大関になったと思ったら、夏場所に大関としてまた優勝。横綱昇進がかかったこの場所で十四日間勝ちっ放し。千秋楽、全勝同士の白鵬戦では敗れたが、文句なしの「横綱」だった。
横綱昇進を受けての恒例の口上は、「不動心を心がけ、横綱の品格、力量の向上に努めます」だった。
彼ならこの言葉通りやってくれるだろう。
白鵬がもう三,四歳若かったなら、柏鵬時代に続く「鵬照時代」もあり得たのではと少々残念な思いがしている。
「暴炎」-真夏の大同江は「生ビールの季節」&「恋の季節だよ~」?
若林盛亮 2021年8月5日

船上レストランから見たチャンジョン街
炎暑のことを朝鮮では「暴炎」(ポギョン)という。
7月の下旬はこの暴炎つづき、暑さに弱い朝鮮の人々はまさにうだりにうだってあえいでいる。
“真っ赤に燃えた太陽だから~ 真夏の海は~ 恋の季節だよ~ ?”
50余年前のピンキーとキラーズのヒット曲にあやかって私たちyobo_yodoは、“真夏の海”ならぬ“真夏の河”、市内の大同江に浮かぶ船上レストランへ、“恋”ならぬ“生ビール”の季節を楽しみに出かけた。
川面から吹く風は心地よく、私は生ビールを立て続けに大ジョッキ3杯を飲み干した。フランクフルト風味のソーセージをつまみにぐいぐいと喉ごしを楽しんだ。みんなもよく飲み、よく食べた。
川面に目を移すとモーターボートが目に入った。
そこには遠目にも新婚さんとおぼしきカップルが乗っていたのでカメラを向けた。望遠にしてみるとカップルの前には「撮影班」のようなビデオカメラ、及び静止画像カメラを持った二人のカメラマンが舳先(へさき)からカップルを撮影しているのが見えた。

真夏の大同江は恋の季節
新婚さんの男性が上着を脱いで彼女に片側を持たせると、モーターボートのスピードが起こす風が上着をひらひらとなびかせ、両手を広げたカップルの頭上に「祝福の風」がはためくような演出になる。
若きカップルには暴炎もなんのその
”真っ赤に燃えた太陽だから~ 真夏の大同江は~ 恋の季節だよ~?”
になるのです。
以降、数組の新婚さんが、結婚式を終えての記念の大同江モーターボート遊覧、「祝福の風」撮影儀式に次々やってきた。
市内を流れる真夏の大同江は、老若男女に暴炎を忘れさせる優しいひととき、「生ビールの季節」、「恋の季節」をアレンジしてくれる粋な河でありました。
祖国愛について考える
赤木志郎 2021年8月5日
BS放送で一年以上かけて放映されていたインドドラマ「ポロス」が終わった。最初はペルシャの侵略、つぎに世界制覇を追求するマケドニアのアレクサンダー大王にたいし、ポロスはインドの独立を侵すものは許さないとして困難な戦いを繰り広げる。その戦いのなかで父と母、兄、妻の両親も戦死する。また、弟や母の兄(地方の王)とその息子などの裏切りも体験する。その過程でいっそう祖国愛を高め祖国愛で人々を奮い立たせ勇敢に戦い、インド統一の始祖とされた。最後に、「祖国のために捧げた精神は子孫代々に受け継がれ、インドの独立を守るだろう」という言葉を残して死んでゆく。ペルシャとの関係やまき散らされた伝染病のために全食糧を燃やさなければならない状況など、いろいろな場面があるが、すべてにわたって祖国愛に貫かれた叙事詩のようなドラマだった。
このドラマを見て、まず、インドの人々の祖国にたいする想いがすごく強いなと感じた。つぎに祖国愛があらゆる困難をうち勝つ力の最大の源泉だと思った。そして、人を信じるのはその愛国心を信じるということ、祖国を守る闘いのなかでいっそう祖国愛が高まり敵をも感動せざるをえないほど高潔なものに至るということなどが感想だ。
このドラマが終わった日は、朝鮮はちょうど7・27祖国解放戦争勝利記念日(いわゆる朝鮮戦争停戦協定締結日)だった。市内に出ると、飾り付けや踊りなど祭りのような雰囲気だった。TVでは、祖国愛をテーマにした「私の生と祖国」「戦士の歌」「祖国と私」などの歌が多く流されていた。
祖国愛についていろいろ考えさせられた日であった。
ゴン攻め
魚本公博 2021年8月5日
コロナ禍蔓延の中での東京五輪。そういう「イヤなこと」を吹き飛ばすかのような日本選手の活躍。とりわけ、開幕早々のスケート・ボードでの最年少13歳で金メダルの西矢椛の金は感動ものでした。
ところで、そこでNHKの解説を務めた瀬尻稜さんの発した言葉が話題になったとか。その言葉とは「すごいゴン攻めやってますねー」という「ゴン攻め」。その説明はなかったので詳しくは分かりませんが、「ゴンゴン攻める」みたいな感じでしょうか。
ある新聞は、この言葉を紹介しながら、少々イヤなことくらい頑張って乗り切ろうという気にさせると。競泳女子400m個人メドレーで金メダルを取った大橋悠依選手が極度の貧血症を克服しての快挙であったことも、あきらめず人生をゴン攻めした結果だろうと書いていました。
阿部兄妹の同時金メダル。卓球男女混合ダブルスで大逆転を演じての水谷・伊藤ペアの金メダル。ソフトボールでの上野投手の超人的な活躍と金メダルなどなど、多くの金メダルやメダルも「ゴン攻め」ですね。
「ゴン攻め」には、かつてのような悲壮感漂う「根性論」ではなく「楽しむ」という気持ちも込められているようです。西矢選手が劣勢にあってもニコニコ顔だったのを聞かれて「だって楽しかったもん」と。楽しいから、あきらめずに「ゴンゴン行く」。大リーグで大活躍の大谷選手についても、そういうことが言われますが、日本の若者の新たな「頼もし像」に好感を持ちます。オリンピックも残りわずかですが、「ゴン攻め」でメダルラッシュ、期待しています。
暑中お見舞い申し上げます
若林佐喜子 2021年8月5日
日本は連日、暑い日が続いているようですが、皆様、いかがお過ごしでしょうか?
朝鮮も7月中旬から高温現象、ポギョム(暴炎)が続き、野外の作業は11時から16時まで禁止でした。特に農業部門では積極的な対策がとられ、テレビでは、毎日、田畑の水管理と給水などに総動員、総集中の様子が報道されていました。8月に入り、梅雨前線の登場でお天気予報に傘のマークが並ぶようになり、やっとポギョムが解消。ちょっと一安心と言いたいところですが、この先、豪雨もあり得るということですので、一難去ってまた一難。まだまだ油断大敵の今日この頃です。
よど農場は、周りに木々が多く、この間は、草も伸び放題?が幸いしてか、きゅうり、キャベツ、唐辛子、特に、今は、トマトが食べごろです。雨が多かったときは、少し色づくとみな腐っていましたが、暴炎の中でトマトも真っ赤に成長です。
平壌の街中では、夏のビンス(氷みず)が大人気です。日本のようにかき氷を山に盛るのではなく氷みずです。そこにアイスクリーム、スイカ、桃などの果物を盛ります。真夏はソフトクリームより頭の芯まで冷えるビンス屋さんが大盛況。そんな姿をみていると、ついつい、日本の昔からあるイチゴ、レモン、メロンシロップのかかった山盛りのかき氷が懐かしく思い出されます。最近はフラッペと呼ばれ色々な種類があるようですね。
まだまだ、暑い日が続きますので、皆様、水分補給をはじめ体調管理にくれぐれも留意され、しっかりこの夏をのりきりましょう。感染拡大がとても心配です。感染防止にも注意して下さい。
「気候変動」
小西隆裕 2021年7月20日

暑中お見舞い申し上げます。盛夏
朝鮮も、この数年、気候変動が顕著だ。
異例の酷暑だったり、台風の連続的上陸だったり、私たちがこちらに来てからの50年を振り返っても、「変動」が目に見えている。恒例だったテドン江上のスケート乗りも、今年などは、川面が完全氷結したかどうかが話題になるくらいになってしまった。
何でこんなことになっているのか。
そこで犯人にされているのが「地球温暖化ガス」、CO2だ。
確かにこれは科学だと言えるだろう。
しかし、これが「脱炭素化(グリーン化)」の大合唱となり、「デジタル化」とともにバイデン政権による米覇権回復、再構築のために利用されているのも事実だ。
G7など各種国際会議で「気候変動」問題が重要事項として繰り返し取り上げられている背景にはこの事実がある。
「脱炭素化(グリーン化)」自体は、「デジタル化」とともにやらねばならないことだ。
しかし、問題は、どのようにグリーン化するか、その中身だ。
高度な最先端科学技術で再生可能エネルギーの特長を存分に生かした、国家主導、地産地消など、自主自治のためのグリーン化か、それとも米系科学技術、外資に依存した安易なグリーン化か。
問われているのは、覇権のための「デジタル化」「グリーン化」か脱覇権のためのそれか、その対決点を鮮明にした闘いだと思う。

高温現象で空模様も異常7月19日
杏(あんず)干し、朝鮮でじわりブームに!の予感
若林盛亮 2021年7月20日
恒例の杏干しの季節がやってきた。
今年のはいい材料を仕入れてすでに塩漬けにして瓶かめにつけ込んだ。後は赤ジソの出るのを待ち、赤く漬け込んだそれを夏の熱い日差しに三日間さらす。毎年変わらない作業工程だが、今年のはうまそうだ。
家庭を持つ前から始めたと思うから、私の杏干し漬け歴はかれこれ40余年の歴史を持つ。
私はなぜか梅干し、なかでも梅干しのおにぎりに思い入れがある。
小学生の頃は母が家で漬けた梅干しでおにぎりを作ってくれて、遠足や運動会でよく食べたものだ。大学生になって東大安田講堂死守戦で逮捕された警察留置場の食事量の余りの少なさに飢餓状態になったとき毎晩「食べる夢」を見たが、そのときいちばん夢に出てきたのが梅干しのおにぎり弁当だった。それで保釈出所後、京都へ帰って知人に梅干しのおにぎり弁当を作ってもらって遠足に行った、それくらい梅干しには思い入れが深い。
朝鮮には、残念ながら梅の木がなかった、だから梅干しもない。でも杏の木はいっぱいあった。なら杏で代用できないかと考え、やってみたらほぼ梅干しそっくりの味になった。以来、杏干しを作ることがこの季節の「村」の風物詩となった。
余談だが蓮池薫さんが朝鮮在住時、なにかの雑誌か本で「よど号グループが杏で“梅干しづくり”をやってる」という記事を目にしてご夫婦で作られたとご本人の著書にあった。やっぱし同胞、考えることは同じやないかとなんとなく嬉しかった。
朝鮮の人は酸っぱいものが総じて苦手、寿司でさえ箸もつけられない人がいた。でも最近は市内に寿司専門店ができたり、外貨ショップで主に帰国した在日の方向けと思われる「杏干し」が細々と売られ出すようにはなった。
昨年も書いたが私たちの案内人のミョンチョルさんの奥さんも「よど号杏干し」に触発されつくるようになり、さらには長男がその「母の味」を覚え、結婚してからは若夫婦で杏干し漬けをやるようになった。じわり朝鮮に広がる杏干し漬けのお話しだが、ささやかな日朝親善ができたとかなと思えたものだ。
極めつけは、先週、市場に行った森さんが「杏の塩漬けが売ってたよ」! という吉報をもたらしたこと。杏をただ塩漬けにしただけのビニールパック入りのものだ。蜂蜜を入れて食べるとけっこうおいしいとか。
朝鮮には杏がそこら中にあって、「果物」として売られているが、果物的消費には限界がある。おそらく現消費量の十倍以上の杏が熟したまま毎年、木から落ちてゆく。こうした大量の余剰杏を塩漬けにすれば食材として役に立てられるはず、誰が目をつけたか知らないがいい着眼だと思った。
欲を言えば、さらにこれを“梅干し”ならぬ“杏干し”として企業的に食品加工工業としてやれば朝鮮の人々の食生活を潤すことになるだろう。私の夢想の羽は大きく広がっている。
人生の一場面を照らす演歌
赤木志郎 2021年7月20日
BS放送で森進一を迎えての番組があった。もともと私と同じ年代で、ハスキーで優しく包み込むような声でダイナミックに唄う森進一を気に入っていた。
鹿児島から中卒後、集団就職で大阪の寿司屋で働きはじめた彼にとって東京は別世界でしかも歌手はそのまた天上の世界であり、歌手になることなど考えたこともなかった。しかし、もって生まれた才能が彼をほおっておかなかった。17歳のときフジテレビののど自慢コンクールで6週一位となり、チャリー石黒氏に見いだされ歌手への道を歩む。はじめは断り、幾度かの誘いで母親に相談して決めたという。デビューも偶然、練習曲を聴いた人が決めたという。
私がTVで初めて森進一が唄うのを見たのは、高校生のときの深夜だった。あまりの上手さでいっぺんに引きこまれた。彼がデビューして今年で55周年を迎える。
私が好きなのは、「おふくろさん」と「さらば友よ」だ。とくに、「おふくろおさん」歌の導入で森進一が自分で「いつも心配かけてばかり、いけない息子の僕でした」を付けて唄っていた。母への思いがジーンと伝わってくる。森進一だけでなく多くの人々の心情ではないのではと思う。私もそのフレーズだけまず覚えてしまった。それが、作詞家川内康範氏の抗議により唄われなくなったのは残念だ。
「さらば友よ」は恋のために列車に乗り去っていく友人への思いを唄った歌だが、私には革命のために奔走する私とそれを見送る友人の姿が重なる。ハイジャック前にカンパを募るためで大学での知り合い幾人かに会った。ある時には友人の下宿に立ち寄り列車表を手にして別れ、ある時には環状線のとある駅で、ある時は大学の近くで、一瞬、会ってちょっと不安そうな眼差しを受けながら旅立ち、それが友との最後の別れとなった。
演歌が好まれるのは、演歌が人生の一場面をスポットライトで照らすかのように浮かばせるからではないだろうか。
TVで見ると森進一さんは随分、老けられたが(失礼! 私はもっとそれ以上)、健康で長生きされ、これからも人生の歌をしみじみと唄いあげてもらいたいものだ。
返事がきました
森順子 2021年7月20日
私たちは、あるサイトと縁があって投稿させてもらっているのですが、今回は、アンケート形式で18個の質問を送ったところ、ロスジェネ世代の方から丁寧な返事が来ました。一番感じたことは、どの答えも現実が反映された重たいものだということです。ここから日本をみて、未来社会を描こうよなんてノー天気に言えないということ、
その前に、様々な人々の悲しみが軽薄な明るさで埋もれ自分の意志表明もできない世のなかへの憤り、そして、それを表現すらできない人々の思い、こういうところまで至って今、一度考えなければと、その大切さに改めて気づかされました。
もう一つは、バランスがとれた食事をとることが大変だということ。とくに若い人の食生活は気になるところだと言います。簡単で便利なファーストフードだけに偏っているのでしょうか。最適な生活を送るには、何よりも栄養バランスのとれた食事ですが、溢れるくらいの食品のなかで何が人にとって良いものかを見極めるのは難しいですよね。今は、持続可能な社会とか言われますが、でも、まずは持続可能な人間でなければ。そのためには、食育を考え食生活改善からだと思ったりしました。
また、私たちに対してアドバイスも下さり、このようにサイトや文章をみて下さる人が少しでも増え今回のような交流ができるよう学び工夫していきたいと思っています。
苦戦するソフトバンク
小西隆裕 2021年7月5日
最近、ソフトバンクが苦戦している。
と言っても、何のことかと思われるだろう。日本のプロ野球の話だ。
これまで5年連続で日本シリーズを制してきた常勝ソフトバンクがパリーグの3位から5位の間を勝率5割前後でウロウロしている。
福岡で育ち、西鉄以来、福岡の歴代チームを応援してきた私としては、朝のニュースでその敗戦を聞くたびに、もう一つ浮かない毎日なのだ。
その原因は、主力選手の怪我などいろいろあるだろう。しかし、一番大きいのは、流れだと思う。
何事にも、勢いや流れというものがある。
テレビで選手たちの顔を見ても、昨年まであった余裕というか、生気、覇気というものが感じられない。皆何となく緊張している。
これでは勝てない。実際、試合でも、ここで勝ち越しという時にもう一本が出ず、負けたり、引き分けたりしている。
もう少しして、オールスター戦が終われば、後半戦に入る。
監督、選手たちがこの苦境をどう脱するか。勢い、流れをどう取り戻すのか。
私にとっての見所はその辺りにある。
「TRUE COLORS」その2-色々いろいろ想像してごらん?
若林盛亮 2021年7月5日
先月の「よど号LIFE」に「TRUE COLORS-あなたの本当の色は美しい」を書いたら、これを読んだ方から、あの歌のいろんな資料がどっさりメールで送られてきた。
歌の題名はやはり「TRUE COLORS」、歌ってるのはシンディー・ローパー、80年代に旋風を起こした女性歌手だ。ご存じの方も多いと思う。30歳でデビュー、遅咲きのスーパー・スター。
この歌は全米でも日本でもヒットチャート1位を記録した。
「あなたの 本当の色は 美しい」という「TRUE COLORS」は、米国ではゲイのデモのテーマ曲にもなっているそうだ。元々、シンディ・ローパーのゲイの友人がエイズで亡くなったり、身近に「自分の色」によって迫害を受けたりする人がいて、彼女はこの歌を歌ったのだとか。
そして彼女の有名な逸話。
東日本大震災直後、日本公演を予定していた全アーチストに帰国するか来ないように通告があった。国際空港は閉鎖、でも彼女だけは横田の米空軍基地に臨時着陸してまで公演をキャンセルしなかった-「こんな時だからこそ行く」が彼女の信条。東日本は原発事故の放射能汚染、余震の危険に皆が戦々恐々のさ中の出来事だ。交通手段がなく徒歩帰宅や避難の人でごった返しの道路、横田から都心に入るのに手間取り翌早朝にやっとホテルに到着したという。さらにはコンサートでは被災者支援の募金を募ることまで彼女はやった。
そんな彼女だからこそ「もし耐えられなくなったら 私を呼んで すぐ行くから」と歌えるのだと思う。
この歌に救われ勇気づけられた人はどれだけ多いことだろう。異端、異色と見られていた青春時代の私は自分に自信というものが持てなかった。だからこの歌の世界がわがことのように思える。
十人十色、人にはそれぞれ色がある。「私には見える 大好きな色 こわがらないで 見せてね」と言ってくれる人はゼッタイ必要、みんなが輝けば国も社会も輝く。
生産性や効率だけで人の価値は決まらない、どんな人も存在すること自体に価値があるという山本太郎の考え方がいま支持を受けつつある。
国だって同じだ。十国十色、世界の国にもそれぞれの色がある。社会主義国だって中国式、ベトナム式、ラオス式、キューバ式、それに朝鮮式と色とりどりだ。十国十色を国際社会が「あなたの色は 美しい」と言えるようになれば、どれだけいいことだろう。
シンディ・ローパーの歌った「TRUE COLORS」が政治の世界にも広がる、そんな時代に向かう予感がする。
そんな世界を想像してごらん? 私はけっして夢想家じゃないと思います・・・
よど農園、近況報告
魚本公博 2021年7月5日

よど農場の初きゅうりと青じそ
久しぶりに、よど農園管理人からの一報です。
今年は雨が多く草取りが大変。毎日、5時から6時半の夕食までの1時間ほどの作業ですので、芽生え始めたものをスコップで削ってさっさと済ますやり方です。それに雑草もあった方が野菜も雑草に負けまいと何かしらの力を蓄えるからか美味い感じがするので余り神経質にならず、大ざっぱにやっています。
今は、キウリが収穫時、黒田さんが毎日のようにバケツに収穫してはアパートの階段に置いて、必要な人に持って行ってもらい、余ったものは食堂に。
そしてキャベツ。前から欲しかったのですが中々種が手に入らなかったもの。それを今年ようやくゲット。小ぶりですがちゃんと玉を撒いて育ちました。取り立ては水々しく柔らかで焼きそば、焼きめしの具にすると最高です。
トマト、ナス、インゲンも花を付け、もうすぐ食べられます。あっ、それからピーマンも市場で買ったものから種を取って植えたところ芽吹き育苗中。ピーマンは高値なので、これも育てば皆に喜ばれるでしょう。
ま、そんなところです。

新鮮でシャキシャキ感が
朝ドラ「おかえりモネ」
若林佐喜子 2021年7月5日
宮城県気仙沼出身のモネ(百音)が天気予報士を目指し、ふるさとに貢献する道を探すという物語で、すでに第7週。今週は、3.11の惨事を目の前にして、何もできなかったことがトラウマになっている自分の心に気づきはじめたモネ。そんなモネに「誰もが、自分は何もできなかったということを多少なりとも抱えている。でも次はきっと何かができるようにと強く思う」と、自らの体験と言葉で、励まし背中を押してくれるベテラン天気予報士の朝岡さん。衝撃的な体験のなかで、自分が何をしたら、どう生きたら良いか悩むモネ。そんなモネは登米で村の人たち、特に夏木マリこと「サヤカ」さんとの生活で、山や海、空は繋がり循環している、人々の生活、人生も。と、いうことに気づかされていきます。
東日本大震災で、気仙沼は地震と津波で大火災が発生しました。2012年に訪朝された今は亡き川口和子弁護士が「当日、事務所から避難しながら7時間かけて自宅に帰った。もし途中で気仙沼の惨状を知っていたら自分はその場で倒れてしまい起き上がれなかった」と話された。その衝撃的な言葉が私の脳裏にインプットされていて、今回、その気仙沼が舞台ということで、興味深かったのです。モネが3・11当日を回想する場面では、川口先生の言葉が重なって見えたかのようでした。
震災後、「3.11世代」という言葉とともに、若い人達の中で「世のため、人のためになることを」という機運が高まったと伝え聞いていました。人は、痛みも怒りも、そして喜びも共有し、そのなかで自分の役割を探し、果たそうと努力する存在。と、いう思いを改めて強くしました。
今、日本は、コロナ禍という国難に見舞われ、異常気象から自然災害も多発しています。そのような中で、多くの人たちが、特に若者たちがモネのように自分の役割を探し求めているような気がしてなりません。私自身も自分に課せられた役割を果たせるよう努力していこうと思います。
モネと若い菅波先生のやり取りを楽しみにしながら、朝ドラにはまっている7月の私です。
集団検診の日
小西隆裕 2021年6月20日
今日は、年に一度、恒例の集団検診の日だ。
朝、ミネラルウォーターをコップ二杯飲んだだけで出発のバスに乗り込んだ。
そこで誰とはなしに持ち上がったのは、検診後、市街の食堂で食事して帰ろうという話。
これまで十数年、一度もなかった話なのに、全員一致でそういうことになった。
そこでわれわれの食堂のお姉さんにその旨断って、出発。
胃カメラまで飲み、流れるように全員の検診が終わったのが午前十時半。
少し早すぎるが、買い物や喫茶も兼ねて、大使館街の商店経営の新しくできた食堂に行ってみた。
いつもわれわれが商店に買い物に行くたびに目にするこの食堂。
レンガの柱にガラス張り、その瀟洒なつくりの割には客の姿が見えない。
食事時でないのを割り引いても、余り期待は持てない。
なのに、その選択に反対の声は挙がらなかった。
やはり皆の心の片隅に、なにがしかの興味があったのだろう。
結果は、「当たり」と言ってよいものだった。
歳の割には、若干食べ過ぎ飲み過ぎて帰還後、
一時間ほど横になってから、日程通り2人対2人バレーまでやった。
少しふらつく状態で、ちょっとオーバーかなという思いもあったが、やはり最後までやってよかった。
後期高齢者前後のわれわれの一日でした。
若林盛亮 2021年6月20日
TRUE COLORS-あなたの本当の色は美しい
BS放送、私の好みの「FOR YOU-静かな夜のSongbook」、DREAM編でとてもいい歌に出会った。録画したので最近、ささやくようなその女性ヴォーカルを毎日のように聴いている。
歌の題名は字幕が読みづらくて不明だがたぶん「TRUE COLORS」(本当の色)といったものだろう。
悲しそうな目ね
弱気にならないでほしいの
難しいよね
自分らしく生きるって
・・・・・
「だけどあなたの色は輝いている 私には見える (私の)大好きな色 こわがらないで 見せてね」と続き
true colors / あなたの本当の色は
are beautiful / 美しい
like a rainbow / 虹のよう
で終わる。
ぐっと来るのは「もしおかしくなって 耐えられなかったら 私を呼んで すぐ行くから」と呼びかけてくれる歌詞。
十人十色というが人それぞれに「自分の色」がある。でも本当の色はどんな色なのか、自分のそれは輝く色なのかなんて自分で気づくのは難しい。
でもこの世にたった一人でも「あなたの本当の色は 美しい」と言ってくれる人がいたらどれだけありがたいことだろう。
自信が持てなくて弱気になったりおかしくなりそうなとき、
「私を呼んでね すぐ行くから」と言ってくれる人、「あなたの本当の色は美しい」と挫けそうな気持ちを奮い立たせてくれる人がいたら強く生きる勇気がわいてくる。
私もお先真っ暗で挫けそうになるとき、いつも誰かに助けられて何とかここまでやってこれた。朝鮮に来てからの50年もそうだ。
古希を過ぎたいまも「本当の色」は何なのか、それを探すための旅は続いている。
十人十色、みんなの色が輝けばどれだけいいだろう。
できるなら「耐えられなかったら 私を呼んで すぐ行くから」と言える人にいつかはなりたいものだ。
喫煙者の言い訳
赤木志郎 2021年6月20日
世界的に禁煙が当然のことになってき、それに合わせ朝鮮でも公共場所の禁煙の法律が出たのが数ヶ月前。それから、喫煙者にとっては非常に不便になっている。灰皿が設置されていない所では吸えない。その灰皿が撤去されるともうお手上げだ。統一通りの市場前もそうなった。テソン百貨店前もそうなった。もちろん、食堂などはたとえ灰皿があったとしても論外だ。だから、目に見えて喫煙者は激減した。
ところで、ある時、数年前に購入していたバラの刻みタバコの塊が出てきた。湿気が少ないので変質していなかった。紙で巻いて吸う方法があるが、上手に巻けない。パイプかキセルなら吸えると思い、それも捜し出した。パイプやキセルを使って吸うと、肺まで吸い込まないで吐くだけなので喉にも悪くない。しかもフィルター付きのタバコより味わいがある。ただ、ヤニを取り除く掃除が大変だ。
TVの時代劇にはキセルがよく登場しているが、かつて喫煙も一つの文化だったと思う。紙タバコのない頃は、量的に多く吸わなかった、いや吸えなかった。キセルではまさに一服だけだった。キセルやパイプを嗜むのもあまり周囲にも迷惑をかけず、健康にもそれほど害にならならず、味わいがあるので、悪くないではないかと最近、思っている。
どんな文化にも価値がある
魚本公博 2021年6月20日
ユネスコの世界文化遺産に「縄文遺跡群」が登録される見通し。事前調査する諮問機関「国際記念物遺跡会議(イコモス)」が「登録」を勧告。7月16日からのオンラインによる「世界遺産委員会」で最終審査され登録が確定します。登録されるのは、1万5000年前の土器片が出土した「大元山元(おおたいもとやまもと)遺跡」、縄文都市と言われる大集落跡の「三大丸山遺跡」、ストーンサークル祭祀の「大湯環状列石」など北海道、北東北17カ所の遺跡群。
長年、日本政府に国内推薦を働きかけてきた人たちは、「これらの遺跡群は、人々が採集・漁労・狩猟で定住を確立した過程を示し、農耕文化以前の人類のあり方や精緻で複雑な精神文化を顕著にしめす物証」と指摘。これがユネスコ諮問機関の勧告理由にもなりました。
今回の縄文遺跡群「登録」の背景には、ユネスコが選考基準を変えたことがあります。これまでの登録が西欧型の石造りの宮殿、教会、町並みなどに偏っていたことへの反省。そういう西欧的基準で文化に優劣を付けることへの反省。
縄文遺跡群はそれに合致していたということです。これまでの定説では、西アジアなどで農耕・牧畜の開始によって定住が始まったとされてきた。ところが縄文は、農耕以前の狩猟採集段階で定住を確立し、社会を発展させていた。
そのことについて、東京都立大の吉田康弘教授は「縄文は、その日暮らしの停滞した文化というイメージをもたれがちだが世界史上例を見ない文化」だと述べています。すなわち西欧的基準から見れば、遅れ停滞していたかのように見える縄文だが狩猟採集を基盤にしながら「定住」を確立し独自の発展を遂げていたのです。
結局それは、「どんな文化にも価値がある」ということではないでしょうか。「どんな人にも価値がある」「どんな地方・地域にも価値がある」「どんな国にも価値がある」など、それぞれを認め尊重する観点。それが求められる時代なのだと思います。
「新しい朝が来た」?
森順子 2021年6月20日
畑のサヤエンドウが実をつけたというので、早速取りに行ってゆでてみたところ、まったく柔らかくならず、あっ、これは旬が過ぎてしまったということだとわかりガッカリ。何事も食べどきがあるってこと。でも、大根の葉やニラ、ホウレン草は、食べ頃、そして待っていたキュウリもいくつかでき、今年はキュウリ豊作になりそうです。
「新しい朝がきた 希望の朝だ」で始まる朝6時30分からのラジオ体操のうた。
少し窓をあけ、テドン江を眺めながらラジオ体操をやっています、今月から。体操は、このうたを聞いてからですが、このラジオ体操のうたは、いつ頃から始まったのでしょうか。最近は、「新しい朝が来た 希望の朝だ 喜びに胸を開け 大空あおげ・・・」と、言われてもなかなかねーという気持ちになるからです。どれくらの方が希望あふれる朝をむかえられているだろうかと、ふと思います。それでも背中を押され、今日一日、頑張ろうという前向きな姿勢で体操する人が多いかも知れません。「新しい朝が来た」と思えるには、まずコロナを収束させてからでしょうか。清々しい気持ちで体操できることを願いながら、そのときまで、私も続けられればいいなあと思っているところです。
野生動物の天国
小西隆裕 2021年6月5日
最近、わが日本人村の鳥たちの逃げ足が遅くなった。
キジだけではない。カケスや名も知れない小鳥たちも私が近づいても、なかなか逃げようとしない。
そんなことを思っていたある日、朝鮮の運転手の人が笑いながら言っていた。
「近頃、何度もキジを轢きそうになった。鳥も、コロナ以来、野鳥にさわるなとなっているのを知っているようだ」。
野生の動物は、地震など天変地異に敏感だと言うが、人間社会の変化にも敏感なのかもしれない。
日本人村だけではない。朝鮮全体が野生動物の天国になっているのに違いない。
私は、今、そのように合点している。
ピョンヤンの夜に舞うホタル
若林盛亮 2021年6月5日
5月末のある夜、事務所に向かう坂道でホタルを見た。
暗闇に点滅する青白い光、それはまぎれもなくホタル! 一匹のホタルが光を放ちながらゆらゆら飛んでいた。
「村」は大同江べり、湿地もあってホタルの生息場になるらしく夏の夜にはたくさんの点滅する光が何とも言えない情緒を醸し出す。でも5月末にもうホタルが見えるのはめずらしい。しばらくホタルに心を奪われて揺れる光を見ていた。
幼い頃、私の隣町に源氏蛍の名所があって母に連れられて見に行ったときはほんとうに驚いた。
無数の源氏蛍が密集して発する光が大きな塊になって揺れ動く光景は子供心にも幽玄境に誘い込まれたものだ。
京都での学生時代に鴨川上流で見たホタルにも特別の想いがある。
ドロップアウトはしたけれど一寸先は闇、空虚と迷いを抱えていた頃、私はある人の下宿近くの夜の鴨川に誘われた。そこには多くはないがホタルが青白い光をひいて夜の河原を飛んでいた。
こんな街中にもホタルがいるんや! 私はしばらく見とれていた・・・「闇の中にも光があるんだよ」となにか背中を押してもらった気がした、とても癒されたことを覚えている。いま思えば、同伴してくれた人の気遣いだったのかも知れない・・・
ピョンヤンに来てからのホタルには「日本人村」の夏の風物詩以上の感慨はなかった。
ある時、野坂昭如原作のアニメ映画「蛍の墓」を見た。
戦災孤児となった幼い兄妹の悲しい物語。敗戦直後日本の食糧飢饉で妹は餓死、兄は妹が大好きだったドロップの空き缶に妹の骨を入れ大切に身につけた。しかしその兄もついに上野駅で餓死、駅員が死体から出てきたドロップの空き缶を無造作に草むらに捨てる、するとそこから無数のホタルが光の帯となって空に舞い上がっていく。悲しくも美しい夢幻の世界。
また「ホタル」という高倉健主演の映画も見た。朝鮮人の特攻隊員が「自分は朝鮮人のために死ぬ」という言葉を残して出撃、帰らぬ人となったその夜、一匹のホタルが現れる。それは朝鮮人特攻隊員の鎮魂されないでさまよう魂なのだろう、そんな映画だった。
それからは闇夜を舞い上がる青白い光を見ると、ホタルは何を訴えているのだろう? そんなことも考えるようになった。
ホタルには不思議な魔力がある。
在朝華僑の人たちを見て
赤木志郎 2021年6月5日
日本、朝鮮、中国は地理的、歴史的、文化的に近い。欧州の人から見れば中国人、朝鮮人、日本人が同じに見えるが、その地理的環境と民族の違いがある。そして、それぞれの故国と離れ暮らしている人々がいる。中国に朝鮮人が多く暮らしているように、ここ朝鮮にも中国人(華僑)がかなりいる。
最近、時々、在朝中国人の人たちを見かける機会があった。かれらを眺めると、中国大陸の人たちと違うし、だからと言って在中朝鮮人や朝鮮人とももちろん異なる。一つの独特な集団をなしている。顔と服装は皆、違うのに、同じ集団だとすぐ気づく。何か共通性があるのだ。中国人だが朝鮮語を話し、服装も小綺麗にしている。女性の髪型なども一人ひとり異なるが、同じ美容院でセットしているのか雰囲気が同じだ。彼らに一つの共通性を感じるのはやはり中国人の血をひいているからだと思う。
私が生まれ育った神戸も在日中国人、在日朝鮮人が多かった。高校のラグビー部の一年下の部員のほとんどが中国人だった。クラスの友人には朝鮮人が多かった。かれらは日本語を母国語のように話すし、ほとんど日本人と変わりがない。異なるのは、日本社会で就職できないなど差別を受けていることだった。しかも、当時は故国が朴正煕の軍事独裁下にあった。政治が彼らの人生に暗い陰を落としていた。
ここ朝鮮での定住中国人にはそういう暗い陰がなく明るい。大国となった自信から来るのか、朝鮮の地で民族的権利が保障されているからなのか。どちらかというと、民族的権利が保障され、社会的地位が安定しているからだと思う。
台湾を戦場にする、というのか
魚本公博 2021年6月5日
台湾は親日国と言われます。それもあってかBSでも台湾の風景、食や温泉、旧植民地時代の町並みなどを紹介する番組をよく見かけます。この前も「迷宮グルメ」で「ひろし」が台湾に行っていました。こうした番組を通じても台湾の人の親日感情をうかがい知ることができます。今年はコロナ禍で日本には行けないので、せめて台湾桜の下で日本の桜見物気分をと、台湾桜の名所に大勢の人が出向いたとか。
こうした台湾に対し、今「台湾有事」が大きく取り上げられています。そのきっかけは米国のインド太平洋軍司令官の「中国は6年以内に台湾を武力侵攻する可能性が高い」発言。そこで日本の親米派、軍拡派が有頂天になって、「台湾有事は間近、日本は台湾を軍事的に支援する体制を早急に整えなければならない」というのですが、ちょっと待てです。それって、台湾を戦場にするということではないのかと。そんなことは台湾の人も望んでいません。
台湾問題は、「一つの中国」の国内問題であり、「両岸問題の平和的解決」が中台両国政府が「合意」する基本路線です。日本は、その「合意」を助けるべきなのであり、米国が仕掛け、「可能性が大」などという為にする「ガセネタ」に乗って、軍事支援を云々するなどもってのほかではないでしょうか。
台湾に対しては、日本も国民的感情として親近感をもっています。その感情を逆利用するかのような「軍事支援」論。BSで見る台湾の美しい風景、人々の親しげな態度や表情を思い出しながら、それはないだろう、そんなことは許されない、許してはならない、との思いを強くします。
田植え「戦闘」
若林佐喜子 2021年6月5日
すっかり深緑の季節です。朝鮮では、先月、総動員で田植えがおこなわれ、現在、青々とした田圃では稲の苗がすくすく育っています。気候不順と激しい朝晩の温度差で苗床の管理も大変ですが、苗が一定の大きさに育ったら最適時に質を保障して一気に植えなければならないそうです。その間は、毎日テレビで、現地からの報道をやっていました。田圃に入ったアナウンサーが仕事を手伝おうとすると、それより歌を歌ってくれとの農場員の要請に答えて歌う場面もあり、つい笑みがこぼれてしまいました。農業は大変だなあーという思いと、まず農業で国の経済の突破口をきり開くという農場員をはじめ朝鮮の人々の気概、熱意にちょっと圧倒されてしまった5月でした。
さて、よど農場も、先日、皆でナスの苗を植えました。穴を掘って肥料を入れ、栄養ポットの苗を置いて土をかけてしっかり抑えます。作業は30分ほどで終わり、最後は、冷たいビールで一息でした。その日は雨模様でナスの苗も水をたっぷり得て、その後もすくすく育っています。その日撮った写真を改めてみたら、土への愛着がにじみでている手、ぎこちない手、やったふりの手、いろいろでした(笑)。これまでは、アスパラ、ほうれん草が食べ頃でしたが、これからは、サヤエンドウ、大根、キュウリなどが楽しみです。
日本では、コロナ禍の影響、巣ごもりで、自宅で料理をする人が増えている一方、食品類の価格が上昇しているそうです。本当に色々と大変ですが、意識的に免疫力を高める食事をとり、感染防止と健康管理にくれぐれも注意して下さい。
PCR検査を受けた
小西隆裕 2021年5月20日
5月初旬、PCR検査を受けられるとの連絡が来て、その翌日皆で受けた。
正直言って、日本のテレビ報道などで、綿棒を喉や鼻に突っ込むPCR検査を見ていたので、少し覚悟して、検査室に入ると、防疫服に身を固めた中年の女の人が二人、そのうち一人が口を開けろと言う。
だが、検査は思いの外簡単だった。唇の裏と奥歯の辺りから綿棒で唾液を採取しただけでOK。綿棒は喉の奥には入れられなかった。結果は明日分かるという。
次の日、めでたく全員陰性。
こんな検査がなぜ積極的にやられないのか、日本の状況を改めて思った一日だった。
ピョンヤンの若き「八方美人」医師
若林盛亮 2021年5月20日
今回もピョンヤンの友人のことを少々。
若き医師、K君のこと、彼は30代半ば、私の長男と次男の中間に当たる世代、いわば息子のような若者だ。
彼は5月初旬に行われた「保健部門体育大会」バレー部門に出場した。
「保健部門体育大会」は毎年この季節、春から初夏にかけて行われ、昨年はコロナ禍で中止となったが今年は道(日本なら都道府県)対抗体育大会に続いて開かれた。バレー競技は1,2部のリーグ制で彼の病院は2部リーグに所属する。なんでも医師、看護婦、職員が千人以上は1部、それ以下の病院は2部所属となっているらしい。
K君はセッター、攻撃を左右、センター、あるいは後ろからのバックアアタックとか振り分けるいわばチームの司令塔、攻撃の要を握る選手だ。
結果は? と聞くと約10チーム中の3位だったと悔しがっていた。
聞くところによるとビッグスリー、強豪は固定されていて1,2,3の順位も毎年変わらないそうだ。どうしても上位チームの牙城が崩せない、今年は世代交代でベテランが抜けて若い新人が多数入ってまだチームができあがってない、これからチーム作りだと来年に向けて奮起中とのこと。
このK君、民間防衛組織の赤衛軍では射撃の名手、病院の文化サークルでは歌もできドラムもたたける万能選手として職場でも重宝がられている。
病院の女子バレーが組織されたときはコーチもやった。性格は素直で真面目、イケメンだから女性にももてるタイプ。
結婚4年目、若い奥さんと3歳の男の子があり、子供の名前は1週間かけて自分が考えたといういいお父さん。でも一時は「夜泣きがうるさくて慢性的睡眠不足で困ってる、ときどき赤ん坊が憎たらしくなりますわ」とぼやいていたが、私はきっと赤ちゃんと奥さんの寵(ちょう)を競ってやがるんだと邪推した。いまは成長した子供の写真を見せたり子煩悩のいいパパになっている。
実はこのK君も前回書いたネット技術者同様、かの「世界的サッカー名手」メッシ所属のバルセロナFC(スペインのクラブ)信奉者、英プレミアリーグのリヴァプールへの改宗を狙っているが、なかなかその牙城を崩せない。
病院では有能で患者に誠実、バレーでは相手を恐れさせるセッター、赤衛軍では名狙撃手、芸術ではいっぱしのミュージシャン、そして家庭では愛妻家にしてよき父、この「八方美人」の若者は朝鮮で大切な私の友人。ちなみに「八方美人」は朝鮮では文字通り多能多才の人を意味する言葉。
この若者の未来に日本人の古希過ぎ爺さんがやれることはあまりないが、応援だけはできる。これが私の国際主義だと思って、これからも彼のよき友人でありたいものだ。
一人は全体のため、全体は一人のため
赤木志郎 2021年5月20日
PCR検査のために市内の親善病院に往く途中で、大きな看板で「一人は全体のために、全体は一人のために」というスローガンが目に入った。このスローガンが掲げられるのは社会主義・共産主義建設をめざす朝鮮において当然のことといえよう。しかし、この数十年間、建物の中で掲げられていても街の目立つところでこのスローガンが掲げられるのは見たことがない。それで「おやっ」と思ったのである。
今年になって、党中央委員会や青年同盟大会で「一人は全体のために、全体は一人のために」というスローガンが強調され、TVでも職場での共産主義的気風が報道されている。だからなのだろう。
日本でもこのスローガンが掲げている所があった。大学生だったとき、灘生協の店に入ったときに、壁に大きく書かれた「一人は万人のために、万民は一人のために」の字が目に入り、少々びっくりした。生協運動の理念となるくらい、この思想が魅力あったのだろう。
言うまでもなく、「一人は全体のために、全体は一人のために」という集団主義は、社会主義・共産主義思想の核をなしている。これまで、世界各国での社会主義をめざす革命闘争においてこのスローガンがよく掲げられた。各国における社会主義運動がさまざまな紆余曲折を経る中で、唯一、一貫して社会主義・共産主義建設を進めてきた国は朝鮮だ。共産主義的道徳美風模範の大会もこれまで何回か開かれた。毎年、困難な炭坑や離島に志願して行く青年たちがいる。そして、国は台風などで被災した地域を都市での住宅建設を中断してまで一気に復旧し、かつてより幾倍もの立派な住宅を建設していく。そこから起きる「社会主義万歳!」の声。
スローガンが建前としてではなく、生活に根付き具現しているものとしてそのスローガンが掲げられている。街の真ん中でこのスローガンが掲げられるようになったのは、社会主義・共産主義建設の新しい段階に入ったのではないかと感じている。
疫病が国のあり方を変えた
魚本公博 2021年5月20日
先日見たNHK・BS放送の「英雄たちの選択」。主人公は橘諸兄(たちばなのもろえ)。奈良時代・聖武天皇の頃の政治家。墾田永世私財法を制定した人です。
この頃、天然痘が大流行し実権を握っていた藤原氏の武智麻呂・房前・宇合・麻呂の4兄弟(藤四子政権)を始め貴族や役人の多くが死亡するなど政府は機能不全の状態に陥ります。そうした中、実権を握った諸兄は、緊縮財政、農民の負担軽減に務め、743年に墾田永年私財法を制定するわけですが。これはそれまでの律令制度を止めたに等しく、いわば天然痘という疫病が「国のあり方」を根本的に変えたというのが番組の趣旨でした。
番組終わりのコメントでメイン出演者の歴史学者・磯田道央さんが面白いことを言っていました。すなわち、こうした大混乱が起きると、日本人の価値観、情念のようなものが表に出てくるのではないかと。
確かに律令制は中国・唐からの輸入品。それを廃止し農民の土地私有を認めるというのは、日本的価値観を認め活かすということであったのかも知れません。
今、コロナ禍の中で、これまでの新自由主義的な効率第一の価値観、さらには資本主義的なカネ第一の価値観に対して「コモン」とか「共生」などが言われ、もっと人間的な生き方をしようよというような声が高まっています。そして、それは日本人が歴史的に持つ日本的価値観に根ざしたもの。と見ることもできるのではないでしょうか。
コロナ禍という試練と混乱の中、人々は新しい生活、新しい社会を求める。それも私達日本人が持つ日本的価値観に基づくものとして。それが模索され実現されてこそ、本当にコロナにうち勝ったということになる。番組を見て、そういう思いを強くしました。ちなみに天然痘もウイルスによる疫病です。
川柳に目がとまり
森順子 2021年5月20日
5月の最初の週は雨も降り温度も下がりセーターを取り出したくらいです。黄砂と強風もやってきて私たち高齢者には要注意の日々でしたが、中旬からは田植えも始まりました。
先日、新聞を見ていたら川柳が目にとまりました。
「税で食う人ばかりがいる叙勲記事」「五輪やる 汝国民病んで死ね」
思わず、そうだよね、と納得する内容ばかり。3回目の緊急事態宣言になっても改善がみられず感染者は増えるばかりじゃないですか。当然ながらオリンピック中止の声が大きくなっていますよね。
それにしても、この川柳、応募する人のセンスのよさと的確さは学びたいところです。現実のなかで、不条理なことを感じながら、ちゃんと日本社会を冷徹にみて判断する人々の目は正しいんだと改めて思い知らされるし、そこには人々が望む社会や人間にとって一番大切なものが込められ教えてくれているようにも思います。
「おちよやん」その2
小西隆裕 2021年5月5日
朝ドラ「おちよやん」の視聴率がもう一つだ。1位は1位だが、20%に届かず、低迷している。
これは心外だ。それで「おちよやん」その2を書くことにした。
まず、出色なのは、毎週のテーマが明確で、山あり谷あり、一つ一つの劇に視聴者を引き込みながら、週を次いで全体の劇を展開していく手法だ。
そうした中、感じ入るのは、作者、脚本家の一人一人の登場人物への愛情の深さだ。一人一人が毎週変わるテーマの中、入れ替わり立ち替わり主役、準主役として登場し、皆個性的で、その他大勢は一人もいないということだ。
そうした中、主役の「おちよやん」こと杉咲花さんの演技が実に印象的だ。役になりきっている。特にその目がいい。観る者を引きつける迫真の演技だ。モデルの浪花千栄子さんとはまた別の大女優になっている。離婚し、一旦はやめるのを決意した芝居の世界で、新天地を見いだし成長していく「おちよやん」のこれからの姿を彼女なら、地で表現していけるのではないか。
観るほどに期待が大きくなる朝ドラ、それが「おちよやん」である。
ピョンヤンのネット技術者
若林盛亮 2021年5月5日
ピョンヤンには心おきなく話のできる友人が何人かいる。その一人がネット技術者のS君だ。
彼はインターネット・サーバーのスター社、タイとの合弁企業の技術者でメール故障の際などでお世話になっている人、不具合が起こると「村」まで来てくれて複雑な技術問題を解決してくれるありがたい存在だ。年齢は40代、うちの長男とほぼ同じ世代、私にとっては若い友人だ。
先々週の日曜日、ネット接続不能になって彼に来てもらった。
彼は「アイゴー(やれやれ)」とため息をつきながらやってきた。多忙な合間に来てくれたらしい。
聞くところによると、いまピョンヤン北東部、サドン地区にできるニュータウン、1万世帯建設場に派遣され、仕事はニュータウンの通信、ネット網構築という大事業の一端を任されているらしい。年内完成が目標の国家的プロジェクトだから日曜祝日返上で働いているとのこと。
不具合の原因は、接続機器の故障と彼は判断、違うものと取り替えてくれて彼の仕事は終わった。いつもながらスピーディーな判断、仕事ぶりはさすがプロ、なにやらプログラムをパチパチと打ち変えて手際よくメールを復旧してくれた。
仕事を終えてビールでのどを潤しながらの歓談。
「リヴァプール、負けましたなあ」とUEFA欧州チャンピオンズ・リーグ8強戦、スペインの強豪レアル・マドリッド戦のことをS君は語り出した。私が英プレミア・リーグのサッカークラブ、リヴァプールのサポーターと知ってのこと。
「もうクロップ監督もおしまいですなあ」とさらに挑発的な言動、これには私はがまんならず、「防御の主力が負傷欠場なんやから仕方ないやろ」と抗弁。
すると「そんな言い訳は通じません、レアルだって防御の要を欠いての勝利でっせ」「要は監督の采配ですやろ」と言ってきた。
「防御の要一人を欠くのと、主力三人を欠くのとはぜんぜん違うやろ! チームの攻守のバランスが崩れるという意味をわかってんのか」と私も譲らず。
彼は「ワッハッハ、そりゃ強がりでしょ? 結果は結果」と笑って取り合わず、私も息子のような相手にこれ以上、熱くなってもいかんと矛を収めた。
実はこのS君、かの「世界的名手」メッシ所属のバルセロナFC(スペインのクラブ)信奉者、数年前からリヴァプールへの改宗を狙っているが、うまくいかない。朝鮮のサッカー・ファンにはメッシ信仰が強い。私は「もうそれは時代の遺物」と説きまくっているが、この岩盤を崩すのは容易ではない。
でも朝鮮でサッカーを語り合える貴重な友人、あまり熱くなりすぎないよう、メッシを圧倒するリヴァプールの力を見せてやるしかないと根気強く取り組むつもりだ。
今日も彼はニュータウン建設場で愛国の知恵と技術をそそいでいることだろう。
「頑張ってや、S君」・・・そしていつの日にか改宗させたるよ。
メーデーの室内「野遊会」
赤木志郎 2021年5月5日
5月1日のメーデーの日に、日本人村の銀杏の木の下で野遊会をやろうということになった。
ところが当日は生憎の雨、シトシトと止まることなく降っている。しかも肌寒いくらいだ。どうするのかを思って事務室に行ったら、廊下にシートを敷き座布団もおき、焼き肉の準備がしてあった。
12時、全員が集まると、大盛りのアヒルの焼き肉が出された。久しぶりの焼き肉だ。しかも、訪朝団の方々と一緒に行ったことのあるアヒル焼き肉専門店から購入したものだから、見るからに美味しそう。食べてみると本当に美味しい。もともとアヒル肉の焼き肉は美味しいが、この日の焼き肉は特別に「おいしい」。専門店の肉を自分で焼いて食べるのが特別、美味しいのかもしれない。タレもその店のものだ。
飲み物は朝鮮製葡萄酒で一番、高価のものだ。といっても12$くらい。私がいつか飲みたいと思っていたものだ。好みにより焼酎、ビールもある。
4キロのアヒルの肉があっという間になくなった。晴れていて野外でできればもっと良かっただろう。
訪朝団の方々と一緒にした賑やかな焼き肉の野遊会を想いだされた。コロナ禍が収束し、訪朝団の方々が再び村に訪れるようになればと思わずにいられなかった、そんなメーデーの日だった。
最近、「言葉」に引っかかる
魚本公博 2021年5月5日
近頃、年をとったからか日本的な言葉や言い回しで妙に気になり引っかかることが増えました。例えば「木で鼻をくくる」という言葉。これは菅首相のぶっきらぼうで話しをはぐらかすような答弁ぶりを批判した表現ですが、一体どういうことなんだろうと食堂でも皆の話題になりました。辞書を見ると元来は「木で鼻をこくる」という「こくる」(掻く)が誤って「くくる」になったものとありました。ちょっと前には「人を食う」も話題になりました。人を人とも思わない態度ということですが、それを「人を食う」と言うのは、確かに釈然としない表現です。
その他にも、私的には「頓珍漢(トンチンカン)」とか、うさんくさい、鼻を明かす、手が焼けるなど色々あります。トンチンカンは、BSの歴史番組で刀を鍛錬するときトンチン、トンチンとリズムを刻んでやるのにリズムを壊すようなカンという音が入ることをもって、場はずれな答え、行動を指していう言葉だと知りましたが、うさんくさいは辞書を見ても分かりませんでした。
若いときには、こうした言葉は話しの流れの中で、あまり頓着せずに使い聞いていたように思います。それで、年をとると思考が深まり若いときには気付かなかったことも色々と考えるようになるものだと思っていました。しかし一方で、年をとると変なところを気にし、こだわるようになるということなのかなと思ったりもします。
思考が深まるのはいいですが、「こだわりじいさん」はいただけませんね。心しなければ。
ふしぎなサボテン
若林佐喜子 2021年5月5日


日本人村はすっかり新緑の季節になりました。そんな中で、ピンクの芝桜、ライラックの花が目を楽しませてくれます。
さらに興味をそそられるのが、事務所の談話室に置かれた鉢植えのサボテンです。背丈は60㎝位の棒状で棘があり、18㎝位の細長い葉をつけています。不思議なのはピンクの花なのです。丸っこい緑色の葉状態から徐々にピンク色の花に変わり、その花の上に蕾が数個つき花を咲かせ、またその上に蕾をつけ、3、4段に。そんな状態の花がすでに10箇所。夏の季節に一番花をつけるということなので一体どうなるのだろうと毎日楽しみに眺めています。
サボテンは多くのO2を出すので、健康にも良いとのこと。挿し木で増やし、みんなの部屋におこうと試みています。残念なのは、名前がわからないこと。サボテンでも愛嬌がありますが、是非どなたか名前を教えて下さい。
それにしても、3度目の緊急事態宣言を発令する状態にしておきながら、いまだ「五輪はやる」との菅政権の暴走ぶりには、心配をとおりこして怒りを感じる5月です。どうか皆様、くれぐれも感染防止と健康管理に留意なさって下さい。
キジの家族
小西隆裕 2021年4月20日
 浚渫船が行き交う大同江
浚渫船が行き交う大同江
春になって、わが日本人村にもキジの数が増えたように思う。
目に付くのは、やはり圧倒的に雄のキジだ。
私の姿が見えても、悠然とコンクリート道路上を歩いている。
その距離が縮まると、おもむろにこれまた悠然と茂みの中に入っていく。
雌はほとんど見かけない。
よく見ると道路の傍らの茂みの中に潜んでいることがある。
また、私と出会うと、真っ先に茂みの中に身を隠すのも雌の方だ
そうしたある日、私が宿舎の角を回って急に姿を現した時のことだ。
けたたましい鳴き声で雄のキジが飛び立った。
と同時に目に入ったのが芝生の上で遊んでいた母と子のキジの一団だ。
小さな子供たちが転がるように必死で茂みの中に駆け込む。
その時、普段見ない光景を目にした。母鳥が悠然と芝生の上を歩いているのだ。
私が近づいても歩みを速めず、最後まで悠然と茂みの中に入って行った。
それを見て私の頭に浮かんだこと、それは「母は強し」だった。
と、ここまで書いて皆に見せたら、
雄は父性愛が弱いから真っ先に逃げたのではなく、外敵の目を自分に引きつけるため大声を上げて逃げるのだという。
なるほど。
それでタイトルも、「キジの母性愛」から「キジの家族」に替えることにした。
 日本人村の春の風景
日本人村の春の風景
ピョンヤンの理髪師-その2
若林盛亮 2021年4月20日
前に書いた「ピョンヤンの理髪師」のその2、続編、4月初旬頃のお話です。
春の陽気が辺り一面ただよう中、ひいきの床屋に行った。例のプロの職人芸のお店だ。
「もういらっしゃる頃だとお待ちしてましたよ」との理髪師アジュモニ(おばさん)の歓迎を受けて初っぱなから心地よく入店。
「もうすっかり春ですね」の言葉に誘われて、「今日はもっと春らしくお願いします」と散髪が始まった。
私の短髪を今日はどんな風に刈りあげるのか、しばらく様子を見た。
アジュモニはハサミで細やかに刈り込みながら、頭を右に左に、あるいは上に下にと鏡を見てあれこれ動かす。つい私が「もうだいたいできてるんじゃないですか?」と言った。するとアジュモニは仰った、「床屋の椅子に座ったら理髪師の命令に従うのよ」。「ハイ服従いたします」と答える私に理髪師は「ホっホっホ」とハサミを動かし続けた。
仕上がりは、この前よりもっと短め、やや丸みを帯びた頭のラインが「春らんまん」カットなのだとか、とてもいい感じ!
感心ついでに「この前のアジュモニの仕事ぶり、書かせてもらいましたよ」と言ったら、「エッ! 私のことですか!」と少し驚きながら「どんなとこに書いてらっしゃるの?」と訊きいてきた。「私らのwebサイトですけど」と答えたら、「それってインターネットですよね」と確かめて、「じゃあ、世界中の人が見るんですよね」と弾んだ声が返ってきた。
そう言われるとちょっとむずがゆい。原理的には「世界中の誰もが見れる」、けれど私たちのフォロワーはそう多くない。あまり失望させるのも何だし見栄もあって、「まあそうですが日本語がわかる人しかだめですけどね」と無難に答えた。
「書いてくださってありがとう」と嬉しそうに、しかし真顔でアジュモニは仰った。
「でもなにも私だけが特別じゃないのよ。わが国では“人民のために奉仕”がサービス業のモットーですから、商店だって食堂だってみんなそうしてる。お客さんもわが国のことはおわかりでしょう?」
それは謙遜というより、朝鮮という国のサービス業に従事する者の心構えがいかなるものか、それを外国人にわからせようとするこの女性理髪師の愛国心を言葉にしたもの。
彼女の職人芸は愛国心と一体! この方はどこをとっても一流だ。
理髪が終わると「お客さんはお茶、お好きですか?」と茶を煎(い)れてくれた。それはとても香り芳しい「薔薇(ばら)茶」、最後のサービスをゆっくり味わわせていただいて「コマスミダ(ありがとう)」とお礼を述べて店を出た。
ピョンヤンの理髪師から何かひとつ教えられた気がして、頭も気分も春らんまんの一日でした。
「青天を衝け」が面白い
魚本公博 2021年4月20日
大河ドラマ「青天を衝け」がなかなか面白いです。大河ドラマは戦国時代や幕末を題材にしたものが多く、これまでの主人公はほとんどが、その時代の主要人物でした。ところが今回のドラマの主人公・渋沢栄一は幕末の頃には一介の庶民。それでドラマは、時代の大事件と一介の庶民の成長物語が並行して描かれるのでスピード感があり、しかも名もない庶民が時代の流れをどのように受けとめたかという感じで描かれるので、それが、これまでの大河ドラマとは一味違った面白さになっているのだと思います。
渋沢栄一は、日本初の民間銀行(第一国立銀行)を設立し多くの企業を起こし「日本資本主義の父」と呼ばれる人物。それであまり好感はもっていなかったのですが、これはと思う点もありました。それは、「道義的な人」ということ。
渋沢は藍商売で才覚を現し、そこを買われて一橋家の家臣になりますが、その主人が徳川慶喜。その慶喜は明治維新で駿河60万石に移住。当時、徳川家の家臣である旗本は3万家。その内の1万300家が駿河に移住したそうですが生活は困窮。それを渋沢は持ち前の才覚を発揮して支えます。基金を集め(ファンド)茶の栽培、製造を行うなど色々な事業を起こし彼らの暮らしが成り立つようにしたそうです。
零落した慶喜を見捨てることなく支え、あまつさえ困窮する多くの旗本たちの生活まで面倒を見るなど。その「道義」的な生き方は、誰にでもできることではないと思います。
「一滴一滴の集まりが大河になる」というのが渋沢の持論だったそうですが、それは現在の「一人一人に価値がある」に通じるものがあります。波瀾万丈の幕末から明治にかけて、青年渋沢がどのように時代の荒波を駆け抜けていくのか、今後の展開が楽しみです。
種まき開始
森順子 2021年4月20日
 今年のアスパラ
今年のアスパラ
10日の土曜日、夕方の畑仕事。この春は体も動きそうなので数年ぶりの参加です。
うねをつくり白菜、ホウレン草、大根の種をまき、そして土をかぶせ水をやり、初めてスコップをもっての労働でした。終わってからはビールや健康水やおやつまで食べて、皆であーだ、こーだと話に花がさいて1時間あまりでしたが、よど農場のささやかな種まきを終えました。
畑にはすでにニラやネギもあり、たらの芽を採って帰り、さっそく夕食に。やっぱりこの季節は人々の生活にとって一番のいい時期だと感じます。そして、今月の末にはトウモロコシを植え5月中旬には田植えが始まり、もうすぐ青々とした光景が広がる朝鮮です。
「照ノ富士」
小西隆裕 2021年4月5日
照ノ富士が優勝した。
この間、BS1の大相撲ダイジェスト版を録画しておいて観るのが習慣と言うか、楽しみになった。
力士が瞬間の勝負のため、力を尽くし、秘術を尽くしてぶつかり合うのを観る楽しみに目覚めた。そんな感じだ。
もちろん、ひいきはいる。その中の一人が照ノ富士だ。
若手有望力士として、いち早く大関になった彼がいつの間にかいなくなった。そのくらいは知っていた。
その彼が序二段まで落ちて、再び上がってきた。
それで注目して観ていたが、とうとう再び大関を狙うところまで来た。
序二段まで落ちて再び大関になった力士は、大相撲の長い歴史でもいないという。
三役まで上がってきて、先々場所は小結で13勝、先場所は関脇で11勝。
今場所も二桁ならばというところで、彼も緊張したことだろう。
一番、一番、脇の甘い彼が、懐に飛び込んできた相手を両手に抱え、何とか勝ちをつかみ続ける姿には必死さが滲んでいた。
千秋楽、ここで勝てば優勝という一番、相手は大関、貴景勝。照ノ富士は、その突き押しを余裕を持って受け止め、逆転圧倒した。白鵬のいない大相撲にあって、最高の実力者としての貫禄だった。
大関から序二段へ、そして再び大関。感じられた貫禄は、その苦労に裏付けられたものだったのだろう。
こういう力士にこそ、横綱になってほしいと思う。
貧しい街が生んだヒーロー、ビートルズとリヴァプールFC(Football Club)
若林盛亮 2021年4月5日
ビートルズ解散後、リーダーだったジョン・レノンは「ワーキングクラス・ヒーロー」という名曲を書いた。「労働者階級のヒーロー」、ビートルズがまさにそうだった。メンバー4人は英国北西部の港町、リヴァプールで労働者階級の子として生まれ、ロックバンドで世界中のヒーローとなった。
リヴァプールにはもう一人(?)の「ワーキングクラス・ヒーロー」がいる。それが英プレミア・サッカーリーグの「リヴァプールFC」だ。1892年来の歴史を誇る古豪だ。
この欄で何度も書いたように私はそのリヴァプールFC大好き人間だ。
しばらく不振の時期が続いたがドイツ人の名将クロップ監督を迎えて、ここ二年間は、欧州チャンピオン(UEFAカップ優勝)に輝き、続いて昨季英プレミア・リーグ優勝を他チームに圧倒的な勝ち点差を付けて勝ち取った。
ところが今シーズンは防御の主力陣の相次ぐ負傷による長期離脱者続出で7位という不振にあえいでいる。でもこの苦境にあってリヴァプール魂そのものの「苦難突破戦」で欧州UEFAカップでは8強進出を決め、険しく困難な道、優勝という目標に向かって邁進している。
祈る思いの私は2月末にメールで送られてきたスポーツ雑誌「Number」、リヴァプール特集号の記事「貧しき街で輝いた欧州最強クラブの30年」を読み返してみた。
1980年代にリヴァプール観戦のためこの街を訪れた筆者はこう書いている。
「当時のリヴァプールはヨーロッパでももっとも貧しい街のひとつだった。・・・‘80年代の欧州最高のフットボールチームはそんな時代を生きていた」。選手の年俸もいまならたった数週間で稼ぐほどの額だったという。
当時、リヴァプールのホーム、アンフィールドでこのチームのアンセム(応援歌)“You’ll Never Walk Alone”(お前は独りじゃない)が歌われると敵地に乗り込んだ相手チームのサポーターからは侮蔑を込めて”You’ll Never Get a Job”(お前らには仕事がない)の大合唱が返ってきた。
リヴァプールはそんな歴史を背負ってきたチームだ。だから今もそのルーツを忘れない。
ホームのアンフィールドで行われる競技時には「フードバンク」が設けられ、ファンが缶詰や日持ちのする食品の袋を持ち寄り寄付する。それらはホームレスや貧しい家庭の人々の手に渡る。またコロナ禍発生当時、献身的に医療に従事する地元の病院に、リヴァプールのある選手が「名前は出さないで」と多額の寄付金を届けた美談もある。
「嵐の中でも前を向いて進むんだ 暗闇を恐れずに」に始まるこのチームの応援歌“You’ll Never Walk Alone”には「嵐の向こうには黄金に輝く空が広がる 夜明けを告げるヒバリの美しい歌声が聞こえる」という歌詞がある。コロナと闘うNHS(国民健康保健サービス)スタッフがこれを歌いながら自らを励ます動画が流れたという。それを見たチームのクロップ監督は涙が止まらなかったそうだ。ある病棟では受け持ち患者の1/3が感染症で亡くなってしまうという悲惨に耐える状況下での逸話だ。
街の人々と苦楽を共にするリヴァプールFC、「貧しき街で輝いた欧州最強クラブ」に刻まれたDNA、今季、主力を失っても「苦難突破戦」に挑むリヴァプール魂をこの街の人々と共に私は愛しチームの勝利を信じたい。
「嵐の向こうには黄金に輝く空が広がる」のだから。You’ll Never Walk Alone!!
水蒸気噴霧器
赤木志郎 2021年4月5日
春になり、アパートのベランダの壁塗りや補修が始まった。それに伴い、部屋の中の掃除、整頓もおこなうことになった。三人家族の生活から一人になったので使っているのは台所と浴室以外に寝室兼書斎の1部屋だけだ。掃除は日曜日にやることになっているが、つい手を抜くこともある。
BS放送でTVを見ていたら、水蒸気噴霧器の宣伝があった。100度の蒸気で汚れを落とすものだ。台所や窓のさんなどの汚れを簡単に落とすだけでなく、カーテンをつけたま汚れを落とすことができ、食器の消毒にも利用できる。手間をだいぶ省け、しかも綺麗になる。
あればいいなあと思っていたら、イタリアとの合弁の中国製のものが商店にあった。70$で購入できた。店で試し、使い方を教えてもらった。
作業が楽になるのが良いし、洗剤を使わないのが良い。もし「暮らしの手帖」の花森編集長が生きていたら、製品テストで太鼓判を押していたのではないかと思った。
春の衣がえとともに住居の壁塗り、家の掃除、四月になったことを実感する。
そろそろ畑作業を始める季節です
魚本公博 2021年4月5日
今年は春の到来が速く、例年ですと4月末から始める畑作業準備にもそろそろ取りかからなくてはと思うこの頃です。
そうした中、「スマート農業」に関する資料を読みました。今、日本の農業の問題は、後継者不足、人手不足。農業人口は200万人を切り、平均年齢67歳、今後数年間で多くの人のリタイアが予想される中で、これらを解消するものとして俄然、注目されているのが「スマート農業」。
機械のロボット化やドローンを使った無人農作業、ビッグデーターの活用により、これまで経験に頼っていた営農のデジタル化。これで一日24時間、365日の作業が可能に。後継者難、人手不足、重労働からの解放、経験の継承、楽しい農業・・・。BS放送などで、その一端を示す映像など見てもいいですね、
幼い頃、父親や母親の日曜農業の手伝いをし、土になじみ、朝鮮に来ても、土いじりを趣味にするなど農業に関心のある私としては、「スマート農業」が「日本の農業」を支え発展させるものになることを願ってやみません。
「デジタル農業」でデメリットとされるものの一つが「野菜の食味」だとか。温室栽培では、そこが難しいようです。そういう意味では、シャベルとクワの旧い農作業も捨てたがたいと力が入ります。
春の息吹
若林佐喜子 2021年4月5日
ピンクのつつじに杏の花、黄色いれんぎょうとタンポポなどが一斉に花開いた日本人村です。先日は、春の日射しに刺激を受け、わが家のベランダ掃除と窓ふきをしました。ベランダの鉢植えの枯れたトマトの苗木を捨てたり、水をまきブラシでこすり綺麗さっぱりに。窓ガラスも積もった埃をふき払ってすっきりです。朝から夕方まで動きまわりちょっと疲れましたが、冬の間に縮こまっていた身体が解きほぐされ心身ともにリフレッシュ、そんな気分の一日でした。
さて、朝鮮ですが、ピョンヤン市一万世帯住宅建設の話題でもちきりです。
先月の23日に、その着工式がありました。地熱や太陽エネルギーを利用したグリーン建築や超高層住宅などが建ち並ぶ近代的な建設見取り図。不当な経済制裁、昨年は過酷な自然災害に見舞われ、さらにコロナ禍対応での非常防疫体制と大変厳しい状況下ですが、自分式に自分の力で、自分の手であらゆるものを建設、創造していく攻撃精神、正面突破戦ということです。
5年前に建造された黎明街が約5千世帯ですので、それよりもかなり膨大な建設になるようです。着工式で発破とともに掘削機が動き出し、その後、テレビで毎日、建設現場の様子が伝えられています。建設を主に担当する人民軍隊をはじめ、セメントや鉄鋼などの建設資材を受けもつ工場や各企業所も技術革新とフル稼働で、皆やる気満々な様子。
春の息吹の中、新しい街ができる市民達の喜びと力強い躍動感が伝わってくる4月のピョンヤン、朝鮮です。
黄砂が来た
小西隆裕 2021年3月20日
3月15日夜、「黄砂が来るので、今日の夜12時から明日の夜12時まで、外に出ず、家に籠もっていてもらいたい」との連絡が入った。
それで、皆それぞれ思い思いだが、私は、パソコンを家に持ち込み、16日一日中、日本からPDFで送ってもらった本を読んで過ごした。「村」の食堂に行くこともできないので、昼食、夕食も自炊。
黄砂に乗って、コロナが飛んでくるからということだったが、それにしてもこの徹底ぶりがあっての「コロナ感染ゼロ」なのだと改めて感心した。
「うざったかった」、でも「なつかしい僕の町」
若林盛亮 2021年3月20日
1月の「よど号LIFE」、「父親の記憶」で私が触れたBS深夜番組「For You-静かな夜のSong Book」、3月は「HOME」をテーマの名曲を取り上げた。
故郷への様々な想いを歌った世界の名曲がわかりやすい日本語意訳詩で紹介される。
80年代に世界的にヒットした名曲「カウントリーロード」のような「故郷に帰りたい」的に純粋に故郷を愛し懐かしむ歌もあるが、故郷への愛憎の入り混じる歌もけっこう多い。
「これは」! と思ったのが「Dirty Old Town」、薄汚れた古い故郷の街を歌ったものだ。
アイルランドか英国北部から出てきたような古い民族楽器主体の地味なバンドThe Pogues、ヴォーカルはいかにも「あんちゃん」風、ケンカで折られたような前歯をむき出して歌う。
でもその素朴なメロディーと歌詞にはとても味わい深いものがあった。
歌詞を全部載せたいところだが、このバンドとメロディの独特な雰囲気がわからないと感じがわからないだろう。だから要約させていただく。
「ガス田跡で巡り会った女の子と運河を眺め夢を語り合った」に始まる彼らの街、そこは「猫は餌を探して通りを行く、女は夜の街に立ち続ける」古くて不潔な街、「春を匂わす風は煙りだらけ」、そんなすたれ、くたびれた街。そんな街に彼らはこう吐き捨てる。
切れ味鋭いオノを作ろう
火炎で鋼に焼きを入れて
枯れ木のように切り倒す
オノで切り倒したいような街、それが彼らの「Dirty Old Town」。
でも最後の歌詞は、「ガス田跡で巡り会った女の子と運河を眺めながら夢を語りあった」という最初の歌詞に戻りながら、そんな街でも「なつかしい俺たちの街」なんだよと締めている。
私にもこれに似た故郷の町への複雑な想いがある。
私の故郷、草津は東海道と中山道の合流点にある宿場町、別に汚れてすたれていたわけではないし、オノで切り倒すなんて考えたわけではないけれど・・・
高3の頃、ビートルズ風の長髪にした。体育教師は「女の子の授業はあっちだ」と言った。それから母校は「うざったい」ものになった。休憩時間にも旺文社の受験用英単語集暗記に熱中する級友らを「アホか」とあざけった。
ビートルズ「同志」と夜の町を延々と「夢を語り」歩いた。「高校生の異性交際」? 町には大人の好奇の目があった。ただビートルズの話をしてるだけなのに・・・。それから故郷の町は「うざったい」ものになった。町の中学の同級会もうんざり、私は誘いを断った。
時は流れ私は赤軍派に参加。ハイジャック決行のはずが「遅刻者」があって計画はいったん中止、福岡から東京に再び戻る電車が私の故郷の町、草津駅を通過した。そのとき姉とよく通った映画館の屋根がちらっと見えた。切なさがこみ上げてきて涙を干すために顔を上に向けた、「草津よありがとう、さようなら なつかしい僕の町・・・」と心はつぶやいていた。
「うざったい」故郷の町が「なつかしい僕の町」になった不思議な体験だった。
百人には「百の故郷の想い」があることだろう。
故郷の同窓もひとりふたりとこの世を去っていく、でもいま残った同窓とメールで「故郷」を語り合える。やはり草津は「なつかしい僕の町」なのだろう。
春の芽生え
魚本公博 2021年3月20日
厳しい冬も去り、めっきり春めいてきました。野山のあちこちでは野草が芽吹き始めましたが最初に芽吹くのがナズナ。日本でも七草粥で食す習慣がありますが、朝鮮でもよく食べられ、食堂ではみそ汁の具や味噌で根を煮込んだものが出されます。体にもよさそうで、ちょっと苦みがありますが中々の美味です。
そして、これからは蕗の薹やアスパラが芽吹きます。これらは昨年、作付けを広げたので楽しみです。その他、ハコベ、イラクサ、カンゾウ、スッパ、ヨモギなども芽吹いてきます。春の野草や芽は何でも食べられ体によいといいますが、休日には握り飯と味噌を用意して野外で野草食というのが私の密かな楽しみ、美味いですよ。
日本は、コロナ禍が収まる気配を見せず、大変な状況。春と言ってもまだまだ寒い、芽吹き始めた野草を見ながらそうした思いにとらわれるこの頃ですが野草にも目を向けて免疫力増強で行きましょう。
よど農場もお目覚め頃
森順子 2021年3月20日
テドン江の氷も溶け、キジやエゾリスも姿を見せ村の光景も春を迎えたという感じです。
さて、そろそろ、よど農場の土壌も温かい陽で目覚めるころです。
今年も昨年のように皆の一致した意向のもと、いつから耕し種まきをするのかは、作業班長さんがこれから計画をたてることになっています。毎年、笑顔と癒しと豊富な実りをもたらしてくれるよど農場は、生活的にも精神衛生的にも私たちにとって大切な場所です。
去年は20種類以上の野菜類があったので今年はそれ以上にしたいですが、まず自分が心を込めた労働をしなければ。そして何よりも、昨年、朝鮮を襲った洪水や台風の被害に見舞われないことを願い、今年の夏はよど農場も朝鮮の農業も豊作にしたいです。
真水と真心
小西隆裕 2021年3月5日
年をとるといろいろなことが思い起こされ、若い頃には考えもしなかった生活の真理のようなものが見えてくるものだ。
そこで今回は、「真心」の一節。
真水とは混じり気のない水だ。
純粋な水に何も他のものが混じっていない、そういう水だということだ。
では、真心とは?混じり気のない純粋な心とは何か?
そもそも純粋な心、純心とは何か?
水の場合は、「H2O」ということで一応説明はつくが、心となると簡単でない。
そこで思い至るのは、心とはもともと良いものだと思われていたということだ。
純粋に他人のこと、皆のこと、公のことを思う心、それが心だということではないか。
そこに自分個人の利益を図る考えが混じると真心ではないということになる。
そこで思うのは、今の世の中、自分の利益を図るのは、人間として当たり前だと考えられているということだ。
実際、人が何かすると、その人の利害関係から考えるのが当たり前になっている。
すなわち、真心という概念自体がこの世からなくなっているということだ。
では、この世に真心というものが全くなくなってしまったのかというと、そうではないと思う。
今日、時代の転換が言われているが、そこでもっとも切実に問われていることの一つがこの真心ではないかと思う。
特にそれは、政治の世界で問われているのではないか。
政治不信が一般的な社会現象となる中、政治家にもっとも問われているのは、この真心だと思う。
真心という概念の復活、時代の転換を切り開く政治家、革命家がもっとも心すべきことではないだろうか。
毎日の生活で、自らを戒めながら。
ピョンヤンの理髪師―「今日は春風にしてみました」に込められた職人芸
若林盛亮 2021年3月5日
最近、床屋は新しい店に行くことにした。安くてサービスがいいからだ。外国人もよく行く店だが、高級店なら千円以上はとられるが、そこは400円そこそこというのも魅力。でもいちばんの魅力はその店の理髪師のプロ魂、職人芸術。
若い頃は床屋いらずのロングヘアーが自慢だった私の髪型もいまはスポーツマン・タイプの短髪スタイル。白髪が目立つようになってからは「年寄り臭くみえないように」というスケベ根性もあって、短髪がけっこう気に入っている。最初の頃は息子から「似合わないよ」と言われたが、いまはすっかり古希過ぎ爺「若林君」の顔になった。
話をピョンヤンの理髪師に戻そう。
2月も終わる先日の土曜日に店に行ったら馴染みの理髪師に「ずいぶん伸びてしまいましたねえ」と言われた。「この前は冬だから寒くないようにちょっと長めに刈り揃えましたからね」と仰せになったが、自分ではそんな細かいことに気づかなかった。
「もう春だから今日は少し短めにしましょう」と彼女は仕事にとりかかった。仕事は実に丁寧でいちいちハサミで刈り込んでくれる。前の店では理髪師がバリカンで一挙に「芝刈り」風にやったので、「ハサミじゃ手間がかかるよね」と冗談紛れに話しかけた。するとそれへの答えぶりがとてもふるったものだった。
「同じ服でも工場の機械でつくった既製服より、人の手で縫い込んだオーダーメイドの方が自分の身体にフィットするでしょ」、だから自分はその人の頭と顔の形に合うように微妙な違いをハサミで創り出すのだと。
この女性理髪師の何気ない仕事ぶりにこんなプロ魂が宿っていたのだ!
マッサージもやってくれるが、これも実に手の込んだものだとわかった。
仕上がりを鏡で見せて「どうですか? 額のシワが伸びたでしょ?」と。なるほど若返った感じがする。それで「どんなクリームを使うの? 自分でもやってみようかな」と訊いたら、またその答えがふるっていた。
「私のようなスベスベの手でやるからいいんであって、貴方のようなごつごつの手では逆効果になりますよ」と言いながら、だから毎日、私のところに来れば10歳以上は若返らせてあげます! とのたまった。
彼女には初級中学校(日本なら小学校高学年)の息子もいて夫と一緒に自分が刈ってやるのだそうだ。「そりゃ自分の旦那と息子、他人との違いを見せたいからね」と仰しゃった。
いやいやこのピョンヤンの理髪師、そんじょそこらのとは違うプロだ。前にも書いたメガネ職人といい、自分の仕事にプロの意地をかける姿は清々しいものだ。
私は春の風を頭に感じながら気分爽快に店を出た。
味噌玉
赤木志郎 2021年3月5日

大豆から作る味噌は栄養価もありながら、味噌汁として日本人には欠かせない。そのなかでも味噌玉の味噌がとりわけ美味しい。そのまま舐めても香ばしいし、味噌汁にすれば極上の味だ。手作りの味噌玉を作って軒下に干していた食堂のオモニがいて、その味噌が美味しかったのを想い出す。
今や、商店でその味噌玉の味噌が売り出されるようになっている。数年前から市場で売り出されていたそうだが、私は知らなかった。私が手にしたのは商店できれいに包装されたものだ。
味噌玉の味噌には、味噌と唐辛子味噌の2種類があり、唐辛子味噌でも唐辛子に苦手な私でも舐めることができる美味しいものだ。この味噌をご飯にかけ、ネギとソーセジーをみじん切りにしてかき混ぜて食べても絶品だ。で、もっぱら味噌玉の味噌を愛用している。
先月は、旧正月が3日間休みなど祭日の多い月で自炊する時が多かった。それで、味噌玉を使った味噌汁や好みのユッケジャン(肉汁)などを作った。連休なので一度で3食分をつくり、連続して食べることになる。味噌汁やユッケジャンは連続して頂いても食欲が湧き、飽きない。ところが、いくら好きなカレーでも3食連続となるとさすが厭になってくる。味噌玉の味噌汁やユッケジャンの味わいがそれだけ深いからなのか、日本人や朝鮮人の体質にあっているからなのか。
食品革命で他にも飲む酢や銀杏の葉のお茶、鉄観音などがでているが、また新しい商品がでるのか、楽しみだ。
遺産
魚本公博 2021年3月5日
2月21日に行われた大分市議会選挙。定数44の内、自民の現職3人が落選した反面社民は現職4人が当選。それも上位5人の内の3人を占めるなど健闘。「大分は社民の牙城、その存在感を示した」などの解説を見ながら、嬉しい気持ちになりました。
それというのも、大分は社民の前身・旧社会党の地盤が強かった県で、50年代60年代の平松郁(かおる)社会党県政の時代は私の少年時代とダブルからです。
私の故郷は別府ですが、その中でも当時は農村地帯だった石垣の出身。地域の中心は農協。農協主催の旅行や野球大会、展覧会(習字、絵画)などが催され、貯金は農協貯金、家電は農協マーク。私の家で最初に買ったテレビも農協マークの入ったテレビでした。
農協はほとんどが自民党の支持基盤になるわけですが農民運動の盛んだった大分や東北などでは社会党色が強かったと聞きますし、石垣農協もそんな感じだったと思います。
石垣では、成人学校、母親教室、料理教室なども催されていました。それとナトコ映画。別府の野菜供給基地だった石垣にはセリ市が5カ所もあり(30m四方ほどをトタン屋根で覆ったもの)、そこでしばしば無料で上映されていた巡回映画がナトコ映画。社会派映画が多くて「沖縄の少年」「警察物語」「生きていて良かった」とか「力道山物語」も観ました。(ナトコ映画、手持ちの辞書で調べても分かりません、どなたか教えていただければ幸いです)
これをもって社会党県政だったからと言うのは合わないかもしれませんが、少なくとも進歩的で共同体的な気運が強かったことは確かです。そうした「和気あいあい」とした共同体的な体験。私が今でも地方問題に興味があるのも、そうした時代、そうした田舎で幼少時代を過ごしたことが原点としてあるからかもしれません。
大分の社民も立憲民主党への合流を決め、これが社民としての最後の選挙。「どうしても社民に投票したくて」とか「(立憲に合流しても)ずっと社民で頑張って欲しい」という声もあったとか。何かそうした時代の遺産という感じがします。社民の皆さんも、この「遺産」を今に生かすという気持ちで頑張ってほしいです。
今日は、ひな祭り
若林佐喜子 2021年3月5日

テドン江の氷もすっかり解け、柳の木も黄色く色づきもうじき芽吹きそうです。
先日は、日本の新聞の「メイクに涙した79歳のばあば」という記事に、ついほっこり。コロナ禍で外出もままならい中、同居の「ばあば」に、口紅から、ファンデーションとフルメイクをしてあげると、鏡を見つめて涙を流し、「生まれてきてくれてありがとう」と言ってくれたとの20歳のAさんの投書。彼女の両親は共働きで幼いときから祖母が面倒をみてくれたそうです。きっと彼女の感謝の気持ちが祖母に伝わり、幼いころからの姿が目に浮かび思わず言葉に出たのでしょうか。
数年前から、「生まれてきてくれてありがとう」「生んでくれてありがとう」と言う言葉が人々の口にされるようになったと聞きます。日常生活で、より「命」の尊さに気づかされる出来事が多い中で、「尊い命」が繋がれていくことの大切さを実感する日々なのだと思います。
コロナ禍で大変な毎日で心が沈みがちです。でも、このような時だからこそ「尊い命」らの健やかな成長を願い、しっかりお祝いをしてあげたいと切に思わずにはいられない3月3日、今年のひな祭りです。
*よど号LIFEの過去の投稿は
http://www.yodogo-nihonjinmura.com/life/
に移動しました。